「SNSを見ていると、つい人と比べて落ち込んでしまう」
「友達のキラキラした投稿に、焦りや疲れを感じる」
そんなふうに、SNS疲れを感じていませんか?
実はその背景には、心理学で解き明かされている社会的比較理論があります。
人は誰でも、自分を知るために他人と比べてしまうもの。
でも、比べ方を間違えると心がどんどん疲れてしまうのです。
この記事では、社会的比較理論の基礎から、
SNS時代に陥りやすい比較のワナ、
そして心を守る具体的な対策までをわかりやすく解説します。
読むことで、SNSに振り回されず、自分らしく過ごせるヒントがきっと見つかるはずです。
「もう比較で疲れた…」と感じている方は、ぜひ続きをご覧ください!
社会的比較理論とは?|心理学でわかる「人と比べる」しくみ

社会的比較理論の意味と歴史
「社会的比較理論」とは、1954年に心理学者のレオン・フェスティンガーが提唱した心理学の理論です。
簡単に言うと、
「人は自分の意見や能力、価値を知るために他人と比べる」
という考え方です。
例えば、こんな場面を想像してみてください。
- 「自分の給料は同年代と比べて高いのか、低いのか」
- 「自分の英語力は他の人と比べてどうか」
- 「自分の体型は周りと比べて太っているのか、痩せているのか」
こうした比較を通じて、私たちは
- 自分の位置づけを知りたい
- 自分に自信を持ちたい
- 周りに遅れたくない
と感じます。
特にフェスティンガーは、
「客観的な基準がないとき、人は他人を基準にする」
と述べています。
たとえば「理想の年収はいくらか?」は数字で答えられますが、それが自分にとって高いのか低いのかは、やはり他人と比べないと分からないものです。
上方比較と下方比較とは?
社会的比較には大きく分けて2つの方向があります。
上方比較(Upward Comparison)
- 自分より優れている人と比べること
- メリット:
- 「自分も頑張ろう!」とモチベーションが上がる
- 成長の目標になる
- デメリット:
- 「自分はダメだ」と落ち込みやすい
- 劣等感が強くなる
例えば、SNSで友達のキラキラした投稿を見て
「自分ももっと努力しよう!」
と思うこともあれば、逆に
「自分なんて全然ダメだ…」
と自己嫌悪に陥ることもあります。
下方比較(Downward Comparison)
- 自分より劣っている人と比べること
- メリット:
- 「自分はまだマシだ」と安心できる
- 不安が和らぐ
- デメリット:
- 慢心したり、他人を見下す原因になる
例えば、
「あの人よりは私の方がまだ仕事ができる」
と思うことで、自信を取り戻す場合がありますが、同時に
「人を見下すなんて良くないことかも」
とモヤモヤすることもあります。
具体例で理解する比較のパターン
身近な例で整理してみましょう。
- 上方比較の例
- SNSで友達が海外旅行に行っている → 「自分も行きたい!頑張ろう!」
- 同僚が資格試験に合格した → 「自分も勉強しよう!」
- 下方比較の例
- SNSで他人が仕事でトラブルを抱えている → 「自分はまだマシだな」
- 知人が転職で苦労している → 「今の仕事を大事にしよう」
つまり比較には、
✅ モチベーションにつながる側面
✅ 劣等感や優越感を生む側面
があるわけです。
社会的比較が人に与える影響
社会的比較には大きな心理的影響があります。
自尊心や自己評価への影響
- 他人より優れていると感じるとき
- 自尊心(self-esteem)が高まり、気分が良くなる
- 他人より劣っていると感じるとき
- 自信を失いやすくなる
- 「自分には価値がないのでは」と悩む
例:
「あの人より収入が高い」と思うと自信がつく
「あの人みたいにキラキラしていない」と思うと落ち込む
劣等感やストレスにつながる理由
社会的比較が行き過ぎると、
- 他人ばかり気になってしまう
- 常に競争している感覚になる
- SNSで「いいね」の数に振り回される
こうした状態が続くと、
- ストレス
- 劣等感
- 心の疲れ
につながります。
特に現代はSNSの発達で、他人の生活が簡単に見えてしまうため、社会的比較の機会が爆発的に増えているのが現状です。
社会的比較は人間にとって自然な行為です。
しかし、うまく付き合わないと自分を苦しめてしまうこともあるため、「誰と比べるか」「何を比べるか」を意識することが大切です。

SNSで社会的比較が激化する理由|「疲れる」「落ち込む」メカニズム
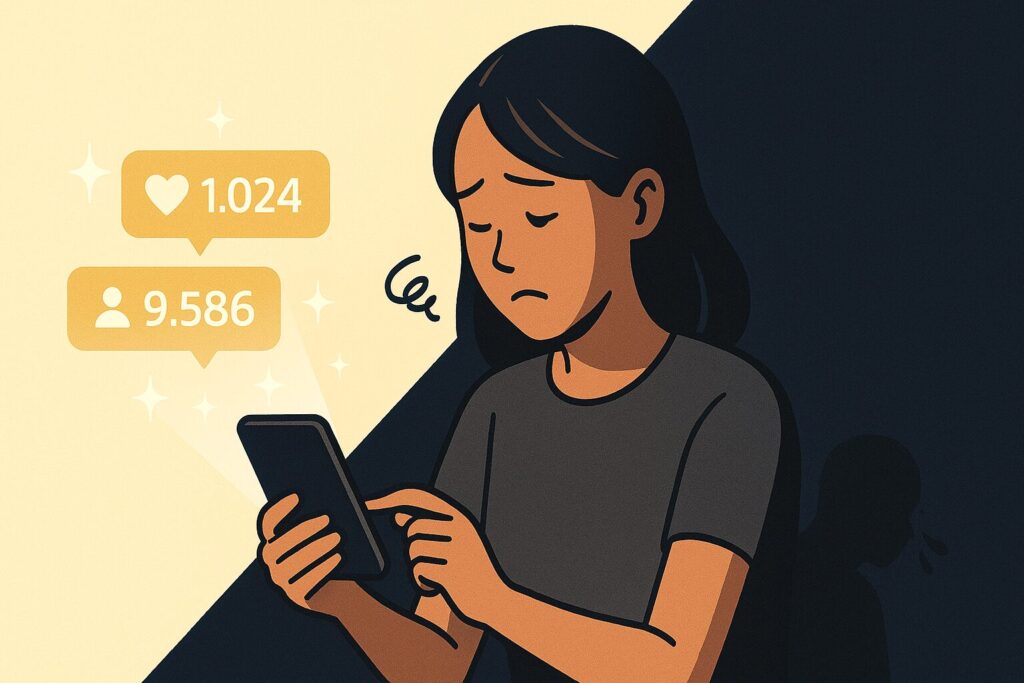
SNSが比較を加速させる仕組み
現代において、私たちが社会的比較を強く意識するきっかけの一つがSNSです。
SNSには次のような仕組みがあり、人々を「他人との比較」へと誘います。
「いいね」「フォロワー数」が引き起こす比較
SNSでは、
- 投稿に「いいね!」がどれだけついたか
- フォロワーが何人いるか
といった数値で可視化される評価が非常に目立ちます。
例えば、
「友達の投稿には1000いいね!がついているのに、自分は50しかつかない…」
といった状況に直面すると、人はつい自分と他人を比べてしまいます。
数字はわかりやすいだけに、
- 他人の評価を基準に自分を測る
- 少ない数字に落ち込む
といった心理が働きやすいのです。
他人の「良い部分」ばかり目に入る理由
SNSに投稿されるのは、多くの場合、
- 楽しい出来事
- 成功体験
- 幸せな瞬間
ばかりです。これはいわば「人生のハイライトシーン」です。
しかし、SNSを見ている側はその背景を知りません。
例:
- 豪華ディナーの写真 → 実際には節約生活をしているかもしれない
- 海外旅行の投稿 → 実は無理して借金をして行った旅行かもしれない
でも、そうは見えません。
私たちは、他人のキラキラした投稿を見て、
「自分だけがつまらない人生を送っているのでは?」
と錯覚してしまうのです。これがSNSの怖いところです。
SNS疲れ・SNSうつの心理的背景
SNSで感じる嫉妬や劣等感
SNSは、他人の「成功」「楽しそうな姿」に溢れています。
そのため、
- 嫉妬
- 劣等感
が簡単に芽生えてしまいます。
例えば、
「同い年のあの人は結婚して幸せそうなのに、私はまだ独り…」
「友達は起業してうまくいってるのに、自分は平凡な会社員のまま…」
こうした比較は、心を大きく消耗させます。
嫉妬は自然な感情ですが、SNSではその頻度が増えやすいのが問題です。
SNSによる承認欲求の高まり
SNSには、
- 「もっといいねが欲しい」
- 「フォロワーを増やしたい」
という承認欲求を強める側面があります。
最初は「楽しく交流するため」だったのに、
- 人からよく思われたい
- 目立ちたい
- 認められたい
という気持ちが強くなりすぎると、投稿の内容を無理に盛ったり、嘘をついてしまうことも。
結果的に、
- 投稿が義務のようになる
- 承認が得られないと落ち込む
という悪循環に陥ってしまいます。

SNSをやめたくなる瞬間とは
SNS疲れを感じる具体的なシーン
SNS疲れを感じるのは、こんな瞬間です。
- 見たくないのに、人の投稿が気になる
- 誰かの楽しそうな投稿を見て虚しくなる
- 自分の投稿に反応が少なくて落ち込む
- 無理に「いいね」を押さなければいけない気がする
こうした小さなストレスが積み重なり、
「もうSNSをやめたい…」
と感じる人は少なくありません。
SNS利用で心が追い詰められるパターン
SNSの怖いところは、一度疲れてもやめづらいことです。
理由は、
- 「情報から取り残される不安」
- 「人間関係が切れてしまう恐怖」
- 「SNSが唯一の交流手段になっている」
などです。
だからつい
- 「やめたいけどやめられない」
- 「しばらく休もう」と思ってもまた戻る
というループに入ってしまうのです。
社会的比較によるSNS疲れを防ぐ!具体的な対策ガイド

比較する相手を変える|「過去の自分」との比較
SNSで疲れる原因のひとつは、他人との比較が止まらないことです。
でも、そもそも比べる相手は「他人」でなくても良いのです。おすすめなのが、
「過去の自分」と比べること
です。
自分の成長に目を向けるメリット
「他人」ではなく「過去の自分」と比べると、
- 自分の成長を実感できる
- 小さな変化にも気づきやすくなる
- 他人に振り回されにくくなる
例えば、
- 「1年前より早起きできるようになった」
- 「文章を前よりスムーズに書けるようになった」
と気づくと、それだけで心が軽くなります。比べる基準を自分に戻すことで、SNSのストレスは減ります。
成長を実感する具体的な方法
「過去の自分」と比べるには記録を残すのがおすすめです。
✅ 日記をつける
✅ スマホのメモに小さな成長を書き留める
✅ 毎月「できたことリスト」を作る
例:
「去年は3㎞しか走れなかったけど、今は5㎞走れる」
「SNSの投稿を見て落ち込む回数が減った」
こうした小さな変化を積み重ねることで、自分軸を取り戻せます。
SNSとの距離を取る工夫
SNSは便利ですが、距離感が大事です。
常に他人とつながり続けるのは、心に負担をかけます。
SNS利用時間を減らす方法
以下のように「見る時間」を制限するのがおすすめです。
✅ SNSは決まった時間だけ見る(例:1日10分)
✅ スマホのタイマー機能を活用する
✅ SNSの通知をオフにする
例えば、
「お風呂上がりの10分だけSNSを見て、それ以外は見ない」
とルールを決めると、無意識にSNSを開くクセを減らせます。
フォロー整理で比較を減らすテクニック
SNS疲れの原因は「他人の情報の入れすぎ」です。
フォロー整理も効果的な対策です。
✅ 見ると落ち込む人はフォローを外す
✅ ポジティブになれるアカウントだけ残す
✅ 「ミュート」機能を活用する
フォローを減らすことに罪悪感を感じる必要はありません。
自分を守るための大事な行動です。
自分の価値基準を見つける
SNSに振り回されないために、何より大切なのは
「自分が本当に大事にしたいことは何か」
を知ることです。
他人の基準に振り回されない考え方
SNSを見ていると、
- 「お金をたくさん稼ぐのが幸せ」
- 「旅行に行くのが充実した人生」
などの価値観が押し寄せてきます。
でも、それがあなたにとって本当に幸せかは別問題です。
例えば、
「自分は収入よりも、家でゆっくりする時間が大事」
「人に認められるより、自分が納得できることを大事にしたい」
というように、自分の基準を持つことが心の安定につながります。
自分軸を作るセルフワーク
簡単にできるワークをご紹介します。
✅ 紙に「大事にしたいこと」を書き出す
✅ 「それはなぜ大事か?」と自問する
✅ 他人の基準ではなく、自分が納得できる理由を探す
例:
「私は健康を一番大事にしたい。なぜなら家族と長く一緒に過ごしたいから。」
こうして言葉にすると、SNSに振り回されにくくなります。

感情を客観視する習慣をつける
SNSを見てモヤモヤするときは、感情を客観視することが効果的です。
モヤモヤを書き出す「感情ノート」
「感情ノート」は簡単です。
✅ SNSを見て感じたことをそのまま書く
✅ どうしてそう感じたかを書いてみる
✅ 読み返して「自分はこう思っていたんだ」と確認する
例:
「友達の投稿を見て、羨ましいと思った。私は今の生活に不満があるのかもしれない。」
書き出すことで、感情を冷静に見られるようになります。
頭の中だけで考えるより、紙に書く方がスッキリします。
- もし「一人で感情整理をするのが難しい」と感じるなら、【Awarefy】
 というアプリもおすすめです。
というアプリもおすすめです。
スマホで簡単に感情を書き出し、振り返る習慣が作れるので、忙しい人でも続けやすいですよ。
関連書籍
セルフコンパッションを活用する方法
「セルフコンパッション」とは、
「自分に優しくする力」
のことです。
SNSで落ち込んだときは、
- 「私は今、頑張ってる」
- 「比べなくても私には価値がある」
と自分に優しい言葉をかけましょう。
他人に優しくするように、自分にも優しくすることが大切です。

感謝リストを活用する
SNSで他人と比べると「足りないもの」ばかりが目につきます。
そんなときこそ大事なのが、
「感謝すること」
です。
比較の負の連鎖を断つ感謝の習慣
感謝の習慣は、
- ネガティブな気持ちを和らげる
- 今あるものの価値に気づける
- 他人と比べる気持ちを減らせる
という大きなメリットがあります。
日常の感謝ポイントを見つけるヒント
感謝するのは大きなことじゃなくてOKです。
✅ 美味しいご飯が食べられた
✅ 好きな音楽を聴けた
✅ 今日も無事に一日が終わった
こうした「小さな感謝」を毎日書き留めると、心が満たされやすくなります。
例:
「今日、空がきれいだった。それだけでも幸せだな。」
感謝は、比較で荒れた心を落ち着ける最強のメンタルケアです。
社会的比較とうまく付き合うために|心を守る思考法

「同化」と「対照」を意識する
社会的比較には、単に「比べる」というだけでなく、比べたあとの心の動きに2つのパターンがあります。
それが「同化(assimilation)」と「対比(contrast)」です。
同化がもたらすモチベーション
同化とは、
「あの人のようになりたい!」
と思って、相手に近づこうとする気持ちのことです。
例えば、
- 「あの人のように健康的に痩せたい」
- 「あの人みたいに仕事ができるようになりたい」
こうした気持ちは、向上心や努力のエネルギーになります。
ただし注意したいのは、
- 相手を理想化しすぎないこと
- 自分らしさを失わないこと
です。
対比で生まれる距離感の功罪
一方、対比とは、
「あの人は特別で、自分とは別世界だ」
と思って、自分と相手の間に線を引くことです。
例えば、
- 「あの人は芸能人だから、自分には関係ない」
- 「あの人は特別な才能があるから、自分とは違う」
対比には良い面も悪い面があります。
✅ 良い面:
- 比較のストレスから距離を取れる
- 自分を守るクッションになる
✅ 悪い面:
- 自分の可能性を狭めてしまう
- 「どうせ無理」と諦めやすくなる
大事なのは、
「同化と対照、どちらが自分にとって楽になれるか?」
を意識して選ぶことです。
嫉妬や羨望との向き合い方
SNSを見ていると、避けて通れないのが嫉妬や羨望です。
でも、これらは「悪い感情」とは限りません。
嫉妬を建設的に変える視点
嫉妬は本来、
- 自分が欲しいもの
- 大事にしたい価値
を教えてくれる大事な感情です。
例えば、
「友達が本を出版したのが羨ましい」
という嫉妬は、
「自分も本を出してみたい」という夢が隠れている
とも言えます。
嫉妬を感じたときは、
✅ 「自分は本当は何を望んでいるんだろう?」
✅ 「そのために何ができるだろう?」
と自問してみてください。
嫉妬は行動のヒントになる感情なんです。

羨望を自己成長につなげる方法
羨望もまた、成長へのきっかけです。
例えば、
- 「あの人の文章が上手で羨ましい」 → 書き方を学ぶ
- 「あの人の暮らしが素敵」 → 自分の生活に取り入れられる部分を探す
羨望を抱いた相手を「学びの先生」として見ると、
「羨ましい」→「真似してみよう!」
に変わります。
羨望を「自分がダメだから」と責めるのではなく、
- 「私にもできることがある」
- 「少しずつ近づけばいい」
と前向きに変換することが大事です。
完璧を目指さないマインド
社会的比較で苦しくなる人の多くは、完璧主義の傾向があります。
比較を手放す「ほどほど思考」
大切なのは、
「人それぞれペースも価値も違う」
と知ることです。
完璧を求めすぎると、
- もっと頑張らなきゃ
- あの人みたいじゃないとダメだ
と自分を追い込みます。
そこで意識したいのが「ほどほど思考」です。
✅ 頑張れるときは頑張る
✅ しんどいときは休む
✅ 人と比べすぎない
この柔軟さが、心を守るカギです。
他人も悩んでいると知る重要性
SNSでは他人の「成功」や「キラキラした面」ばかり見えますが、現実には誰もが悩みを抱えています。
例:
SNSで笑顔の人も、裏では仕事に行きたくなくて泣いているかもしれない
大切なのは、
- 人は見えない部分を抱えている
- 自分だけが苦しいわけじゃない
と知ることです。
「みんな完璧じゃない」と理解するだけで、心はずいぶんラクになります。
社会的比較は人間の自然な心の働きです。
完全になくすことはできませんが、
- 同化と対比を使い分ける
- 嫉妬や羨望を行動に変える
- 完璧を手放す柔軟さを持つ
これらを意識することで、心を守りながら自分らしく生きることができます。
社会的比較を手放す「自我にこだわらない」思考

社会的比較を手放すには自我にこだわらないことも効果的です。
自我にこだわらないとは?
ここでいう「自我にこだわらない」とは、例えばこういう状態です:
- 「自分はこうでなければいけない」という考えを手放す
- 人と比べて自分の立場や価値を過剰に気にしない
- 物事を「自分の問題」としすぎず、広い視野でとらえる
つまり、自分という枠にとらわれず、視野を広げる姿勢のことです。
社会的比較との関係
社会的比較で苦しくなるのは、たいてい
「自分が劣っているのでは」
「もっと認められたい」
という強い自我の意識が原因です。
- 「自分はあの人より上か下か」
- 「SNSで目立たないと価値がない」
- 「他人より評価されたい」
こんなふうに、自我を中心に世界を見てしまうと、比較が止まらず苦しくなります。
自我にこだわらないことの効果
① 比較への執着が減る
「自分はこうあるべき」という考えを緩めると、
- 他人と比べる必要がなくなる
- 自分のペースでいられる
結果的に、比較によるストレスが激減します。
② 視野が広がる
例えば、
- 「人それぞれ事情がある」
- 「自分もあの人も人生の一部を見せているだけ」
と捉えられるようになり、他人に振り回されにくくなります。
③ 自己受容が高まる
自我にこだわりすぎないことで、
- 完璧を目指す気持ちが和らぐ
- 自分の不完全さも受け入れやすくなる
→ 結果、自己肯定感や安心感が上がります。

実践のヒント
- 「まぁいいか」と言うクセをつける
- 自分の考えをノートに書き出して客観視する
- 自分だけでなく周りの人も悩んでいると想像してみる
- 「人間はみんな不完全」と思い出す
結論
「自我にこだわらない」は、社会的比較の悪循環を断ち切る大きな武器です。
比べる気持ちを完全にゼロにはできませんが、
「比べてもいいけど、そこに自分の価値を預けすぎない」
という姿勢が、心をラクにしてくれます。
関連書籍
SNS批判に振り回されないセルフイメージの作り方

SNSに振り回されないブレない自分を作るには、自我にこだわるのではなく、セルフイメージ(自分の物語)にこだわるのがおすすめです。
自我にこだわらずにセルフイメージ(物語)にこだわるとは?
- 自我にこだわる → その瞬間の感情や出来事にとらわれる状態
- セルフイメージ(物語)にこだわる → 自分の人生や目標という「大きな流れ」で物事を捉える状態
つまり、
「今この瞬間の自分」に執着しすぎず、
「自分の物語の全体像」を大事にする
という考え方です。
自我とセルフイメージ(物語)の違い
- 自我は点
→ 今この瞬間の「感情」や「反応」そのもの
→ 例:「SNSで批判された!ムカつく」「悲しい」 - セルフイメージは線
→ 自分の人生を通した「物語」や「方向性」
→ 例:「自分はこういう人間でありたい」「批判はスルーして、自分のやるべきことに集中する」
具体例で解説
自我にこだわる場合
- SNSで批判された
→ 「許せない!」「自分はダメなんじゃないか」と感情が揺さぶられ、そこに意識が集中する
これは「点」にこだわっている状態です。
→ その場の感情に支配される
セルフイメージにこだわる場合
- SNSで批判された
→ 「自分の物語の中で、この批判は大したことじゃない」
→ 「自分のやりたいことを続けるほうが大事」
批判があっても、
- スルーする
- 冷静に対処する
- 「自分はこういう人間」と信じて行動を続ける
こう考えられると「線」で物事を見られるようになります。
→ 全体の物語を優先し、一時的な感情に振り回されない
まとめ
- 自我にこだわる → 今この瞬間に心がとらわれる「点」の視点
- セルフイメージ(物語)にこだわる → 自分の人生全体の「線」の視点で捉える
SNSなど、他人の評価を受けやすい場面で特に重要なのは、
「自分の物語に集中する」こと
です。
そうすることで、一時的な批判や感情に振り回されず、自分の価値や方向性を保てるようになります。


まとめ|社会的比較理論を知り、SNS疲れから自由になる

社会的比較は人間にとって自然なもの
ここまでお読みいただきありがとうございます!
改めてお伝えしたいのは、
「社会的比較は自然な感情」
ということです。
人は本能的に、
- 自分の立ち位置を知りたい
- 安心したい
- 成長したい
と思う生き物です。
そのため、他人と比べるのはごく自然な心の働きです。
ただ、現代はSNSという便利だけど過酷な世界があり、比較が行きすぎやすいのも事実です。
比較を悪者にしすぎない考え方
社会的比較を完全になくそうとするのではなく、
- 「比較してもいい。でも振り回されすぎない」
- 「比べるなら過去の自分と比べよう」
- 「嫉妬も成長のきっかけになる」
と考えることが大事です。
比較を敵視するよりも、
「うまく付き合う」
という視点を持つ方が、心の負担を減らせます。
SNS時代こそ、自分を守る知識が大事
SNSが当たり前になった今、
- 誰かの人生のキラキラした部分
- 成功体験
- 華やかな日常
が、24時間いつでも目に入ります。
でも忘れないでほしいのは、
SNSは人生の「一部」しか映していない
ということです。
心を守るために今日からできること
SNS疲れを感じたとき、ぜひ以下を意識してみてください。
✅ 比較する相手を「昨日の自分」にする
✅ SNSを見すぎないルールを作る
✅ 自分の価値基準を大切にする
✅ 感情を書き出して整理する
✅ 小さな感謝を毎日見つける
例えば、
「今日は空がきれいだった」
「コーヒーが美味しかった」
そんな些細なことでも、心をホッとさせてくれます。
また、
「私は私のペースでいい」
と、自分に優しい言葉をかけることも大切です。
セルフコンパッションは、SNS時代を生き抜く強力な味方です。
社会的比較理論を知ることで、
- 「比較してしまう自分はダメだ」と責める必要がなくなる
- 比較との付き合い方を自分で選べるようになる
- SNS疲れから少しずつ自由になれる
という大きなメリットがあります。
心の健康を守りながら、楽しくSNSと付き合っていきましょう!


