「どうせ何をやっても無駄だ」
そんなふうに感じて、やる気が出ないことはありませんか?
もしかするとそれは、学習的無力感という心のクセかもしれません。
この記事では、
- 学習的無力感の正体
- 自分に当てはまるか分かるチェックリスト
- 子どもの頃の家庭環境との関係
- 大人になってからの克服法
- 心を支えてくれる名言たち
をわかりやすく解説します。
読むことで、「無駄じゃないかもしれない」と思えるきっかけが見つかり、
小さな一歩を踏み出す勇気が湧くはずです。
学習的無力感とは?意味と特徴をわかりやすく解説

学習的無力感の定義と提唱者セリグマンとは
「学習的無力感(learned helplessness)」とは、
「自分が何をしても状況は変わらない」と思い込んでしまう心理状態のことです。
この言葉を提唱したのは、アメリカの心理学者 マーティン・セリグマン です。
彼は1960年代後半に行った実験で、犬に電気ショックを与えました。
最初は犬も逃げようと必死でしたが、
- どんなに頑張っても逃げられない状況を何度も経験すると、
- 最終的には逃げられる状況になっても、
- 犬はもう動こうとせず、ただうずくまってしまったのです。
つまり「どうせ無理だ」と学習してしまったんですね。
この状態をセリグマンは「学習的無力感」と呼びました。
人間にも同じことが起こりうる、と後の研究で示されました。
学習的無力感が生まれる心理的メカニズム
学習的無力感は、主に 「失敗体験の積み重ね」 から生まれます。
たとえば:
- 勉強しても全然成績が上がらない
- 頑張っても上司に認められない
- 人間関係でいつも否定される
こうしたことが繰り返されると、
「もう何をしてもムダだ」と考えるようになり、
挑戦する意欲を失ってしまうのです。
専門的には、このとき
- 自分に原因があると考える(内的帰属)
- 全てがうまくいかないと考える(全体化)
- いつまでも変わらないと考える(永続化)
という思考のクセが関わっているとされています。
難しく聞こえるかもしれませんが、要するに
「全部自分のせいで、どうせずっと変わらない」
と思い込むことが問題の根っこなのです。
学習的無力感とうつ病・自己効力感の関係
学習的無力感は、実は うつ病 と深い関係があります。
無力感が強くなると、
- 「自分はダメだ」
- 「何をやっても変わらない」
- 「生きている意味がない」
といった 抑うつ的な考え方 に陥りやすくなるからです。
また、学習的無力感は 自己効力感(self-efficacy) とも密接に関係しています。
自己効力感とは:
「自分ならできる」という感覚や自信
無力感が強い人は、この自己効力感が非常に低い傾向があります。
逆に自己効力感が高い人は、
「うまくいかなくても、別の方法を試そう」と思えるので、
無力感に陥りにくいのです。
だからこそ、理解すれば対処や克服も可能です。

【チェックリスト】あなたは学習的無力感かもしれない

学習的無力感をチェックする質問例
自分が学習的無力感かもしれないと不安に思う方は多いでしょう。
以下のチェックリストに当てはまるか試してみてください。
✅ 「どうせ何をやっても無駄だ」とよく思う
✅ 一度失敗すると「自分はダメだ」と強く感じる
✅ 努力する前から諦めることが多い
✅ うまくいかないと全て自分のせいだと思ってしまう
✅ 将来に希望が持てず、不安ばかり感じる
✅ 新しいことを始めるのが怖いと感じる
✅ 人から褒められても「たまたまだ」と思ってしまう
2つ以上当てはまる人は、学習的無力感の傾向があるかもしれません。
ただし、これはあくまで目安です。深刻に悩む場合は専門家への相談も検討してくださいね。
よく見られる思考パターン・行動の特徴
学習的無力感の人には、特有の思考のクセや行動パターンが見られます。
具体的には、次のような特徴があります。
■ 思考パターン
- 全か無か思考
→ 「完璧じゃなければ失敗」と極端に考える - 過度の一般化
→ 1回の失敗で「自分は何をやってもダメだ」と思い込む - 自己批判が強い
→ 何でも自分の責任だと感じる
■ 行動パターン
- チャレンジを避ける
→ 「どうせ失敗する」と思い、新しいことを避ける - 受け身になりがち
→ 意見を言わず、状況に流される - 達成感を感じにくい
→ 成功しても「運が良かっただけ」と思う
こうした思考や行動は、本人も気づかないうちに身についていることが多いのです。
学習的無力感とただの甘えの違い
「学習的無力感は甘えなんじゃないの?」と悩む人も少なくありません。
しかし、この2つはまったく別物です。
【甘えとは?】
- 自分で行動できるのにやらない
- 「やりたくない」と自分の意思で避けている
- 責任を取りたくない気持ちが強い
【学習的無力感とは?】
- 「やっても無駄だ」と思い込んでしまう心理状態
- 過去の経験による学習の結果
- 本人も「やらなきゃ」と思っているが動けない
例えるなら、
- 甘えは「歩きたくないから座ってる」状態。
- 学習的無力感は「歩きたくても気力が出てこないで、立ち上がれない」状態。
つまり、甘えは意図的ですが、学習的無力感は無意識の心のブレーキなのです。
大人の学習的無力感は甘え?周囲との誤解と本当の問題

「甘え」と言われる理由
大人の学習的無力感を抱えている人は、周囲から
「それは甘えなんじゃないの?」
と言われることがあります。
その背景には、こんな誤解が潜んでいます。
- 「大人なら努力して乗り越えられるはず」という思い込み
→ 社会では「頑張れば何とかなる」という価値観が強い。 - 見た目では無力感が分かりにくい
→ 一見、元気に見えたり、普通に仕事しているように見える。 - 怠けているように見えてしまう
→ 「行動しない」姿が、周囲には努力不足に見える。
しかし、学習的無力感は甘えや怠けではなく、過去の経験によって心がブレーキをかけてしまう状態です。
本人だって「変わりたい」「頑張りたい」と思っているのに、
心が「どうせムダだ」と囁き、動けなくなっているのです。
周囲に理解されないときの対処法
無力感を抱えているとき、一番辛いのは
「周りに理解してもらえないこと」かもしれません。
ではどうしたらいいのでしょうか?以下の方法を試してみてください。
① 小さなことでも言葉にする
- 「今ちょっと疲れていてうまく動けないんだ」
- 「こういうことがあって、自信がなくなっている」
自分の状態を簡単でもいいので伝えるだけで、周囲の誤解は減ります。
② 誰か一人でも理解者を持つ
- 家族
- 友人
- カウンセラー
全部を分かってもらおうとせず、一人でいいから話を聞いてくれる相手を探してみましょう。
③ ネガティブな人からは距離を置く
- 「甘えだ」と責める人がそばにいると、無力感が強化されやすい。
- 物理的・心理的に距離を置くのも大事です。
甘えと学習的無力感を分ける3つのポイント
無力感と甘えを見分けるには、以下の3つのポイントが大切です。
① 動きたいけど動けないか?
- 甘え: やる気がなく、自分でやらない選択をしている。
- 無力感: 本当はやりたいけれど「どうせ無理だ」と思い込み、動けない。
② 自分を責めているか?
- 甘え: 責任を外に押し付けることが多い。
- 無力感: 「自分がダメだからだ」と自分を責めがち。
③ 過去の失敗経験が原因か?
- 甘え: 特に過去の経験に関係なく「やりたくない」だけの場合も。
- 無力感: 繰り返しの失敗や否定が原因で、「何をしてもムダ」と学習してしまう。
まとめると、
- 甘え → 意図的な怠慢
- 無力感 → 経験による心のブレーキ
学習的無力感は、本人の努力不足ではありません。
過去の経験が「心に壁」を作ってしまった状態なのです。
周囲の理解が得られないと苦しいですが、正しい知識を持つことが自分を責めない第一歩になります。
学習的無力感と子どもの頃の家庭環境の関係
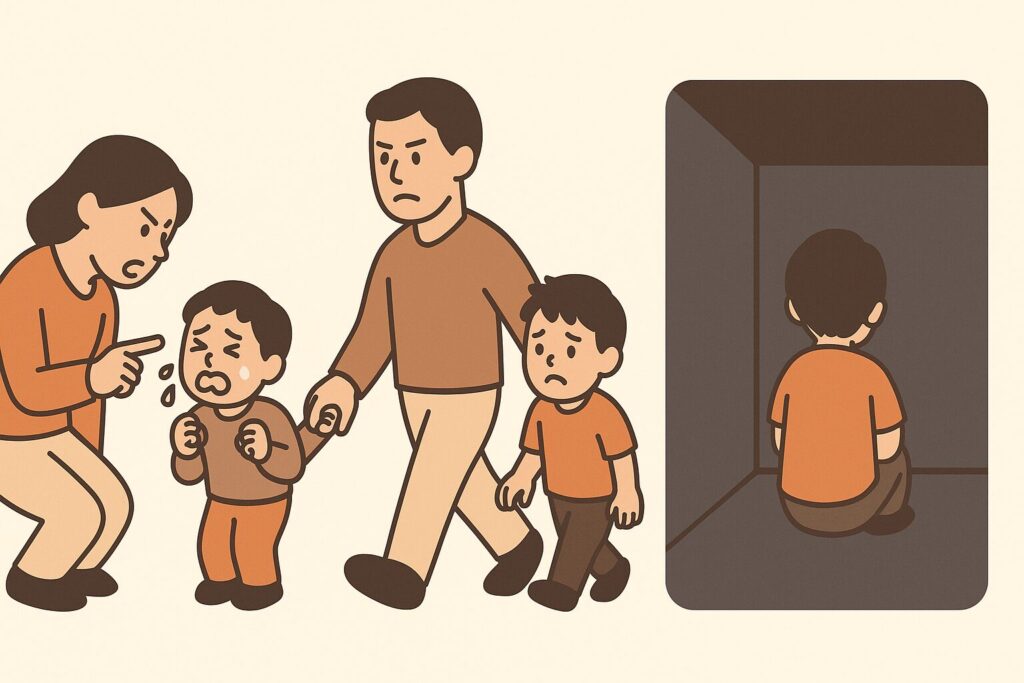
家庭環境が影響する心理的理由
学習的無力感は、生まれつきの性格だけでなく、
子どもの頃の家庭環境が大きく関わっています。
なぜかというと、家庭は子どもにとって
- 最初に接する社会
- 自分の価値を感じる場所
だからです。
例えば、親から繰り返し
- 「なんでできないの?」
- 「お前はダメだな」
- 「黙って言う通りにしろ」
など否定や命令を浴び続けると、子どもは
「自分が何をしても意味がない」
と無力感を学習してしまうのです。
家庭は本来、子どもに
- 失敗しても大丈夫と思える安心感
- 自分で選び、決められる感覚
を育む場所です。
それがないと、「努力してもムダ」という思考に陥りやすくなります。
厳格・過保護・無関心など家庭環境別の影響
家庭環境にはさまざまなパターンがあり、
それぞれ学習的無力感の原因となり得ます。
以下に具体例を挙げますね。
■ 厳格・支配的な家庭
- いつも正解を求められる
- 間違うと激しく叱られる
→ 自分の意思を出すことが怖くなり、「どうせ何をしても怒られる」と思い込む。
■ 過保護・過干渉な家庭
- 親が先回りしてすべてやってしまう
- 子どもが自分で決める機会がない
→ 「自分には何もできない」と思い込み、挑戦する気力を失う。
■ 無関心な家庭
- 褒めてもらえない
- 失敗しても放置される
→ 「頑張っても誰も見てくれない」と感じ、無力感を覚える。
■ ネガティブな家庭環境(DVや家庭内不和など)
- 暴言や暴力が日常
- 家庭が安心できる場所でない
→ 「世界は危険で、何をしても無駄」という強い無力感を抱きやすい。
親の対応が「無力感」か「自信」かを分ける
同じ失敗でも、親の対応次第で無力感になるか、自信になるかが決まります。
例えば、テストで点が悪かったとき:
- 「なんでできないの!」 → 無力感を育む
- 「どこが難しかった?一緒に考えよう」 → 挑戦する気持ちを育む
また、親がよく使う言葉も大きな影響を与えます。
無力感を育む言葉
- 「どうせ無理でしょ」
- 「お前には無理だ」
- 「失敗したら恥ずかしいよ」
自信を育む言葉
- 「失敗しても大丈夫だよ」
- 「やってみてから考えよう」
- 「挑戦しただけですごいよ」
ただし、挑戦を勧めること自体は素晴らしいことですが、
どんな挑戦でも「良い挑戦」とは限りません。
相手や状況をよく見極めた上で、
「今は止める」ことも立派なサポートです。
親は完璧である必要はありません。
しかし、子どもが「自分の行動には意味がある」と思える関わりをすることが、
無力感を防ぐ大きなポイントになります。
もし今、大人になって無力感に悩んでいても、過去の家庭環境を知ることは、
自分を責めないための大切な手がかりになります。
大人の学習的無力感を克服する方法

「学習的無力感は子どもの頃の経験が影響する」とお伝えしましたが、
大人になってからでも克服は可能です!
ここでは具体的な方法をご紹介しますね。
小さな成功体験を積み重ねるコツ
学習的無力感の最大の特徴は
「何をしてもムダ」という思い込み。
これを打ち破るためには、
「やれば変わる」という体験を少しずつ積むことがとても大切です。
ポイントは、
- 小さい目標を立てる
→ 例:「朝起きたらカーテンを開ける」 - できたら自分を褒める
→ 「今日もできた!自分頑張ってる!」
たとえ些細なことでも、
「自分の行動が結果を生む」という感覚が、
無力感の反対である自己効力感を育てます。
無理に大きな目標を立てる必要はありません。
小さな「できた!」を繰り返すことが、心を回復させる第一歩です。
認知行動療法(CBT)を活用する方法
もし無力感が強く、なかなか行動できない場合は
認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)
が非常に効果的です。
CBTは簡単に言うと、
「物事の受け取り方(認知)を修正するトレーニング」
例えば、失敗したとき
- 無力感の人:
→ 「やっぱり自分はダメだ」 - CBTを取り入れた人:
→ 「失敗したけど、次はやり方を変えよう」
CBTではこんな練習をします:
- ネガティブな考えを書き出す
- その根拠を探す
- 他の見方がないか考える
これを繰り返すことで、
「全て自分のせい」「何をしてもムダ」
という思い込みが少しずつ緩んでいきます。
もし一人で難しければ、
カウンセラーや心理士に相談するのも良い方法です。
また、認知行動療法をもっと手軽に試したい方には、アプリの【Awarefy】
![]() もおすすめです。
もおすすめです。
Awarefyは、ネガティブな考えを書き出したり、他の見方を探すなどのCBTのワークをアプリ上で実践できるツールです。
隙間時間で取り組めるので、無力感を感じたときの心の整理に役立ちます。
少しずつでも思考を整える習慣を作ることで、無力感に振り回されにくくなるはずです。
周りの人に相談する重要性
「自分だけがこんな風に感じているのでは?」
と孤立する人は多いですが、無力感に悩む人はたくさんいます。
誰かに話すだけでも、
- 気持ちが整理できる
- 「分かるよ」と言ってもらえる
- 別の解決策が見つかる
というメリットがあります。
相談相手は、
- 家族
- 友人
- 職場の信頼できる人
- カウンセラーや医師
誰でも構いません。
一人で抱え込まないことが何より大切です。
無力感を抱えているとき、
「周りに相談するのは恥ずかしい」と感じてしまう方も多いかもしれません。
でも、ずっと一人で抱え込むよりも、
専門家に話すことで気持ちが整理され、心が少し軽くなることもあります。
もし「誰にも話せない」と感じるなら、
家にいながら相談できるオンラインカウンセリング「Kimochi」
![]() のようなサービスを利用してみるのも一つの方法です。
のようなサービスを利用してみるのも一つの方法です。
無理に解決しなくても大丈夫。
話すこと自体が、無力感をほぐす第一歩になるかもしれません。
「変えられること」に意識を向ける思考法
学習的無力感の人は、
「すべて自分のせい」
「世の中はどうにもできない」
と極端に考えがちです。
しかし、全てを変える必要はありません。
自分が変えられる部分に目を向けるだけで、無力感は軽くなります。
例えば:
- 「上司の性格は変えられない → 自分の伝え方を変えてみよう」
- 「世の中は変わらない → 自分の行動だけは選べる」
次のステップを考える際は、
✅ 「今、自分にできることは何か?」
と自分に問いかけてみましょう。
小さな行動でも、無力感から抜け出す大きな力になります。
学習的無力感は、長い間の思い込みによって作られた心のクセです。
だからこそ、焦らず少しずつ取り組むことが何より大切です。
学習的無力感を克服するための励ましの名言集
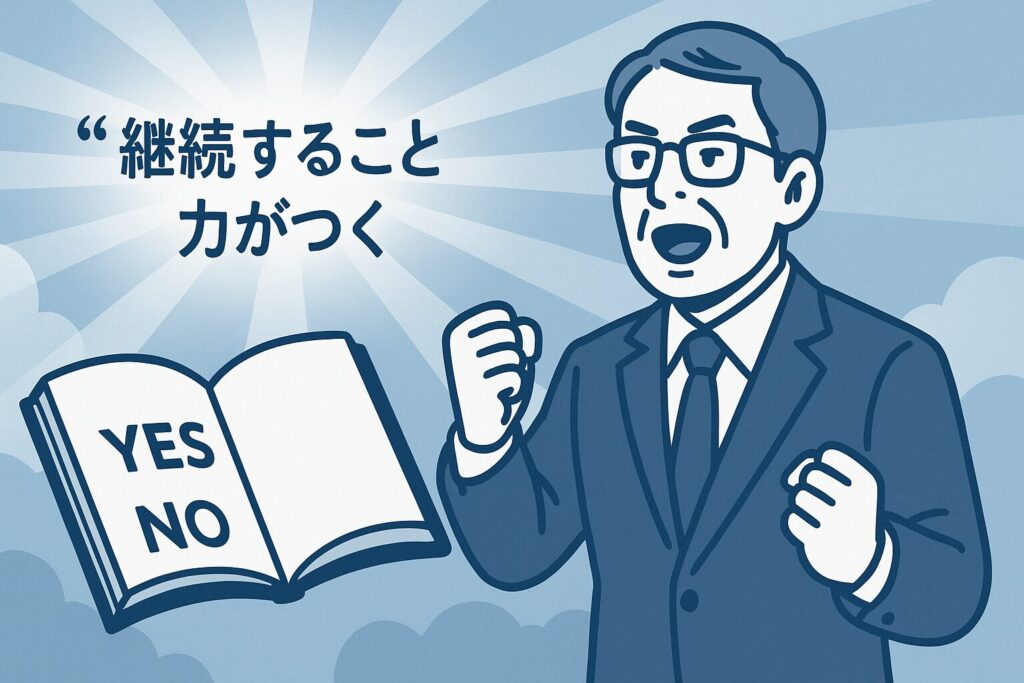
学習的無力感に苦しんでいるとき、
一番つらいのは「もうダメだ」と思い込んでしまうことです。
そんなとき、言葉の力はとても大きな助けになります。
ここでは、心に響く名言をいくつかご紹介しますね。
羽生善治の名言:「挑戦を続けることこそ才能」
将棋界のトップであり続けた羽生善治さんは、こんな言葉を残しています。
「何かに挑戦したら 確実に報われるのであれば、
誰でも必ず挑戦するだろう。
報われないかもしれないところで、
同じ情熱、気力、モチベーションをもって
継続しているのは非常に大変なことであり、
私は、それこそが才能だと思っている。」
これはまさに、学習的無力感の克服の核心を突いた言葉です。
- 「どうせムダ」と諦めたくなる
- でも、報われる保証がなくても続けることに意味がある
羽生さんも、勝ち続けている裏で、
数えきれないほどの敗北を経験しています。
それでも挑戦を続けたからこそ、輝き続けられる。
この言葉は、無力感で苦しいとき、背中を押してくれるはずです。
鴨川会長(はじめの一歩)の名言:「成功した者は皆努力しておる」
漫画『はじめの一歩』の鴨川会長の言葉も、多くの人を励ましています。
「努力した者が全て報われるとは限らん。
しかし,成功した者は皆すべからく努力しておる。」
この言葉には、次のような大切な意味が込められています。
- 世の中には理不尽がある
- 努力しても報われないことは確かにある
- でも、成功する人は必ず「努力」という過程を通っている
無力感を感じるとき、
「どうせ努力してもムダ」と思いがちです。
しかし鴨川会長の言葉は、
「結果がすぐに出なくても、成功するためには努力をする必要がある」
という真実を教えてくれます。
その他心に響く名言と解説
無力感を克服するために役立つ、他の偉人たちの言葉もご紹介しますね。
■ ネルソン・マンデラ
「It always seems impossible until it’s done.」
(すべては、成し遂げるまでは不可能に思えるものだ。)
挑戦する前は不可能に思えることも、
一歩踏み出せば状況は変わるという力強いメッセージです。
■ ヴィクトール・フランクル
「When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.」
(状況を変えられないときは、自分を変えることが求められる。)
無力感を感じるときに大切なのは、
「状況は変えられないけれど、自分の考え方や行動は変えられる」
という気づきです。
■ ヘンリー・フォード
「Whether you think you can, or you think you can’t—you’re right.」
(できると思うか、できないと思うか。どちらも正しい。)
自分がどう思うかが行動を決める。
無力感を感じたときほど、この言葉を思い出したいですね。
名言は、心が折れそうになったときに、再び立ち上がるきっかけをくれる大きな力になります。
どれか一つでも、あなたの心に響く言葉があれば嬉しいです。
挑戦か撤退か?学習的無力感を超えるための判断基準とワイルズの物語

挑戦を続けることは素晴らしい。
羽生善治さんや鴨川会長の言葉は、確かに私たちを勇気づけてくれます。
しかし現実には、どんな努力も必ず報われるとは限らないのも事実です。
むしろ挑戦を続けることで、心身をすり減らし、別の大切なものを失うこともあります。
だからこそ、私たちには常に問うべきことがあります。
それは――
「これは挑戦を続けるべき局面か、それとも戦略的に撤退すべき局面か」
という問いです。
戦略的撤退を考えるべきケース
- 命や健康を危険にさらす挑戦
- 法的・倫理的に問題がある挑戦
- 経済的・時間的コストが致命的に見合わない挑戦
- 自分の価値観や幸福を著しく損ねる挑戦
挑戦が自分や周囲を傷つけるリスクが大きい場合、勇気を出して「撤退する」こともまた重要な選択です。
ワイルズとフェルマーの最終定理に学ぶ判断基準
この「挑戦か撤退か」の判断の良い例が、フェルマーの最終定理を巡るアンドリュー・ワイルズの物語です。
ワイルズは少年の頃、フェルマーの最終定理に憧れ、証明しようと試みました。
しかし成長するにつれ、問題があまりに巨大で、当時の数学では太刀打ちできないことを知り、一度は諦めます。
つまり、戦略的撤退を選んだわけです。
しかしその後、他の数学者たちの研究(フライの楕円曲線や谷山–志村予想)が突破口を開きました。
「この難問も、新たな理論で解けるかもしれない」と道が見えたとき、ワイルズは再び挑戦を決意し、7年間の孤独な研究の末に証明を完成させました。
彼は最初から無謀に突っ走ったのではありません。
解決可能性の兆しが見えた時に再挑戦した。
これが「挑戦すべきか、撤退すべきか」の一つの判断基準だと思います。
最終的には自分の納得がすべて
挑戦するか撤退するか――
最終的にその答えを出すのは自分自身です。
周囲が何と言おうと、
- 自分が納得できるか
- 後悔が少ないか
- 自分にとって意味があるか
を基準に決めるしかありません。
無力感を感じたときは、自分の挑戦が
- 「無謀な突撃」なのか
- 「可能性がある挑戦」なのか
を一度立ち止まって見直してみるのも、大切なことだと思います。
まとめ|学習的無力感は克服できる

記事全体のおさらい
ここまで、学習的無力感について詳しくお話してきました。
最後にポイントを整理しましょう。
✅ 学習的無力感とは?
- 「自分の行動では何も変わらない」と思い込み、挑戦を諦める心理状態
- アメリカの心理学者マーティン・セリグマンが提唱
✅ 原因は?
- 繰り返す失敗体験や否定的な経験
- 子どもの頃の家庭環境(厳格・過保護・無関心など)が大きく影響
✅ 甘えとは違う!
- 甘え → 自分でやらない選択をしている
- 学習的無力感 → 過去の経験から「どうせ無理」と思い込む心のクセ
✅ 大人になってからでも克服できる方法
- 小さな成功体験を積む
- 認知行動療法(CBT)を試す
- 周囲に相談する
- 「変えられること」に目を向ける
✅ 名言に勇気をもらおう
- 羽生善治さん:「挑戦を続けることこそ才能」
- 鴨川会長:「成功した者は皆努力しておる」
- 偉人たちの言葉は無力感に立ち向かう力をくれる
学習的無力感は経験によって身についた心のクセです。
だからこそ、適切な方法を知れば、少しずつ変えていくことができます。
そしてそれは、年齢に関係なく、誰にでも可能なことなのです。
無力感を感じたときにまずできる一歩
もし今、あなたが「何をしてもムダだ」と思っているなら、
まずは 小さな一歩 を踏み出してみてください。
例えば:
- 「今日は5分だけ散歩する」
- 「好きな音楽を1曲聴く」
- 「やりたいことを紙に書き出してみる」
それだけでも、
- 自分が動けた
- 自分で決められた
という感覚が生まれます。
その感覚こそ、学習的無力感を克服する大きな第一歩です。
「報われないかもしれないところで、挑戦を続けることこそが才能」(羽生善治)
どんなに小さくても、行動には必ず意味があります。
未来は、今日の小さな行動から変わり始めます。

