やる気のある自分と、怠けたい自分。優しくしたいのに、イライラしてしまう自分。そんな“複数の自分”に戸惑うこと、ありませんか?
実はその心の葛藤、心理学では「内的家族システム(IFS)」という考え方で説明できます。IFSとは、心の中を“家族のようなチーム”と捉え、怒りや不安などの感情を敵ではなく「守ろうとしている味方」として理解するアプローチです。
この記事では、IFSの基本概念から3つのパーツの仕組み、セルフワークのやり方までをやさしく解説します。
読後には、「自分を責めないで心を整える」ヒントがきっと見つかるはず。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
内的家族システム(IFS)とは?|“心の中の家族”を理解する心理学モデル

IFSの基本概念|人の心は“1人”ではなく“チーム”でできている
私たちは普段、「自分は一人の人間」と思い込んでいます。
しかし実際の心の中には――喜んでいる自分、怒っている自分、怠けたい自分、頑張ろうとする自分など、たくさんの“声”が存在します。
心理学では、このような複数の自己(parts)が共存している状態を「多声的自己(multiplicity)」と呼びます。
内的家族システム(Internal Family Systems/IFS)は、この考えをベースに、「心の中にも家族のような関係性がある」と考える心理モデルです。
IFSによると、心の中はまるでチームや家族のように、それぞれの“パーツ”が異なる役割を担っています。
たとえば――
- 「ミスをしないように必死で管理する自分」
- 「ストレスから逃げようとする自分」
- 「過去の痛みを抱えている自分」
これらはすべて「あなたの一部」であり、対立しているように見えても、実はあなたを守ろうとしている存在なのです。
リチャード・シュワルツが提唱した“心の家族構造”とは
IFSを提唱したのは、アメリカの家族療法家 リチャード・C・シュワルツ(Richard C. Schwartz)。
1980年代、リチャード・シュワルツは、摂食障害のクライアントたちとの関わりを通して、ある重要なことに気づきました。
それは、彼らが自分の心の中を「ひとりの自分」ではなく、いくつもの“部分(パーツ)”や“内なる声”として語っていたということです。
たとえば、
「食べたい自分」と「食べてはいけない自分」
「頑張る自分」と「もう疲れたという自分」
――そんな矛盾する“自分たち”の会話が心の中で起きていたのです。
「人の心も、まるで家族のように複数の“メンバー”が関係し合っているのではないか?」
彼はこの観察から、心の中にも小さな家族(内的家族)が存在するという理論を体系化しました。
IFSは、家族療法の「関係性を見る視点」をそのまま個人の内面に適用したモデルなのです。
シュワルツはこう言います。
「心の中には“悪い部分”など存在しない。すべてのパーツには良い意図がある。」
この考え方が、IFSの核であり、多くの人が「自分を責めずに癒す」方法として注目する理由でもあります。
セルフ(Self)とパーツ(Parts)の関係をわかりやすく解説
IFSでは、心の中の構成を大きく2つに分けます。
| 構成要素 | 説明 | 例え |
|---|---|---|
| セルフ(Self) | 心の中心にある“本来の自分”。落ち着き・思いやり・好奇心を持ち、他のパーツを導くリーダー的存在。 | 家族でいう「穏やかで理解のある親」 |
| パーツ(Parts) | 心の中の“部分的な自分”。それぞれの役割や感情を持ち、時に衝突する。 | 子どもたち・兄弟・親戚のような存在 |
たとえば、仕事で失敗したとき――
- 「もっと頑張れ」と叱るパーツ
- 「疲れた…もうやめたい」と嘆くパーツ
- 「そんな自分を責めてはいけない」と守ろうとするパーツ
これらの“内なる家族”をまとめるのが、セルフ(本来の自分)の役割です。
IFSでは、癒しとは「悪い部分を消すこと」ではなく、セルフがリーダーシップを発揮し、パーツ同士の関係を整えることだと考えます。
IFSの仕組み|心の中にいる3つのパーツを理解しよう

IFSでは、人の心を「セルフ(本来の自分)」と「パーツ(部分的な自分)」の関係として捉えます。
特にパーツは、3つの主要なタイプに分けられ、それぞれが異なる役割で私たちを守ろうとしています。
ここからは、その3つのパーツを分かりやすく紹介していきましょう。
🔹 マネージャー(管理者)|失敗を防ごうと頑張る部分
マネージャーは、あなたの中で「問題を起こさないように」と頑張る部分です。
完璧主義、自己管理、他人への配慮、ルールを守る意識――これらはすべてマネージャーの働きです。
たとえば、
- 「失敗しないように細かく確認する」
- 「周囲に迷惑をかけないよう我慢する」
- 「怒りを見せたら嫌われる」と感情を抑える
こうした行動は、実はあなたの心の安全を守るためのもの。
マネージャーは、あなたが傷つかないように、常に前線で“防御”しているのです。
ただし、頑張りすぎると「心の緊張が続く」「息が詰まる」などの弊害も生まれます。
IFSでは、このマネージャーを責めず、感謝と理解の姿勢で接することが重要です。
🔸 ファイアファイター(消防士)|感情を抑え込もうとする部分
マネージャーが「予防担当」なら、ファイアファイターは「緊急対応担当」です。
つまり、感情が爆発しそうになった時に「火消し役」として動きます。
たとえば、
- ストレスが限界になって暴飲暴食してしまう
- 怒鳴ってしまう、SNSで反論してしまう
- ゲームや動画に没頭して現実逃避する
これらの行動は「悪い癖」ではなく、ファイアファイターが苦しみからあなたを守ろうとしている反応です。
「痛みを感じないようにする」ことが目的なので、短期的には楽になりますが、根本解決には至りません。
IFSでは、ファイアファイターにも「守りたい意図」があると理解し、その背後にある感情(恐れ・悲しみなど)に気づいていくことを大切にします。
🩵 エグザイル(追放された子ども)|心の奥に隠れた傷ついた部分
エグザイル(Exile)とは、心の中で「追い出された存在」。
それは、過去のつらい経験やトラウマ、抑え込んだ感情を抱える“内なる子ども”です。
たとえば、
- 「誰にも必要とされなかった」記憶
- 「親に怒られた」恐怖や悲しみ
- 「恥ずかしい思いをした」トラウマ的記憶
これらを抱えたパーツは、痛みを再体験しないように心の奥に閉じ込められます。
マネージャーやファイアファイターは、このエグザイルが表に出ないように働いているのです。
IFSの癒しとは、セルフ(本来の自分)がこのエグザイルに優しく寄り添い、
「もう隠れなくても大丈夫だよ」と伝えるプロセス。
それにより、心の統合(インテグレーション)が進んでいきます。
それぞれのパーツは“悪者”ではない|すべての部分にはポジティブな意図がある
IFSの最大の特徴は、どのパーツも「敵ではない」という考え方です。
怒り、恐れ、逃避――どんな反応にもあなたを守るための理由があります。
| パーツ | 役割 | 隠れた意図 |
|---|---|---|
| マネージャー | 問題を防ぐ | 失敗や拒絶から守る |
| ファイアファイター | 感情を抑える | 苦しみを感じないようにする |
| エグザイル | 痛みを抱える | 本当の自分の感情を守る |
IFSでは、これらのパーツを「コントロール」するのではなく、理解し、対話し、信頼関係を築くことが目的です。
そうして初めて、セルフ(本来の自分)がリーダーとして心全体を導けるようになるのです。
IFSは、心の複雑な動きを「良い」「悪い」で分けずに、すべての自分を理解しようとする心理学。
この姿勢こそが、自己否定をやわらげ、心の調和を取り戻す第一歩となります。
IFSが注目される理由|“自分を責めずに癒す”新しい心理アプローチ
IFS(内的家族システム)は、ここ数年で急速に注目を集めています。
その理由は、「自分の中のネガティブな部分を“悪者扱いしない”」という、これまでの心理療法とは違う温かいアプローチにあります。
ここでは、IFSがどのように従来の心理学と異なり、なぜ多くの人が「深く癒される」と感じるのかを見ていきましょう。
従来の治療との違い|パーツを「変える」より「理解する」
多くの心理療法では、問題の原因を「修正する」「なくす」ことを目標にしていました。
たとえば――
- 「怒りを抑える練習をしよう」
- 「ネガティブ思考をポジティブに変えよう」
といったアプローチです。
一方、IFSは“変える”より“理解する”ことを重視します。
怒りや恐れの感情を「悪い」と判断せず、
「その怒りは、何を守ろうとしているのだろう?」
と優しく問いかけます。
たとえば「すぐにイライラする自分」も、実は心を守る“パーツ”が反応しているだけ。
このようにIFSでは、「どんな反応にも意味がある」と考え、感情の奥にある“守りの意図”を見つけることから癒しが始まります。
自己否定ではなく“非病理化”を重視するアプローチ
IFSの基本姿勢は「すべてのパーツには良い意図がある」。
これはつまり、「怒る自分も、怠ける自分も、全部“自分の味方”である」という考え方です。
心理学の専門用語で言うと、これは非病理化(non-pathologizing)アプローチ。
「この感情は悪い」「この性格はダメ」という病理的ラベルを貼らず、
「それも自分の中で生きる大切な一部」と認める
ことが前提になります。
この視点は、自己批判や罪悪感で苦しんできた人にとって特に効果的。
「否定ではなく理解」を軸にしているため、心が徐々に安心を取り戻していきます。
マインドフルネスやセルフコンパッションとの共通点
IFSは、近年注目されているマインドフルネス(気づきの心理学)や
セルフ・コンパッション(自分への思いやり)と深くつながっています。
共通するのは、「感情を抑えずに観察し、受け入れる」という態度。
| 比較項目 | IFS | マインドフルネス/セルフコンパッション |
|---|---|---|
| 視点 | 「自分の中の複数のパーツを理解する」 | 「今の自分に気づき、批判せず受け入れる」 |
| 目的 | セルフ(本来の自分)がリーダーになる | 苦しみを受け入れ、心の安定を取り戻す |
| 手法 | 内的対話・パーツとのコミュニケーション | 呼吸瞑想・自己への優しい声かけ |
つまりIFSは、マインドフルネスの「今ここにある気づき」をさらに発展させ、
「その気づきを通して心の“家族”を整える」実践的心理モデルなのです。


トラウマ治療・セルフケアの現場で広がるIFSの応用
IFSは現在、トラウマ治療・依存症回復・カウンセリング・コーチングなど、幅広い分野で導入されています。
その理由は、以下の3点です。
- 再現性が高く安全
感情を直接掘り起こすのではなく、「パーツを通じて間接的に癒す」ため、フラッシュバックを起こしにくい。 - セルフケアとして実践できる
専門家の支援がなくても、IFSのプロセス(気づく→観察する→対話する)を日常生活に応用できる。 - 自己受容を促す
「どんな自分も否定しない」という姿勢が、自己肯定感や回復力(レジリエンス)を高める。
たとえば、ストレスが高いときに「怒っている自分」を排除するのではなく、
「怒っている部分に何が起きているの?」と優しく話しかける――
これがIFS的なセルフケアです。
心の中の“複数の自分”と仲良くなるステップ|IFSセルフワークのやり方
IFS(内的家族システム)の魅力は、専門家でなくても自分で実践できるセルフワークがあることです。
難しい理論を知らなくても、IFSの基本的な流れを理解すれば、心の中で起きる葛藤や不安を「やさしく整理」できるようになります。
ここでは、IFSの代表的な実践法「6Fステップ(Find・Focus・Feel・Befriend・Fear・Free)」のうち、初心者でも取り組みやすい4つのステップを紹介します。
① 気づく(Find)|今どんな感情の“自分”が出ている?

最初のステップは、「今、自分の中でどんなパーツが反応しているかに気づく」ことです。
たとえば、次のような場面を想像してみてください。
- 上司に注意されてイラッとした
- SNSで誰かの成功を見て落ち込んだ
- 失敗して「自分はダメだ」と感じた
そのとき心の中には、「怒っている自分」「落ち込んでいる自分」「責める自分」など、複数の“声”が存在しています。
IFSでは、まずそれを否定せずにただ気づくだけでOKです。
「ああ、今“怒ってる自分”が出てるんだな」
「“比べて落ち込む自分”が出てきたな」
この“気づき”が、セルフ(本来の自分)がリーダーシップを取り戻す第一歩になります。
② 観察する(Focus)|感情を切り離して眺める
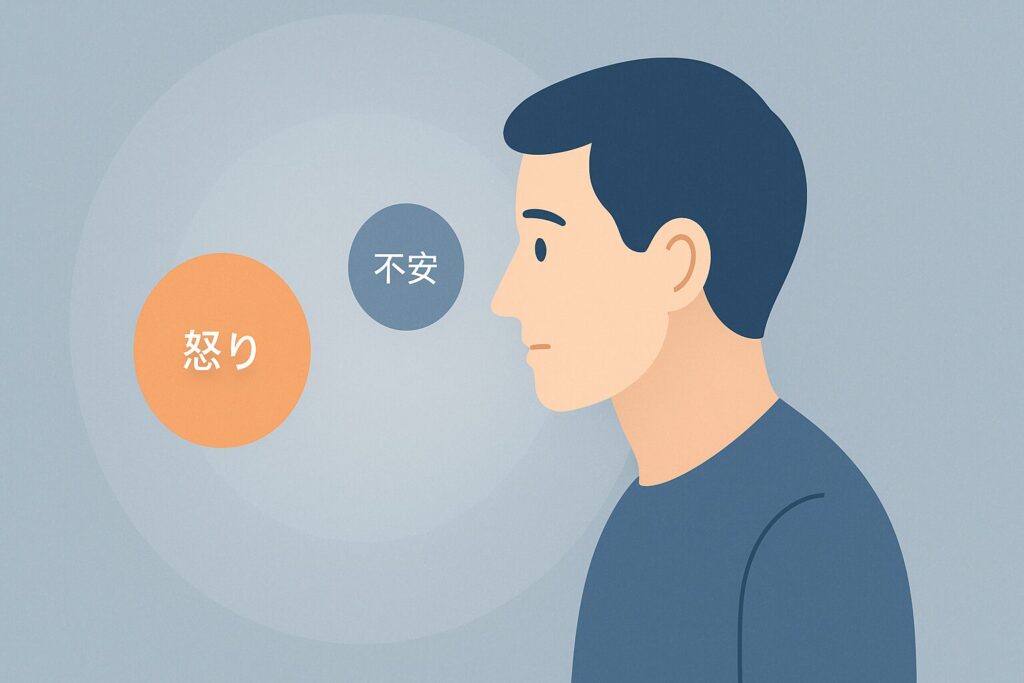
次に行うのは、「その感情を少し距離をとって観察する」ことです。
IFSでは、これを“セルフとパーツの分離”と呼びます。
たとえば、次のように意識を変えてみましょう。
「私は怒っている」→「怒っている“部分”がある」
「私は不安だ」→「不安を感じている“自分の一部”がいる」
この言い換えをするだけで、感情に飲み込まれにくくなります。
まるで、映画の登場人物を少し離れた席から見ているような感覚です。
ここで大切なのは、評価しないこと。
「良い」「悪い」と判断せず、「ただ観察する」。
それが、心のスペース(余白)を生み出します。
③ 対話する(Befriend)|そのパーツに優しく話しかける

感情を観察できたら、次はそのパーツにやさしく声をかける段階です。
IFSでは「内的対話」をとても大切にします。
たとえば――
「怒っているんだね。何がそんなに嫌だったの?」
「不安な気持ちを教えてくれてありがとう」
「あなたは何を守ろうとしているの?」
このように、自分の一部を“他人のように扱う”ことで、心の緊張がゆるんでいきます。
パーツは「分かってもらえた」と感じた瞬間に、防衛反応を弱めてくれるのです。
ポイントは、正しい答えを探さないこと。
目的は「理解」ではなく「関係を築く」こと。
IFSでは、「怒り」や「不安」を“心の中の大切なメンバー”として扱います。
④ 解放する(Free)|過去の痛みを手放していくプロセス
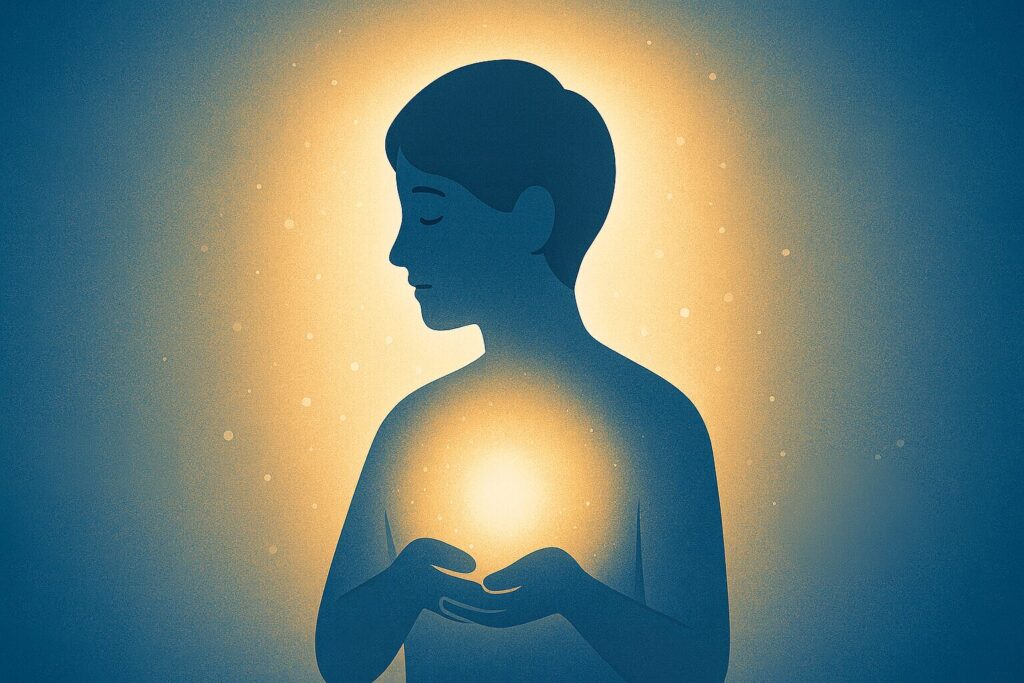
パーツとの信頼関係が生まれると、その奥から“エグザイル(追放された傷ついた自分)”が顔を出すことがあります。
それは、長年心の奥にしまい込んでいた感情――悲しみ、恐れ、孤独など。
IFSの癒しの瞬間は、セルフ(本来の自分)がその傷ついたパーツに語りかけるときです。
「もう大丈夫だよ」
「あなたの痛みをわかっているよ」
この“理解”と“安心”のメッセージによって、パーツが抱えていた負担(burden)が少しずつ解放されていきます。
すると、不安や怒りが和らぎ、心に穏やかな統合感が戻ってくるのです。
⚠️ 注意点|無理に掘り下げず“安全な距離”を保つこと
IFSのセルフワークはとても効果的ですが、注意すべきポイントもあります。
- 過去のトラウマが強い場合は専門家のサポートを受ける
- 感情が激しくなったら、一度「今は離れよう」と距離をとる
- 無理に「癒そう」とせず、“理解するだけ”で十分
IFSは「問題を解決する技術」ではなく、「自分と仲良くなる練習」です。
自分の中のパーツたちと安全な距離を保ちながら、少しずつ信頼を築くことが、癒しの本質なのです。
IFSと他の心理モデルの違い|対話的自己・エゴステイト療法との比較
IFS(内的家族システム)は、単独の理論というよりも、「自己の中に複数の声がある」という概念を発展させた心理モデルです。
そのため、他の理論――たとえば対話的自己理論やエゴステイト療法とも深い関係があります。
ここでは、それぞれのモデルとIFSの違い・共通点を整理しながら、「なぜIFSが現代的で柔軟なアプローチなのか」を解説します。
対話的自己理論との共通点|“複数の声を持つ自己”という視点
オランダの心理学者ハーミンス(Hubert Hermans)が提唱した対話的自己理論(Dialogical Self Theory)では、
人の心は「一人の自己」ではなく、複数の“内的ポジション(立場)”が対話する社会のような構造を持つとされています。
たとえば、
- 「仕事での自分」
- 「家族の中の自分」
- 「理想を追う自分」
- 「弱音を吐きたい自分」
これらが、心の中で会話をしている――というのが対話的自己の考え方です。
IFSもこの点で非常に近く、心の中に「パーツ(parts)」が存在し、それぞれが自分なりの声や意図を持っていると考えます。
両者の共通点は、自己を“多声的存在(polyphonic self)”として捉えることです。
ただし違いは、IFSはその“対話”を癒しのプロセスとして構造化した点にあります。
対話的自己が「自己を理解する理論」だとすれば、IFSはそれを「自己を癒す実践」にまで発展させたモデルといえます。

エゴステイト療法との違い|“部分を癒す”から“調和させる”へ
もう一つ、IFSとしばしば比較されるのがエゴステイト療法(Ego State Therapy)です。
これは、ジョン・G・ワトキンスとヘレン・ワトキンスによって提唱された心理療法で、
「人の心は複数の“自我状態(Ego States)”から成り立つ」という前提を持ちます。
たとえば、
- 子どものように甘えたい“自我状態”
- 完璧を求める“管理的自我状態”
- 他人を助けたい“世話焼き自我状態”
これらの“自我”がぶつかることで葛藤やストレスが生まれるというのが、エゴステイト療法の基本的な考えです。
IFSとの主な違いは、目的とアプローチのニュアンスにあります。
| 比較項目 | エゴステイト療法 | IFS(内的家族システム) |
|---|---|---|
| 前提 | 心は複数の自我状態で構成される | 心は複数の“パーツ”が共存する家族システム |
| アプローチ | 問題のある自我を修正・統合 | すべてのパーツを理解・調和させる |
| 目的 | 内的なバランスを回復 | セルフ(本来の自分)がリーダーとなる |
| スタンス | 「一部を治す」 | 「全体を受け入れる」 |
IFSは、「一部を変える」よりも「全体を調和させる」方向に重きを置いています。
つまり、「問題のある部分」を排除するのではなく、そのパーツの意図を理解し、セルフのもとで再びチームに戻すことが目的なのです。
IFSが「心の社会モデル」と呼ばれる理由
IFSがユニークなのは、心を“システム(system)”として捉えている点です。
つまり、心の中の一つひとつのパーツは独立した個性を持ちながらも、全体として相互に影響し合う存在だということ。
この発想は、社会システムや家族システム理論(ボーエンなど)と共通しています。
たとえば、家族の一人が強くストレスを抱えると、他の家族も無意識にバランスを取ろうとするように、
心の中でも「あるパーツが苦しむと、別のパーツが助けに入る」――そんな連鎖反応が起こります。
IFSではこの構造を「心の家族システム」として捉え、セルフが“調停者”となって内部の調和を保つことを目的としています。
このモデルが現代の心理療法の中でも評価されるのは、
- 社会心理学や対人関係論と親和性が高い
- “個人”よりも“関係性”を重視する
という、統合的な視点を持っているからです。
IFSを日常に活かす方法|自己理解・人間関係・ビジネスにも応用できる

IFS(内的家族システム)は、心理療法としてだけでなく、日常生活のあらゆる場面に応用できる自己理解のフレームワークです。
ここでは、感情のセルフケアから人間関係、ビジネスや創作の分野まで、IFS的な視点をどのように活かせるかを具体的に見ていきましょう。
イライラ・不安・罪悪感に気づいたら“そのパーツと会話する”
たとえば、次のような瞬間を思い出してみてください。
- 「どうしてもイライラが止まらない」
- 「人の目が気になって不安になる」
- 「少し休むだけで罪悪感が湧く」
こうしたとき、多くの人は「我慢しよう」「気のせいだ」と感情を抑え込みます。
しかしIFSでは、それを“内なるパーツからのメッセージ”として受け取ります。
たとえば――
「イライラしている部分は、どんなことを守ろうとしている?」
「罪悪感を感じる部分は、何を恐れている?」
と、まるで友人に話しかけるように内なる声に耳を傾けるのです。
すると、感情の裏側にある「本当の望み」や「守りたい気持ち」が見えてきます。
このようにIFSは、感情を敵ではなく、味方として扱うセルフケアの方法でもあります。
チームマネジメントやリーダーシップにも役立つセルフリーダーシップ理論
IFSの考え方は、ビジネスの現場でも注目されています。
リーダーやマネージャーは、チームを導く前にまず自分の内なるチーム(内的家族)を整えることが大切だからです。
たとえば、
- 「焦って成果を出そうとする自分」
- 「失敗を恐れて決断を避ける自分」
- 「人に嫌われたくない自分」
これらの“内なるメンバー”を意識し、それぞれの声を理解することで、感情的な衝動に流されにくくなります。
結果として、
- 冷静な判断ができる
- 他者に寛容になれる
- 組織の多様な意見を調和させられる
IFS的に言えば、「セルフ(本来の自分)」がリーダーとして内外の調和を保つ状態です。
これは、近年注目されているセルフリーダーシップ理論や心理的安全性の高い組織づくりにも通じます。
創作・自己表現における「内なる声」との協働
IFSは、アート・小説・音楽・デザインなど、創作活動にも応用できる心理モデルです。
創作の過程では、次のような“内的対話”がよく起こります。
- 「もっと完璧にしないと」
- 「こんなの誰も見てくれない」
- 「それでも描きたい、表現したい」
このとき、IFSの視点を取り入れると、
「完璧を求める自分」と「自由に表現したい自分」が同じチームにいるだけだ
と気づけます。
どちらの声も「作品を良くしたい」「自分を守りたい」という共通の目的を持っているのです。
この気づきがあると、創作の苦しみが和らぎ、
“内なる衝突”を創造のエネルギーに変えることができます。
まとめ|“どの自分も味方にできる”と心が軽くなる

IFS(内的家族システム)の最大のメッセージは、
「どんな自分も、あなたを守ろうとしている」
ということです。
怒り・不安・怠け・嫉妬――どんな感情も、すべてはあなたを守るために生まれた“内なる家族(パーツ)”です。
それを排除したり、無理に変えようとするのではなく、理解し、受け入れ、調和させる。
これがIFSの核心です。
内的家族システムは「自分を治す」より「理解する」心理学
IFSの目的は、「問題を解決する」ことではなく、自分の内側との関係を築くことです。
つまり、IFSは「心を修理するツール」ではなく、心の関係性を整えるアプローチ。
IFSは“治療”というよりも、“共存と理解の心理学”。
自分を治すのではなく、自分と仲直りする――その先に、自然な回復が生まれます。
“悪い部分”は存在しないというIFSのメッセージ
IFSの創始者リチャード・シュワルツは言います。
「すべてのパーツにはポジティブな意図がある。悪い部分など一つもない。」
たとえば――
- 「失敗を恐れる自分」は、あなたを守るために慎重になっている
- 「怒っている自分」は、不当な扱いに気づかせようとしている
- 「怠ける自分」は、休息が必要だと訴えている
どれも“敵”ではなく、“大切なメッセンジャー”です。
IFSを実践するうちに、人は「心の中で対立していた部分が、実は協力し合える存在だった」と気づくようになります。
その瞬間、心の中に静かな安心感が戻ってくるのです。
今日からできる一歩|「今どんな自分が出てる?」と問いかけてみよう
IFSは、特別な時間や道具がなくても始められます。
最もシンプルな実践法は、日常の中で「今どんな自分が出てる?」と自分に質問すること。
たとえば――
- 「焦ってる自分がいるな」
- 「守りたい自分が出てる」
- 「不安な自分も、頑張ってるんだな」
この一言の問いかけで、セルフ(本来の自分)がリーダーシップを取り戻します。
感情に支配されるのではなく、感情と対話する自分に戻れるのです。
そして、そうした小さな理解の積み重ねが、
- 自己否定の減少
- 他人への寛容さ
- 心の安定と回復力(レジリエンス)
へとつながっていきます。


