「どうして大人になってから、自分に自信が持てないんだろう…?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
仕事で失敗するとすぐに落ち込む、人からの評価に振り回される、自分を好きになれない——。
それ、「自己肯定感の低さ」が関係しているかもしれません。
この記事では、心理学の知見をもとに「大人が自己肯定感を育てる3つのステップ」をわかりやすく解説します。
“ありのままの自分を受け入れる”感覚ってどういうこと?
「安全基地」って何?
そんな疑問にも丁寧にお答えします。
後半では、今日からできる簡単な習慣やおすすめ書籍も紹介していますので、
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
なぜ大人になってから自己肯定感が低いと感じるのか

自己肯定感とは、「ありのままの自分に価値があると思える感覚」のこと。
でも、大人になってから「なんだか自分に自信が持てない」「人と比べて落ち込む」「何をしてもうまくいかない気がする」と感じる人は少なくありません。
それは単なる性格の問題ではなく、心理的な背景や過去の経験が大きく関係しています。
この章では、自己肯定感の低さに気づくきっかけや、深層心理に隠れた原因を3つの視点から解説します。
①大人になってから気づく「自己肯定感の低さ」の正体
子どもの頃は「自分に自信がない」とはっきり自覚することは少ないもの。
しかし社会に出て、仕事や人間関係、恋愛や家族といった場面で挫折を経験すると、「自分には価値がないのでは?」という感覚がじわじわと現れてきます。
特にこんなシーンで気づく人が多いです:
- 仕事でミスをしたとき、必要以上に落ち込む
- 褒められても「たまたま」「そんなことない」と受け取れない
- 他人の成功を素直に喜べず、自分と比較してしまう
これらはすべて、自分を肯定する力(自己肯定感)が足りていないサインともいえます。
②子ども時代の家庭環境や親との関係が影響する理由
心理学では、自己肯定感は幼少期の養育者との関係(特に親)によって形成されると考えられています。
心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した「愛着理論」では、親からの安定した愛情=“安全基地”があることで、子どもは安心して外の世界に挑戦でき、自分の存在に価値を感じられるようになるとされます。
反対に…
- 親の期待に応えないと愛されないと思っていた
- ミスをすると叱られすぎたり、否定されたりした
- 家庭内で安心できる居場所がなかった
こうした体験は、「自分はダメだ」「人に迷惑をかける存在だ」という思い込みにつながりやすく、大人になっても無意識に自分を責める傾向を引き起こします。
③「自分はダメだ」と思ってしまう習慣の心理的メカニズム
「どうせ自分なんて」「また失敗するかも」――
こうした思考は、認知のクセとも呼ばれます。
認知行動療法では、私たちは出来事そのものではなく、それをどう解釈するか(思考パターン)によって感情や行動が決まるとされます。
たとえば:
- 他人に挨拶を返されなかった → 「嫌われたに違いない」と考える
- 仕事で注意された → 「自分は役立たずだ」と思い込む
こうしたネガティブな自己評価の繰り返しが、自己肯定感をさらに下げるループをつくります。
でも、これは「性格」ではなく、「習慣」です。
つまり、見方や行動を変えることで書き換えることが可能だということです。

心理学的にみる「自己肯定感」とは?構造と正体

「自己肯定感」と聞くと、「ポジティブな性格」や「自信があること」と思いがちですが、実はそれだけではありません。
心理学的にはもっと多面的で深い概念として捉えられています。
この章では、自己肯定感を正しく理解するために役立つ3つの視点を紹介します。
①自己肯定感は6つの要素で構成されている(中島輝氏のモデル)
自己肯定感を6つの「感」に分けて体系化したのが、心理カウンセラー中島輝氏のモデルです。
以下の6つがバランスよく整うことで、安定した自己肯定感が育つとされています:
- 自己受容感:ありのままの自分を受け入れる
- 自己信頼感:自分を信じることができる
- 自己効力感:自分はできるという感覚
- 自己決定感:自分の人生を自分で選んでいる感覚
- 自己有用感:誰かの役に立てていると感じる
- 自己尊重感:自分には価値があると感じる
これらの要素は相互に影響し合っていて、一つが欠けると他も不安定になりやすいのが特徴です。
つまり、自己肯定感は「1つの感情」ではなく、複数の心理的な土台から成る“心の体力”のようなものなのです。
③愛着理論と「安全基地」:ボウルビィの視点
自己肯定感の源流をたどると、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した「愛着理論」に行き着きます。
この理論では、乳幼児期における養育者との関係性が、のちの自己肯定感に深く関わるとされています。
ボウルビィは、子どもにとって親(または養育者)が「安全基地」であることの重要性を強調しました。
つまり、
- 傷ついたときに安心して戻れる場所
- 挑戦したいときに背中を押してくれる存在
このような関係が築けた子どもは、「自分は大丈夫」「誰かに守られている」という深い安心感=基本的信頼感を持てるようになります。
この信頼感こそが、大人になっても自分を信じられる土台=自己肯定感へとつながるのです。

③「高める」のではなく「高まる」感覚とは
ここで大切なのが、「自己肯定感を高めよう」と頑張るほど、逆に苦しくなることがあるという点です。
なぜなら、意識的に「自分をもっと好きにならなきゃ」と努力するほど、「やっぱり今の自分はダメなんだ」と否定から始まってしまうことが多いからです。
ポイントは、
- 自分で無理にコントロールしようとしない
- 小さな体験や日常の工夫の中で、自然と湧き上がる感覚を大切にする
という姿勢です。
つまり、自己肯定感は「トレーニングでつくる筋肉」というより、「丁寧に育てる植物」のようなもの。
焦らず、自然に“高まっていく”感覚を持つことが、長く続く自己肯定感の土台になります。
次の章では、こうした心理学的な理解をふまえて、実際にどうすれば自己肯定感が高まっていくのか?
その「3つのステップ」を解説していきます。

大人になってから自己肯定感を高める3つの心理学的ステップ

ここでは、自己肯定感を高めるための3つのステップを心理学的に紹介します。
この3ステップは、前述した「6つの感」の中でも特に重要な要素であり、段階的に積み上げることが可能なプロセスです。
「根拠のない自信」を持とうとするのではなく、地に足のついた心の土台を育てるためのステップです。
ステップ① 自己受容感を育てる:ありのままの自分を認める
まず最初の土台は、「自己受容感」です。
これは、今の自分を「良い」「悪い」で判断せずに、そのままを認める力です。
✅ 自己受容感を育てるヒント:
- 「こんな自分もOK」と心の中でつぶやく
- 失敗や弱さを責めず、「人間だもの」と受け入れる
- 他人と比較する前に、「自分は何を大切にしたいか?」を問い直す
たとえば、「緊張して声が震える自分はダメ」と思うのではなく、
「緊張するのは、それだけ大切に思っているからだ」と意味づけを変えることで、受容が深まります。

ステップ② 自尊心を育てる:自分の価値を肯定する
次に重要なのが「自己尊重感=自尊心」です。
これは、「自分は存在しているだけで価値がある」と思える感覚です。
大人になると、仕事の成果や評価に依存しがちですが、それに関係なく“自分の価値は揺るがない”という意識が大切です。
✅ 自尊心を育てる方法:
- 過去の成功体験を思い出して、自分をねぎらう
- 「誰かの役に立った」経験を振り返る
- 自分の良いところを毎日1つ書き出す
小さなことでも構いません。
「昨日より少し丁寧に挨拶できた」「ご飯を作った」でも、自分を肯定する材料になります。

ステップ③ 自己効力感を高める:小さな成功体験を積み重ねる
最後のステップは、「自己効力感」、つまり「自分にはできる」という実感を育てることです。
これはバンデューラという心理学者が提唱した理論で、行動を継続するうえで重要な心理的要因とされています。
✅ 自己効力感を高めるコツ:
- すぐにできる小さな行動目標を立てる(例:5分間の片付け)
- 結果より「行動したこと」を褒める
- 行動できたことを記録して見える化する
「ブログを1本書く」よりも、「PCを開いて見出しを1つ書く」など、ハードルを極端に下げることで達成感を得やすくなります。
次の章では、やりがちな「逆効果な自己肯定感アップ法」について紹介します。

無理にポジティブになるのは逆効果?間違った自己肯定感の高め方

自己肯定感を高めたいと思うあまり、間違ったアプローチをしてしまう人は少なくありません。
特に、「前向きでいよう」「ポジティブに考えよう」とする努力が、かえって心を追い詰める原因になることもあります。
ここでは、よくある勘違いと、正しい向き合い方について解説します。
「前向きに考えよう」とするほどつらくなる理由
「もっとポジティブにならなきゃ」と自分に言い聞かせたこと、ありませんか?
実はこの思考法には、ネガティブな感情を“否定”してしまうリスクがあります。
人間の脳は、否定されると反発する性質があるため、
「不安になるな」と言われるほど、逆に不安が強くなることがあります。
これは「思考抑制の逆説効果(白熊効果)」と呼ばれる心理現象で、
感情を押さえ込もうとすると、かえってその感情が頭の中で強調されてしまうのです。
つまり、「感情にフタをする」ほど、心の負担は大きくなってしまいます。
自己肯定感が「高まる」人の特徴とは?
自己肯定感が自然に高まる人には、共通する特徴があります。
それは、
- 無理に自分を変えようとしない
- ネガティブな感情があっても「それでOK」と思える
- 完璧を目指さず、小さな変化を喜べる
つまり、「ありのままの感情」と付き合える柔軟さを持っているのです。
心理学では、これを「ネガティブ・ケイパビリティ(不確実さに耐える力)」とも呼びます。
「すぐ答えを出さなくてもいい」「解決できなくてもいい」という余白を持つことで、心の自由度が増し、自己肯定感が“高まっていく”のです。

自分以外の力も借りてOK:環境・人間関係の整え方
自己肯定感は「1人でなんとかするもの」と思われがちですが、実は外的な環境も非常に大きく影響します。
たとえば:
- 居心地のいい場所に身を置く(お気に入りのカフェ、片付いた部屋など)
- 否定しない人と話す(共感してくれる友人やカウンセラー)
- 無理なく感情を出せる時間をつくる(ひとりの時間、ジャーナリングなど)
心理学では、こうした「外部の支え」を自己肯定感の“安全基地”として捉えます。
大人になってからこそ、「頼れる環境」を意識的につくることで、自然に自信が育っていくのです。
無理に頑張るのではなく、がんばらなくても大丈夫な環境づくりが、自己肯定感を高める近道になります。
次は、具体的な「日常の習慣」からアプローチする方法を紹介します。
今日からできる!自己肯定感が自然に高まる具体的な習慣
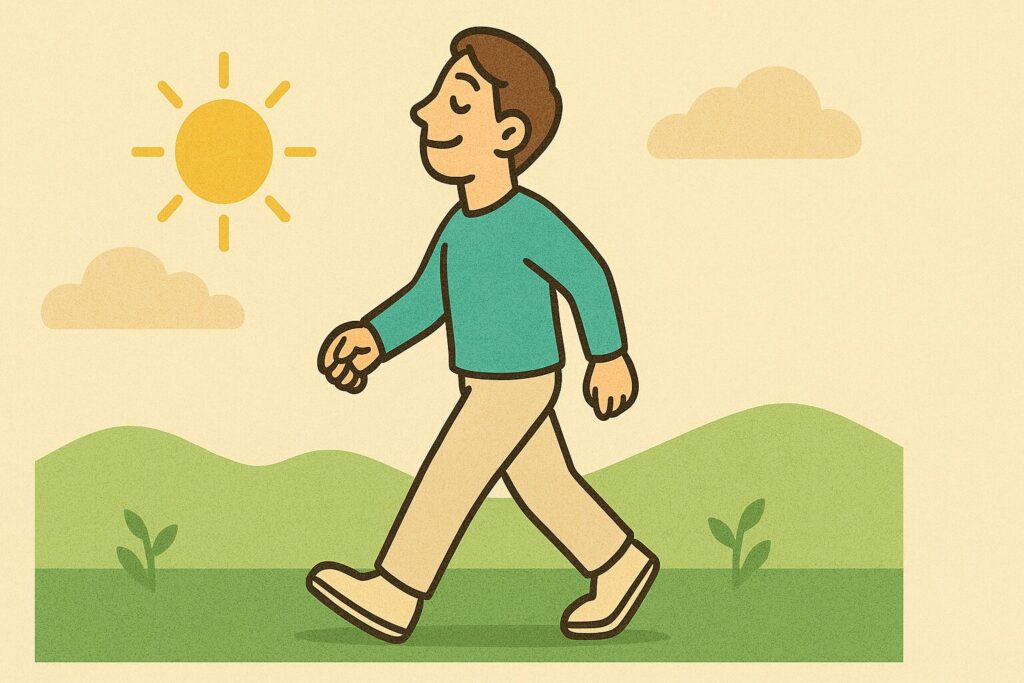
自己肯定感は「高めよう」と気合を入れるよりも、日常の中で自然に育つ環境と行動が大切です。
ここでは、初心者でもすぐに取り入れやすく、心理学的にも効果がある具体的な習慣をご紹介します。
自己肯定感トレーニングの例:ほめ日記・イメージワーク
① ほめ日記
1日の終わりに、自分をほめることを3つ書き出すだけのシンプルなワークです。
例:
- 朝きちんと起きられた
- 苦手な人に挨拶できた
- ご飯をちゃんと作った
小さなことでもいいので、できたこと・がんばったことを記録しましょう。
「自分もけっこうやれてるかも」と実感が積み重なり、自尊心が育っていきます。
② イメージワーク
目を閉じて、「安心できる場所」「応援してくれる人」「うまくいった場面」などを思い浮かべるワークです。
脳は現実と想像の区別が苦手なため、ポジティブなイメージを繰り返すと、実際の感情にもよい影響を与えます。
環境を整える:片付け・香り・音・色などの五感刺激
五感を通じた環境の変化は、気分の安定や自己肯定感の向上に直結します。
- 視覚: 散らかった部屋を少しだけ整える、好きな色の小物を取り入れる
- 聴覚: リラックスできる音楽や自然音を流す
- 嗅覚: アロマや香りの良い入浴剤で「安心感」を高める
- 触覚: 肌ざわりのいい服や寝具を使う
- 味覚: 自分のために丁寧に作った食事を味わう
「快」を感じる時間が増えるほど、自分の感情や行動に対する肯定感も自然に増していきます。
身体を動かす:セルフハグ・ウォーキングなど
心と身体はつながっているため、身体へのアプローチも非常に効果的です。
- セルフハグ: 両腕で自分をギュッと抱きしめ、「よくがんばってるよ」と心の中で声をかけてみましょう
- ウォーキング: 外の空気を吸って、リズムよく歩くことで、思考が整理され心が落ち着きます
- ストレッチや深呼吸: 緊張した筋肉や呼吸をゆるめることで、副交感神経が優位になり、安心感を得られます
これらの行動は自分へのやさしさ=セルフコンパッションにつながり、結果として自己肯定感が“高まる”土台になります。
まとめ|大人でも遅くない。自己肯定感は今から育てられる

自己肯定感が低いと感じていても、あきらめる必要はありません。
むしろ大人になった今こそ、自分の手で自己肯定感を育てるチャンスです。
まずは「否定しないこと」から始めよう
自己肯定感を高める第一歩は、今の自分を否定しないことです。
「こんな自分じゃダメだ」と思ってしまうと、心が委縮して成長の余地も狭まってしまいます。
ですが、「今の自分でもいい」「そんな自分もここまで生きてきた」と少しでも受け入れることで、内面に安心感と余裕が生まれます。
自己否定の癖に気づいたら、「そう思ってしまう自分も悪くない」と一言つぶやくだけでも十分です。


小さな一歩で「自分は大丈夫」と感じる経験を重ねていこう
自己肯定感は、一発逆転のように一気に高まるものではありません。
毎日少しずつ、「自分にできたこと」「頑張ったこと」「乗り越えたこと」に目を向け、“小さな成功体験”を積み重ねていくことがポイントです。
たとえば:
- 朝起きられた
- 人に挨拶できた
- 片づけを5分できた
- 書こうと思っていたメモを1行だけ書いた
…など、ほんの些細なことでもOKです。
その積み重ねが、「自分は意外とやれる」「自分は大丈夫」という自己効力感につながり、やがて自己肯定感の土台となります。
人生のどのタイミングでも、自己肯定感は育て直せます。
今のあなたのままでも、少しずつ変わっていけます。
焦らず、比べず、まずは今日の自分を優しく見守るところから始めてみましょう。
自己肯定感をもっと深く学びたい人へ|おすすめの本・アプリ・サービス
「自己肯定感を高めたい」「自分をもっと受け入れたい」――
そんな前向きな気持ちが芽生えた方へ、これからの一歩に役立つリソースをご紹介します。
自分に合った方法を見つけることで、心の土台は少しずつ整っていきます。
無理なく、楽しく、続けられるものを探してみてくださいね。
✅ 書籍(じっくり読みたい人向け)
- 『自己肯定感の教科書』(中島輝)
→ 自己肯定感を「6つの感」で分かりやすく解説。ワークも豊富で実践向き。 - 『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健)
→ 他人の評価から自由になり、「自分の人生を生きる」勇気を与えてくれる一冊。
✅ アプリ(毎日の習慣に取り入れたい人へ)
- Awarefy
 (アウェアファイ)
(アウェアファイ)
→ 認知行動療法に基づいたセルフケアアプリ。感情記録や思考整理が簡単にできます。
✅ Webサイト・サービス(相談したい・知識を深めたい人へ)
- kimochi

→ オンラインカウンセリングサービス。話すことで自分を整理したい方におすすめ。


