「報酬をもらったのに、なぜかやる気が続かない…」そんな経験、ありませんか?
勉強にご褒美をつけたら逆にやる気をなくしたり、趣味がお金のための作業になって楽しめなくなったり──。実はそれ、アンダーマイニング効果という心理現象が関係しています。
この記事では、アンダーマイニング効果の意味や仕組みをやさしく解説しながら、実際に起こりやすい具体例や、逆効果にならない報酬の使い方もご紹介します。さらに、やる気を持続させるための実践的なアドバイスも盛り込んでいます。
モチベーションを上手に保ちたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
【アンダーマイニング効果とは?|外発的報酬でやる気が下がる現象】

「前は夢中でやっていたのに、報酬が発生したら急にやる気がなくなった…」
そんな経験はありませんか?
これは心理学で「アンダーマイニング効果(undermining effect)」と呼ばれる現象の一例です。
■ アンダーマイニング効果の定義と心理学的背景
アンダーマイニング効果とは、もともと自発的に楽しんでいた行動に報酬が加わることで、内発的なやる気(モチベーション)が下がってしまう心理現象のことです。
たとえば、絵を描くのが大好きな子どもがいたとします。
その子に「絵を描いたらお小遣いをあげる」と言い続けると、やがて「お小遣いのために描く」になってしまい、絵そのものを楽しむ気持ちが薄れてしまうのです。
この現象は、1970年代に心理学者エドワード・デシ(Edward Deci)の実験により初めて科学的に示されました。
実験では、学生にパズルを解く活動をさせたところ、「報酬を与えられたグループ」は報酬がなくなった後の継続率が大きく下がったのです。
■ 外発的動機付けと内発的動機付けの違い
この現象を理解するには、「動機付け」には2種類あることを知っておくと便利です。
- 内発的動機付け:自分がやりたいからやる(例:楽しいからやる)
- 外発的動機付け:外からのご褒美・評価・お金などで動かされる(例:褒められるからやる)
本来、内発的なやる気は長く続き、満足感や創造性にもつながります。
しかし、外発的な報酬が強くなると、その内発的な動機が「報酬目的」にすり替わり、行動の「意味づけ」が変わってしまうのです。
■ なぜ報酬がモチベーションを下げるのか?
報酬によってやる気が下がる理由は、大きく3つあります:
- 「自分で選んでやっている」という感覚が薄れる(統制感の喪失)
- 「やること自体が楽しい」という意識が薄れる(内発的動機の弱化)
- 「報酬がなければやらない」という依存状態が生まれる
つまり、報酬は短期的にはやる気を引き出すけれど、長期的にはやる気をむしばむ可能性があるのです。
アンダーマイニング効果は、私たちの「やる気の質」に関わる大切なテーマです。
次は、この効果が実際にどんな場面で起こるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
【アンダーマイニング効果の代表的な具体例】

アンダーマイニング効果は、私たちの身近な場面でも多く見られます。
ここでは、「報酬でやる気が下がってしまう」典型的な3つの事例を紹介します。
① お金をもらうことで趣味がつまらなくなるケース
たとえば、絵を描くことが好きだった人が、「副業として絵を売ろう」と考え始めたとします。
最初は楽しく描いていたのに、だんだん「売れる絵」「依頼主が喜ぶ絵」を意識しすぎて、「自由に描く楽しさ」が消えていく。
このように、報酬が加わることで、趣味が「仕事」になり、やる気が下がることはよくあります。
🎨 補足:「趣味が義務になる」と感じたとき、アンダーマイニング効果が起きている可能性が高いです。
②子どもに「勉強したらご褒美」を与えるとどうなるか
親が「テストで100点とったらゲーム買ってあげるよ」と言ったとします。
最初は子どももやる気になりますが、そのご褒美がなくなった瞬間、勉強をしなくなることがあります。
これは、「勉強=自分の成長のため」ではなく「ご褒美を得るため」に変わってしまったためです。
特に、内発的な好奇心や達成感を育てたい場面では、ご褒美戦略は逆効果になりやすいので注意が必要です。
③ 仕事で必ずしも「報酬アップ=やる気アップ」とはならない理由
昇給やボーナスがモチベーションになる――これは一見正しそうに見えますが、必ずしも長続きしません。
なぜなら、「やりがい」や「達成感」を重視して働いていた人が、数字や報酬のために働くようになると、仕事そのものの満足感が薄れてしまうことがあるからです。
また、「インセンティブのために動く社員」になってしまうと、報酬がなければ手を抜くようになり、職場全体のモチベーション文化が崩れるリスクもあります。
もちろん、報酬アップがやる気を高める効果も一時的にはあります。誰でも給料が上がれば嬉しく、短期的なモチベーションは高まります。
しかし心理学的には、その効果は一時的で外発的な刺激に過ぎず、やりがい(内発的動機)を損なうこともあるとされているのです。
つまり、報酬はやる気の「スイッチ」にはなっても、エンジンにはなりにくいというわけです。
とはいえ、すべての報酬がモチベーションを下げるわけではありません。実は、報酬がやる気を高めるケースもあり、それは「エンハンシング効果(motivation-enhancing effect)」として知られています。
このあと詳しく解説していきます。

このように、アンダーマイニング効果はあらゆる分野に存在し、「本来のやる気」を損なう恐れがあります。
では、この現象の仕組みを、次は心理学的な視点から深掘りしてみましょう。
【報酬がやる気を下げるメカニズムを科学的に解説】

アンダーマイニング効果は単なる「気分の問題」ではなく、心理学的なメカニズムによって説明されています。
ここでは、代表的な理論「自己決定理論(SDT)」を軸に、その根拠をわかりやすく解説します。
■ 自己決定理論(SDT)との関連
自己決定理論(Self-Determination Theory:SDT)は、エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された、人の動機づけに関する有力な理論です。
この理論によれば、私たちは以下の3つの基本的欲求を満たしているときに、もっともやる気が高まります。
- 自律性:自分の意思で行動していると感じられること
- 有能感:うまくできている、成長できていると実感できること
- 関係性:他者とのつながりや貢献を感じられること
外発的な報酬が加わると、この「自律性」が損なわれ、“自分の意志でやっている感覚”が弱まることがモチベーション低下の大きな要因になります。

■ 人は「自分の選択」で動きたいという心理
私たちは、「誰かに強制されている」よりも、「自分で選んだ」ことの方がやる気が出るという性質を持っています。
たとえば…
- 「あなたが選んだ本を読んでください」→ やる気が出る
- 「この本を絶対に読んでください」→ モチベーションが下がる
報酬があると、「自分の選択」ではなく、「報酬のために動かされている」と感じてしまい、動機の主導権を失ってしまうのです。
■ 統制感の喪失がやる気を奪う理由
ここで重要なのが「統制感(コントロール感)」です。
人は本能的に、自分の行動を自分でコントロールしている感覚=統制感を求めています。
しかし、報酬が提示されると、それは外部からのコントロールと解釈されがちです。
- 「〇〇をやったら〇円あげるよ」
- 「評価が上がれば昇進するよ」
このような条件付きの外発的動機付けは、統制感を奪い、やる気を下げる方向に働くことが心理学的に示されています。
つまり、アンダーマイニング効果の本質は、報酬によって「自律性・統制感・内発的動機」が損なわれることにあります。
次は、「報酬が逆にやる気を高めるケース」についても見ていきましょう。
【エンハンシング効果との違いは?|逆にやる気が上がるケースもある】

アンダーマイニング効果とは逆に、報酬がやる気を高めることもある――それが「エンハンシング効果」です。
この2つの効果の違いを理解すれば、「報酬=悪」ではなく、使い方次第でモチベーションを上げる武器にもなることが見えてきます。
■ アンダーマイニング効果との比較
アンダーマイニング効果とエンハンシング効果は、報酬の与え方や状況によって分かれます。違いを整理すると以下の通りです:
| 特徴 | アンダーマイニング効果 | エンハンシング効果 |
|---|---|---|
| モチベーションの変化 | 内発的→低下 | 外発的→上昇 |
| 報酬のタイプ | コントロール的(指示・条件付き) | 情報的(成果の承認) |
| 例 | 「これをやったらご褒美」 | 「よく頑張ったね、ありがとう!」 |
| 内発的動機 | 弱まる | 強化されることもある |
つまり、報酬が「命令」になると逆効果になり、「承認や励まし」として機能するとプラスに働くのです。
■ 報酬がやる気を高める条件とは?
報酬によってやる気が高まるのは、以下のような状況です。
- 報酬が意外性を持っている(サプライズボーナスなど)
- すでに行動を自発的にしている人に対して与える
- 報酬が「あなたの努力を評価したい」という形で伝わる
たとえば、「○○してくれたからお礼に○○を贈るね」といった感謝を示す報酬は、むしろ内発的動機を強めることがあるのです。
■ 教育や仕事で応用する際の注意点
エンハンシング効果をうまく活用するには、以下の点に注意しましょう。
- 条件付きにしない:「これをやったら〇〇」はNG
- 評価よりプロセスを承認する:「結果が良かった」ではなく「努力が素晴らしかった」
- 報酬が主目的にならないようにする
特に子育てや社員教育では、「ご褒美が目当て」になってしまうと習慣化や成長の妨げになりやすく、やる気を奪うリスクがあるのです。
次は、こうしたアンダーマイニング効果を日常生活でどう防ぐかという実践的な方法について解説します。
【アンダーマイニング効果を防ぐには?|モチベーション低下を防ぐ実践的アドバイス】

アンダーマイニング効果を防ぐには、報酬に頼らず、行動の「内側」にある動機を大切にすることが大切です。
ここでは、モチベーション低下を防ぎつつ、やる気を長く保つための実践的なヒントを紹介します。
■「行動の意味づけ」を再確認する方法
まずは、「なぜそれをやるのか?」という目的や意味を自分で考えることが大切です。
これを心理学では「意味づけ再構成(reframing)」といいます。
たとえば…
- 「読書をするのは、知識を得るため」ではなく「自分の世界を広げる楽しみ」
- 「筋トレはダイエットのため」ではなく「毎朝の自信づけになる」
このように、自分の価値観や人生の目的と結びつけると、行動が「自分ごと」になり、やる気が持続しやすくなります。
■ 報酬より「達成感」や「価値観」を重視する
「〇〇すればお金がもらえる」ではなく、「〇〇をやり切った自分が好き」
このように、自分自身の達成感・成長実感・価値観に注目することが大切です。
具体的には…
- ✅ 終わった後の達成感にフォーカスする
- ✅ 自分の価値観に沿った目標を立てる(例:「人の役に立ちたい」)
- ✅ 小さな成功を自分で認める習慣をつける
これにより、他人からの報酬に左右されない「内なるやる気」が育ちます。
■ 内発的動機を育てる環境づくりとは
自分自身の工夫だけでなく、周囲の環境づくりも非常に重要です。
理想的な環境とは:
- 🎯「自分で選べる余地」がある(自由度・選択肢)
- 🧩「挑戦と達成感」が得られる(ちょっと難しいタスク)
- 👥「認め合える関係性」がある(励まし・共感)
たとえば職場であれば、目標を自分で決められる/過程を評価してくれる/成長実感があることが、モチベーションを支えるポイントとなります。
モチベーションは、与えられるものではなく「自分で育てるもの」。
次章では、報酬と上手に付き合う方法を科学的に紹介します。
【報酬とモチベーションの正しい付き合い方|活用するには?】
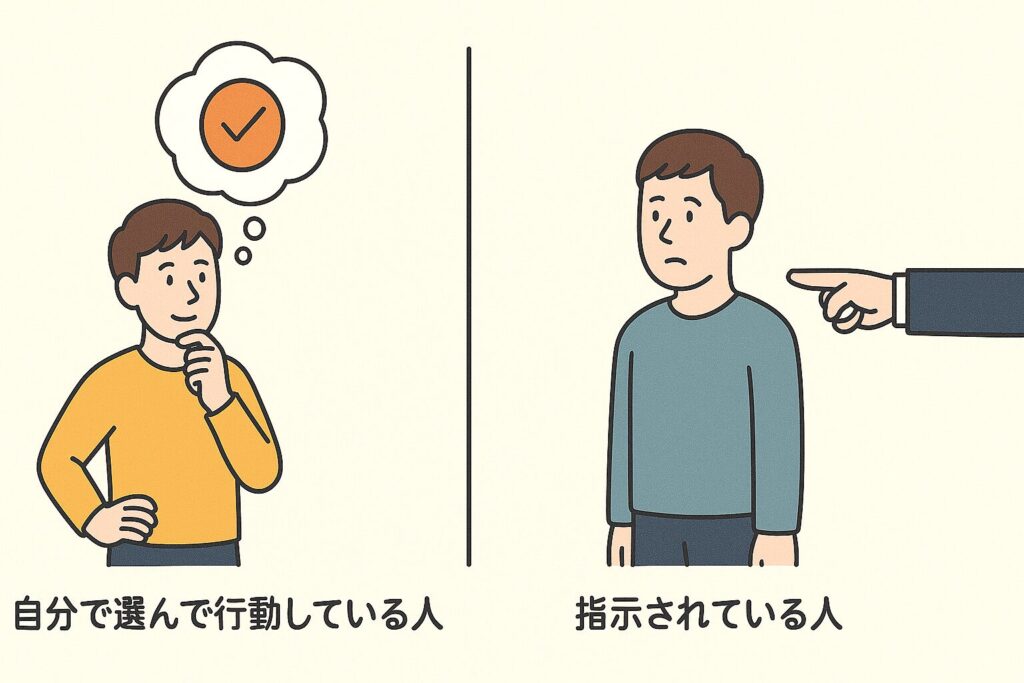
報酬=悪いもの、とは限ります。
大切なのは、報酬の「使い方」や「タイミング」です。
ここでは、アンダーマイニング効果を避けながら、やる気を高める報酬の活用法を紹介します。
■ 短期的報酬と長期的動機のバランスをとる
報酬は「即効性のあるモチベーションブースター」として有効です。
特に、やる気が出ない初動や苦手タスクへの取りかかりに有効。
ただし、報酬だけに頼り続けると、長期的なやる気(内発的動機)は弱まります。
🔸活用のコツ:
- 「最初の一歩」にご褒美を設定(例:10分だけやったらコーヒー休憩)
- 習慣化するまでは報酬で支援、定着後は「報酬なし」に切り替える
- 長期的な目標と結びつけて報酬を設計する(例:勉強=将来の自由)
このように、「短期のやる気」と「長期の目的」をつなげるのが理想です。
■ 自己決定感を保ちながら報酬を設計する方法
アンダーマイニング効果を避けるには、「自分で選んでやっている感覚(自己決定感)」を保つことが不可欠です。
💡ポイント:
- 「〇〇しないと報酬がもらえない」ではなく「〇〇したら自分にご褒美」
- 他人からの強制ではなく、自分で報酬を設定する
- 報酬を選べるようにする(例:お菓子/映画/休憩の中から選ぶ)
このように、「報酬を受け取る主導権を自分に戻す」ことが、やる気を守るコツです。
■ 内発的モチベーションを高める3つの工夫(自律性・有能感・関係性)
自己決定理論(SDT)によれば、人の内発的動機づけを高めるには以下の3要素が不可欠です:
- 自律性(自分で選んでいる感覚)
- 有能感(できた・成長できたという実感)
- 関係性(誰かとつながっている感覚)
🔸応用例:
- 自律性:タスクのやり方や順番を自分で決める
- 有能感:達成を記録する/フィードバックをもらう
- 関係性:仲間と進捗を共有する/励まし合う環境を作る
報酬に頼るのではなく、こうした内面の動機が育つ場を整えることが、持続可能なやる気につながります。

報酬とうまく付き合うことで、短期的なやる気と長期的な意欲のバランスが取れるようになります。
次章では、今回の内容をまとめ、あなたに合ったモチベーション戦略を見直すヒントを紹介します。
【まとめ|やる気を高めたいなら「動機づけの質」を見直そう】
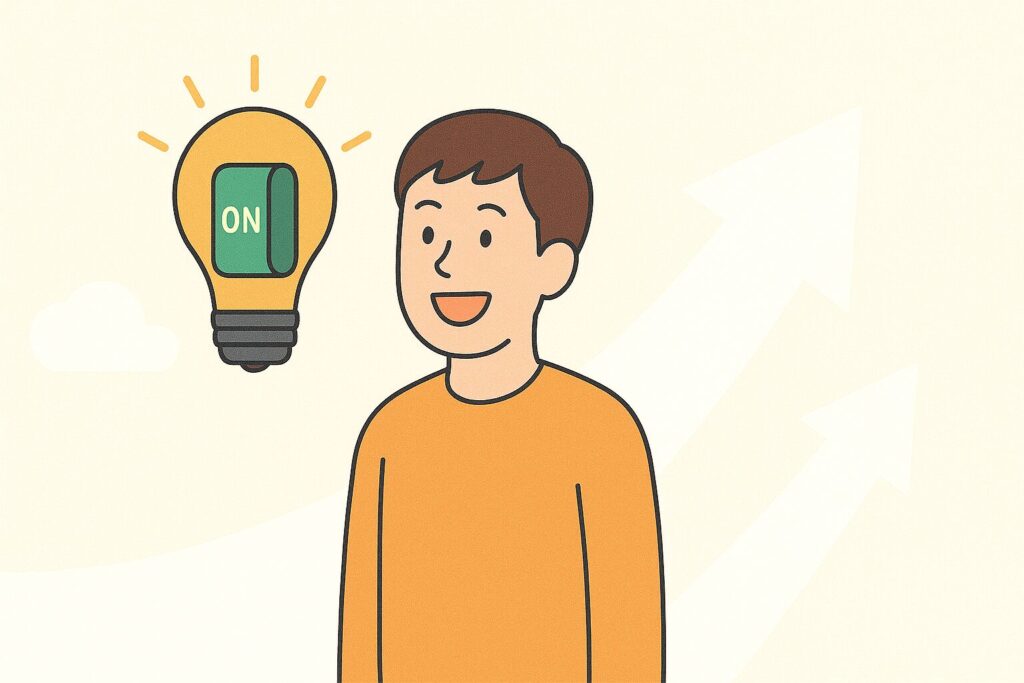
ここまで「アンダーマイニング効果」と呼ばれる、報酬がやる気を下げる心理現象について解説してきました。では、改めて重要なポイントを振り返ってみましょう。
■ 今回紹介した理論の要点まとめ
- アンダーマイニング効果とは、外からの報酬によって内側からのやる気が低下する現象。
- 特に、「自分の意思でやっていたこと」が「報酬のためにやること」に変化すると、モチベーションが損なわれやすい。
- ただし、報酬=悪ではない。使い方次第で効果的にやる気を高められる。
■ 報酬の使い方を見直すことがやる気維持の鍵
報酬がやる気を下げるのは、「報酬の設計ミス」や「押しつけ感」が原因です。
✅ やる気を維持するために意識したいこと:
- 報酬はご褒美ではなく「達成の確認」に使う
- 「自分の選択」で動けている感覚(自己決定感)を大切にする
- 外的報酬に依存しすぎず、「やりたい理由」を言語化する
報酬と内発的動機を両立させることで、持続可能なモチベーションが手に入ります。
■ あなたに合ったモチベーション戦略とは
モチベーションには個人差があります。だからこそ、
- 自分が「どんなときにやる気が出るか」
- 「どんな報酬なら嬉しいか」
- 「何のためにやるのか」
…を一度立ち止まって見直してみてください。
今回紹介した考え方や工夫は、学習・仕事・習慣づくりなど、さまざまな場面で役立ちます。

