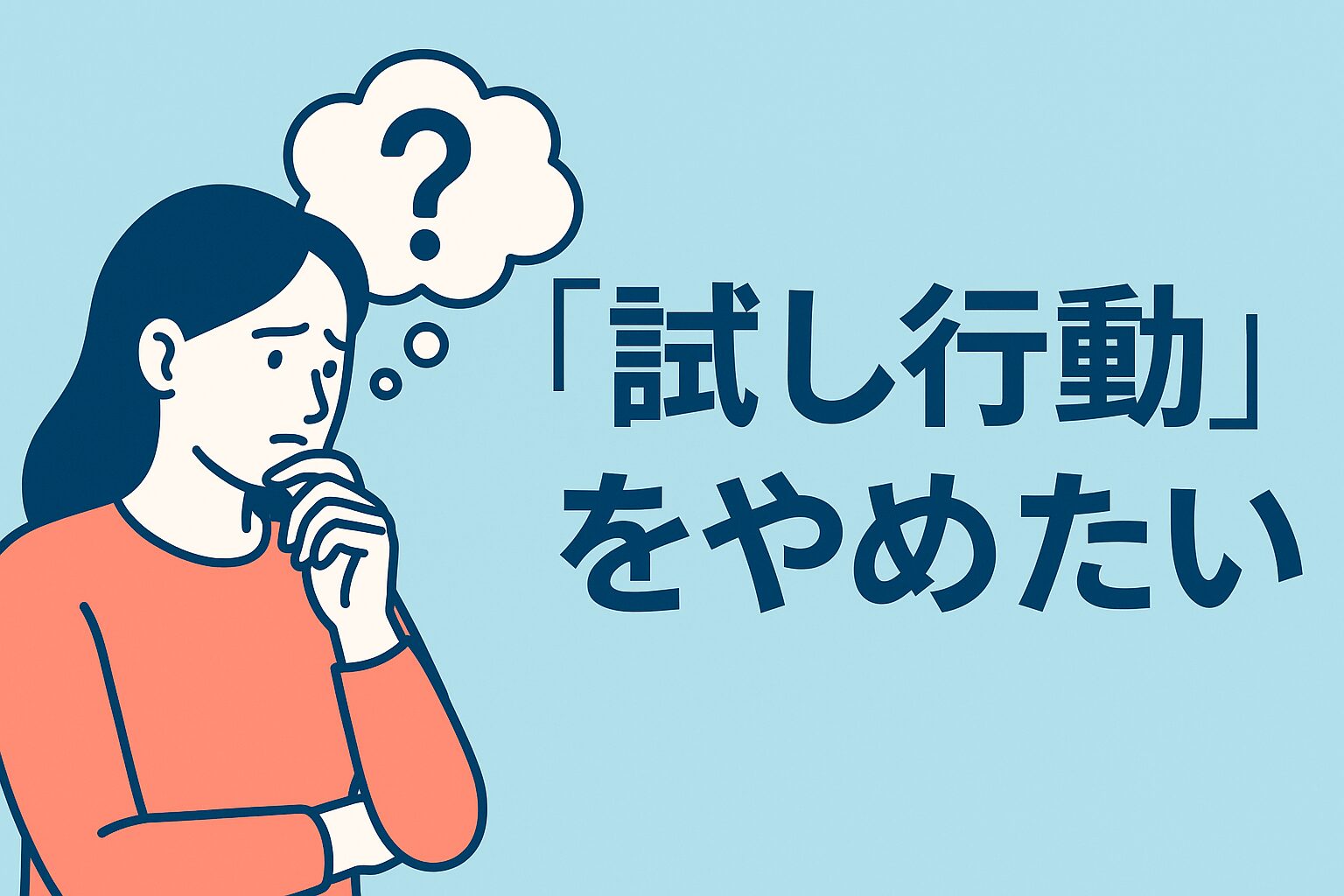「なんでそんなことするの?」と自分でも不思議に思うような行動、つい取ってしまったことはありませんか?
返信をわざと遅らせたり、相手を不安にさせて反応を見る――それは「試し行動」と呼ばれるもの。大人になっても、この行動がやめられずにモヤモヤしている人は意外と多いんです。
この記事では、試し行動をしてしまう心理的な背景(見捨てられ不安や愛着スタイルなど)から、人間関係を壊すメカニズム、そして今日から実践できる改善ステップまでを、わかりやすく解説します。さらに、心理学の有名理論や研究も取り入れ、行動を変えるためのヒントをまとめました。
読むことで「なぜ自分はやってしまうのか」が明確になり、「どうやってやめるか」が具体的にイメージできるようになるはずです。
自分も相手も大切にできる関係を築くために、ぜひ最後まで読んでくださいね。
大人の試し行動とは?恋愛・人間関係で起こる具体例

試し行動の意味と定義(心理学的な視点)
試し行動とは、相手の愛情や信頼を確かめるために、わざと相手を不安にさせたり困らせたりする行動のことです。
心理学的には「愛情確認行動」とも呼ばれ、子どもだけでなく大人の人間関係でも見られます。
この行動の根底には、
- 「本当に自分を大切にしてくれているのか」
- 「見捨てられないだろうか」
という不安や恐れがあります。
たとえるなら、橋の強度を確かめるために何度も揺らしてしまい、そのせいで橋自体が壊れてしまうようなものです。確かめたくてやった行動が、かえって関係を壊す原因になります。
恋愛でよくある試し行動のパターン
恋愛関係では、次のような試し行動がよく見られます。
- わざと返信を遅らせて、相手の反応を見る
- 他の異性と仲良くして嫉妬させる
- 「別れよう」と脅して相手の愛情を測る
- 無理なお願いをして、どこまで受け入れてくれるか試す
一見すると冗談や軽い駆け引きに見えるかもしれませんが、相手にとってはストレスや不信感の原因になります。
職場や友人関係で見られる試し行動の例
試し行動は恋愛だけではなく、職場や友人関係でも起こります。
- 職場
- わざと期限ギリギリで仕事を渡して、助けてもらえるか試す
- あいまいな指示を出して、相手が自分の意図を汲めるか確認する
- 友人関係
- 連絡をしばらく絶って、相手から連絡してくるかを観察する
- 困っているとアピールして、どこまで助けてくれるかを見る
こうした行動は、短期的には相手の反応を知る手段になりますが、長期的には信頼の残高を減らし、関係を悪化させるリスクが高まります。
まとめると、大人の試し行動は「相手の愛情や忠誠心を測るための行動」ですが、その多くは相手に負担を与え、関係を壊す危険があります。次は、このような行動をなぜ大人になってもしてしまうのか、その心理的背景を見ていきます。
なぜ大人になっても試し行動をしてしまうのか【心理的背景】
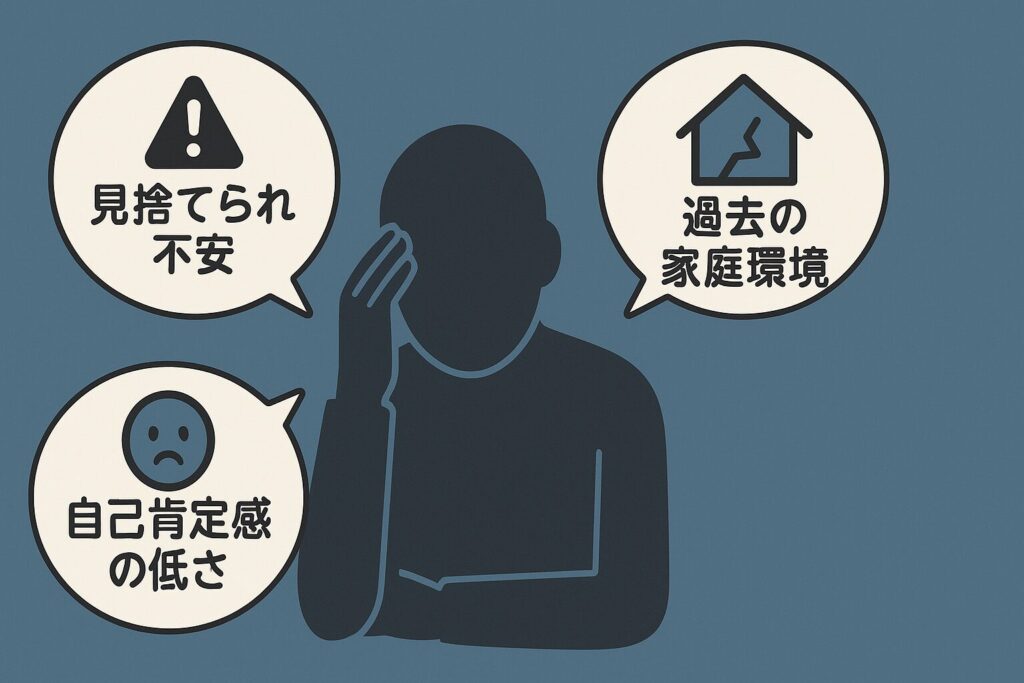
見捨てられ不安と愛着スタイル(不安型・恐れ回避型)
大人になってからの試し行動の大きな背景にあるのが、見捨てられ不安です。
これは「相手が自分を置いていってしまうのではないか」という強い恐れで、愛着理論(ジョン・ボウルビィ提唱)では、幼少期の人間関係で形成された愛着スタイルが関係していると考えられます。
- 不安型:相手に強く依存し、離れられることを極端に恐れる
- 恐れ回避型:本当は親密さを求めているが、傷つくのを避けて距離を取る
どちらのタイプも、「確かめずにはいられない」という心理が働きやすく、試し行動が出やすくなります。



自己肯定感の低さと承認欲求の影響
自己肯定感が低いと、「自分は愛されるに値しないのではないか」と感じやすくなります。
その不安を埋めるために、相手からの承認を何度も確認したくなるのです。
- 「相手が応えてくれれば安心」
- 「応えてくれなければ、やっぱり自分はダメなんだ」
というゼロか百かの思考に陥りやすくなり、確認のための行動(=試し行動)が習慣化します。


過去の人間関係や家庭環境からの影響(アダルトチルドレンなど)
子ども時代に、親や養育者からの愛情が安定して得られなかった場合、大人になってからもその影響が残ります。
特に、アダルトチルドレン(機能不全家庭で育った大人)の場合、相手の反応を常に気にしながら行動する傾向が強くなります。
例:
- 親の機嫌を取らないと安全でいられなかった
- 期待に応えないと見捨てられる経験をしてきた
- 愛情や承認が条件付きでしか与えられなかった
こうした過去の経験が「愛情は不安定なもの」「確かめなければなくなる」という信念を作り、試し行動の土台となります。
まとめると、大人の試し行動は単なるわがままではなく、不安・自己否定感・過去の経験が複雑に絡み合って起きています。
次は、この試し行動が人間関係を壊すメカニズムについて解説します。
試し行動が人間関係を壊す理由

信頼残高(愛情の銀行口座理論)が減っていく仕組み
スティーブン・R・コヴィーが提唱した「愛情の銀行口座理論」では、人間関係は銀行口座のように「信頼の預け入れ」と「引き出し」で成り立つと説明されます。
- 預け入れ:思いやり、感謝、誠実な行動
- 引き出し:批判、無視、裏切り、不信感を与える行動
試し行動は、この「引き出し」にあたります。
短期的には「愛情を確認するため」でも、繰り返すほど信頼残高が減少し、関係修復が難しくなります。
自己充足予言で悪循環が起きる流れ
自己充足予言とは、「こうなるはずだ」と思い込んだことが、実際にその通りの結果を招く心理現象です。
試し行動の場合の流れはこうです:
- 「きっと見捨てられる」と思う
- その不安から相手を試す行動をする
- 相手が疲れて距離を置く
- 「やっぱり見捨てられた」と感じる
こうして、不安を裏付ける証拠ばかりが集まり、行動が強化されてしまいます。
相手の感情が疲弊し、距離を取られるプロセス
試し行動は、相手に心理的負担をかけます。
最初は心配や愛情から応じてくれるかもしれませんが、繰り返されると疲れや苛立ちが積み重なります。
- 「信じてもらえていない」と感じる
- 自分の誠実さや努力が報われないと感じる
- 関係が重く、息苦しくなる
その結果、相手は距離を置くようになり、本当に関係が薄れてしまうことも少なくありません。
まとめると、試し行動は本人にとっては「安心を得るための行動」ですが、相手にとっては「信頼を削る行動」になり、結果として関係を破壊するリスクが非常に高いのです。
次は、この悪循環を断ち切るための改善ステップを具体的に解説します。
試し行動をやめるための改善ステップ

自分の感情に気づく(認知行動療法の視点)
試し行動をやめる第一歩は、自分がどんな感情からその行動をしているのかに気づくことです。
認知行動療法(CBT)では、行動の背後にある「自動思考(瞬間的な考え)」を意識することが重要とされています。
- 行動の直前にどんな不安や考えが浮かんだかメモする
- 「今の不安は事実?それとも推測?」と自分に問いかける
- 感情と事実を切り分けて考える
このステップだけでも、衝動的に試し行動をする回数が減ります。

安心感を自分で作る行動(趣味・友人時間・セルフケア)
相手に安心感を求めすぎると、依存状態になりやすくなります。
そこで、自分の生活の中に安心感を生み出す要素を増やすことが効果的です。
- 好きな趣味に没頭する
- 気を使わず話せる友人との時間を持つ
- 十分な睡眠・食事・運動などのセルフケア
これらを日常に取り入れることで、相手に「常に安心を与えてほしい」という圧力が減ります。
相手に直接ニーズを伝えるコミュニケーション法
試し行動の代わりに、率直に自分の気持ちや必要なことを伝える習慣を持ちましょう。
- 「本当は不安だから、○○してくれると助かる」
- 「こういう時に安心できるのは、□□してもらえた時」
ポイントは、相手を責める言い方ではなく、自分の気持ちを主語にして伝える(Iメッセージ)ことです。

小さな成功体験を積んで自己効力感を高める
自己効力感とは、「自分ならできる」という感覚のことです。
試し行動をやめるためには、小さな約束を守る・不安を我慢できた経験を積むことが大切です。
例:
- メッセージの返信を急がず、10分だけ待ってみる
- 不安になった時に深呼吸をしてから行動する
- 試し行動を我慢できた日をカレンダーにチェックする
こうした小さな積み重ねが、自分への信頼感を取り戻す土台になります。

まとめると、試し行動をやめるためには
- 感情に気づく
- 安心感を自分で作る
- ニーズを率直に伝える
- 小さな成功体験を積む
という流れが効果的です。
次は、この改善を支えるために役立つ有名理論や研究を紹介します。
改善に役立つ有名理論・研究と活用法
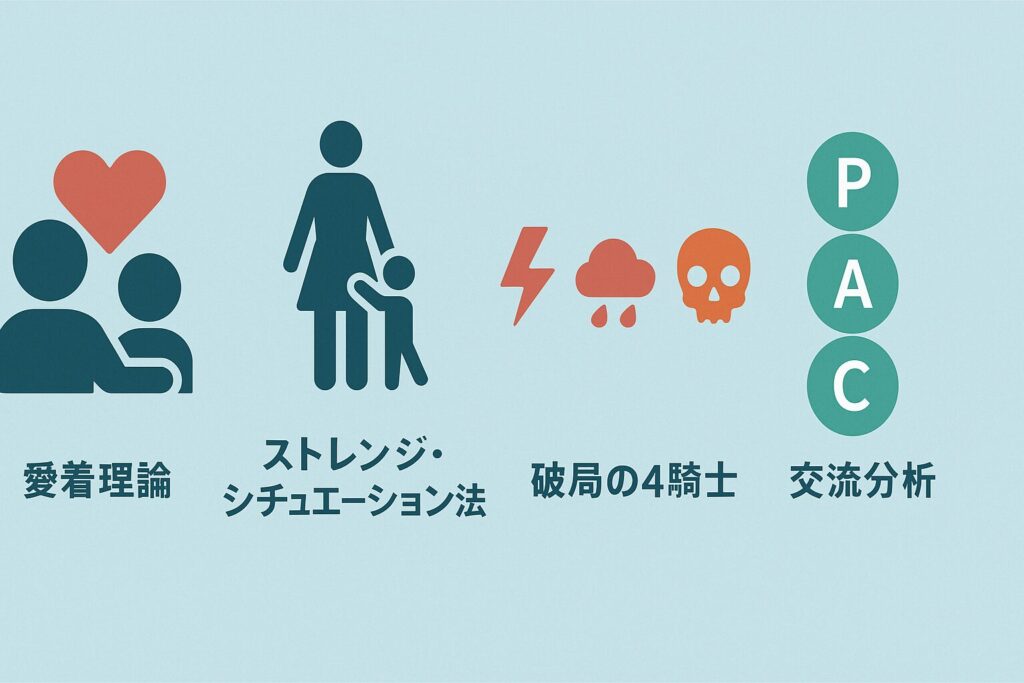
ジョン・ボウルビィの愛着理論
愛着理論は、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した、人間関係の安心感や不安感の土台を説明する理論です。
幼少期に親や養育者との間で築いた「安全基地」が、大人になってからの人間関係にも影響します。
試し行動は、多くの場合この安全基地が不安定だった人に見られます。
理解しておくと、「自分の反応は性格ではなく、学習された行動だったんだ」と気づきやすくなります。

メアリー・エインスワースのストレンジ・シチュエーション法
ボウルビィの理論を実証したメアリー・エインスワースは、親子の分離・再会を観察するストレンジ・シチュエーション法という実験を行いました。
これにより、愛着スタイルは大きく安定型・不安型・回避型に分けられることがわかりました。
不安型の人は、相手を試す行動をとりやすい傾向があり、自分がどのタイプかを知ることが改善のヒントになります。

ゴットマン研究所の「破局の4騎士」理論
夫婦関係の研究で有名なジョン・ゴットマン博士は、関係を壊す行動として批判・防御・侮辱・逃避の4つを「破局の4騎士」と名付けました。
試し行動は、この中の批判や防御として現れることがあります。
つまり、試し行動をやめることは、破局の予兆を減らすことにもつながります。
ゴットマン博士の4騎士
- 批判(Criticism)
- 人格や性格を否定するような言い方で相手を責める
- 侮辱(Contempt)
- 相手を見下す、皮肉やあざ笑いなど軽蔑を示す
- 防御(Defensiveness)
- 自分の非を認めず、言い訳や反撃で応じる
- 逃避(Stonewalling)
- 相手の話を聞かず、感情的にシャットダウンする状態
エリック・バーンの交流分析(心理的ゲーム)
交流分析では、人間関係のやり取りを「親・大人・子ども」の3つの自我状態で説明します。
試し行動は「子ども」モードの不安や甘えから出やすく、相手も「親」モードで反応してしまうと、心理的ゲームが繰り返されます。
この仕組みを知ると、「大人」モードで冷静に会話することができ、試し行動の連鎖を断ち切りやすくなります。

まとめると、試し行動を改善するには、自分の心理的背景を理解するだけでなく、愛着理論・人間関係の研究・交流分析といった理論を活用すると、客観的に行動を見直せます。
次は、改善を目指す中でやりがちな失敗と注意点を解説します。
試し行動をやめたい人がやりがちな失敗と注意点

「相手をコントロールしない」と意識することの重要性
試し行動の裏側には、「相手の反応を自分の思い通りにしたい」というコントロール欲求があります。
しかし、人間関係において相手を完全にコントロールすることは不可能です。
むしろ、コントロールされていると感じた相手は、防衛的になり、関係が冷え込む危険があります。
改善の第一歩は、「相手を動かそうとするより、自分の感情や行動を整える方が結果的に関係は良くなる」という意識を持つことです。
変化を焦りすぎて元に戻ってしまうケース
試し行動は長年の習慣になっている場合が多く、一度で完璧にやめるのは難しいのが現実です。
最初はうまくいっても、ストレスや不安が強くなったときに元に戻ることがあります。
これを防ぐためには:
- 「多少戻っても、改善の過程の一部」と受け止める
- 小さな成功体験を積み重ねて、自信を育てる
- 完璧主義を手放す
という姿勢が大切です。
専門的なサポートを使うタイミング(カウンセリングなど)
もし試し行動が人間関係や生活に大きな影響を与えている場合、専門家のサポートを受けるのも選択肢の一つです。
例えば:
- 心理カウンセリングや認知行動療法(CBT)
- 愛着スタイル改善のためのEFT(感情焦点型療法)
- 対人関係療法(IPT)
特に、過去のトラウマやアダルトチルドレン的な背景が強い場合は、自力だけで変えようとすると負担が大きくなります。
専門家と一緒に進めることで、安全かつ持続的な改善が可能になります。

まとめると、試し行動をやめる過程では
- 相手をコントロールしようとしない
- 変化を焦らない
- 必要に応じて専門的サポートを活用する
という3つのポイントを意識することで、改善が加速します。
まとめ|試し行動をやめることは、信頼を取り戻す第一歩
やめるためのキーポイント再確認
ここまで解説してきた内容を振り返ると、試し行動をやめるための核心は次の4つです。
- 自分の感情に気づく
- 不安や恐れの正体を知ることが、衝動的な行動を止める第一歩。
- 安心感を自分で作る
- 趣味や友人時間、セルフケアで「心の安全基地」を外部に依存しすぎない。
- 相手に率直にニーズを伝える
- 責める言い方ではなく、Iメッセージで希望を伝える。
- 小さな成功体験を積む
- 我慢できた・不安に耐えられたという経験が自己効力感を育てる。
小さな行動変化から始める重要性
試し行動は長年の習慣になっていることが多く、一気にやめようとすると反動が出やすいです。
そこで重要なのは、「今日できる小さな一歩」から始めることです。
例:
- 返信を遅らせる代わりに、正直に「今忙しいから後で話そう」と伝える
- 不安を感じたら、相手に連絡する前に深呼吸を3回する
- 試し行動をしなかった日をカレンダーに記録する
こうした小さな積み重ねが、信頼関係の修復と自己信頼の回復につながります。
最後に
試し行動は、相手の愛情を確かめたいという自然な欲求から生まれることもあります。
しかし、その方法が「相手の信頼を削る形」になってしまえば、望む結果から遠ざかってしまいます。
やめる努力は、相手との関係だけでなく、自分自身との関係を修復する第一歩です。
今日からできることを一つ選び、小さな変化を積み重ねていきましょう。