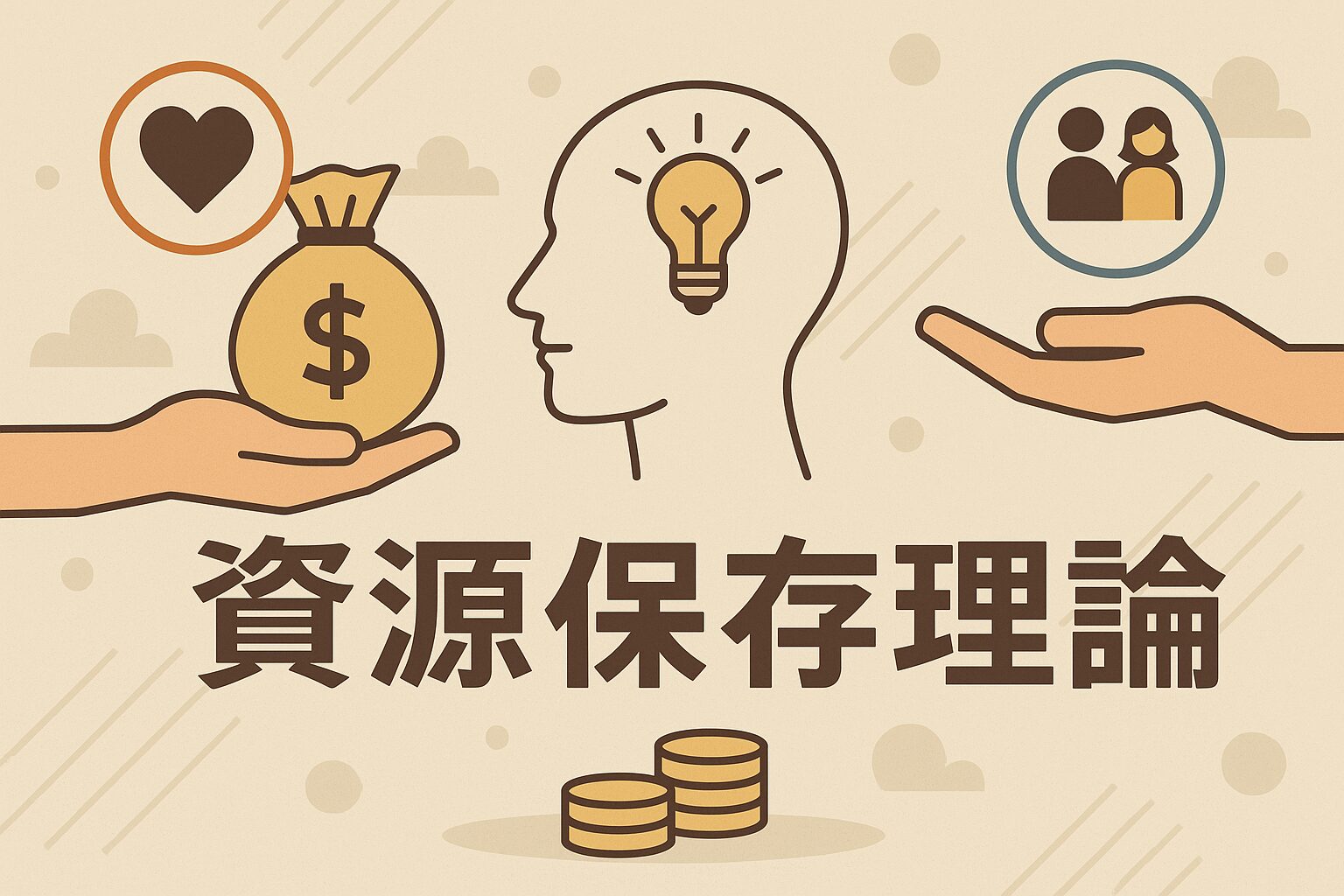仕事や人間関係で「どうしてこんなにストレスを感じてしまうんだろう?」とモヤモヤしたことはありませんか?
✔ 頑張っているのに疲れが抜けない
✔ 人との関係に振り回されてしまう
✔ 小さな失敗で心が折れそうになる
実はその背景には、心理学でいう「資源保存理論」が関わっているかもしれません。これは「人は大切な資源(お金・健康・人間関係・自尊心など)を失うと強いストレスを感じる」という考え方です。
この記事では、資源保存理論の基本から「なぜ人はストレスに弱くなるのか」、さらに個人差・応用方法・哲学的な視点(メメント・モリや覚悟)まで、分かりやすく解説します。読めば、自分にとって大事な資源をどう守り、増やし、そして執着しすぎないかのヒントが見つかるはずです。
ストレスに振り回されない生き方を考えるきっかけに、ぜひ最後まで読んでくださいね。
資源保存理論とは何か|基本の意味と考え方
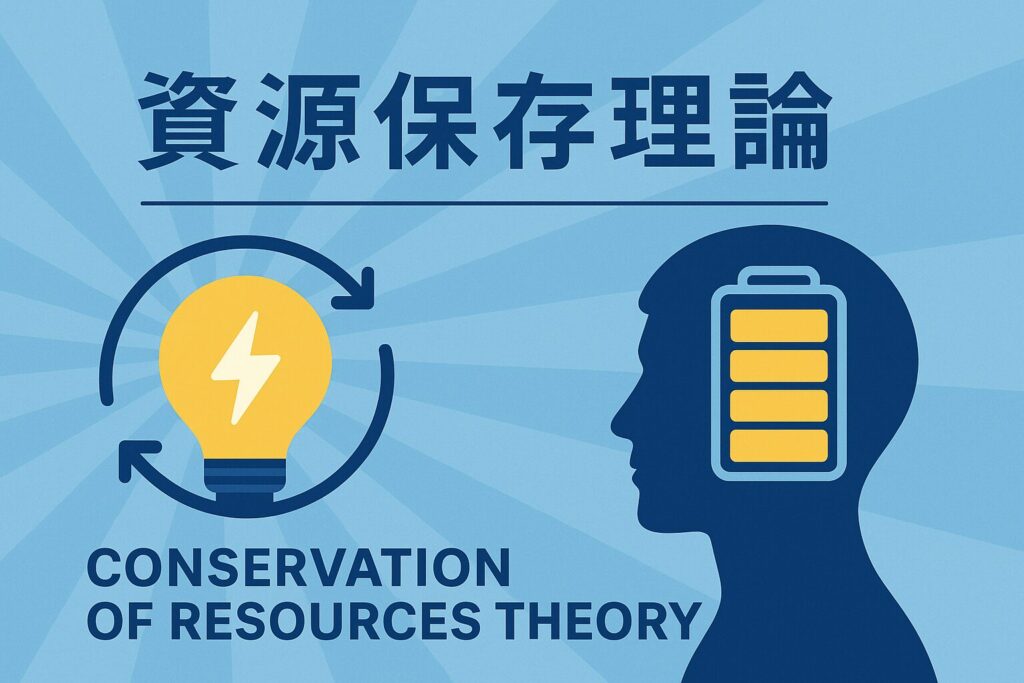
資源保存理論(Conservation of Resources theory, COR理論)とは、アメリカの心理学者ステファン・ホブフォール(Stevan E. Hobfoll)が1989年に提唱した、ストレスを理解するための心理学理論です。
この理論では、人がストレスを感じるのは「資源を失ったとき」「これから失いそうなとき」「失った資源を取り戻せないとき」だと説明されます。ここでいう「資源」とは、単なるお金や物だけでなく、時間・健康・人間関係・自尊心・知識といった幅広いものを指します。
資源保存理論の定義とポイント
- 人は、自分にとって価値ある資源を守りたい、増やしたいと考える。
- ストレスは「資源を失う・奪われる・回復できない」ときに強まる。
- 資源を得ることは幸福感や安心感につながり、逆に失うと不安や疲労につながる。
👉 例えるなら、「人生は資源の口座のようなもの」。
口座にお金(資源)がしっかり入っていれば、多少の出費(ストレス)があっても安心です。
しかし残高が少ない状態で出費が続けば、精神的にも不安定になりやすいのです。
提唱者ホブフォールと理論の背景
ステファン・ホブフォールは、ストレス研究において「なぜ人が追い込まれるのか」を説明するためにこの理論を考案しました。従来の理論は「刺激と反応」や「認知の仕方」に焦点を当てていましたが、ホブフォールはもっとシンプルに、「人は大事なものを失うのが怖い」という根源的な心理に注目したのです。
資源の種類(物質的・心理的・社会的・エネルギー)
資源保存理論でいう「資源」は、大きく4つに分類されます。
- 物質的資源:お金、家、衣食住など生活に必要なもの
- 心理的資源:自尊心、自己効力感、希望、知識、スキル
- 社会的資源:家族や友人のサポート、信頼、ネットワーク
- エネルギー資源:時間、体力、集中力
これらは相互に影響し合います。たとえば「お金(物質的資源)」を失えば「安心感(心理的資源)」も失いやすく、逆に「信頼できる仲間(社会的資源)」があれば失敗しても立ち直りやすい、という具合です。
資源保存理論の特徴:人によって資源の優先順位が異なる
人が大切にする資源はそれぞれ違います。
- ある人にとっては「収入」が最重要資源
- ある人にとっては「家族や友人との時間」が最優先
- また別の人は「健康」や「自由な時間」に最も価値を置く
このように、どの資源を重視するかの優先順位が違うため、同じ出来事でもストレスの大きさが変わるのです。
資源保存理論で分かる「人がストレスに弱くなる理由」

資源保存理論は、なぜ人がストレスに弱くなるのかをシンプルに説明してくれます。ポイントは「資源の喪失」と「その連鎖」にあります。
資源の喪失が最大のストレス要因になる
資源保存理論によれば、ストレスの最大の原因は「資源を失うこと」です。
- 収入が減る(物質的資源の喪失)
- 健康を損なう(エネルギー資源の喪失)
- 信頼できる仲間を失う(社会的資源の喪失)
このように、大切なものを失ったとき、人は大きな不安や落ち込みを感じます。
なぜ「得られないこと」より「失うこと」が苦しいのか
心理学では「損失回避バイアス」と呼ばれる傾向があり、人は「得られる喜び」よりも「失う苦しみ」を強く感じやすいのです。
- 例:給料が1万円増えた喜びより、1万円減ったショックの方が大きい。
資源保存理論もこれを裏づけており、失うことへの恐怖やストレスが、日常生活の行動や心の安定に大きく影響します。

資源スパイラル(悪循環と好循環)の仕組み
資源の増減は連鎖しやすく、これを資源スパイラルと呼びます。
- 悪循環(ロス・スパイラル)
- 例:失業 → 収入減少 → 自尊心低下 → 人間関係悪化 → さらにストレス
- 好循環(ゲイン・スパイラル)
- 例:新しい資格取得 → 自信アップ → 昇進 → 収入増 → 家族の安心感
つまり、小さな資源の失敗が連鎖して大きなストレスになる一方、小さな成功も積み重ねればストレスに強い状態を作れるのです。
資源保存理論と関連する心理学モデル
資源保存理論は単独で使われるだけでなく、他の心理学モデルとも結びつけて理解されることが多いです。ここでは、特に関連が深い3つのモデルを紹介します。
①ジョブ・デマンド・リソース(JD-R)モデルとの関係
JD-Rモデルとは、仕事に関する「要求(デマンド)」と「資源(リソース)」のバランスで、ストレスや燃え尽きが決まるとする理論です。
- 仕事の要求が大きい(長時間労働、ノルマ、責任の重さ)
- 資源が少ない(サポート不足、裁量権がない、報酬が低い)
この組み合わせで、燃え尽きや離職リスクが高まります。逆に、資源が充実していれば高い要求を受けてもパフォーマンスを発揮できるのです。
資源保存理論の「資源を守ることがストレス対処の鍵」という考え方は、このJD-Rモデルの基盤になっています。

②レジリエンス理論とのつながり
レジリエンス(心の回復力)は、困難やストレスから立ち直る力を意味します。資源保存理論と深く関係しており、
- 「心理的資源(自尊心・希望)」
- 「社会的資源(サポート・信頼)」
- 「エネルギー資源(体力・時間)」
これらを持っている人ほど、逆境から回復しやすいと説明されます。つまり、資源を多く持つ人は「ストレスに強く、レジリエンスも高い」と言えるのです。

③認知的評価理論(ラザルス)との違い
ラザルスの認知的評価理論は、ストレスは「状況をどう解釈するか」で決まると考えます。
- 「これは脅威だ」と判断 → ストレスが高まる
- 「これは挑戦だ」と判断 → ストレスは小さくなる
一方、資源保存理論は「資源の増減そのもの」に注目します。
つまり、ラザルスは“頭の中の解釈”を重視し、ホブフォールは“現実の資源”を重視するという違いがあります。

資源保存理論に対する主な批判・限界
資源保存理論(COR理論)にもいくつかの批判や限界が指摘されています。
1. 「資源」という概念が広すぎる
- 資源には「お金・健康・時間・自尊心・人間関係」など幅広いものが含まれるため、定義が曖昧になりやすい。
- 研究者によって「どこまでを資源とみなすか」が異なり、比較や検証が難しいという指摘があります。
2. 文化差を十分に説明できない
- 欧米では「個人の成果」や「自己効力感」が資源として重視される一方、日本のような集団主義文化では「人間関係の調和」や「周囲の評価」が資源として大きい。
- 資源保存理論は普遍的なモデルを目指していますが、文化や社会背景による違いを過小評価していると批判されます。
3. 「資源喪失=ストレス」という図式が単純すぎる
- 実際には、資源を失ってもそれを「挑戦」と捉えて成長につなげる人もいる。
- この点では、ラザルスの認知的評価理論(状況をどう解釈するかでストレスが決まる)の方が柔軟だとする研究者もいます。
4. 測定の難しさ
- 「資源の量」をどう数値化するのかが課題。
- 例えば「人間関係のサポート」を失った場合、それをどのくらいの資源喪失として扱うのかは主観的になりやすい。
5. 強い「損失バイアス」前提への疑問
- COR理論は「失うことが最もストレスになる」と強調しますが、覚悟や死生観を持つ人、ミニマリストのように「失っても気にしない人」もいる。
- こうした人々をうまく説明できない点が、批判として挙げられます。
まとめ
資源保存理論は「ストレス=資源の喪失」という直感的でわかりやすいモデルですが、
- 資源の定義が広すぎる
- 文化や個人差を十分に扱えていない
- 資源を失っても必ずしもストレスとは限らない
といった批判があります。
そのため、現在は他の心理学理論(レジリエンスや認知的評価理論など)と組み合わせて使われることが多いです。
資源保存理論の活用例|日常・仕事・人間関係
資源保存理論は学術的な理論ですが、私たちの日常や仕事、人間関係にも役立つヒントを与えてくれます。ポイントは「資源を守る・増やす・奪われないようにする」ことです。
日常生活で資源を守る方法(睡眠・運動・趣味)
- 睡眠:十分な睡眠は「体力」「集中力」というエネルギー資源を回復させる。
- 運動:定期的な運動は健康資源を増やし、ストレス耐性を高める。
- 趣味:好きな活動は心理的資源(自尊心や楽しみ)を補充してくれる。
👉 日常の小さな習慣が、資源の「貯金」を増やすことにつながります。
仕事で資源を失わない工夫(サポート・裁量・人間関係)
- 上司や同僚のサポートがあれば、心理的資源や社会的資源が守られる。
- 裁量権があると、自分でコントロールできる感覚が増え、自己効力感が維持される。
- 良好な人間関係は、ストレスが高い状況でも資源を失いにくくする。
👉 反対に、評価が不透明でサポートもなく孤立した環境は、資源を失うリスクが高く、燃え尽きの原因になります。
人間関係における資源(信頼・つながり)を大切にする
- 信頼関係:安心して頼れる人がいることは、強力な社会的資源。
- つながり:家族や友人、趣味仲間とのつながりは、困難なときに支えになる。
- 感謝や助け合い:お互いの資源を補い合える関係は、資源スパイラルを「好循環」に変えてくれる。
👉 人間関係は目に見えにくい資源ですが、実際には最も大きなクッションとなり、ストレスを和らげてくれるのです。
資源保存理論を超える視点|覚悟やメメント・モリの考え方

資源保存理論は「資源を失うことがストレスの大きな要因」と説明しますが、実際にはその枠組みを超えて、資源の増減にあまり左右されない人も存在します。その背景には「覚悟」や「死生観」のような深い価値観があります。
資源に執着しない生き方の強さ
- ミニマリストや禅的な思想を持つ人は、物やお金といった外的資源への依存度が低い。
- 「なくても生きられる」という考え方は、喪失へのストレスを大幅に減らす。
- 資源を絶対視しないことで、むしろ自由に生きられる強さを得ている。
死生観や覚悟が心理的資源になる
- メメント・モリ(memento mori:死を想え)という思想では、「人は必ず死ぬ」という前提を受け入れる。
- 「どうせ失うものなら、今ここに集中しよう」という覚悟が、心理的な安定につながる。
- 資源保存理論的に見ると、この覚悟そのものが心理的資源として機能し、ストレスを和らげる働きを持つ。
資源保存理論を「超える」精神的な支え
- ホブフォールの理論は多くの場面に当てはまるが、人の心は単に資源の増減だけでは説明できない部分がある。
- 哲学・宗教・武士道・禅のような「超越的価値観」は、資源保存理論を超えた視点を提供する。
- つまり、資源を守る発想に加えて、資源への執着を手放す力もストレスに強くなる大きな要素になる。
まとめ|資源保存理論を理解すればストレス対策が見えてくる
資源保存理論は、「人は大切な資源を失うときに最も強いストレスを感じる」というシンプルで分かりやすい考え方です。
日常生活、仕事、人間関係のあらゆる場面で、この理論は役立ちます。
自分にとっての資源を見つけることが大事
- 人によって大切にする資源は違います(お金・健康・人間関係・自由な時間など)。
- まずは「自分にとっての最重要資源は何か?」を振り返ることが、ストレス対策の第一歩です。
- 例:仕事の評価が一番大事な人もいれば、家庭の安心感が大事な人もいます。
資源を守り、増やし、執着しすぎないバランスが重要
- 守る:睡眠・運動・人間関係など、資源を失わない習慣を意識する。
- 増やす:学びや趣味を通じて、新しい心理的・社会的資源を蓄える。
- 手放す:必要以上に資源に執着せず、「失っても仕方ない」と思える柔軟さを持つ。
👉 この3つのバランスを取ることで、ストレスに強く、しなやかに生きることができます。