「やる気って、どうして続かないんだろう?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
たとえば──
「興味があったのに、三日坊主で終わった」
「褒められてもイマイチやる気が出ない」
「自分のやる気スイッチがどこにあるのか分からない」
そんなモヤモヤ、実はあなたの“内側にある3つの欲求”が関係しているかもしれません。
この記事では、心理学の理論「自己決定理論(Self-Determination Theory)」をもとに、
人が自然とやる気になるメカニズムをわかりやすく解説します。
「自律性・有能感・関係性」という3つのキーワードを軸に、モチベーションの種類や続かない理由、教育・仕事・子育てへの活かし方まで幅広くご紹介。
やる気を「根本から理解し直したい」方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
自己決定理論とは?|人が自分から動きたくなる理由

私たちはなぜ、自然とやる気が湧いて行動できるときと、全くやる気が出ずに先延ばししてしまうときがあるのでしょうか?
この疑問に答えてくれるのが、自己決定理論(Self-Determination Theory:SDT)です。
◆ 自己決定理論の定義と基本の考え方
自己決定理論とは、「人は本来、自分の内側から動こうとする力(=内発的動機)を持っている」という前提に立った心理学理論です。
この理論によると、行動を継続するためには「やらされている感覚」ではなく、自分で選んで行動しているという感覚=自己決定感が重要になります。
つまり、モチベーションを高めるには、単に外から「やれ!」と言われるのではなく、自分の意志で「やろう」と思える状況が必要なのです。
◆ エドワード・デシとリチャード・ライアンの理論背景
自己決定理論は、アメリカの心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによって1970年代に提唱されました。
彼らの研究のきっかけは、ある実験でした。
被験者にパズルを解いてもらい、一部の人には金銭報酬を与えるという条件を設定したところ、報酬がなくなるとやる気が下がるという現象が観察されました。
この実験は、外からの報酬が内側からのやる気を奪うことがあるという「アンダーマイニング効果」として有名です。
このような研究を通して、デシとライアンは「モチベーションの“質”」に着目する必要性を示しました。

◆ モチベーションの「質」を重視する理由とは?
一般的に「モチベーション」というと、ある・ないで語られがちです。
しかし自己決定理論では、「どのような理由で動いているのか(=動機の質)」が大切だと考えます。
たとえば:
- 「怒られるからやる」=外発的動機(質が低い)
- 「興味があるからやる」=内発的動機(質が高い)
このように、やる気の源が内側にあるか外側にあるかで、その行動の持続性や満足度が大きく変わってきます。
つまり、「やる気がない」のではなく、「自分でやると感じられない環境がやる気を奪っている」ことが多いのです。
✅ ポイントまとめ
- 自己決定理論は、「人が自発的に行動したくなる条件」を科学的に解き明かす理論。
- モチベーションは「どれだけ高いか」よりも、「どんな質か」が重要。
- 人のやる気を引き出すには、「選べること」「成長実感」「つながり」がカギとなる。
自己決定理論の3つの基本的心理欲求とは?

自己決定理論の中心にあるのが、人間が本能的に持つ3つの「基本的心理欲求」です。
この3つの欲求が満たされることで、私たちは内側から自然とやる気が湧いてくる状態になります。
◆ ① 自律性(Autonomy)|自分で選ぶ感覚がカギ
自律性とは、「自分の意思で行動している」と感じられる感覚のことです。
たとえば、「勉強しなさい」と言われてやるのと、「自分で目標を立てて取り組む」のとでは、やる気の質が全く違います。
✅ 自律性が高まる場面の例
- 仕事のやり方を自分で決められる
- 学習テーマを自分で選べる
- 自分のペースで進められる
つまり、「自分で選んだ」と感じられることが、やる気の根っこになるのです。
◆ ② 有能感(Competence)|できた!という成長実感
有能感とは、「自分はできる」「成長している」と感じられることです。
人は、何かを達成できたときにやる気が高まりやすくなります。逆に、失敗ばかりで進歩を実感できないと、やる気は急速にしぼみます。
✅ 有能感を育てる方法
- 小さな成功体験を積む(ToDoを1つこなすだけでもOK)
- フィードバックをもらう(褒め言葉やアドバイス)
- 自分の成長を見える形で記録する(手帳やアプリなど)
「もっとできるようになりたい」と思えるようになると、自然に行動が続いていきます。

◆ ③ 関係性(Relatedness)|人とのつながりがやる気を支える
関係性とは、「他人とのつながり」や「受け入れられている感覚」を指します。
孤独だったり、否定されたりしていると、どんなに興味のあることでもやる気が続きません。
✅ 関係性が満たされるとき
- 仲間と一緒に取り組める
- 話を聞いてくれる人がいる
- 自分の存在が必要とされていると感じる
人は「誰かのために」「一緒に頑張っている」と感じると、行動への意欲が高まります。
◆ 3つの欲求が満たされたときに起こる変化
この「自律性・有能感・関係性」の3つが満たされていると、次のような状態になります:
- 内発的動機(心からやりたい)が自然と高まる
- 行動が継続しやすくなる
- ストレスが減り、幸福感や自己肯定感が高まる
逆に、どれか一つでも満たされていないと、モチベーションは不安定になります。
たとえば、「やり方は自由だけど誰にも認めてもらえない」といった状況では、やる気は続きにくいのです。
✅ まとめ
| 心理欲求 | 概要 | 満たされると… | 例 |
|---|---|---|---|
| 自律性 | 自分で選んで動いている感覚 | 主体的になれる | 自分でやる内容や方法を選べる仕事や学習 |
| 有能感 | 自分にはできると感じられること | 成長意欲が高まる | 成果が評価される、上達を実感できる場面 |
| 関係性 | 人とのつながりや安心感 | 継続する力が生まれる | 信頼され、仲間と協力できる環境 |
この3つの欲求は、人間が本能的に求めるエネルギー源。
やる気を高めるには、まず「どの欲求が満たされていないか?」を見直すことが大切です。
自己決定理論でわかる動機づけの種類と違い

自己決定理論では、「モチベーションの量(多い・少ない)」よりも、モチベーションの「質(どんな理由で動いているか)」が重視されます。
この視点から、人間のやる気は連続的なグラデーション(スペクトラム)としてとらえられます。
◆ 内発的動機と外発的動機の違いとは?
まず押さえておきたいのが、「内発的動機」と「外発的動機」という基本的な違いです。
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 内発的動機 | 好き・楽しい・興味があるからやる | 趣味・ゲーム・創作活動など |
| 外発的動機 | 報酬・評価・義務・圧力でやる | 成績のために勉強、怒られたくなくて仕事する など |
どちらが「良い・悪い」ではありませんが、内発的動機の方が長続きしやすく、精神的な満足感も高いという研究結果が多く存在します。
◆ 動機づけスペクトラムと4つの段階的分類
自己決定理論では、動機づけをより細かく分類し、次のような5つの段階で説明します。
| 動機のタイプ | 内容 | 自律性 |
|---|---|---|
| 外発的動機づけ(External Regulation) | 報酬・罰など外的要因で動く | 低い |
| 取り入れ的調整(Introjected Regulation) | 義務感・罪悪感で動く | やや低い |
| 同一化的調整(Identified Regulation) | 価値を認めて動く | やや高い |
| 統合的調整(Integrated Regulation) | 自己の価値観と統合されて動く | 高い |
| 内発的動機づけ(Intrinsic Motivation) | 純粋な好奇心や楽しさで動く | 非常に高い |
この分類を見ると、「外発的=やる気がない」とは言い切れず、外発的動機も自律的に変化しうることがわかります。
◆ アンダーマイニング効果|報酬でやる気が下がる理由
「お金をもらったら、逆にやる気がなくなった」
そんな経験はありませんか?これがアンダーマイニング効果(やる気の低下効果)です。
これは、エドワード・デシらの実験で示された現象で、「もともと内発的に動いていた行動に、報酬を与えるとやる気が下がることがある」とされています。
✅ たとえば…
- 絵を描くのが好きな子どもに「上手に描いたらお菓子をあげる」と言った結果、楽しさよりもお菓子目当てになってしまう。
- ゲーム開発者が報酬目当てになると、「作りたいもの」より「売れるもの」を優先して創造性が低下する。
報酬や圧力で人を動かそうとすると、本来持っている内発的動機を壊してしまう危険性があるのです。
✅ ポイントまとめ
- やる気には「内発的」と「外発的」があり、内発的な方が長続きしやすい
- 外発的動機も、自律性の高い段階に変化できる
- 報酬でやる気を奪うこともある(アンダーマイニング効果)
動機の「質」を意識することで、表面的なやる気ではなく、根っこから湧いてくるモチベーションを育てることができます。
なぜやる気が続かないのか?自己決定理論で読み解く心理

「やらなきゃいけないのに、どうしても続かない」
「最初はやる気があったのに、途中で冷めてしまう」
そんな悩みは多くの人が抱えています。
自己決定理論は、この“やる気が続かない理由”を心理的メカニズムから明確に説明してくれます。
◆ 強制・義務・報酬がモチベーションを下げる理由
やる気を失う最大の原因のひとつが、「やらされ感」です。
以下のような環境では、自律性が損なわれ、モチベーションが低下しやすくなります。
- 「提出期限だからやる」
- 「怒られたくないからやる」
- 「ボーナスのためだけにやる」
このような行動はすべて外発的動機づけであり、自律性がない状態です。
一時的には動けても、長期的には疲弊したり、興味を失ったりして続かなくなります。
◆ 「自分で決めた」と感じられないと続かない
自己決定理論では、「選択できることがやる気の根源」とされています。
たとえば、同じ仕事でも…
- 上司に「これをやれ」と言われた → やる気が出ない
- 自分で「やりたい」「必要だ」と思ってやる → 続く
この違いは「自己決定感の有無」にあります。
✅ 自己決定感を高める工夫
- 自分で計画を立てる
- タスクに名前をつけて「意味」を与える。
例:「部屋の掃除」→ 「集中力を取り戻す環境づくり」。名前を変えることで「ただの雑用」ではなく、「目的ある行動」として意味づけされます。 - 小さな選択肢でも自分で決めるようにする
小さな「自分で決めた」という感覚の積み重ねが、継続のカギになります。
◆ やる気が出る人・出ない人の違い
やる気が続く人には、3つの心理的欲求(自律性・有能感・関係性)が自然と満たされる環境が整っていることが多いです。
| 続く人の特徴 | 続かない人の特徴 |
|---|---|
| やり方を選べる | 指示されるだけ |
| 達成感を感じる | 失敗や停滞が多い |
| 応援してくれる人がいる | 孤独・批判される |
これは意志の強さの差ではなく、環境と動機の質の違いです。
✅ まとめ
- やる気が続かない原因は、内発的動機が育たない環境にある
- 特に「やらされ感」が強いと、やる気は奪われる
- 自分で選び、達成感を感じ、人とつながることで、やる気は自然に高まる
やる気を責めるのではなく、「自分がどんな状態で動きやすいのか」を理解することが、持続力の第一歩です。
自己決定理論の活用事例|教育・仕事・子育てへの応用

自己決定理論は、ただの理論にとどまらず、教育・ビジネス・子育てといった日常のあらゆる場面で活用されています。
どんな現場でも共通するのは、「自律性・有能感・関係性」の3つの欲求をどう満たすかが、やる気やパフォーマンスの鍵になるということです。
◆ 教育分野|「自分で学ぶ」力を育てる実践法
学校教育や塾の現場では、テストの点や偏差値に偏ったアプローチではなく、内発的な学習意欲を育てる指導法が注目されています。
✅ SDTを活かした教育のポイント
- 自律性:選べる課題・テーマを導入する(例:自由研究、探究学習)
- 有能感:小テストや習熟度に合わせた達成体験を重ねる
- 関係性:先生が「評価者」ではなく「伴走者」として接する
「やらされる学び」から「自分で学ぶ姿勢」へのシフトこそが、学習継続のポイントになります。
◆ 職場・組織|やらされ感のない職場が成果を生む
職場においても、社員のモチベーションを「報酬や昇進」だけに頼るのではなく、仕事そのものの意味や裁量の大きさが重要です。
✅ 自己決定理論を生かす組織づくり
- 自律性:タスクの方法や順番を任せる、フレックスタイムの導入
- 有能感:明確なフィードバック、スキルアップの支援制度
- 関係性:心理的安全性のあるチーム、ピアサポート文化の促進
Googleの「20%ルール(自分のやりたいことに使える時間)」なども、SDTの思想を活かした事例です。
◆ 子育て・家庭|褒め方や声かけの工夫で自律を育てる
自己決定理論は、子どものやる気や自信を育てるためのヒントにもなります。
ポイントは、「コントロールするのではなく、支える」という姿勢です。
✅ SDTを踏まえた子育てのコツ
- 自律性:「どっちにする?」と選択肢を与える
- 有能感:「よくできたね」より「がんばってたね」の過程を認める
- 関係性:「いつでも見てるよ」「味方だよ」という安心感を伝える
報酬やご褒美だけでは、子どもは自分で動けるようになりません。
「自分で考えて選ぶ」経験を積ませることで、長期的なやる気を育てることができます。
✅ まとめ
| 活用分野 | 自律性の育て方 | 有能感の育て方 | 関係性の育て方 |
|---|---|---|---|
| 教育 | 自分で選べる課題 | 達成を実感できる評価 | 先生との信頼関係 |
| 仕事 | 裁量のある業務設計 | 明確な目標とフィードバック | 心理的安全性 |
| 子育て | 自分で決める習慣づけ | 小さな成功の積み重ね | 親の無条件の支援姿勢 |
あらゆる分野に共通しているのは、「人は信頼され、任されたときに最も力を発揮する」という原則です。
モチベーション理論との比較で深まる理解
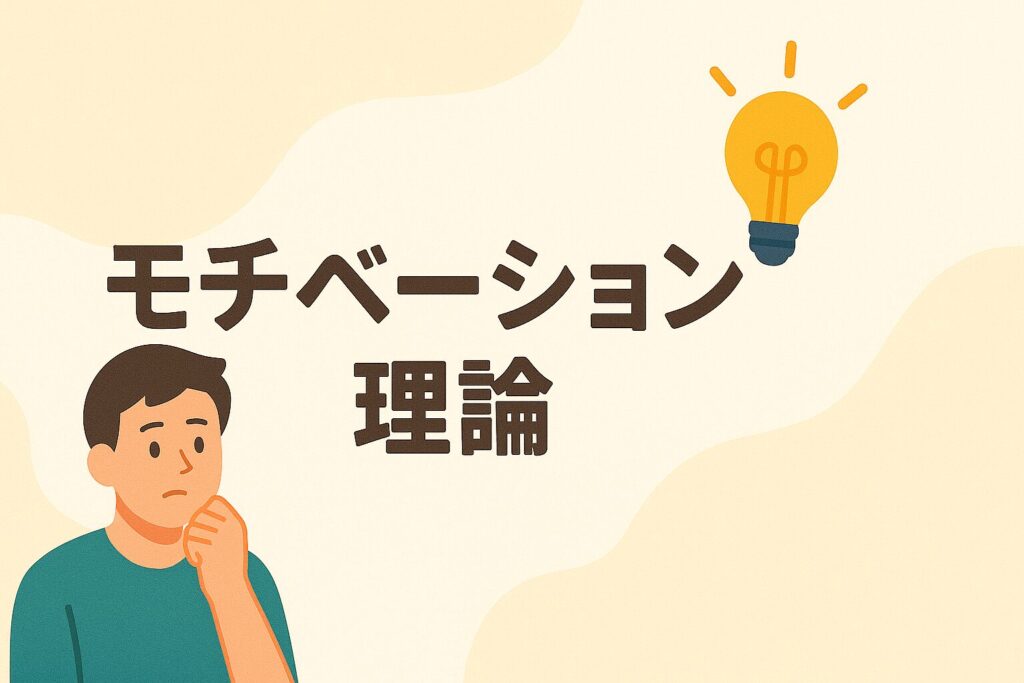
自己決定理論(SDT)は、数あるモチベーション理論の中でも、「人間の内側から湧き出るやる気」に焦点を当てた理論です。
他の代表的な理論と比較することで、自己決定理論の独自性や実用性がよりクリアになります。
◆ モチベーション3.0との共通点と違い
『モチベーション3.0』(ダニエル・ピンク著)は、自己決定理論をベースに、ビジネス向けに再構成された理論です。
✅ モチベーション3.0の3要素
| 要素 | 自己決定理論の対応 |
|---|---|
| 自律性(Autonomy) | 自律性 |
| 熟達(Mastery) | 有能感 |
| 目的(Purpose) | 関係性+価値観との統合的調整 |
つまり、モチベーション3.0は、自己決定理論の3欲求に「目的意識」を加え、現代の働き方に合わせて進化させた理論とも言えます。
違いとしては、ピンクはより実践に特化し、「組織設計」や「リーダーシップ」にすぐ活かせるフレームで解説している点が特徴です。
◆ フロー理論との違い|「没頭」と「動機」の関係
フロー理論(チクセントミハイ)は、やっていることに没頭し、「時間を忘れるほど集中できる状態」を意味します。
これもやる気と関係がありますが、フローは「行動中の心理状態」、一方のSDTは「行動する前の動機づけ」に注目しています。
✅ 両者の違いを整理すると:
| 理論 | 焦点 | キーワード |
|---|---|---|
| 自己決定理論 | 行動の動機 | 自律性・有能感・関係性 |
| フロー理論 | 行動中の体験 | 没頭・挑戦とスキルのバランス・楽しさ |
内発的動機が強いと、フロー状態に入りやすくなるため、両者は補完的な関係にあると言えます。

◆ 目標設定理論や強化理論との位置づけ
✅ 目標設定理論(ロック&レイサム)
- 明確で挑戦的な目標ほど成果が上がるとされる
- ただし、動機の質や自律性を無視すると逆効果になる可能性も
(例:完璧主義や過度なプレッシャーで逆にモチベーションが下がる)

✅ 強化理論(スキナーのオペラント条件づけ)
- 行動に報酬(ご褒美)や罰を与えることでコントロールする
- 行動主義的で短期的には有効だが、自己決定理論の観点では内発的動機を損なうリスクがある

✅ 自己決定理論の位置づけ
- 行動の頻度ではなく、「どんな理由で動いているか」という内面の質に注目
- 長期的なやる気や幸福感の土台をつくる理論
✅ まとめ:自己決定理論の特徴は「やる気の根っこ」を育てる視点
| 理論 | 注目点 | 主な活用分野 |
|---|---|---|
| 自己決定理論 | 動機の質と自律性 | 教育・ビジネス・子育て全般 |
| モチベーション3.0 | 実践的モチベーション設計 | 組織マネジメント・働き方改革 |
| フロー理論 | 没頭と体験の質 | 仕事・スポーツ・創作活動 |
| ゴール設定理論 | 目標の明確さと難易度 | 業務改善・成果管理 |
| 強化理論 | 報酬・罰による行動調整 | トレーニング・初期指導場面 |
こうして比較すると、自己決定理論は「やる気の根っこ」にアプローチする数少ない理論であり、短期ではなく、長期の自立的成長を支えることが分かります。
まとめ|モチベーションを高めるには「自律・成長・つながり」がカギ

ここまで紹介してきた自己決定理論の本質は、人間は本来「やる気のある存在」であるという前提に立っています。
そのやる気が発揮されるかどうかは、「自律性・有能感・関係性」=3つの基本的欲求が満たされているかにかかっているのです。
◆ 3つの欲求が満たされる環境を意識しよう
やる気を育てたいなら、「どうやってやる気を出すか」ではなく、「どういう環境ならやる気が自然に出るか」を考えることが大切です。
✅ 自己決定理論の3つの心理的欲求(おさらい)
| 欲求 | 内容 | 満たす工夫の例 |
|---|---|---|
| 自律性 | 自分で選んでいる感覚 | 選択肢を持つ/自由に決める余地をつくる |
| 有能感 | できる・成長している感覚 | 小さな成功体験/明確なフィードバック |
| 関係性 | 他者とつながっている感覚 | 支援的な人間関係/共感と安心感 |
これらの欲求が1つでも欠けると、モチベーションは一気に不安定になります。
まずは「自分のやる気がどこで止まっているか?」をチェックしてみましょう。
◆ 外発的動機だけに頼らない仕組みづくり
外からの報酬や罰(=外発的動機)は一時的に人を動かすには効果がありますが、持続性や内面的満足感には限界があります。
むしろ、外発的動機だけに頼ると…
- やらされ感が強くなる
- 報酬がないと動けなくなる
- 自分の内側からの意欲が損なわれる(アンダーマイニング効果)
だからこそ、自律性をベースにした「内発的動機」が自然に育つ環境設計が重要です。

◆ 日常でできる内発的動機づけの工夫
日々の生活の中でも、自己決定理論は実践できます。
以下のような小さな工夫が、やる気の質を大きく変えるきっかけになります。
✅ 今日からできる3ステップ
- 選択肢を持つ習慣をつくる
例:作業の順番を決める・タスクを自分で組み立てる - 小さな達成を記録する
例:「できたことリスト」を作る・完了マークをつける - 信頼できる人と関わる
例:進捗を共有する相手を持つ・困ったときに話せる人をつくる
内発的動機は「生まれつきの性格」ではなく、整った環境と工夫で誰でも育てられる能力です。

✅ 最後に
やる気は「意志の強さ」ではなく、心理的欲求が満たされているかどうかで決まります。
だからこそ、他人のやる気を引き出したいときも、自分のやる気を保ちたいときも、
「自律・成長・つながり」というキーワードを大切にしてください。

