「これからの時代、何を信じて計画を立てればいいのか分からない…」
そんな不安を感じたことはありませんか?
AIの進化、気候変動、価値観の多様化――。
先が読めない時代に、「この先どうなるんだろう…」とモヤモヤしていませんか?
一生懸命計画を立てても、想定外の出来事で振り出しに戻る。
そんな経験をした人にこそ知ってほしいのが、シナリオプランニングという考え方です。
これは、未来を“当てる”のではなく、複数の可能性を描いて備える思考法。
この記事では、
- シナリオプランニングの基本と意味
- 石油危機を乗り越えたシェル社の成功事例
- 具体的な進め方(4ステップ)と応用法
をわかりやすく解説します。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
シナリオプランニングとは?──「未来を予測しない」戦略思考の基本
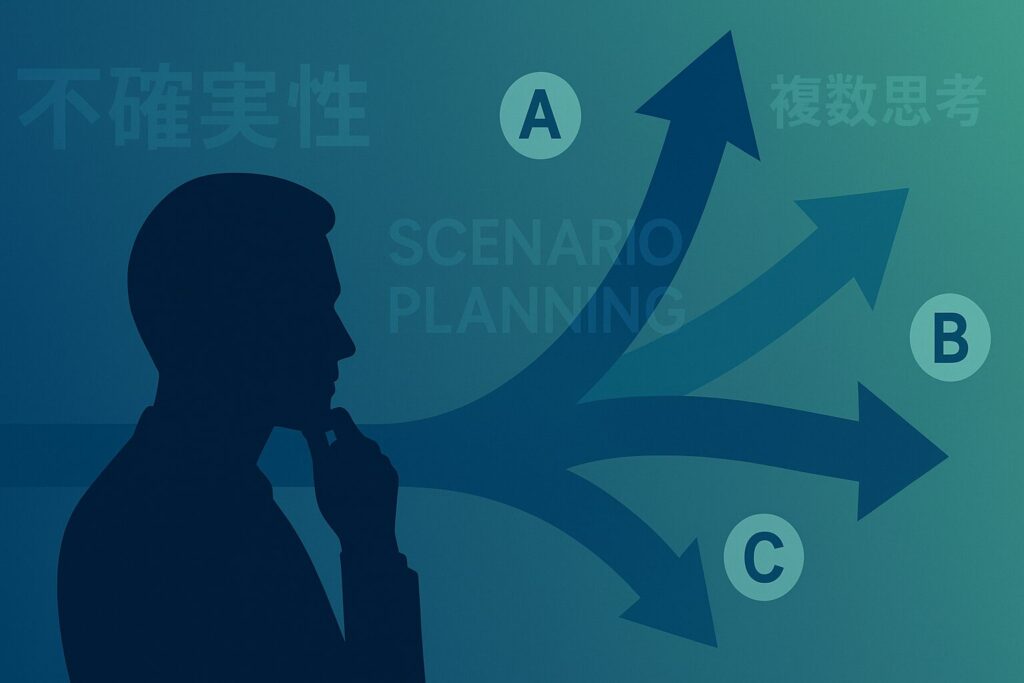
「未来を予測する」のではなく、「複数の未来を想定して備える」——。
これがシナリオプランニング(Scenario Planning)の根本的な考え方です。
現代社会は、経済・技術・環境・価値観のどれをとっても変化が激しく、ひとつの“正しい未来予測”が成立しにくい時代です。
そんな中で注目されているのが、この「未来を1つに決めない戦略思考」です。
未来を“1つ”に絞らない理由:予測よりも準備が重要
多くの人や企業は、「どんな未来が来るか」を正確に予測しようとします。
しかし、現実は予想外の出来事(パンデミック、戦争、AIの進化など)が次々と起こり、“予測の精度”よりも“変化への対応力”が問われるようになりました。
ここで大切なのは、次の発想です。
「当てること」よりも、「備えること」。
シナリオプランニングでは、
- 未来の可能性をいくつか描く
- それぞれのシナリオにどう対応すべきかを考える
- どの未来が来ても“耐えられる戦略”を立てる
という流れで思考を進めます。
つまり、不確実な未来を“敵”ではなく、“想定内”にするための準備法なのです。
不確実性の時代に必要な「複数思考」とは
今の時代は「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる、
変動性(Volatility)・不確実性(Uncertainty)・複雑性(Complexity)・曖昧性(Ambiguity)
が高い環境にあります。
そのような状況では、「正解を1つに絞る思考」ではなく、複数の可能性を同時に持つ“複数思考”が重要です。
たとえば、
- 「もしAの方向に社会が進んだら、私たちはどう動くか?」
- 「逆にBの方向になったら、どんなチャンスがあるか?」
というように、“もしも”を前提にした仮説思考を鍛えていくのです。
この発想を身につけることで、「未来が読めない不安」が「どんな未来にも対応できる安心」へと変わります。

シナリオプランニングの定義と目的をわかりやすく解説
シナリオプランニングとは、
「未来に起こり得る複数の状況(シナリオ)を描き、そのどれにも対応できる戦略を立てる手法」
です。
目的は単に「未来を想像する」ことではなく、
- 不確実性を受け入れる
- 変化のパターンを理解する
- 行動の選択肢を増やす
ことにあります。
つまり、未来を「当てる」ためではなく、
“今の意思決定をより賢くするための道具”がシナリオプランニングです。
この考え方は、企業の経営戦略だけでなく、
キャリア設計・人生の方向性・社会課題の解決など、幅広い分野で活用されています。
まとめると:
- 未来は「予測」ではなく「準備」するもの。
- 不確実性を恐れるのではなく、複数の可能性を想定しておく。
- シナリオプランニングは、「どんな未来が来ても動じない思考力」を育てる。
シナリオプランニングが生まれた背景──「シェル社」が生き残った理由
シナリオプランニングが注目されるようになったきっかけは、1970年代の石油危機にさかのぼります。
この危機を事前に想定し、見事に乗り切った企業がありました。
それが、オランダのロイヤル・ダッチ・シェル社(Shell)です。
1970年代の石油危機とシェル・シナリオモデル
当時、世界の多くの企業は「石油価格は安定して続く」と信じていました。
しかし1973年、オイルショック(第一次石油危機)が発生し、原油価格は約4倍に高騰。
多くの企業が経営危機に陥りました。
ところがシェル社だけは、比較的冷静に対応できたのです。
その理由は、事前に「石油供給が突然止まるシナリオ」を描いていたから。
経営陣はすでに“ありえない未来”を想定していたため、迅速に対応策を実行できました。
これが後に「シェル・シナリオプランニング・モデル」として知られるようになり、
世界中の企業が「未来を複数想定する思考法」に注目するきっかけとなりました。
教訓: 「起こりそうもない未来」を想定しておくことこそが、最大の備えになる。
代表的な理論・モデルから学ぶ|実務で使えるシナリオ思考の枠組み
シナリオプランニングは「考え方」だけでなく、実際に使える具体的なフレームワーク(枠組み)が数多く存在します。
それぞれの特徴を知ることで、自分や組織に合った使い方が見えてきます。
楽観・現実・悲観シナリオ
シナリオプランニングにはさまざまなモデルがありますが、
まずは最も基本的で直感的な「3つの未来シナリオ」を理解しておくと全体像がつかみやすくなります。
この考え方は、どの理論モデルにも共通する“核”の部分です。
| シナリオ | 内容 | 目的・考え方 |
|---|---|---|
| 楽観シナリオ(Optimistic Scenario) | すべてが順調に進み、理想的な未来が実現する。 | チャンスを見つけ、理想を描く視点を持つ。 |
| 現実シナリオ(Probable Scenario) | 現在の延長線上で、もっとも起こりそうな未来。 | 状況を冷静に分析し、今の方向性を確認する。 |
| 悲観シナリオ(Pessimistic Scenario) | 予期せぬリスクや問題が重なり、悪化する未来。 | リスクを想定し、備えを具体的に考える。 |
この3つの視点を持つことで、
「どんな未来が来ても慌てない」柔軟な思考が身につきます。
四象限モデル(2軸4象限で未来を整理)
四象限モデル(2×2マトリクス)は、縦軸・横軸に不確実性の高い要因を配置し、以下のように未来を4パターンに整理します。
| 変化の要素(ドライバー) | 技術が進む | 技術が停滞する |
|---|---|---|
| 経済成長する | A:革新が加速する未来 | B:成長維持型の未来 |
| 経済停滞する | C:格差拡大の未来 | D:停滞と保守化の未来 |
このように“異なる4つの世界観”を並行して考えることで、
「どんな未来でも通用する施策」や「どの未来ならチャンスがあるか」を客観的に整理できます。
CLA(因果層分析)モデルで「深層構造」から未来を読む
オーストラリアの未来学者ソヘイル・イナヤトゥラが提唱した「Causal Layered Analysis(因果層分析)」は、
未来を4つの“深さ”で捉える思考法です。
| 層の名前 | 内容 | 例(AIの未来を考える場合) |
|---|---|---|
| 表層(Litany) | ニュース・データなどの事実 | 「AIが仕事を奪う」 |
| システム層 | 背景の構造や仕組み | 労働市場・教育制度の変化 |
| 世界観層 | 社会の価値観や文化 | 「人間中心かテクノロジー中心か」 |
| 神話・物語層 | 深層にある物語・信念 | 「人類の進化」「創造主の夢」など |
このモデルは「表面の問題の奥にある構造や価値観を可視化する」のが特徴。
組織文化や社会課題の分析にも応用できる、より哲学的なシナリオ思考です。
バックキャスティングやバックキャスティングとの違い
シナリオプランニングは、よく他の未来設計手法と混同されます。
そこで、違いと使い分けを整理しておきましょう。
| 手法 | 目的 | 思考の方向性 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| フォアキャスティング | 過去から未来を予測 | → 未来へ | データ分析中心。予測精度に依存。 |
| バックキャスティング | 理想の未来から逆算 | ← 現在へ | 「望ましい未来」実現のための行動計画。 |
| シナリオプランニング | 不確実性に備える | ↔ 双方向 | 複数の未来を想定し、意思決定を柔軟にする。 |
つまり、
- フォアキャスティング:予測
- バックキャスティング:理想からの逆算
- シナリオプランニング:不確実性への備え
というように、目的とアプローチが異なります。
また、実務ではこれらを組み合わせて使うケースも多く、
たとえば「バックキャスティングで理想像を描き、シナリオプランニングでリスクに備える」といった応用も可能です。
まとめると:
- シナリオプランニングには複数の実用モデルがある。
- 四象限モデルは「不確実性の整理」に強い。
- CLAモデルは「価値観の深層」まで掘り下げる。
- 他の未来設計手法と組み合わせることで、より実践的な戦略思考になる。
シナリオプランニングの進め方|4ステップで「未来の可能性」を描く
理論を理解したあとは、実際にどう進めるかがポイントです。
ここでは、初心者でも実践できるシナリオプランニングの基本4ステップ+オプション(2軸4象限モデル)を紹介します。
この流れを覚えるだけで、個人のキャリア設計から企業戦略まで幅広く応用できます。
① 目的設定:どんな未来を考えるのかを明確にする
最初に行うのは、「どんな未来について考えたいのか」を決めることです。
これは「望ましい未来」ではなく、「考えるべき領域(テーマ)」を決める段階です。
たとえば:
- 仕事:業界の変化・働き方の未来
- 社会:テクノロジーや人口変動の影響
- 個人:キャリア・家族・お金・生き方
ここを明確にすることで、後のステップで出すアイデアが現実と結びつきます。
💡 ポイント
目的は「問題解決」ではなく「未来の探索」から始めるのがコツ。
② 変化のドライバーを洗い出す(社会・技術・価値観など)
次に、未来を左右する変化の要因(ドライバー)を広く出していきます。
代表的な方法が PEST分析(政治・経済・社会・技術) です。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 政治(Political) | 規制・法改正・国際関係・安全保障 |
| 経済(Economic) | 為替・雇用・物価・市場変化 |
| 社会(Social) | ライフスタイル・価値観・人口動態 |
| 技術(Technological) | AI・再エネ・自動運転・通信技術 |
ここでは、「自分ではコントロールできない外部変化」を中心に考えることが重要です。
それが未来の分岐を生む“ドライバー”になります。を分けて考えること。
特に後者の“不確実な変化”が、シナリオの鍵になります。
③ 3つの未来を描く:「楽観・現実・悲観」シナリオの考え方
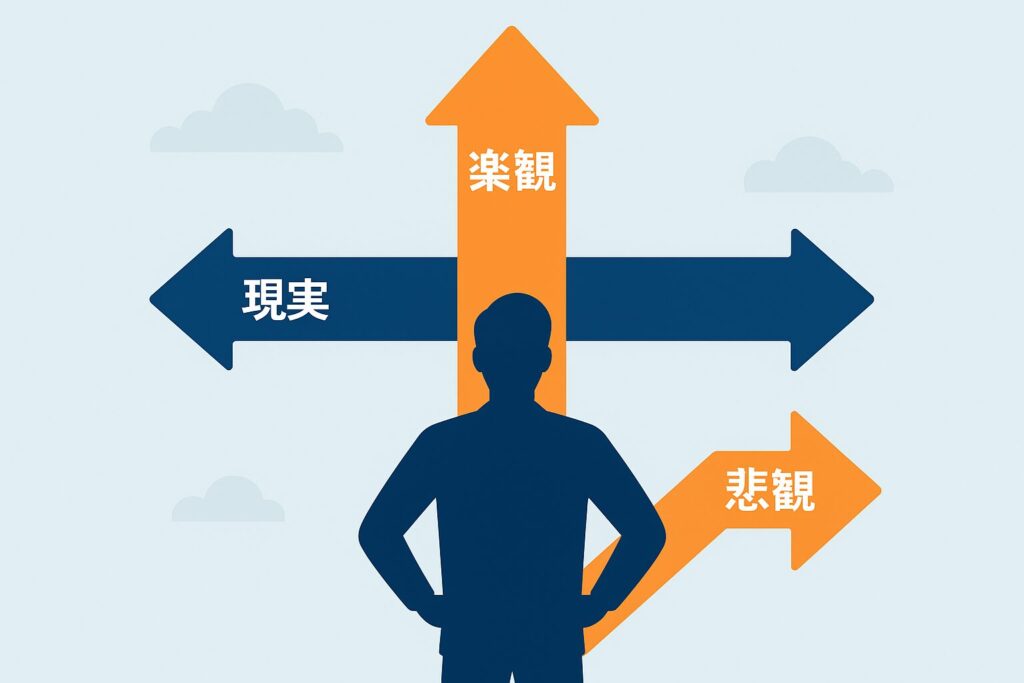
次に、未来を1つに決めず、3つの代表的なシナリオを描きます。
これは初心者にも非常に理解しやすく、個人・組織の両方で使える考え方です。
| シナリオ | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 楽観シナリオ(Optimistic) | すべてがうまくいく未来。理想的な変化やチャンスが広がる。 | AIが雇用を創出し、社会が効率化する。 |
| 現実シナリオ(Probable) | 現在の延長線上にある、もっとも起こりやすい未来。 | AIが一部の業務を自動化するが、人の役割も残る。 |
| 悲観シナリオ(Pessimistic) | 想定外のリスクやトラブルが重なる未来。 | AIによる失業や情報格差が広がる。 |
この3シナリオを同時に考えることで、
「最悪を避けつつ、最良を目指す」現実的な柔軟戦略を描けます。
💡 ポイント
楽観シナリオ=希望を描く力
悲観シナリオ=備える力
現実シナリオ=行動の基準この3つのバランスが「変化に強い思考」を生み出します。
「2軸4象限モデル(Four-Quadrant Scenario Model)」(オプション)
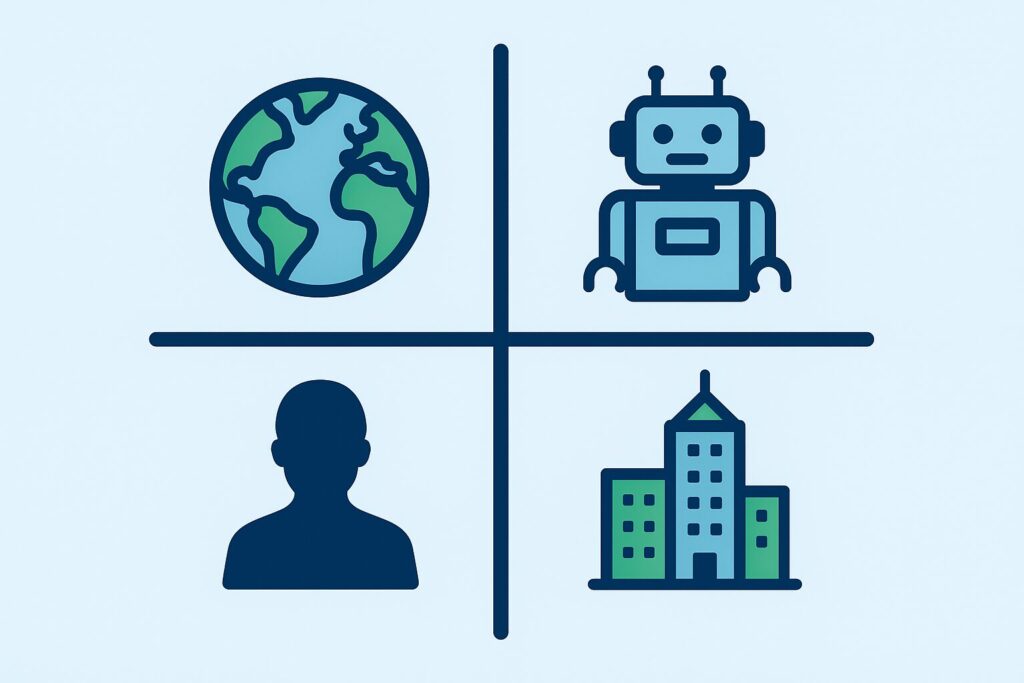
なお、より構造的に考えたい場合は、洗い出した変化の要因をもとに「2軸で4つの未来を整理する方法」もあります。
たとえば「技術進化の速さ × 社会の価値観」のように、2つの軸で未来を分類するやり方です。
ただし、まずは「楽観・現実・悲観」の3シナリオで思考を広げるだけでも十分に効果があります。
■ 手順の概要
- 不確実性が大きい要素を2つ選ぶ
(例:技術進化の速さ × 社会の価値観) - それを縦軸・横軸に配置する
- 交点を基準に4つの象限をつくり、それぞれを“未来の世界”として描く
たとえば、
- 縦軸:テクノロジーの進化(早い/遅い)
- 横軸:社会の価値観(競争重視/共存重視)
この2軸を交差させると、以下のような4つのシナリオ空間が生まれます。
| 変化のドライバー | 共存重視 | 競争重視 |
|---|---|---|
| 技術が進化 | A:AIと人が共創する社会 | B:企業主導で効率化が進む社会 |
| 技術が停滞 | C:地域コミュニティ中心の社会 | D:保守的で格差が固定化する社会 |
この段階では“正しさ”よりも“多様な可能性”を重視しましょう。
④ シナリオをもとに「今の戦略」を見直す
最後に、それぞれの未来シナリオに基づき、「今、何をすべきか」を見直します。
ここでは、3シナリオ+2軸4象限の両方を活かして、現実的かつ柔軟な戦略を立てていきます。
■ まずは3つのシナリオで方向性を確認
| シナリオ | 今の戦略・行動方針 |
|---|---|
| 悲観シナリオ(最悪のケース) | リスク分散・備蓄・保険・複数収入の確保など、「守り」の強化。 |
| 現実シナリオ(最も起こりそうな未来) | 現状を見直し、効率化や継続改善で安定基盤を築く。 |
| 楽観シナリオ(理想の未来) | 新規投資・挑戦・新事業・スキル拡張など、「攻め」の戦略を試す。 |
💡 ポイント
「悲観=守り」「楽観=攻め」「現実=軸の維持」
この3つの視点をセットで考えると、どんな変化にも強くなります。
■ 発展編:2軸4象限モデルで“未来×戦略”をマッピングする
さらに一歩進んで、2つの不確実性を軸に4つの未来像を整理します。
たとえば、以下のような軸を設定してみましょう。
- 縦軸:技術進化のスピード(早い/遅い)
- 横軸:社会の価値観(競争重視/共存重視)
| 技術進化 ↓ × 価値観 → | 競争重視 | 共存重視 |
|---|---|---|
| 急速進化 | 💼 ハイテク競争社会 AIや自動化で生産性が最重要。競争に勝つために学習とスピードを強化。 | 🌍 テクノロジー共存社会 AIと人が協力。教育・倫理・持続性への投資が鍵。 |
| 緩やかな進化 | 🏭 既存構造維持社会 現状維持と改善が中心。効率化・品質向上で安定を重視。 | 🏡 ローカル共生社会 地域や人間関係重視。小規模ビジネス・コミュニティ戦略が有効。 |
■ このマッピングから導ける戦略発想
- 「共通して重要な要素」=どの未来でも通用する“長期資産”
→ 例:柔軟性、学習力、人的ネットワーク、デジタルリテラシー - 「特定シナリオで強い要素」=投資・挑戦すべき“戦略領域”
→ 例:AIスキル・環境対応・ローカル事業など - 「最悪シナリオで弱い要素」=あらかじめリスク回避・撤退検討
→ 例:単一顧客・単一収入源への依存、過剰投資、在庫リスク、需要減少に弱いビジネスモデル
こうして“4つの未来×自分の戦略”を並べると、
「どの方向にも動ける」多軸思考の戦略マップができます。
✅ まとめ
- 3シナリオ:今の方向性を整理する「思考の地図」
- 2軸4象限:未来の環境に合わせて戦略を柔軟に再設計する「戦略の地図」
どちらも、「最悪を避け、最良を掴むための準備ツール」です。
未来は“読むもの”ではなく、“選びながら創るもの”として活用しましょう。
まとめると:
シナリオプランニングの基本4ステップは次の通りです。
- 目的を明確にする
- 変化のドライバーを洗い出す
- 「楽観・現実・悲観」シナリオを考える。
(オプション)2軸で4つの未来を描く。 - 今の戦略を見直す
このプロセスを繰り返すことで、
未来への不安が「選択肢のある安心」へと変わります。
シナリオプランニングの効果とメリット|なぜ今注目されているのか

シナリオプランニングは単なる「未来予測の代替」ではありません。
その本質は、不確実な時代に強い“思考の筋力”を鍛える手法です。
ここでは、企業にも個人にも役立つ4つの主要なメリットを紹介します。
想定外への耐性が高まる(リスクマネジメント)
シナリオプランニングの最大の強みは、「想定外」を減らすことです。
あらかじめ複数の未来を想定しておけば、どんな変化が来ても「想定内」として冷静に対応できます。
たとえば企業であれば:
- 原材料価格が高騰した場合
- AIや自動化で業界構造が変化した場合
- 法規制や国際情勢が不安定になった場合
こうした“もしも”を事前にシナリオ化しておくことで、緊急時の意思決定スピードが格段に上がります。
ポイント:
未来のリスクを「避ける」のではなく、「想定して備える」ことで恐れが小さくなる。
思考の柔軟性と創造性が鍛えられる
シナリオプランニングでは、「AかBか」を決めるのではなく、「AもBも起こり得る」と考えます。
このプロセスが、固定観念にとらわれない柔軟な思考を育てます。
さらに、未来を“ストーリー”として描くため、創造性(クリエイティビティ)も刺激されます。
たとえば:
- 「もしテクノロジーが想像以上に進化したら?」
- 「もし逆に、人間中心の社会に回帰したら?」
というように、ありえそうでありえない未来を言語化する力が身につきます。
この発想力は、イノベーションや新規事業の立案にも直結します。
組織の意思決定が多様な視点で強化される
従来の会議や経営判断では、「1つの正解」を求めがちです。
しかし、シナリオプランニングは多様な立場や視点を持ち寄るプロセスが重要。
- 若手社員が描く「理想の未来」
- ベテランが感じる「現実的リスク」
- 外部専門家が見る「構造的変化」
これらを統合することで、組織の集合知が可視化されるのです。
結果として、「誰かの意見に偏った判断」ではなく、多角的な意思決定ができるようになります。
VUCA時代の戦略立案に最適な理由
現代は、VUCA(ブーカ)と呼ばれる「変動・不確実・複雑・曖昧」な時代。
この環境では、5年先どころか1年後さえ予測が難しい。
だからこそ、
- 変化を恐れずに柔軟に考える力
- どんな状況でも行動を選べる戦略の多様性
が求められています。
シナリオプランニングはまさにこの「VUCA耐性」を高めるための方法です。
不確実性をコントロールできないなら、不確実性と共に生きる思考法を身につける。
未来は、読むものではなく、対応力で乗りこなすもの。
まとめると:
- 想定外を想定内にする「リスク耐性」が身につく
- 柔軟な思考と創造的発想を育てる
- 組織の意思決定が多角的になる
- VUCA時代の生存戦略として最適
シナリオプランニングの応用例
個人キャリアへの応用:10年後の3つの自分を描く
シナリオプランニングはビジネスだけでなく、人生やキャリア設計にも有効です。
1️⃣ 最良の未来(Best Scenario)
理想が実現している状態。自分が望む働き方・暮らし方を具体的に描く。
2️⃣ 現実的な未来(Probable Scenario)
現状の延長線上にある、最も起こりそうな未来。
3️⃣ 最悪の未来(Worst Scenario)
うまくいかなかった場合のリスクや挫折も想定しておく。
この3つを同時に考えることで、
「どんな未来でも行動を止めないための心の準備」ができます。
未来を1つに決めないことが、むしろ“安心”を生む。
バックキャスティングとの併用で“理想の未来”を逆算
実践的な方法として、
バックキャスティング(Backcasting)との併用も効果的です。
- シナリオプランニング:起こりうる複数の未来に備える
- バックキャスティング:「望ましい未来」から逆算して今を考える
つまり、
「最悪の未来を避けつつ、理想の未来に近づく」
というバランスの取れた未来設計が可能になります。
この2つの手法を組み合わせることで、
単なるリスク対策ではなく「創造的な未来デザイン」へと発展させることができます。
まとめると:
- 個人では不安を減らすキャリア設計ツールとして応用可能。
- バックキャスティングと組み合わせると「理想と現実の橋渡し」ができる。
まとめ|未来は「予測する」より「複数で考え、行動する」

ここまで解説してきたように、シナリオプランニングは単なる「未来予測の手法」ではありません。
それはむしろ、不確実性を受け入れながら、行動の幅を広げるための思考法です。
この章では、記事全体の要点を整理しつつ、今日から実践できる一歩を提案します。
未来を固定せず、行動の選択肢を増やす思考法
私たちはつい、「未来はこうなるはずだ」とひとつのシナリオに依存してしまいがちです。
しかし、現実の世界では、複数の未来が同時に進行しているとも言えます。
たとえば:
- テクノロジーが急速に進化する未来
- 環境制約で社会がスローダウンする未来
- 人間中心の価値観が再び重視される未来
これらのどれが“正しい”かは誰にも分かりません。
だからこそ、複数のシナリオを想定し、それぞれに対応できる選択肢を持つことが重要です。
もちろん、「未来は分からないのだから、起こってから考えればいい」という考え方もあります。
実際、それも一つの戦略でしょう。
ただ、シナリオプランニングは“予測を当てる”ためではなく、“動じない自分や組織をつくる”ための準備です。
起こってから考える力と、起こる前に備える力——どちらも未来を生き抜くための重要な思考です。
今日からできる小さな実践:「3つの未来」を描いてみよう
難しいフレームを使わなくても、次のような簡単な方法で、
シナリオプランニングを日常に取り入れることができます。
1️⃣ 紙に「最良の未来」「現実的な未来」「最悪の未来」と3つの枠を書く
2️⃣ それぞれの未来で「自分は何をしているか」「どんな気持ちか」を想像する
3️⃣ 3つの未来に共通して“必要そうな力や習慣”を見つける
4️⃣ その中から「今すぐ始められる行動」を1つだけ書き出す
このシンプルなワークだけでも、
「未来の不安」が「今やるべきこと」へと変わっていく感覚を得られます。
具体例
1️⃣ 「最良=理想の自分として穏やかに暮らす」
「現実=時々不安はあるが安定している」
「最悪=ストレスで体調を崩している」
2️⃣ それぞれで「自分は何を感じているか」を想像する
→ 最良:感謝と充実感/最悪:焦りと孤独感
3️⃣ 共通して必要な力や習慣
→ 「自分を責めない」「小さく整える習慣」「話せる人を持つ」
4️⃣ 今すぐできる行動
→ 「夜寝る前に“今日できたこと”を1行書く」
この記事のまとめ:
| 観点 | 要点 |
|---|---|
| シナリオプランニングとは | 不確実な未来に備え、複数の可能性を描く思考法 |
| 生まれた背景 | シェル社が石油危機を想定して生き残った実例 |
| 代表モデル | 楽観・現実・悲観シナリオ、四象限モデル、CLAなど |
| 手順 | ①目的設定 → ②ドライバー抽出 → ③「楽観・現実・悲観」シナリオ、2軸設定 → ④戦略見直し |
| メリット | リスク耐性・創造性・柔軟性・多様な意思決定 |
| 応用例 | 企業・自治体・個人キャリア・政策立案など |
| 本質 | 未来を「準備」と「創造」で乗り越える |
未来は予測できなくても、備えることはできる。


