「ちょっとした失敗や人の言葉が、いつまでも頭から離れない…」
「悪いことばかり考えて、心が疲れてしまう…」
そんなふうに、考えすぎで悩んでしまうことはありませんか?
その原因のひとつが、私たち全員に備わっているネガティビティバイアスという脳のクセです。
この記事では、ネガティビティバイアスの仕組みや、
そして考えすぎを和らげる具体的な方法をわかりやすく解説します。
読み終えるころには、
「自分だけじゃない」と安心でき、ネガティブに振り回されずに過ごすヒントがきっと見つかるはずです。
ネガティビティバイアスとは?意味と心理学的な背景

私たちは日々、良いことも悪いことも経験しています。
けれど、嫌なことばかり頭に残ってしまうことってありませんか?
それこそが、まさに「ネガティビティバイアス」という心のクセです。
ネガティビティバイアスの定義とは?簡単にわかる説明
ネガティビティバイアスとは、簡単に言うと、
「人はポジティブな情報よりもネガティブな情報を強く感じ、記憶に残しやすい」という心の傾向です。
例えば、こんな経験はありませんか?
- 10人に褒められても、たった1人に批判されるとずっと気になる
- 楽しかった旅行より、旅先でのトラブルの方を鮮明に覚えている
これは脳が、危険や失敗などのネガティブな情報を優先的に覚えるからです。
人間にとってネガティブは、単なる「嫌なこと」ではなく、生き延びるための重要情報でもあったんですね。
人はなぜネガティブに偏るのか?進化心理学の視点
進化心理学という分野では、このバイアスを人類の生存戦略だと考えます。
太古の昔、人間は自然の中で暮らしていました。
- 美味しい果実を見逃しても命に関わらない
- でも、猛獣の気配や毒のある植物を見逃すと命に関わる
つまり、ポジティブを見逃すより、ネガティブを優先する方が生き残る確率が高かったのです。
その性質が現代の私たちにも強く残っているため、些細な失敗や批判でも、過剰に反応してしまうのです。
ネガティビティバイアスと脳の仕組みの関係
では、脳のどんな部分がこのバイアスに関わっているのでしょうか?
重要なのは扁桃体(へんとうたい)という脳の部位です。
- 扁桃体は「感情の司令塔」と呼ばれ、特に恐怖や不安に敏感
- 危険を察知すると即座に体を緊張させ、逃げる準備をする
扁桃体はポジティブなことよりも、ネガティブな刺激に2倍以上強く反応するとされています。
だからちょっとしたネガティブ情報でも、脳が「これは重大な問題かも!」と捉えやすいのです。
また、ネガティブな出来事は海馬(かいば)という記憶をつかさどる部位にもしっかり刻まれやすく、
「忘れたいのに忘れられない」という状態を引き起こす原因にもなります。
ネガティビティバイアスに関する有名な研究や理論
ネガティビティバイアスは心理学や行動経済学の世界でも、非常に有名な概念です。
代表的な研究をいくつかご紹介します。
- バウマイスターらの研究(Bad is stronger than good)
- 「悪いことは良いことより強い」という有名な論文で、
悪い出来事は良い出来事より2倍〜5倍心に影響を与えると指摘しています。
- 「悪いことは良いことより強い」という有名な論文で、
- カーネマンとトヴェルスキーの「損失回避」
- ノーベル賞を受賞したカーネマンの研究で、
人は利益を得る喜びより、同じ額を失う痛みの方が2倍以上大きく感じると証明されました。
これもネガティビティバイアスの一種です。
- ノーベル賞を受賞したカーネマンの研究で、
- SNSの研究
- ネガティブな投稿はポジティブな投稿より拡散されやすい、という研究もあり、
現代社会でこのバイアスが増幅されていることが問題視されています。
- ネガティブな投稿はポジティブな投稿より拡散されやすい、という研究もあり、

ネガティビティバイアスの具体例|日常生活に潜む「考えすぎ」の原因

ネガティビティバイアスは「心のクセ」なので、気づかないうちに私たちの日常生活のあらゆる場面に潜んでいます。
「なんでこんなに考えすぎてしまうんだろう」と感じるとき、実はこのバイアスが関わっていることが多いのです。
ここでは、具体的な例や背景をわかりやすく解説します!
日常で起こりがちなネガティビティバイアスの例
まずは日常のシンプルな例をいくつかご紹介します。
- 上司に少しきつく注意されただけで、一日中気分が落ち込む
- 道で知り合いに無視された気がして、「嫌われたかも」とずっと考えてしまう
- 仕事で一度ミスをすると、「自分はダメだ」と繰り返し思い出してしまう
こうした現象は、実際にはそれほど深刻でないことが多いのに、ネガティブな解釈を繰り返してしまうことが原因です。
脳が「危険かもしれない」と過剰に反応しているんですね。
SNSやニュースに潜むネガティビティバイアス
現代人に特に多いのが、SNSやニュースによるネガティビティバイアスの刺激です。
- ネガティブなニュースばかり目につく
- SNSで誰かの怒りの投稿を見て不安になる
- 自分には関係ないのに「自分も同じ目に遭うかも」と怖くなる
これはSNSのアルゴリズムも影響しています。
ネガティブな投稿の方が人々の興味を引きやすく、シェアや「いいね!」が増えるからです。
たとえばTwitterで「怒り」「批判」「炎上」といった言葉が入っている投稿は、
ポジティブな投稿より何倍も拡散されやすいことが研究で示されています。
結果として、私たちは「世の中は悪いことだらけ」と感じやすくなってしまうのです。
人間関係でのネガティビティバイアスの影響
人間関係にもネガティビティバイアスは深く影響します。
- 相手が少し不機嫌だと、「自分のせいかも」と思い込む
- 恋人や友人のちょっとした言葉をネガティブに解釈する
- 良い思い出より、ケンカやトラブルばかり思い出す
こうしたバイアスは、相手の気持ちを勝手に悪く想像してしまう原因になります。
人との距離感が不安になり、コミュニケーションを避けてしまう人もいます。
でも実際には、相手が疲れていただけ、忙しかっただけ…ということも多いものです。
ネガティビティバイアスが心に残りやすい理由
では、どうしてネガティブなことだけがいつまでも心に残るのでしょうか?
理由は次の通りです。
- 脳は危険を忘れないようにプログラムされている
- 「次は同じ失敗をしないように」という防衛本能が働くため
- 感情が強い出来事ほど記憶に刻まれやすい
- 特に恐怖や不安は、脳の扁桃体が強く反応し、海馬に深く記憶を刻む
- ネガティブな考えは繰り返し思い出しやすい
- 「反すう思考」と呼ばれ、頭の中で何度も再生してしまうクセがある
たとえば、「恥ずかしい失敗」を寝る前にふと思い出し、
「なんであんなこと言っちゃったんだろう」とグルグル考えて眠れなくなるのもネガティビティバイアスの影響です。
ネガティビティバイアスが引き起こす悩みとリスク
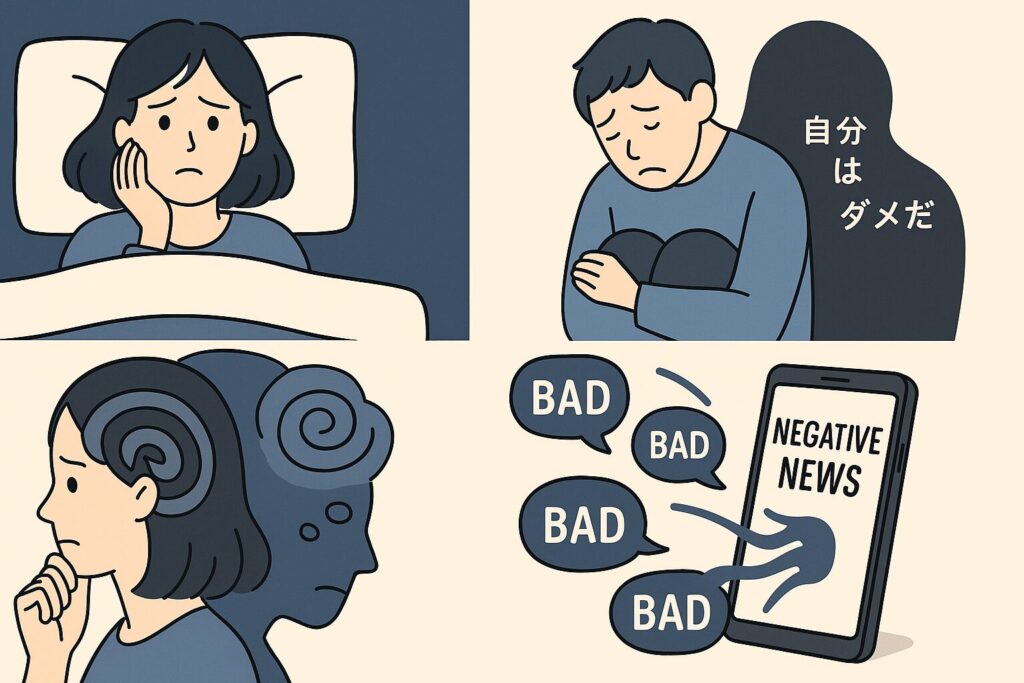
ネガティビティバイアスは、単に「嫌なことを覚えてしまう」というだけでなく、
私たちの心や生活にさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。
ここでは、考えすぎによる具体的な悩みやリスクをわかりやすく解説します。
考えすぎによるストレスや不安
ネガティビティバイアスが強い人ほど、物事を必要以上に深刻に考えてしまいがちです。
- 「もし〇〇が起こったらどうしよう…」と延々と不安になる
- 小さな失敗が頭から離れず、ずっとモヤモヤする
- 不安で夜眠れなくなる
こうした状態を*「反芻思考」と呼びます。
「反芻思考」とは、牛が食べ物を何度も口の中に戻して噛み直すことを指しますが、
心の中でも嫌な記憶や不安を何度も何度も思い返してしまうのです。
その結果、ストレスホルモン(コルチゾール)が増え、心も体も疲れやすくなります。
ネガティビティバイアスが自己肯定感を下げる仕組み
ネガティビティバイアスは、自己肯定感の低下にも大きく関わっています。
例えば:
- 一度の失敗で「自分はダメな人間だ」と思い込む
- ほめられたことより、叱られたことばかり思い出す
- 「どうせ自分なんか」と自信をなくす
これは脳がネガティブ情報を優先して覚えるため、
ポジティブな評価が頭に入りにくくなるからです。
結果的に「自分には価値がない」という自己否定のスパイラルに陥りやすくなります。
悪いことばかり考えてしまう心理的負の連鎖
ネガティビティバイアスは、悪いことばかり考える「負の連鎖」を生みます。
その流れは次のようなものです。
- 嫌な出来事を思い出す
- 「また同じことが起きるかも」と不安になる
- さらに別の不安や失敗も思い出す
- 気分が落ち込み、行動できなくなる
こうして、どんどんネガティブ思考が増幅してしまいます。
たとえば、過去に人前で失敗した経験があると、
「また失敗するかも」という恐怖が強まり、行動を避けてしまうことがあります。
それによって、チャンスを逃したり、人間関係が狭まったりするリスクが高まるのです。
ネガティブ情報に振り回される現代人の問題
現代は、ネガティビティバイアスをますます強めやすい環境です。
- SNSやニュースのネガティブ情報が絶えず目に入る
- 他人の怒りや批判の投稿が拡散されやすい
- 悪い出来事が強調される報道が多い
こうした情報が私たちの脳に刺激を与え、
「世の中は危険だ」「不安だ」という感覚を増幅させます。
そして結果的に:
- 気持ちが落ち込みやすくなる
- 人間関係や仕事に悪影響が出る
- 無意識にネガティブな情報ばかり探してしまう
このように、ネガティビティバイアスを放置すると、日常生活がどんどん苦しくなる可能性があります。
ネガティビティバイアスは、私たちの心を守るための本能でもありますが、
現代社会では強すぎることで逆に心を疲れさせてしまうことも多いのです。
ネガティビティバイアスを和らげる考えすぎない方法

「ネガティビティバイアスがあるのはわかったけど、じゃあどうすれば考えすぎずにすむの?」
多くの人が一番知りたいのは、きっとこの部分だと思います。
ここでは、ネガティビティバイアスを和らげる具体的な方法を、分かりやすくご紹介します!
ネガティビティバイアスに気づくことが第一歩
まず大事なのは、自分が今ネガティビティバイアスの影響を受けていると気づくことです。
例えば:
- 「あれもこれも不安だ」と思い始めたとき
- 「どうせダメだ」と決めつけたくなったとき
こんなとき、「あ、ネガティビティバイアスかもしれない」と一度立ち止まってみましょう。
気づくだけで、心に少し距離ができて、感情に振り回されにくくなります。
これは「メタ認知」という心の働きで、自分を客観的に観察する力とも言えます。
ポジティブを意識的に増やす習慣とは?
ネガティビティバイアスは自然にポジティブよりネガティブを優先してしまいます。
だからこそ、意識してポジティブを探す習慣を作るのが効果的です。
簡単にできる方法は例えば以下の通りです。
- 三行ポジティブ日記
→ 今日あった「良かったこと」を3つ書き出す - ありがとうリスト
→ 誰かや何かに感謝したいことを毎日ひとつ書く - ポジティブ振り返りタイム
→ 寝る前に「今日うまくいったこと」を思い出す
こうした小さな習慣でも、脳のポジティブ回路が活性化し、ネガティブに偏りすぎない心を育てられます。
思考を書き出して整理する「感情ノート」活用法
頭の中でぐるぐる考えているだけだと、ネガティブ思考はどんどん膨らみます。
そんなときは、思い切って紙やスマホに書き出すことがおすすめです。
【感情ノートの書き方の例】
- 不安やモヤモヤを書き出す
→ 例:「上司にきついことを言われて不安」 - その出来事の事実だけを書いてみる
→ 「上司が声を荒げて注意した」 - 別の可能性を考える
→ 「上司は他のことでイライラしていたかもしれない」 - 自分ができることを書いてみる
→ 「次は確認してから行動しよう」
こうすることで、感情が整理され、
「本当に大ごとなのか?」と冷静に考えられるようになります。
関連書籍
SNSやニュースとの上手な距離の取り方
ネガティビティバイアスを強める大きな要因が、SNSやニュースの過剰摂取です。
次のような対策を試してみましょう。
- SNSをチェックする時間を決める
→ 例:「朝と夜だけ見る」 - ネガティブ投稿が多いアカウントをフォロー解除
- ポジティブな発信をする人をフォローする
- ニュースアプリの通知を減らす
SNSやニュースは便利ですが、無制限に浴び続けると不安や怒りに心が支配されやすくなるので、
意識的に距離を取ることが大切です。
ネガティビティバイアスを手放すマインドフルネスのすすめ
「マインドフルネス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
簡単に言うと「今この瞬間に意識を向ける」練習です。
例えば:
- ゆっくり呼吸に集中する
- 食事を五感で味わう
- 散歩しながら周りの景色や音に意識を向ける
これを繰り返すことで、脳が「今ここ」に戻り、
過去の失敗や未来の不安に引きずられにくくなります。
マインドフルネスは、科学的にもストレス軽減やネガティブ思考の減少に効果があるとされています。
最初は1分間の深呼吸からでも十分です。
ネガティビティバイアスは完全に消すことはできません。
でも、こうした方法を実践することで、考えすぎを減らし、穏やかに過ごすことができます。
ネガティビティバイアスとうまく付き合うために大切なこと

ネガティビティバイアスを完全になくすことはできません。
それは私たちが生き延びるために備わった、人間の本能的な機能だからです。
大切なのは「どうしたらこのバイアスに振り回されず、うまく付き合えるか」ということ。
ここでは、そのために覚えておきたい心構えや考え方を解説します。
「悪いことが目立つのは人間の性質」と理解する
まず知っておいてほしいのは、ネガティビティバイアスは誰にでもある普通のことだという事実です。
- 「私って心が弱いのかな…」
- 「ネガティブすぎておかしいのかも」
と悩む必要はありません。
人間は生き残るために、危険や嫌なことに敏感でいるよう進化してきました。
だから、悪いことの方が強く心に残るのは当たり前なのです。
この事実を知るだけでも、「自分だけじゃない」と少し心が軽くなりますよ。
自分を責めないための心理的ヒント
ネガティビティバイアスが強く出ると、つい自分を責めがちです。
でも、自分を責めすぎると余計にネガティブの沼にはまってしまいます。
自分を責めないためには、次のようなことを意識してみてください。
- 「今は不安になっているだけ」と心の中で声をかける
→ 感情と自分を切り離す練習です。 - 完璧を目指さない
→ ネガティブな感情が出るのは仕方ない、と認める。 - 「まあ、いいか」を口癖にする
→ 少し気持ちを緩める言葉です。
大事なのは「ネガティブになった自分」を否定しないこと。
受け入れるだけでも、心の負担は軽くなります。
長期的に考えすぎを減らすための心構え
ネガティビティバイアスと付き合うには、短期的な対処法だけでなく長期的な視点が大切です。
以下のような心構えを持つと、考えすぎを少しずつ減らせます。
- 悪いことが起きても、それがすべてではないと知る
→ 人生は良いことも悪いことも混ざっているもの。 - 「10年後には覚えていないかもしれない」と考えてみる
→ 長期の視点を持つだけで心が楽になります。 - 失敗も経験のうち、と割り切る
→ 完璧でなくても大丈夫、と自分に言い聞かせる。
こうした考え方を繰り返すうちに、
ネガティブな出来事に過剰に心を奪われる時間が少しずつ減っていきます。
専門家に相談するのも一つの選択肢
もしネガティビティバイアスによる考えすぎが、
- 日常生活に支障をきたすほど辛い
- 眠れない、食欲が落ちた
- 強い不安や落ち込みが続いている
そんな場合は、一人で抱え込まないでください。
心理カウンセラーや医師など専門家に相談することも立派な対策です。
最近はオンラインカウンセリングもあり、家にいながら気軽に相談できます。
話すだけで心が軽くなることも多いので、遠慮せず頼ってくださいね。
もし「対面はちょっとハードルが高いな…」と感じる方には、オンラインカウンセリング「Kimochi」
![]() もおすすめです。
もおすすめです。
スマホやパソコンで自宅から相談できるので、忙しい人や外出が不安な方でも安心です。
専門家と話すことで、ネガティビティバイアスによる考えすぎが整理でき、心が少し軽くなるきっかけになるかもしれませんよ。
HSPとネガティビティバイアスの関係

最近、「HSP(Highly Sensitive Person/ハイリー・センシティブ・パーソン)」という言葉をよく耳にするようになりました。
HSPとは、簡単に言うと刺激に敏感で、感情を深く感じ取りやすい人のことです。
実はこのHSPの特性と、ネガティビティバイアスには深い関わりがあります。
ここでは、その関係をわかりやすく解説します。
HSPはネガティブ情報を強くキャッチしやすい
HSPの人は、五感が敏感で、周りの人の表情や声のトーン、小さな変化にもすぐ気づきます。
そのため、次のような傾向が起きやすいのです。
- 他人の機嫌が少し悪いだけで「自分のせいかも」と感じる
- ネガティブなニュースを見ると、自分のことのように心を痛める
- 人混みや騒音で気疲れしやすい
これは脳が、危険や不快を素早く察知しようとする「ネガティビティバイアス」の働きを、より強く受けやすいからです。
HSPの脳はネガティブ刺激に敏感
脳科学的にも、HSPの人は脳の扁桃体(へんとうたい)が活発に働きやすいことがわかっています。
扁桃体は、恐怖や不安などのネガティブな感情を素早く反応する場所です。
そのため:
- 嫌な出来事をいつまでも引きずる
- 小さなトラブルが頭から離れない
- 「また同じことが起きるかも」と考え続けてしまう
こうした状態に陥りやすくなります。
まさにHSPの繊細さが、ネガティビティバイアスを増幅させてしまうのです。
HSPとネガティビティバイアスを和らげるヒント
では、HSPの人はどうしたらネガティビティバイアスの影響を減らせるのでしょうか?
以下のような方法が効果的です。
- 情報を取捨選択する
→ ニュースやSNSを見すぎない。ネガティブ情報を意識的に減らす。 - 感情を紙に書き出す
→ 頭の中でグルグル考えず、文字にすることで整理しやすい。 - 安心できる環境を作る
→ 静かな時間や一人の空間を確保する。 - マインドフルネスを取り入れる
→ 「今ここ」に意識を向ける練習をする。
HSPの人は、豊かな感受性や深い共感力という素晴らしい長所を持っています。
ネガティビティバイアスと上手に付き合えば、その敏感さは大きな強みにもなるのです。
まとめ|ネガティビティバイアスを知り、考えすぎに振り回されない毎日へ
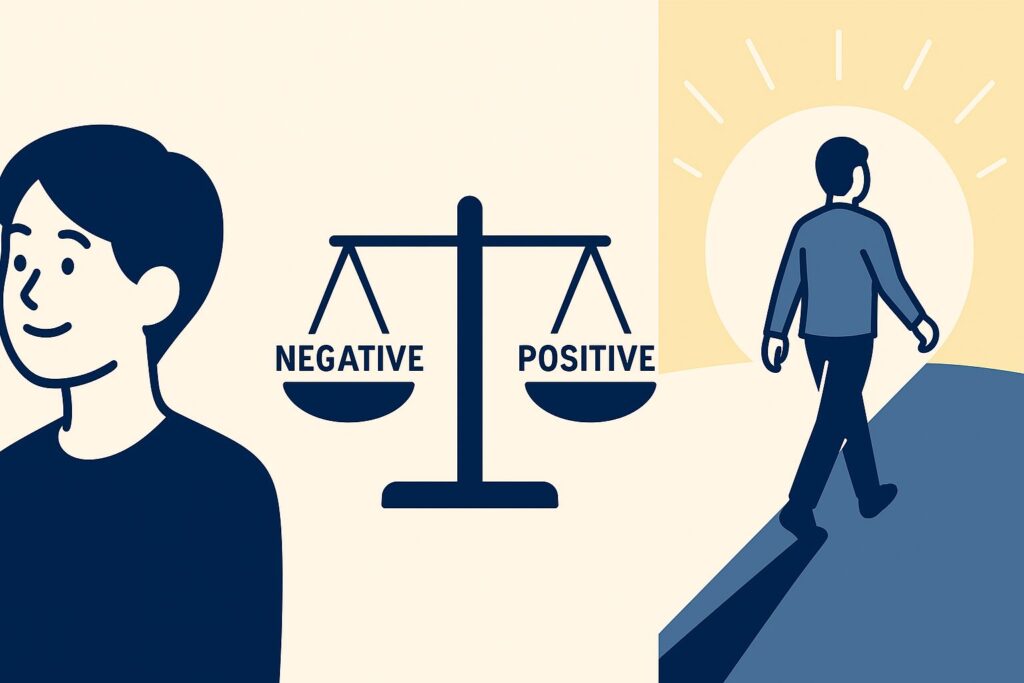
ここまで、ネガティビティバイアスとは何か、そして考えすぎないための方法についてお話ししてきました。
最後に、この記事で紹介した重要なポイントをまとめました。
ネガティビティバイアスを知るだけでも楽になる理由
まず知っておいてほしいのは、ネガティビティバイアスは誰にでも備わっている脳の仕組みだということです。
「人間はもともと危険に敏感になるようにできている」
こう理解するだけで、少し心が楽になりませんか?
「自分だけがおかしいんじゃない」と思えることは、ネガティブな感情に振り回されないための第一歩です。
今日からできる小さな一歩
ネガティビティバイアスは、完全に消せなくても弱めることは十分できます。
そのために、ぜひ今日からできる小さな一歩を試してみてください。
例えば:
- 今日あった「良かったこと」を3つ書き出す
- ネガティブになったら「これは脳のクセかも」とつぶやく
- SNSやニュースをチェックする時間を決める
- 深呼吸を1分だけしてみる
大きなことを変えなくても、こうした小さな行動の積み重ねが、
ネガティブの波を少しずつ穏やかにしてくれます。
不安が強いときはどうする?
とはいえ、時には不安や考えすぎがどうしても止まらないこともありますよね。
そんなときは、次のようにしてみてください。
- 「今は不安なだけ」とラベリングする
→ 感情をただの状態として捉える練習です。 - 誰かに話す
→ 声に出すことで気持ちが整理されることがあります。 - 必要なら専門家に相談する
→ 一人で抱え込むより、早く楽になる道もあります。
「不安が強いのは自分の弱さだ」と思わないでください。
脳の仕組みであり、誰にでも起こることなのです。
ネガティビティバイアスは、人間にとって大切な防衛本能でもあります。
でも、現代社会ではそれが行き過ぎて、心を疲れさせてしまうこともあります。
知ることは、対処するための第一歩。
自分の心のクセを理解し、考えすぎに振り回されない毎日を過ごしましょう。

