誰かを失ったとき、時間が経っても現実を受け入れられない——そんな経験はありませんか?
「どうしてこんなに悲しいの?」「いつまでこの気持ちは続くんだろう?」と、自分の感情に戸惑う人は少なくありません。
この記事では、心理学者エリザベス・キューブラー=ロスが提唱した「悲嘆の5段階モデル」をもとに、
人が喪失をどう受け入れていくのかをわかりやすく解説します。
「否認」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」という5つのプロセスを通して、
私たちの心がどのように“理解”と“回復”へ向かっていくのかを見ていきましょう。
また後半では、「5段階モデルの限界」や「現代のグリーフケア(悲嘆ケア)」、
そして悲しみを意味づけ直す心理学的アプローチも紹介します。
どうか焦らず、あなたのペースで読み進めてくださいね。
キューブラー=ロスとは?悲嘆の5段階モデルの基本を理解する
人が大切な存在を失ったとき、心の中ではどんな変化が起きるのでしょうか。
その問いに真正面から向き合ったのが、エリザベス・キューブラー=ロス(Elisabeth Kübler-Ross)です。
彼女の提唱した「悲嘆の5段階モデル(Five Stages of Grief)」は、半世紀以上にわたり心理学・医療・カウンセリングの現場で広く引用されてきました。
エリザベス・キューブラー=ロスの経歴と理論の背景
キューブラー=ロスは1926年生まれのスイス出身の精神科医で、1960年代にアメリカで終末期医療(ターミナルケア)の研究を行いました。
当時の医療現場では、患者に「死」を正面から語ることはタブー視されていました。
しかし彼女は、死を隠すのではなく、理解し、尊厳を持って受け止めることが重要だと考えたのです。
患者へのインタビューを重ねるうちに、彼女は共通する心の変化に気づきました。
それが、「否認」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」という5つの心理的プロセスです。
この発見が後に「悲嘆の5段階モデル」として体系化されました。
『死ぬ瞬間(On Death and Dying)』に描かれた研究内容
1969年に出版された彼女の代表作『死ぬ瞬間(On Death and Dying)』は、世界40か国以上で翻訳され、死生学の古典となりました。
この書籍では、末期患者200人以上への面接をもとに、死を宣告された人がどのように心の準備をしていくかがリアルに描かれています。
悲嘆の5段階モデルが注目された理由と心理学への影響
この理論が多くの人に支持された理由は、“人の心は段階的に整理されていく”というわかりやすさにあります。
喪失に直面したとき、「自分は今どの段階にいるのか」を理解することで、混乱や恐怖を言語化しやすくなります。
その後、このモデルは死別に限らず、離婚・失業・病気・人生の転機など、
あらゆる「喪失体験」の心理理解に応用されるようになりました。
また、キューブラー=ロスの研究は、心理学だけでなくグリーフケア(悲嘆ケア)・スピリチュアルケア・臨床心理・教育現場にも影響を与え、
「死を語ることは生を深く理解することでもある」という新しい価値観を広めました。
悲嘆のプロセス5段階|それぞれの意味と特徴をわかりやすく解説

キューブラー=ロスが提唱した「悲嘆の5段階モデル(Five Stages of Grief)」は、
喪失という現実を心が少しずつ受け止めていく心理的なプロセスの地図です。
この5段階は「順番通りに進む」ものではなく、人によって順序や強弱、期間も異なります。
ときに前後したり、ある段階に長くとどまったりするのが自然な反応です。
以下では、各段階の意味・心理状態・典型的な思考や行動を、初心者にもわかりやすく解説します。
① 否認(Denial)|現実を受け入れられない心の防衛反応
最初に現れるのは、「まさか」「そんなはずはない」と感じるショックと否認の反応です。
これは、あまりにも大きな現実から自分を守るための心の防衛機能(防衛反応)。
- よくある思考:「きっと何かの間違いだ」「夢じゃないの?」
- よくある行動:現実を直視せず、いつも通りの生活を続けようとする。
👉 否認は「逃げ」ではなく、心が痛みに耐えられるよう準備する時間でもあります。
現実を少しずつ処理する“緩衝材”のような段階です。
② 怒り(Anger)|理不尽さや不公平さに対する感情の爆発
次に現れるのは、「なぜ自分が」「どうしてこんなことに」という怒りや恨みの感情です。
この怒りは相手・状況・神・医者・自分自身など、行き場のないエネルギーとして向けられます。
- よくある思考:「あのときもっとこうしていれば」「誰かのせいだ」
- よくある行動:人や環境への苛立ち、自己攻撃的な言葉、涙を伴う感情表出。
👉 怒りは、「本当は悲しい」気持ちを覆い隠す防衛反応。
怒れるのは、失ったものを大切に思っている証でもあります。
③ 取引(Bargaining)|「もし〜なら」という希望的な思考
現実を少しずつ受け入れ始めると、人は「もしあのとき○○していたら」と、
運命や神との“取引”を試みる段階に入ります。
- よくある思考:「もう少し頑張れば救われるかも」「もし奇跡が起きたら…」
- よくある行動:宗教的祈り、願掛け、努力による償いの行動など。
👉 この段階は、「失われたものを取り戻したい」という切実な希望の表れです。
やがて現実を受け入れる準備段階として、次の“抑うつ”へと移行していきます。
④ 抑うつ(Depression)|深い悲しみと無力感の時期
ここでは、喪失の現実が心に深く浸透し、悲しみ・孤独・無気力に包まれます。
涙が止まらなかったり、何もしたくなくなったりすることがあります。
- よくある思考:「もう何も意味がない」「自分は一人だ」
- よくある行動:引きこもり、睡眠や食欲の乱れ、沈黙が増える。
👉 抑うつは「異常」ではなく、自然な悲嘆の過程です。
この時期に感情を押し殺すより、静かに悲しみを感じきることが心の回復につながります。
⑤ 受容(Acceptance)|現実を受け止め、穏やかに前へ進む段階
最終段階は、現実を完全に理解し、新しい日常へと適応する時期です。
悲しみが消えるわけではありませんが、心の中で穏やかな受け入れが起こります。
- よくある思考:「もうあの人はいないけれど、心の中にいる」
- よくある行動:故人を思い出して感謝する、新しい趣味や人間関係を築く。
👉 受容とは「忘れること」ではなく、悲しみと共に生きることを選ぶ段階です。
このプロセスを通して、人は再び生きる力を取り戻していきます。
悲嘆の5段階モデルの限界と誤解されやすいポイント
キューブラー=ロスの「悲嘆の5段階モデル」は、多くの人に心の地図を与えた重要な理論ですが、近年では「必ずしもすべての人に当てはまるわけではない」と見直されています。
ここでは、誤解されやすい点と、現代の心理学が重視する「柔軟な理解」の視点を整理します。
悲嘆は“段階的”ではない|人によって異なる感情のプロセス
5段階モデルは、まるで「順番通りに進むステップ」のように捉えられがちです。
しかし実際には、人によって順序も期間もバラバラで、怒りを感じない人もいれば、受容まで何年もかかる人もいます。
悲嘆とは、時間の経過で“終わる”ものではなく、波のように揺れ動く感情のプロセスです。
ある日は平穏に過ごせても、ふとしたきっかけで涙があふれる。
それが人間の自然な反応です。
👉 つまり、悲嘆は「段階を踏む課題」ではなく、行きつ戻りつする心の旅路なのです。
「自分の悲しみ方が間違っている」と感じてしまう危険
5段階モデルが広く知られた結果、
「怒りを感じない自分はおかしいのでは?」
「もう抑うつが終わったのに、また悲しくなるのは後退では?」
と感じてしまう人が少なくありません。
これは、モデルが“正しい悲しみ方”を示すものではないことを忘れてしまう誤解です。
悲嘆には「正解」も「順番」もなく、その人の感じ方すべてが自然なプロセスです。
たとえば、ある人は怒りを通らず静かに受け入れ、
また別の人は何年も取引の段階にとどまることがあります。
どちらも“間違い”ではありません。
現代のグリーフケアでは“柔軟な理解”が重視されている
近年のグリーフセラピーでは、
キューブラー=ロスのモデルを「絶対的な段階」ではなく、理解のための目安として扱います。
代わりに重視されているのが、
- 個人の体験を尊重するナラティブ(語り)アプローチ
- 悲嘆を“克服”ではなく“意味づけ”として理解する意味再構築理論(Meaning Reconstruction Theory)
といった、より柔軟で現実的な視点です。
この流れの背景には、
「悲嘆は終わるものではなく、“新しい形で生き続ける”もの」
という考え方があります。
つまり、悲しみを手放すのではなく、それを自分の一部として再統合していくことが、癒しの核心なのです。
現代の心理学が示す新しい視点|意味再構築理論との関係

「悲嘆の5段階モデル」は、喪失体験を理解するための土台として今も重要ですが、
現代の心理学では、それをさらに発展させた考え方として「意味再構築理論(Meaning Reconstruction Theory:MRT)」が注目されています。
この理論は、悲しみを“乗り越える”のではなく、「人生の意味を再びつくり直す」ことに焦点を当てています。
ロバート・ニーメイヤーの「意味再構築理論(MRT)」とは
提唱者はアメリカの心理学者ロバート・A・ニーメイヤー(Robert Neimeyer)。
1990年代以降、彼はグリーフ(悲嘆)研究の流れを大きく変えた人物です。
ニーメイヤーは、「人が悲しみに苦しむのは、“意味の崩壊”が起きているからだ」と指摘しました。
つまり、死別や喪失によって、
「自分は安全な世界に生きている」
「人生には秩序がある」
といった信念が壊れてしまうのです。
そのため、回復には「失ったものを忘れること」ではなく、
“新しい意味”を再び構築することが大切だと説明しています。
悲嘆を“乗り越える”ではなく“意味づけ直す”という考え方
多くの人が誤解しやすいのが、「悲しみを早く乗り越えることが回復」と考える点です。
しかしMRTでは、悲嘆は克服ではなく、再定義(redefinition)のプロセスとされています。
たとえば、
- 「あの人がいなくなっても、自分の中に教えが残っている」
- 「失ったからこそ、今の自分がある」
- 「悲しみを通して、人に優しくなれた」
といった形で、喪失に新しい意味や価値を見いだすことが大切なのです。
このように、「悲嘆=終わるもの」ではなく、“変化し続ける関係”として理解されます。
これは、現代グリーフケアの中心概念である「継続的な絆(Continuing Bonds)」とも一致しています。
5段階モデルから“意味づけ・成長”へと進化するグリーフセラピー
キューブラー=ロスの5段階が「受容」で終わるモデルだったのに対し、
ニーメイヤーの理論ではその先に「再構築」や「成長」があります。
この理論の特徴は以下の通りです。
| 観点 | 悲嘆の5段階モデル | 意味再構築理論(MRT) |
|---|---|---|
| 焦点 | 感情の受け入れ | 意味の再構築 |
| ゴール | 現実の受容 | 人生の再定義と成長 |
| アプローチ | 段階的モデル | 個人の物語と意味づけ |
| 回復観 | 終了(終わり) | 継続(変化しながら続く) |
MRTでは、悲しみの中にある「問い」を大切にします。
「なぜこの出来事が起きたのか?」
「私はこれから何を大切にして生きたいのか?」
こうした問いに向き合うことで、人は徐々に生の意味を再発見し、
悲しみを抱えながらも前向きに生きる力を取り戻していくのです。

悲嘆の5段階をどう活かす?心の回復を支える実践的なヒント
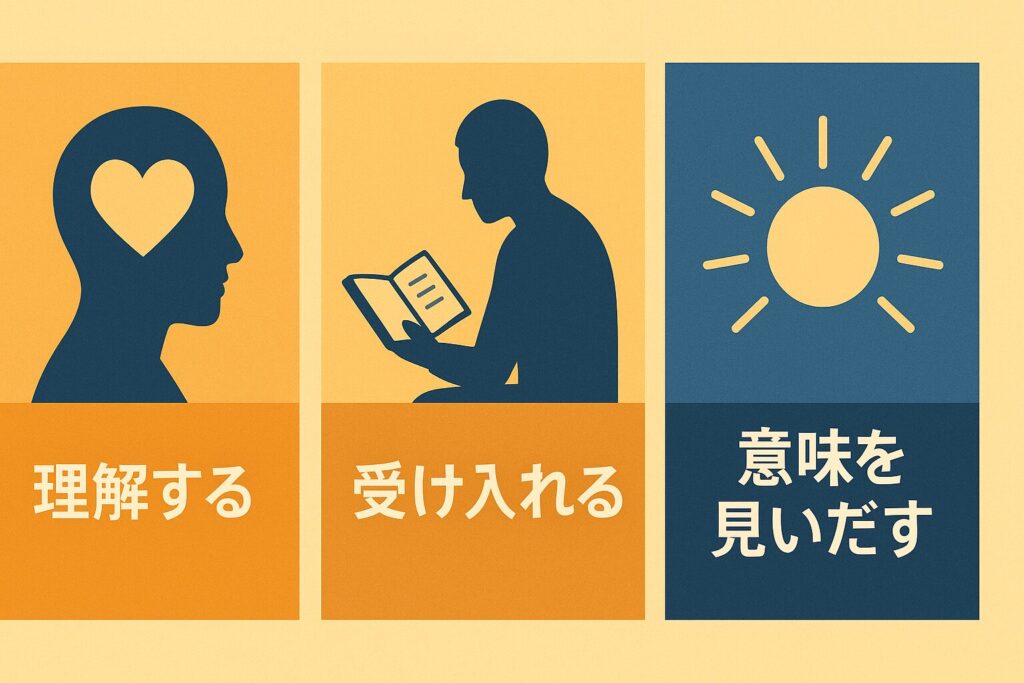
キューブラー=ロスの「悲嘆の5段階」は、単なる理論ではなく、自分や他者の心を理解する手がかりとして活かすことができます。
この章では、悲嘆を「無理に乗り越える」ものではなく、「丁寧に向き合う」ための実践的な方法を紹介します。
悲しみの段階を理解することで、自分や他者を責めない
悲嘆のプロセスを知っておくと、
「今の自分はおかしいのでは?」という自己否定を減らすことができます。
- 否認は「まだ受け止めきれない」自然な反応
- 怒りは「失ったものを大切に思っている証」
- 抑うつは「心の痛みを静かに感じている時間」
と理解できれば、感情を悪いものとして排除せず、受け止めやすくなるのです。
また、他者に対しても「まだ受け入れられない段階なんだ」と気づけると、
不用意に励ますよりもそっと寄り添う姿勢をとれるようになります。

無理に前へ進もうとしない「感情の受け入れ方」
悲嘆の回復には、「前向きにならなければ」という焦りを手放すことが大切です。
人は、感情を無理に抑え込むほど、心の回復が遅れてしまいます。
感情を受け入れる3つのステップ:
- 気づく:「今、自分は怒っている」「寂しい」と名前をつける。
- 認める:「この感情も自然なこと」と否定しない。
- 感じきる:涙やため息など、体を通して感情を流す。
これは心理学でいう「セルフ・コンパッション(自己への思いやり)」の実践にも通じます。
感情を抑えるのではなく、「感じていい」と許すことが、心の再生の第一歩です。
感じきる: 涙やため息など、体を通して感情を流すこと。
ここでいう「感じきる」とは、感情に溺れることではなく、“今、自分が何を感じているか”をただ認める行為です。
悲しみや怒りを無理に押さえつけるよりも、安全な場所で自然に出てくる反応を許すことが、心の緊張を和らげます。
ただし、いつまでもその感情に留まる必要はありません。
涙を流したり、深呼吸したりして感情が一段落したら、「もう大丈夫」と受け流す意識を持ちましょう。
このように「感じきる → 受け流す」はセットで行うのが理想です。
感じることで心がほぐれ、受け流すことで少しずつ前へ進む準備が整います。
感情を敵にせず、“通り過ぎる波”として見守る姿勢が、心の回復にはとても大切です。
意味を再構築するための具体的な方法(書く・語る・行動する)
悲嘆を“癒す”というより、“意味をつくり直す”ための行動をとることで、心は少しずつ整理されていきます。
代表的な方法は次の3つです。
- 書く(ジャーナリング):
思いや感情をノートに書き出すことで、頭の中の混乱が整理されます。
たとえば「その人への手紙を書く」「自分へのメッセージを書く」など。 - 語る(ナラティブ):
信頼できる人やカウンセラーに話すことで、自分の経験に言葉と意味が生まれます。
「語ること=癒すこと」といわれるほど、悲嘆では言語化が重要です。 - 行動する(アクション):
小さな行動を通して、失ったものとの“新しい関係”を築いていきます。
例:写真を飾る/記念日に花を供える/学びを誰かに伝える など。
これらの行動は、ニーメイヤーのいう「Meaning Reconstruction(意味の再構築)」を支える実践です。
悲しみを無理に消すのではなく、生きる意味の形を少しずつ変えていくことが目的です。
まとめ|悲嘆の5段階は“心の地図”として使う
ここまで見てきたように、悲嘆の5段階モデルは「正しい悲しみ方」を示すものではなく、
人が大きな喪失を経験したときに心がどのように変化していくのかを理解するための心の地図です。
重要なのは、「段階を完了させる」ことではなく、自分の感情の流れをやさしく観察することです。
段階にとらわれず、自分のペースで癒えていく
悲嘆のプロセスは、誰一人として同じではありません。
ある人は怒りを通らずに静かに受け入れ、
別の人は何年も取引や抑うつの段階に留まることがあります。
しかし、それぞれのプロセスには意味があります。
心はいつも「理解したい」「守りたい」「つながりたい」と動いています。
だからこそ、焦らず、比べず、自分のペースで癒えていくことが大切です。
- 感情が戻ってきても、「まだ悲しいのは自然なこと」
- 涙が出ても、「それは心が動いている証拠」
- 少し笑える日が来たら、「癒しが始まっているサイン」
このように、自分の心のサイクルを責めずに見守る姿勢が、最も優しい回復の方法です。

