「変わりたいのに、なかなか行動できない…」
そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
転職、習慣、恋愛、人間関係──
頭では「このままじゃダメだ」とわかっていても、
なぜか“今のまま”を選んでしまう。
その裏には、私たちの脳がもつ現状維持バイアスという心理が働いています。
この記事では、
- 現状維持バイアスとは何か(専門用語をやさしく解説)
- 人が変化を避ける心理的メカニズム
- 日常・ビジネスでの具体例
- そして、現状維持バイアスを無理なく克服する3つのステップ
をわかりやすく紹介します。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
現状維持バイアスとは?意味と基本的な考え方

現状維持バイアスの定義をわかりやすく説明
「現状維持バイアス(Status Quo Bias)」とは、
“変化するよりも、今のままでいたい”と感じる心理傾向のことです。
たとえば──
- 「転職したいけど、今の職場に不満はないし…」
- 「スマホを買い替えたいけど、設定が面倒そう」
- 「人間関係を変えたいけど、波風を立てたくない」
こうした“動きたいのに動けない”状態は、怠けではなく、脳の自然な防衛反応です。
私たちは、変化に伴う「不確実さ」や「リスク」よりも、
“今の状態の安心感”を重視してしまうようにできています。
つまり現状維持バイアスとは、
「現状=安全」「変化=危険」
と無意識に判断してしまう人間の思考のくせなのです。
なぜ人は変化を恐れるのか?損失回避との関係
この心理を説明する代表的な理論が、
行動経済学で有名なプロスペクト理論です。
この理論では、人は「得をする喜び」よりも「損をする痛み」を約2倍強く感じるといわれています。
これを損失回避性(loss aversion)と呼びます。
たとえば──
- 「転職して収入が上がるかも」よりも、「転職して失敗したらどうしよう…」
- 「新しい挑戦で成功するかも」よりも、「今の安定を失うのが怖い」
というように、“失う恐れ”が、行動を止めてしまうのです。
この損失回避の心理が、現状維持バイアスの中心的なエンジンになっています。
つまり、「変化すること=損をするリスク」と感じるほど、人は今の状態にとどまりやすくなります。

似ている概念との違い(保有効果・慣性・選択回避)
現状維持バイアスと混同されやすい心理概念もあります。
違いを整理しておくと理解が深まります。
| 概念名 | 内容 | 現状維持バイアスとの関係 |
|---|---|---|
| 保有効果(Endowment Effect) | 自分が持っているものを、実際より高く評価する傾向。 | 「今ある状態を手放したくない」点で共通。 |
| 慣性(Inertia) | 習慣や惰性で、同じ行動を繰り返すこと。 | 「面倒だから変えない」という日常的現象。 |
| 選択回避(Choice Avoidance) | 選択肢が多すぎて、決断できなくなる現象。 | 「決められない結果、今のまま」を選ぶ。 |
これらはすべて、「変わらないことに安心を感じる」という点でつながっています。
現状維持バイアスは、それらを包括する“変化にブレーキをかける心理”の総称といえるでしょう。
💬 まとめ
現状維持バイアスは、「今のままが安全」という無意識の思い込みから生まれる。
その背景には、損失回避・慣性・所有欲など、人間の本能的な防衛反応がある。
人はなぜ変われないのか?現状維持バイアスが生まれる心理的メカニズム

脳が変化を「危険」と感じる仕組み
私たちの脳は、新しいこと=リスクとして処理するように進化してきました。
これは「リスク回避本能」とも呼ばれる仕組みです。
原始時代、人間にとって“変化”は生命の危険を意味していました。
・知らない場所に行く → 捕食者に出会うリスク
・新しい食べ物を試す → 毒かもしれないリスク
こうした環境で生き延びるために、脳は「今の状態を保つ=安全」と判断するようになったのです。
現代では、転職・引っ越し・人間関係の変化なども、脳にとっては「未知のリスク」に見えます。
そのため、理屈では「変わった方がいい」とわかっていても、
脳の防衛反応(不安・ストレス反応)が働き、行動を止めてしまうのです。
損失を避ける心理と“今の安心”への執着
私たちは「得をすること」よりも「損をしないこと」を優先する傾向があります。
これは前章でも触れた損失回避性が大きく関係しています。
たとえば──
- 「転職すれば給料が上がる」よりも、「今の安定を失うかもしれない」
- 「新しい挑戦で成長できる」よりも、「失敗して恥をかくかもしれない」
このように、人は“変化した後の後悔”を恐れるのです。
そして、今の安心や慣れた生活を守るために、無意識に現状維持を選びます。
この心理は、「安心=快」「変化=不安」という感情のバランスによって強化されます。
変化を避ける理由は“理屈”ではなく、感情の防衛反応なのです。

習慣・慣れ・自動思考による現状維持
もうひとつの要因が、習慣化された思考(自動思考)です。
心理学者ダニエル・カーネマンは、人間の思考を次の2つに分けました。
- システム1:直感的・自動的・速い思考(例:いつもの道を無意識に歩く)
- システム2:意識的・論理的・遅い思考(例:新しい道をナビで確認しながら歩く)
多くの行動は「システム1」で自動的に処理されています。
そのため、新しい選択肢を考えるにはエネルギーを使う必要があり、
脳は自然と“いつも通り”を選びたがるのです。
この現象は、仕事・人間関係・生活習慣すべてに当てはまります。
「面倒だから」「いつもの方が楽だから」と感じるとき、
それはまさに自動思考が現状維持を選んでいる瞬間です。
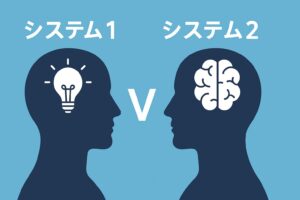
💬 まとめ
現状維持バイアスは、「変化=危険」「今=安全」と判断する脳の本能によって生まれる。
不安・損失回避・自動思考という3つのメカニズムが、私たちを“今のまま”に留めている。
現状維持バイアスの具体例|日常・ビジネスでの「変わらない選択」
日常生活の例(転職・健康・人間関係など)
現状維持バイアスは、私たちの日常の小さな選択の中にも深く潜んでいます。
たとえば──
- 転職:「今の職場にも不満はあるけど、辞めるのは不安」
- 健康習慣:「運動した方がいいと分かっているけど、今の生活を変えたくない」
- 人間関係:「距離を置いた方が楽だと思うけど、気まずくなりたくない」
これらはすべて、“今の安心感”を守ろうとする心理が働いている状態です。
変化することよりも、「このままで問題がないなら、リスクを取りたくない」という気持ちが勝ってしまうのです。
この傾向は決して怠けではなく、脳が安全を優先する自然な反応。
しかし、「行動しないこと=失うチャンスも多い」という点を意識しないと、成長の機会を逃してしまうこともあります。
ビジネス・組織の例(変革への抵抗)
企業や組織の中でも、現状維持バイアスは大きな壁になります。
「前例があるから」「昔からこうしてきたから」といった慣習の力は強力です。
たとえば──
- 新しいシステム導入に反対する
- 古いルールや会議体制を見直せない
- 改善提案があっても、「トラブルが怖いから」と見送る
これらは変化の不確実性より、現状の安定を優先する典型例です。
心理的には「失敗の責任を取りたくない」「変化後の結果が読めない」というリスク回避の思考が根底にあります。
組織レベルでは、こうした現状維持バイアスがイノベーションの停滞を招くこともあります。
そのため、近年の企業経営では「心理的安全性」や「小さな実験文化」が重視されているのです。

デジタル時代の例(サブスク・デフォルト設定)
現状維持バイアスは、デジタルサービスでも日常的に活用されています。
たとえば──
- サブスクリプションの自動更新
→ 「解約しようと思っていたけど、まあいいか」と継続してしまう。 - 通販サイトの定期購入がデフォルト設定
→ “今のまま”購入ボタンを押す方が楽。 - スマホアプリの通知ONが初期設定
→ 多くの人が設定を変えず、そのまま通知を受け続ける。
これらはすべて、「初期設定=デフォルト効果」を利用した設計です。
「設定を変えるのが面倒」「今のままで困っていない」という心理が働き、
結果的に企業側にとっても、ユーザー側にとっても“行動が固定化”されるのです。
このように、現状維持バイアスはビジネス戦略やUI設計にも応用されており、
人の「何もしない選択」を前提にした仕組みが至るところに存在しています。
💬 まとめ
現状維持バイアスは、転職・健康・人間関係などの日常から、
企業の意思決定、さらにはデジタルサービスの設計にまで影響しています。
「変わらない」という選択は、実は“最も自然に選ばれる行動”です。
現状維持バイアスを克服する3つのステップ

① 小さな変化から始める(段階的曝露)
現状維持バイアスを乗り越える第一歩は、「いきなり大きく変えようとしない」ことです。
人の脳は急な変化にストレスを感じるため、
まずは「少しずつ慣らす」=段階的曝露(エクスポージャー)の考え方が効果的です。
たとえば──
- 「毎日ランニング」ではなく、まずは1日5分だけ歩く
- 「転職する」ではなく、求人サイトを1回だけ覗いてみる
- 「人間関係を変える」ではなく、1人との距離感を少し変えてみる
このように、「成功体験を積み重ねる」ことで、脳が「変化=危険ではない」と学習します。
小さな変化は心理的負担が少なく、結果的に行動を継続できる確率が高くなるのです。

② “変わらない”ことのリスクを意識する
現状維持には安心感がありますが、「変わらないリスク」にも目を向けることが大切です。
たとえば──
- 今の職場に不満がなくても、成長の機会を逃すかもしれない
- 健康を後回しにすると、将来の医療費が増えるかもしれない
- 人間関係を放置すると、ストレスが溜まって関係が壊れるかもしれない
こうした「現状のままにするデメリット」を紙に書き出す・見える化することで、
“変わらないことも実はリスク”だと実感できます。
人は「損をしたくない」心理が強い生き物。
ならばそれを逆手にとり、「行動しないことで損をする」構図を意識すると、行動のモチベーションが上がります。
③ 環境をデザインして行動を後押しする
意志の力だけで現状維持バイアスを克服するのは難しいもの。
そこで役立つのが、「環境を味方につける工夫」=ナッジ設計です。
ナッジ(nudge)とは、「そっと後押しする仕組み」を意味します。
たとえば──
- スマホの通知をOFFにして、集中しやすい環境を作る
- 朝のルーティンを可視化して、選択の手間を減らす
- 健康的な食べ物を目に入りやすい場所に置く
- やる気が出る環境を“初期設定”にしておく(例:作業デスクを整える)
これらはすべて、「行動を変えやすくする環境設定」です。
人は意識よりも環境に影響されやすい生き物。
つまり、「自分を変える前に、環境を変える」のが最も現実的な方法なのです。

💬 まとめ
現状維持バイアスを克服するには、
①小さな変化で慣らす → ②変わらないリスクを見える化 → ③環境で後押し、
という3ステップで“行動しやすい自分”を作ることが大切。
現状維持バイアスと上手に付き合う|「変わらない自分」を責めない考え方
現状維持も“自己防衛”の一種である
「変われない自分はダメだ」と感じる人は多いですが、
実は現状維持は人間の自然な自己防衛反応です。
変化には必ず「不確実性」がつきまといます。
脳はその不確実性を“危険”とみなし、あなたを守るためにストップをかけているのです。
たとえば、
- 失敗したくない
- 人にどう思われるか怖い
- 新しい環境に不安を感じる
こうした感情は、すべて「生き延びるための防御反応」。
つまり、「変わらない=悪い」ではなく、「変化を慎重に扱う脳の仕組み」なのです。
この視点を持つだけで、自分への批判的な気持ちがやわらぎ、
「今の自分もちゃんと守ろうとしている」と思えるようになります。
バイアスを理解して、意識的に選択する
現状維持バイアスを完全に消すことはできません。
大切なのは、その存在に気づき、意識的に選択する力を持つことです。
たとえば──
- 「今のままでいい」と思ったら、一度「それは本心? それとも安心を選んでる?」と問いかけてみる
- 「変化したくない」と感じたら、「変わらないリスク」と「変わるリターン」を紙に書き出す
- 「やらない理由」を考えたら、「もし“怖さ”がなかったら自分はどうするか?」と想像してみる
このように、バイアスを“見える化”するだけで思考の自動運転を止めることができます。
現状維持を選ぶのも自由、変化を選ぶのも自由。
重要なのは、「どちらを選ぶか」を自分の意思で決めることです。
現状維持バイアスを味方にする思考法
意外に思えるかもしれませんが、現状維持バイアスは必ずしも悪いものではありません。
安定や継続を支える強力な力にもなります。
たとえば、
- 習慣を守る力(例:毎朝の散歩や日記の継続)
- 信頼関係を維持する力(例:長く同じ仲間と協力できる)
- ルーティン化による集中力(例:同じ手順で仕事を始める)
つまり、「維持する力」を“よい方向”に使うことがポイント。
変化を恐れて止まるのではなく、安定をベースに「次の一歩」を積み重ねていく。
変化とは、今ある安定を土台に“少しずつ広げていくこと”。
現状維持バイアスを敵ではなく味方として扱えば、
「安心しながら成長できる自分」へと変わっていけます。
💬 まとめ
現状維持バイアスは“弱さ”ではなく、“自分を守る知恵”。
バイアスを理解し、意識的に選択すれば、変わらない自分を責める必要はない。
むしろその安定力を活かして、穏やかに変化を進めていこう。
まとめ|現状維持バイアスを理解すれば、少しずつ変化を起こせる
変わらないことも悪ではない、意識することが第一歩
現状維持バイアスは、誰にでもある自然な心理反応です。
それは自分を守るための安全装置のようなもの。
ただし、その存在に気づかないまま放置すると、
「本当は変わりたいのに動けない」という葛藤を生むことがあります。
まずは、「自分は今、現状維持を選んでいる」と意識することが第一歩です。
その気づきがあるだけで、無意識の選択から“自分で決める選択”へと変わります。
心理を知ることで“変化への不安”を減らせる
現状維持バイアスの仕組みを理解すれば、
「自分は怠けている」のではなく、「脳が安全を守ろうとしている」とわかります。
この理解は、自己否定をやわらげ、行動のハードルを下げる効果があります。
たとえば──
- 不安を感じたら「これは防衛反応だ」と気づく
- 変化が怖いときは「小さな一歩」から始める
- 環境を整えて「行動しやすい仕組み」を作る
心理学的な仕組みを知ることで、変化を「怖いこと」ではなく
「安全に扱える現象」として捉えられるようになります。
小さな成功体験が、未来の変化を後押しする
現状維持バイアスを克服する最も確実な方法は、
小さな成功体験を積み重ねることです。
「ちょっと行動してみた」「少し慣れてきた」という成功は、
脳に「変化しても大丈夫」という安全の証拠を残します。
この“安心の記憶”が、次の行動をより自然にしてくれるのです。
変化は、一気に起こすものではなく、
「昨日より一歩進んでいる」と感じる積み重ね。
現状維持バイアスを理解し、うまく付き合えば、
自分を守りながら確実に変化できる生き方ができるようになります。
💬 まとめ
小さな一歩を積み重ねることで、“今”も“未来”も安心して進化できる。



