「キャリア理論って、たくさんあってよく分からない…」
「どれが自分に合ってるの?」「そもそも何のために学ぶの?」――そんな疑問やモヤモヤを感じたことはありませんか?
キャリア理論は、働き方や人生の選択を考えるうえでとても役立つ“考え方の地図”のようなもの。自分の性格に合った仕事の見つけ方、人生のステージごとのキャリア設計、偶然をチャンスに変える視点など、理論ごとに特徴があります。
この記事では、初心者でも分かりやすいように代表的なキャリア理論を一覧で紹介し、選び方のヒントや実践例もあわせて解説しています。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
キャリア理論とは?|働き方や職業選択を支える考え方

キャリア理論とは、「人がどのようにして仕事や職業を選び、キャリアを築いていくのか」というプロセスを理論的に説明した枠組みのことです。
就職や転職、キャリアチェンジなど、人生のあらゆるタイミングで「自分に合った仕事は何だろう?」と迷うことがあります。
そんなとき、キャリア理論を知っておくことで、感覚だけに頼らず、自分の考えや方向性を整理しやすくなるのです。
キャリア理論が注目される理由とは?
近年、キャリア理論が改めて注目されている背景には、以下のような社会の変化があります。
- ✅ 終身雇用の崩壊:ひとつの会社にずっと勤める時代ではなくなった
- ✅ 働き方の多様化:正社員、フリーランス、副業など、選択肢が増えた
- ✅ 自己理解の重要性の高まり:自分で意思決定する力が求められる
こうした中で、「自分らしいキャリアをどう築くか」が重要な課題になり、キャリア理論を学ぶ価値が高まっているのです。
キャリア理論が使われる場面(教育・支援・転職など)
キャリア理論は、実はさまざまな場面で活用されています。
- 🎓 キャリア教育(中学・高校・大学など)
→ 生徒が「将来何になりたいか」を考える授業などで活用 - 🧑💼 キャリアカウンセリング・コンサルティング
→ ハローワークや人材サービスなど、職業選択のサポート現場で使用 - 🏢 企業の人材育成や人事制度
→ 昇進や配置転換などのキャリアパス設計にも理論が応用されている - 🔄 個人の転職・副業・再出発
→ 自分の価値観や強みを知りたい人の自己分析ツールとしても使える
このように、キャリア理論は一部の専門家だけでなく、誰もが活用できる知識なのです。
理論を学ぶメリット:自己理解・意思決定の助けに
キャリア理論を学ぶと、以下のようなメリットがあります。
💡 自分を客観視できる
「なぜ今の仕事がしっくりこないのか」「どんな環境なら自分は力を発揮できるのか」などを、理論の枠組みで整理できるようになります。
💡 選択肢を広げやすい
キャリアの選択肢を「正解/不正解」ではなく、自分に合っているか/いないかという視点で判断できるようになります。
💡 不安や迷いに対して説明がつく
「自分はなんとなくこうしたいと思っているけど、それって間違ってない?」という悩みに対しても、理論の裏付けが安心材料になることがあります。
📌 たとえばこんなふうに使えます
- 「自分の性格に合う職業って何?」→ ホランド理論で診断できる
- 「将来が不安で進路が決まらない」→ スーパー理論で長期視点を持てる
- 「偶然の出会いを活かしたい」→ クランボルツ理論でOKと捉えられる
キャリア理論の代表モデル一覧|基本と特徴をざっくり解説
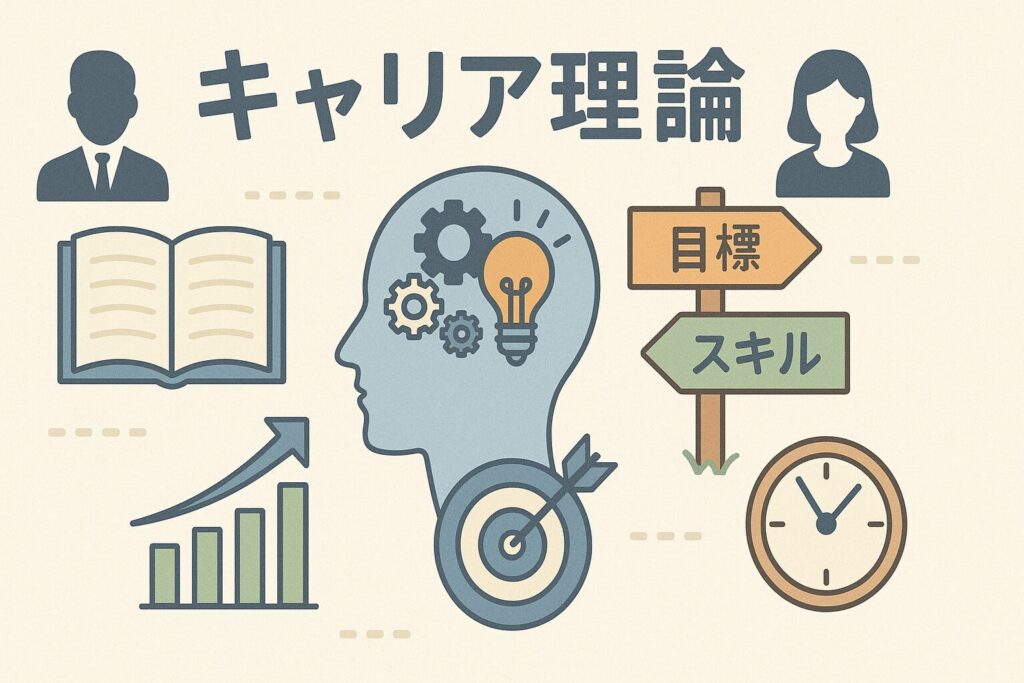
ここからは、初心者の方にもわかりやすく、キャリア理論の代表的な5つのモデルをご紹介します。
それぞれの理論には、キャリアの考え方や選び方に対する独自の視点があり、「自分にしっくりくる理論」が見つかることもあります。
まずは「ざっくりと特徴を知りたい」「どれを学べばよいかわからない」という方に向けて、わかりやすく解説していきます。
①ホランドの職業選択理論|性格と職業のマッチング(RIASEC)
ホランド理論は、「人の性格と職業の相性には法則がある」という前提に基づいた理論です。
6つの性格タイプと、それに対応する職業タイプを分類し、マッチングを図ることで職業選択の納得感を高めようという考え方です。
🔑 6つの性格タイプ(RIASEC)
| タイプ | 特徴 | 向いている仕事の例 |
|---|---|---|
| R:現実的 | 手を使った作業が好き | 技術職、整備士、大工など |
| I:研究的 | 論理的・分析が得意 | 研究者、SE、分析官など |
| A:芸術的 | 表現・創造性に富む | デザイナー、作家、映像編集など |
| S:社会的 | 人に関わるのが好き | 教師、看護師、カウンセラーなど |
| E:企業的 | リーダーシップ型 | 営業、起業家、マネージャーなど |
| C:慣習的 | ルール重視・正確性 | 事務職、会計、行政職など |
🧩 活用法:診断テスト(RIASECテストなど)を受けると、自分のタイプに合う職業の候補がわかります。
②スーパーのキャリア発達理論|キャリアはライフステージで変わる
スーパー理論は、「キャリアは一生をかけて発達していくもの」と考えるライフスパン(人生全体)志向の理論です。
キャリア形成を5つの段階に分け、それぞれに合った課題があると示しています。
📅 5つのキャリア段階
- 成長期(0〜14歳):興味・価値観・自己概念が育つ
- 探索期(15〜24歳):進路選択や職業体験を重ねる
- 確立期(25〜44歳):仕事に本格的に定着していく
- 維持期(45〜64歳):役割の維持・スキルの深化
- 衰退期(65歳以降):リタイア・次の役割へ
🧭 ポイント:そのときどきの年齢や状況に応じて、「どんなキャリア選択をすべきか」を見直す指針になります。
③クランボルツの社会学習理論|偶然をチャンスに変える考え方
「予測できない偶然の出来事が、キャリアに大きな影響を与える」と考えるのがクランボルツ理論です。
この理論では、「偶然に出会った人や出来事をどう活かすか」がキャリア形成にとって重要とされます。
🌀 計画された偶発性(Planned Happenstance)
クランボルツは、人生には偶然が多いからこそ、
- 好奇心を持つ
- 柔軟に対応する
- チャンスに飛び込む準備をしておく
という姿勢が重要だと説いています。
🎯 応用:「キャリアに正解はない」「目の前の経験を大切にすれば道は拓ける」というメッセージは、今の時代にもぴったりです。
④シャインのキャリア・アンカー理論|価値観から考えるキャリア
シャインは、「人は自分の中に“アンカー(錨)”のような価値観を持っていて、それを基準にキャリアを選ぶ」と考えました。
🪝 代表的な8つのキャリア・アンカー
| アンカー | 意味 |
|---|---|
| 専門・職能的能力 | 専門性を活かす働き方がしたい |
| 全般管理能力 | 組織をまとめるマネジメントがしたい |
| 自立・独立 | 自由に働きたい/起業したい |
| 保障・安定 | 安定収入・福利厚生を重視 |
| 起業家的創造性 | 新しいものを生み出したい |
| 奉仕・社会貢献 | 社会や人の役に立ちたい |
| 純粋な挑戦 | 難題や目標に挑戦したい |
| 生活様式との調和 | 家族・趣味との両立を重視したい |
🔍 活用法:自分のアンカーを知ることで、「何を重視して働きたいか」が明確になり、転職や進路選びで迷わなくなります。
⑤サヴィカスのナラティブ理論|自己物語としてキャリアを捉える
サヴィカスは「キャリアは物語(ナラティブ)であり、人はそれを語りながら自分を理解する」というアプローチを提唱しました。
これは、過去の経験を意味づけ、未来に活かすという柔軟で個別性の高い理論です。
💬 こんな問いがカギ
- 子どもの頃に憧れていた人は?
- これまでの人生で誇らしかった瞬間は?
- 大切にしてきた価値観や習慣は?
🧠 応用:キャリアに悩んだとき、「過去の経験から自分の軸を再構成する」ために非常に役立ちます。特にカウンセリングやコーチングの現場で活用されています。
✅ サヴィカス(Mark L. Savickas)は、「ナラティブ理論」そのものの創始者ではありませんが、
キャリア発達の文脈にナラティブを取り入れた第一人者であり、
彼の理論は「キャリア・ナラティブ理論」や「キャリア構築理論(Career Construction Theory)」として知られています。

比較でわかる!キャリア理論の使い分けと選び方のヒント
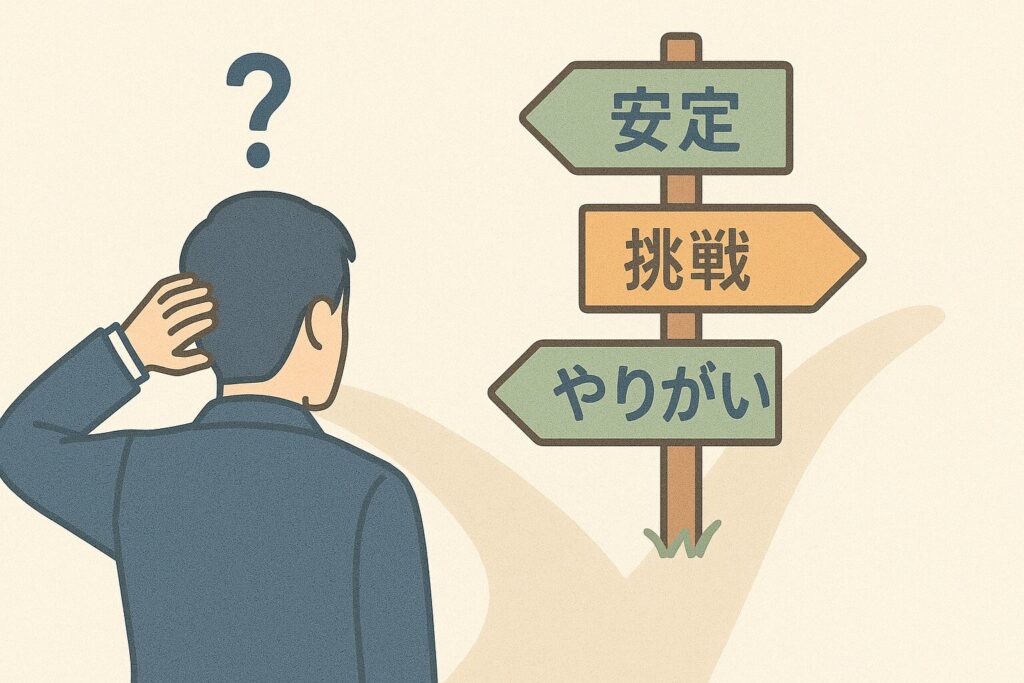
キャリア理論にはさまざまな種類があり、それぞれに得意な分野や活用シーンがあります。
ここでは、「どの理論がどんな場面に向いているのか?」をわかりやすく整理し、自分に合った理論を選ぶヒントを紹介します。
科学的に実証されている理論はどれ?信頼性の観点から比較
キャリア理論の中でも、科学的な信頼性(=実証研究の多さや検証のしやすさ)を重視する人には、以下の理論がおすすめです。
🔍 実証データが豊富な理論
| 理論名 | 信頼性の特徴 |
|---|---|
| ホランド理論 | 性格タイプの測定ツール(RIASECテスト)があり、世界的に研究実績が豊富 |
| スーパー理論 | 長期的な発達モデルとして、多くの教育機関で採用実績あり |
| SCCT理論(社会的認知的キャリア理論) | 心理学の知見に基づき、自己効力感などの因子が明確に測定可能 |
このような理論は、進路指導・就職支援・キャリア教育などのフォーマルな場面で特に使いやすいとされています。
柔軟性・現代性で選ぶなら?変化の時代に向いた理論
「時代の変化に対応できる柔軟な考え方が知りたい」という方に向いているのは、“型にはまらない”キャリア理論です。
🔄 不確実な時代に合う理論
- クランボルツ理論
→ 偶然の出会いや出来事をチャンスに変える「計画された偶発性」の考え方
→ 正解がない現代のキャリアにフィット - キャリアアダプタビリティ理論
→ 「変化に適応する力」を高めることで、転職・副業・ライフイベントに柔軟に対応できる - サヴィカスのナラティブ理論
→ 自分の過去の経験を物語として捉え直すことで、「キャリアに意味を見出す」ことができる
🎯 どれも正解がない時代に「どう進むか迷っている人」に役立つ視点です。
「自己理解」「適職探し」に役立つ理論はどれ?
「自分に合う仕事って何?」「どんな職場が向いてる?」といった適職探しや自己理解をしたい方には、次の理論がおすすめです。
🧩 自己分析・適職発見に向いている理論
| 理論名 | 活用のポイント |
|---|---|
| ホランド理論 | 性格タイプと職業環境の相性を視覚的に捉えやすい(RIASEC) |
| シャイン理論 | 「何を重視して働くか(安定?挑戦?自由?)」が明確になる |
| ナラティブ理論 | 自分の過去の経験を深掘りし、自分らしいキャリアの方向性を発見できる |
📌 どの理論も、「自己分析ツール」「ワーク」「問いかけ」などを通して、自分の考え方や行動パターンを見つめ直すことができます。
表で比較|理論ごとの特徴・対象者・活用場面
最後に、主要キャリア理論を特徴・対象者・おすすめの場面ごとに一覧表でまとめました。
| 理論名 | 主な特徴 | 向いている人 | 活用場面 |
|---|---|---|---|
| ホランド理論 | 性格と職業の相性分析 | 自分に合う職業を知りたい | 適職診断・進路相談 |
| スーパー理論 | 人生全体でのキャリア発達 | 長期的視点を持ちたい人 | ライフデザイン |
| クランボルツ理論 | 偶然をキャリアに活かす | 明確な目標がない人 | キャリア迷子のサポート |
| シャイン理論 | 価値観からキャリアを選ぶ | 転職・再出発を考えている人 | キャリアチェンジの判断材料 |
| サヴィカス理論 | 経験の物語化・再構成 | 自分の過去を活かしたい人 | キャリアの再設計・支援現場 |
キャリア理論はそれぞれが「違う視点」でキャリアを捉えており、自分の状況や目的に応じて選ぶことが大切です。
次は、これらの理論を実際の生活や支援でどう活用するのか?を具体的に見ていきましょう。
キャリア理論の活用例|実生活・キャリア支援での使い方

キャリア理論は「知識」として学ぶだけでなく、日常生活やキャリアの意思決定に“使えるツール”として活用することができます。
ここでは、キャリアに悩んだときや、キャリア支援の現場で実際にどう使われているかを具体的に紹介します。
キャリアに悩んだときに理論がどう役立つか
人生の中で「このままでいいのかな?」「転職すべき?」「やりたいことが分からない」と迷うことは誰にでもあります。
そんなとき、キャリア理論は不安や迷いを“言語化”し、整理する手助けになります。
📌 例えばこんな場面で使えます
- 自分に合った働き方を見つけたい → シャインのキャリアアンカーで価値観を明確化
- やりたいことが分からない → クランボルツ理論で「偶然を活かす」という考えに切り替える
- この仕事に意味を感じない → サヴィカスのナラティブ理論で「なぜこの選択をしてきたのか」を物語にする
キャリアカウンセリングや教育現場での活用方法
キャリア理論は、プロの支援者によっても積極的に活用されています。
🎓 教育現場(中学・高校・大学など)では…
- スーパー理論をもとに、「ライフステージごとのキャリア発達」を学ばせる
- ホランド理論を用いて、職業興味テストや適職診断を実施
- ナラティブ理論を使って、「過去の経験から将来を考える」授業を行う
🧑💼 キャリアカウンセリングの現場では…
- クランボルツ理論で「偶然もキャリアの一部」と受け止め、柔軟に進路支援
- シャインのアンカー理論で「転職の軸」や「働く価値観」を見つめ直すサポート
🛠️ 理論をベースにした質問やワークが多く用意されており、再現性の高い支援が可能です。
あなたに合ったキャリア理論の見つけ方のコツ
キャリア理論は数多くありますが、全部を学ぶ必要はありません。
大事なのは「今の自分の悩みにフィットする理論を選ぶ」ことです。
💡 選び方のヒント
- ✅ 将来が漠然として不安な人 → クランボルツ理論
- ✅ 自分の強みや適職を知りたい人 → ホランド理論 or シャイン理論
- ✅ キャリアを一度リセットしたい人 → サヴィカスのナラティブ理論
- ✅ これからの人生設計を考えたい人 → スーパー理論
🧭 理論は「正解」ではなく、「視点」を提供してくれるもの。
いくつか読んでみて、「これ、自分に合ってるかも」と感じたものを深掘りするのがベストです。
キャリア理論は、キャリア支援の専門家だけのものではありません。
人生に迷ったとき、選択に悩んだとき、自分の価値観が揺らいだとき——その“道しるべ”として活用できるツールです。
次は、今回紹介した代表理論以外にも、今注目されている新しいキャリア理論を紹介していきます。
補足:その他の注目キャリア理論と現代的アプローチ

ここまでは「代表的な5つのキャリア理論」を紹介してきましたが、キャリアの多様化が進む現代では、さらに柔軟で実践的な理論も注目を集めています。
ここでは、特に現代の働き方や価値観に合った、知っておきたいキャリア理論を4つご紹介します。
①SCCT(社会的認知的キャリア理論)|自己効力感に注目
SCCT(Social Cognitive Career Theory)は、心理学者バンデューラの「社会的認知理論」をベースにしたキャリア理論です。
この理論では、キャリア形成には以下の3つが深く関係すると考えられています。
🔑 3つの構成要素
- 自己効力感:自分はできる!という信念
- 結果期待:これをやれば、こんな良いことが起きそう
- 目標設定:やりたいことを明確にする力
📌 特に「やりたいことはあるけど、自信がない…」という人にとって、この理論は行動を後押しする強力な視点になります。
②キャリアアダプタビリティ理論|変化に適応する力とは
キャリアアダプタビリティ理論は、「予測不可能な変化の中で、自分らしいキャリアを築くには“適応力”が重要」という考え方です。
🧭 4つの適応力(4C)
- 関心(Concern):将来への意識・計画性
- 統制(Control):自分で決める力
- 好奇心(Curiosity):多様な選択肢への探求心
- 自信(Confidence):実行する自信
🌍 転職・副業・リスキリングが当たり前になった今、この4Cを育てることが、柔軟なキャリア形成の鍵になります。
③フェミニスト・構造的キャリア理論|背景・環境に注目する視点
従来のキャリア理論は「個人の選択や努力」に焦点を当ててきましたが、フェミニスト理論や構造的理論は違います。
🔍 特徴的な視点
- 社会構造や文化的背景がキャリア選択を制限している場合がある
- ジェンダー・階級・家庭環境など、外部要因もキャリアに強く影響する
📣 たとえば「育児のためにキャリアを諦めた女性」や、「選択肢が限られていた環境で育った人」などに対して、個人の責任ではなく、社会の構造を問い直す視点を提供してくれます。
④パラレルキャリア・ポートフォリオ理論|複業時代の新しい考え方
働き方が一つに決まっていた時代は終わり、今や「複業」「副業」「マルチキャリア」が一般的になりつつあります。
そこで注目されているのが、以下の2つの考え方です。
💼 パラレルキャリア
- 本業以外に「もう一つの軸」を持つ生き方(例:会社員+地域活動)
📁 ポートフォリオキャリア
- 複数の仕事やスキルを組み合わせて生計を立てる(例:ライター+講師+物販)
このような考え方に基づくキャリア理論は、「1つの会社に縛られず、自分らしく働く方法」を模索する人にとって非常に実用的です。
次はまとめとして、「自分に合ったキャリア理論をどう選ぶか」「複数理論の組み合わせ方」などを解説していきます。
まとめ|自分に合ったキャリア理論を知って、納得のいく働き方を

キャリア理論にはさまざまな種類があり、それぞれが異なる視点や価値観からキャリアの在り方を説明しています。
本記事では、初心者の方にもわかりやすく、代表的な理論とその使い方をご紹介してきました。
ここでは最後に、「どの理論を選べばいいかわからない」「どう使えばいいの?」という方のために、選び方や活用のコツをお伝えします。
迷ったときは「目的」や「悩み」から選ぶのがコツ
キャリア理論に正解はありません。
大切なのは、「今の自分が何に悩んでいて、何を知りたいのか?」という視点で選ぶことです。
🧭 目的別のおすすめ理論
| 悩みや目的 | 向いている理論 |
|---|---|
| 自分に合った仕事を知りたい | ホランド理論、シャイン理論 |
| 将来が不安で動けない | スーパー理論、キャリアアダプタビリティ理論 |
| やりたいことが分からない | クランボルツ理論、サヴィカス理論 |
| 転職・再出発を考えている | シャイン理論、ナラティブ理論 |
| 複業や自由な働き方をしたい | ポートフォリオ理論、パラレルキャリア理論 |
📌 自分の状況にマッチした理論を選ぶことで、より実践的な気づきや行動のヒントを得られます。
理論は組み合わせて使ってもOK
ひとつの理論だけにこだわる必要はありません。
むしろ、複数の理論を組み合わせて活用することで、より立体的な視点が得られます。
例:こんな組み合わせ方もおすすめ
- ホランド理論で自分の性格と適職を把握
+ シャイン理論で「働く上での価値観」を見つける
+ クランボルツ理論で偶然の出来事を前向きに捉える
このように「性格 × 価値観 × 行動の視点」を統合することで、キャリアの迷いが整理されやすくなります。
📝 最後に
キャリア理論は、「知識」ではなく「人生をデザインするためのツール」です。
自分の人生を他人任せにせず、納得できる道を選ぶために、ぜひ理論の視点を活用してみてください。

