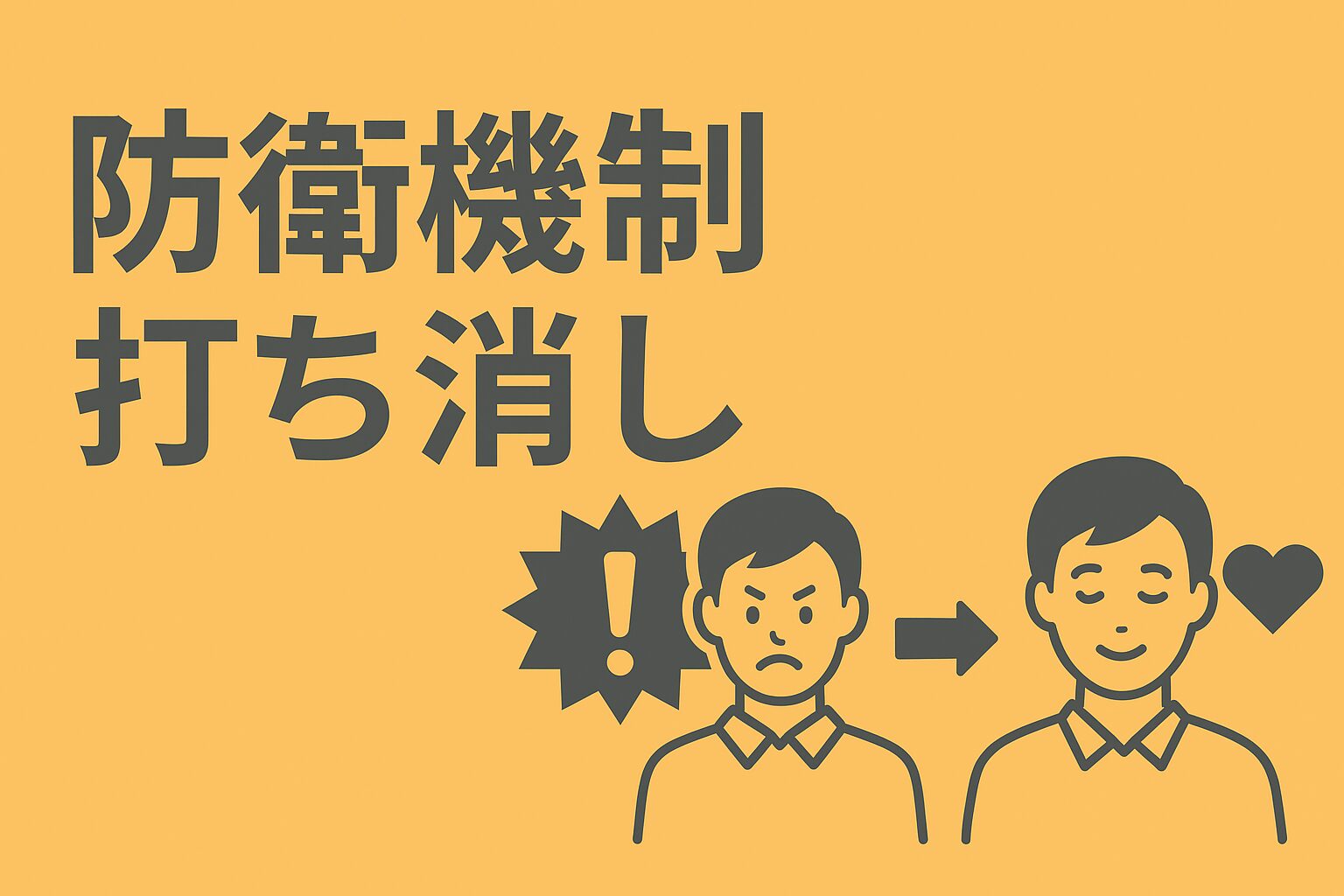「つい言いすぎた後に、慌てて優しくしてしまった…」「心の中で良くないことを思ったのに、無意識に帳消しにしようとする行動をとってしまう…」そんな経験はありませんか?
実はそれ、心理学でいう防衛機制のひとつ「打ち消し(undoing)」かもしれません。打ち消しとは、不安や罪悪感を「反対の行動」で帳消しにしようとする心の働きです。
この記事では、打ち消しの意味や心理的な仕組みをわかりやすく解説しながら、子ども・恋人・職場など日常に見られる具体例を紹介します。さらに、メリットとデメリット、他の防衛機制(否認・抑圧・反動形成など)との違いも整理。最後には「どう気づいて活かすか」のヒントまでご紹介します。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
防衛機制の「打ち消し」とは?心理学での意味を解説

「打ち消し(undoing)」は、心理学でいう防衛機制の一つです。
防衛機制とは、ストレスや不安・罪悪感などから自分の心を守るために、無意識に働く心理的な仕組みのこと。
その中でも打ち消しは、「悪いことをした」「よくない感情を持ってしまった」という気持ちを、後から反対の行動で帳消しにしようとする反応を指します。
打ち消し(undoing)の定義と基本的な特徴
- 定義:自分の中にある望ましくない感情や行動を、「反対の行動」で補うことで、なかったことにしようとする防衛の働き。
- 特徴:実際には「悪いこと」は消えないが、本人の心の中では「バランスを取った」と感じ、安心できる。
例えるなら、
「つい友達に嫌なことを言ってしまったけど、その後すぐに優しくフォローして仲直りを図る」
といった行動が典型です。
「罪悪感を帳消しにする」心の働き
打ち消しが働く背景には、強い罪悪感があります。
- 「悪いことをしてしまった」
- 「心の中で良くないことを考えてしまった」
そんなときに、人は無意識に「埋め合わせ」や「やり直し」をしようとします。
たとえば、恋人に浮気心を抱いたあとに、急にプレゼントを買ったり、優しく接するのもこの一例です。
つまり打ち消しは、罪悪感を軽減するための心の応急処置といえます。
打ち消しと無意識の関係
重要なのは、打ち消しは多くの場合、無意識のうちに起こるという点です。
本人は「悪いと思ったから埋め合わせしている」と自覚しているとは限りません。
無意識の中で、
- 「マイナスの感情」 → 「プラスの行動で打ち消す」
というプロセスが自然に働いているのです。
このような仕組みが働くことで、私たちは強い不安や罪悪感を抱えても、一時的に心の安定を保ちやすくなります。
防衛機制の打ち消しの具体例|日常生活でよくあるパターン
打ち消しは教科書的な説明だけでは少し抽象的に感じるかもしれません。
ここでは、身近な日常でよく見られるパターンを具体的に紹介します。
子どもが親に暴言を吐いたあとに「大好き」と抱きつく
子どもは感情をコントロールする力がまだ弱いため、思わず「もう嫌い!」「死ね!」といった強い言葉を親にぶつけてしまうことがあります。
その直後に、急に笑顔で「大好き!」と言って抱きついたり、甘えてくることがあります。
これは、親を傷つけてしまった罪悪感を、愛情表現で打ち消そうとしている典型的な例です。
親子関係でよく見られる自然な心の働きといえるでしょう。
恋人やパートナーに浮気心を抱いたあとに過剰に優しくする
恋人以外の人に一瞬でも惹かれたり、心の中で浮気心を抱いてしまったとき。
「こんなこと考えるなんて自分はひどい」と罪悪感を持ち、無意識に相手に対してやたら優しくなったり、プレゼントを買ったりすることがあります。
これは「心の中の裏切り」を、表面的な優しさで帳消しにしようとする打ち消しの典型例です。
パートナー側からすると「急にどうしたの?」と不自然に感じることもあります。
職場で上司に不満を抱いたあとに必要以上に丁寧に接する
仕事で上司に対してイライラや不満を感じた後、翌日に妙に丁寧な態度を取ってしまうことがあります。
たとえば、普段よりも低姿勢に接したり、細かく報告・連絡・相談をしてみたり。
これは、上司に対するネガティブな感情を、表向きの「丁寧さ」で打ち消す行動です。
「怒りを抱いたままでは関係が壊れてしまう」という無意識の恐れも背景にあります。
防衛機制の打ち消しがもたらすメリットとデメリット

打ち消しは、心を守るために働く防衛機制のひとつです。
しかし、その働きがプラスに出る場合もあれば、マイナスに働いてしまう場合もあります。
ここでは、打ち消しのメリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット:不安や罪悪感をやわらげる効果
- 打ち消しは、強い罪悪感や不安を感じたときに心を落ち着かせる役割を果たします。
- 「悪いことをしてしまった」という気持ちを、その後の良い行動で心理的に相殺することで、精神的な安定を取り戻せます。
例:
- 子どもが暴言を吐いたあとに「大好き」と言って抱きつく → 親子の関係が壊れるのを防ぐ
- 恋人に罪悪感を抱いたときに優しくする → 関係悪化を回避する
👉 このように、人間関係を維持する上で役立つ場面も多いのです。
デメリット:根本的な解決にはつながらないリスク
- 打ち消しは一時的に安心感を与えてくれる反面、多くの場合は問題の本質的な解決に直結しにくいとされています。罪悪感や不安の「原因」を見つめないまま、埋め合わせの行動でやり過ごしてしまうことがあるからです。
ただし、人によってはその行動をきっかけに「同じことは繰り返さない」と決意したり、関係修復につながるケースもあります。つまり、便利な心の仕組みではあるものの、長期的に見れば自分の感情や行動の背景を振り返ることが大切です。
例:
- 上司への不満 → 「丁寧に接する」ことで罪悪感を薄めるが、根本の不満や職場環境は変わらない。
👉 その結果、同じ問題が繰り返される可能性があります。
繰り返されることで問題が固定化する可能性
- 打ち消しが習慣化すると、「罪悪感 → 埋め合わせ」で処理するサイクルができあがります。
- 本当の感情や不満を見つめ直さないため、長期的には心のモヤモヤが解消されず、人間関係に「不自然さ」や「ギクシャク感」が残ることもあります。
つまり、打ち消しは短期的には心を守るが、長期的には課題解決を遅らせるリスクがあるのです。
打ち消しと他の防衛機制との違いを比較
打ち消しは「悪いことをした・思ってしまった」という罪悪感を、反対の行動で帳消しにする防衛機制です。
しかし、他の防衛機制(否認・抑圧・反動形成・合理化など)と混同されやすい部分があります。
ここでは、それぞれの違いを整理してみましょう。
否認との違い|現実を「なかったこと」にするのか
- 否認(denial):起きた出来事そのものを「そんなことは起きていない」と否定する。
例:病気を告知されても「誤診に違いない」と思い込む。 - 打ち消し(undoing):出来事を否定せず、「良い行動を加えて相殺する」。
例:暴言を吐いた後に「大好き」と言う。
👉 否認=事実を消す/打ち消し=事実を認めて帳消しにする、この違いがポイントです。

抑圧との違い|感情を押し込めるのか、行動で相殺するのか
- 抑圧(repression):不快な感情や欲求を、意識に上がらないよう心の奥に押し込める。
例:怒りを自覚できず「なんとなくモヤモヤ」と残る。 - 打ち消し:感情を消すのではなく、行動で埋め合わせる。
例:上司への不満を抱いた後に、過剰に丁寧な態度を取る。
👉 抑圧は「感情を隠す」、打ち消しは「感情を認めて行動でバランスを取る」。

反動形成や合理化との違い|混同しやすい防衛機制との整理
- 反動形成(reaction formation):本音とは真逆の態度を取る。
例:本当は嫌いな相手に、過剰に優しくする。 - 合理化(rationalization):自分に都合の良い理由をつけて正当化する。
例:「失敗したけど、練習不足のせいだから仕方ない」と考える。 - 打ち消し:嫌な感情や行動を「後から補う行為」で帳消しにする。
👉 「反動形成」と「打ち消し」は似ているようで、「反対の態度を取る」のか「後で埋め合わせる」のかで区別できます。


まとめると:
- 否認=事実をなかったことにする
- 抑圧=感情を押し込める
- 反動形成=本音と逆の態度を取る
- 合理化=もっともらしい理由でごまかす
- 打ち消し=後から相殺する行動をとる
防衛機制の打ち消しに気づき、日常に活かすヒント

打ち消しは無意識に働くことが多いため、まずは「自分が打ち消しをしているかもしれない」と気づくことが大切です。
気づくことで、罪悪感や不安を和らげつつ、より建設的な方法で感情を整理できるようになります。
「自分は今、打ち消しをしているかも」と気づく方法
- 急に必要以上に優しくしたり、プレゼントをしたくなるとき
- 普段よりも過剰に丁寧に振る舞ってしまうとき
- 「あれ?なんだか不自然だな」と自分でも感じるとき
こうした行動パターンに気づいたら、それが打ち消しのサインかもしれません。
日記やセルフモニタリングで感情を整理する
打ち消しに気づいたら、次は自分の感情を言葉にして整理することが大切です。
- 日記に「本当はこう感じていた」と書き出す
- 感情と行動をセットで振り返る(例:イライラ → 翌日やたら丁寧になった)
- 自分の行動の「裏にある気持ち」を見つける
👉 感情を言語化すると、打ち消しに頼りすぎずに済みます。
カウンセリングや自己理解につなげる視点
もし打ち消しが頻繁に起きていて、日常生活や人間関係に影響を与えていると感じるなら、専門家との対話も有効です。
- カウンセリングでは「なぜ打ち消しをしてしまうのか」を一緒に整理できる
- 無意識の罪悪感や不安にアプローチできる
- 自己理解を深め、人間関係にも役立てられる
打ち消しは悪いものではありませんが、気づいて向き合うことでより健康的に活用できるのです。
まとめ|防衛機制の打ち消しを理解して自己理解を深めよう
ここまで、防衛機制の一つである打ち消し(undoing)について、意味や具体例、そして活かし方を解説してきました。
最後に、記事全体のポイントを整理しておきましょう。
打ち消しを知ることで見える心の仕組み
- 打ち消しとは:「望ましくない感情や行動」を、その後の「良い行動」で帳消しにしようとする心の働き。
- 具体例:子どもが暴言を吐いた後に「大好き」と言う、恋人に浮気心を抱いた後に優しくする、職場で不満を抱いた後に丁寧に接する。
- 役割:罪悪感や不安を軽減し、心の安定を保つための防衛機制。
この仕組みを理解すると、「自分の心がなぜそう動いたのか」が見えやすくなります。
自己理解と人間関係に役立てるポイント
- 気づくこと:「あ、今の自分の行動は打ち消しかも」と振り返るだけで、自己理解が深まります。
- 整理すること:日記やセルフモニタリングを通じて「本当の気持ち」を言語化する。
- 活かすこと:気づきを人間関係に応用し、不自然な言動を減らすことで、より自然で健全な関わり方ができるようになります。
👉 打ち消しは、心を守るための自然な防衛反応です。
しかし、無意識のまま繰り返すと問題を先送りにしてしまうこともあります。
だからこそ、理解して気づくことで「自己理解のきっかけ」や「人間関係を改善するヒント」として活かしていけるのです。