「人はなぜ他人の行動を真似してしまうのか?」
たとえば、子どもが親の口調を真似したり、SNSで人気の人の習慣を自分も取り入れてみたり──。
そんな“観察からの学び”には、実は心理学的な仕組みがあります。
それが社会的学習理論(Social Learning Theory)。
人は他人の行動を「見て・覚えて・真似して・続ける」ことで成長するという考え方です。
この記事では、
- 社会的学習理論の基本と背景
- バンデューラが提唱した「4段階モデル」の流れ
- 教育・職場・SNSなど、日常での具体的な活かし方
をわかりやすく解説します。
「人がどう変わるのか」「どうすれば良い影響を与えられるのか」が見えてくるはずです。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
社会的学習理論とは?人は「観察」から学ぶ心理学
私たちは、誰かの行動を「見ているだけ」で、自然と学んでいることがあります。
例えば——
- 子どもが親の口調を真似する
- 新人が上司の接客態度を観察して覚える
- SNSで「人気の人の行動」を参考にする
これらはすべて、社会的学習理論(Social Learning Theory) で説明できる現象です。
社会的学習理論の基本定義
社会的学習理論とは、「人は他人の行動を観察し、その結果を見て学ぶ」という考え方です。
提唱者は心理学者のアルバート・バンデューラ(Albert Bandura)。
彼は、私たちが経験を通してだけでなく、他者の行動や結果からも学べることを実験的に示しました。
たとえば、誰かが「挨拶をして褒められた」のを見たとき、
私たちは「挨拶をすれば自分も褒められるかも」と学びます。
このように他人の成功や失敗を通じて行動を学ぶ仕組みを、心理学的に整理したのが社会的学習理論です。
提唱者アルバート・バンデューラの功績
バンデューラは、20世紀の心理学において大きな転換をもたらした人物です。
当時主流だったのは、行動主義(Behaviorism)という考え方でした。
行動主義は「刺激(S)→反応(R)」というシンプルな法則で人間の行動を説明しようとしましたが、
そこには「人がどう考えているか」という内面の認知が含まれていませんでした。
バンデューラはそこに「待った」をかけ、
「人の行動は、環境だけでなく、認知や観察によっても変わる」
と主張します。
彼は行動主義に認知心理学の要素を融合させ、
「他人を観察し、頭の中でイメージし、行動を再現する」という過程を理論化しました。
これが後に社会的認知理論(Social Cognitive Theory)へと発展します。
社会的学習理論が生まれた背景と時代的意義
1950〜60年代、テレビやメディアの影響力が急速に拡大した時代。
「子どもがテレビの暴力を真似するのでは?」という問題意識が高まっていました。
このとき登場したのが、バンデューラの有名な「ボボ人形実験」です(後の章で詳しく解説)。
この実験によって、
「人は報酬を受け取らなくても、観察だけで行動を学ぶ」
という事実が明らかになりました。
つまり、学習は「経験」だけでなく「観察」によっても成立する。
これは、教育・社会・メディア・ビジネスに至るまで、
“人は影響し合いながら学ぶ存在” であることを示した、画期的な理論だったのです。
まとめ:社会的学習理論のポイント
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 提唱者 | アルバート・バンデューラ |
| 基本概念 | 他人の行動と結果を観察することで学ぶ |
| 背景 | 行動主義に認知的視点を取り入れた |
| 意義 | 「見るだけで学ぶ」観察学習のメカニズムを理論化 |
| 応用例 | 教育・子育て・職場・SNS・広告など人の行動全般 |
バンデューラの4段階モデルとは?観察学習のプロセスをわかりやすく解説
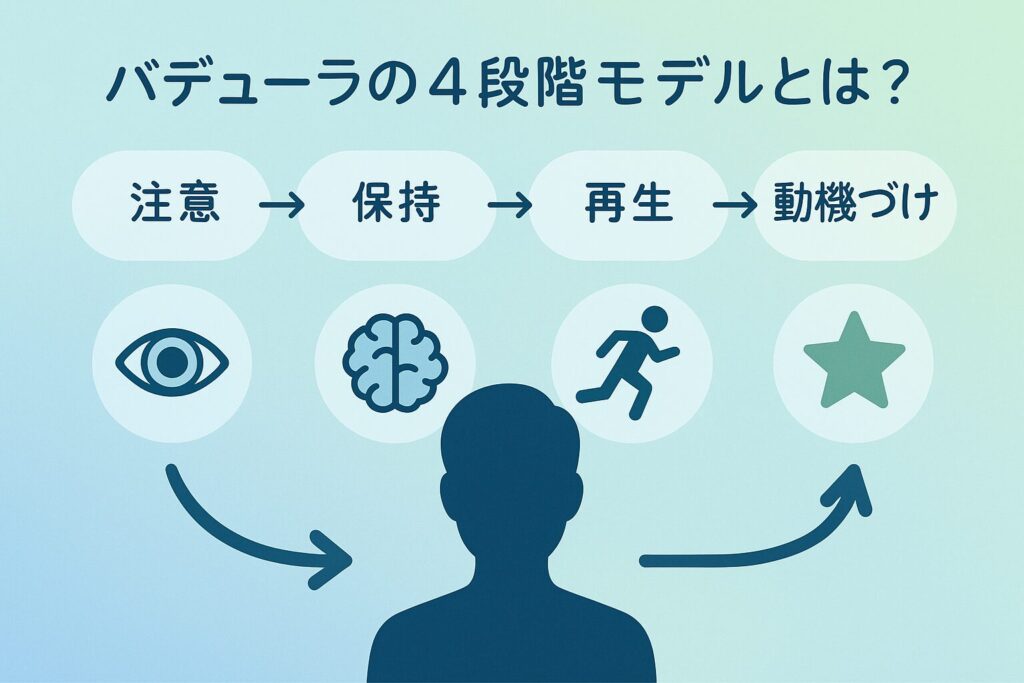
社会的学習理論の中核にあるのが、バンデューラが提唱した「観察学習の4段階モデル」です。
人が他者の行動を「見て→理解して→まねて→続ける」には、4つの心理的ステップが必要だとされます。
このプロセスを理解すると、
「なぜ真似される人とされない人がいるのか」
「どうすれば行動が定着するのか」
が、分かりやすくなります。
① 注意(Attention)|まずモデルに注目する段階
観察学習の第一歩は、「誰の行動を見るか」です。
これを心理学では注意の段階と呼びます。
人は無意識に「自分に関係がありそう」「魅力的」「信頼できる」と感じた人に注意を向けます。
たとえば──
- 子どもは憧れの親や先生の行動をまねしやすい
- 社員は尊敬される上司や先輩の言動を真似する
- SNSでは人気のインフルエンサーの行動が模倣されやすい
つまり、モデルの魅力・信頼性・類似性が強いほど、注意が集まりやすくなります。
逆に、興味を引かない人の行動は学習されにくいのです。
② 保持(Retention)|観察した行動を記憶する段階
次に必要なのが、観察した内容を記憶に残すこと。
ただ「見ただけ」では忘れてしまいます。
記憶を強化するには、以下のような工夫が有効です。
- 言語化する:「あの人はまず〇〇していたな」と手順を頭で整理する
- イメージ化する:動作や流れを映像のように思い出せるようにする
たとえば、スポーツ選手が他人のフォームを頭の中で繰り返しイメージするのは、保持段階の典型的な例です。
この「頭の中での再生」が、後の行動再現の基盤になります。
③ 再生(Reproduction)|記憶した行動を再現する段階
観察して記憶した行動を、実際にやってみる段階です。
これを「再生(reproduction)」と呼びます。
ここでは、身体的スキルや練習の回数が大きく影響します。
- 最初はぎこちなくても、何度も繰り返すことで上達する
- 行動を実際にやってみることで、脳がフィードバックを得て修正する
たとえば、YouTubeで料理動画を見て「なるほど!」と思っても、
実際にやってみると上手くいかない──これは保持から再生へのギャップです。
何度も試すことで、行動が定着していきます。
④ 動機づけ(Motivation)|行動を続けたいと思う段階
最後に大切なのが、「その行動を続けたいと思える理由」です。
これがなければ、学習した行動は一時的で終わってしまいます。
ここで登場するのが、報酬(reward)と代理強化(vicarious reinforcement)という考え方。
- 自分が褒められた、うまくいった(直接的報酬)
- 他人がその行動で褒められているのを見た(代理強化)
このようなポジティブな結果が見えると、行動を続ける意欲が高まります。
逆に、他人が罰せられるのを見た場合は、その行動を避けるようになります。
つまり、他人の成功・失敗も自分の学習材料になるのです。
✅ まとめ:観察学習の4ステップ
| 段階 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 注意 | 模範となる人に注目する | 憧れの人・信頼できる人に興味を持つ |
| 保持 | 行動を記憶する | 言葉・映像で頭の中に残す |
| 再生 | 実際にやってみる | 真似して行動を試す |
| 動機づけ | 行動を続ける意欲を持つ | 成功・称賛・報酬・代理強化 |
社会的学習理論の代表的な研究|ボボ人形実験の意味

社会的学習理論を語る上で欠かせないのが、「ボボ人形実験(Bobo doll experiment)」です。
これは、「人は他人を観察するだけで行動を学ぶ」という考えを実証した、有名な心理学実験です。
🧪 実験の概要と結果
1961年、アメリカの心理学者アルバート・バンデューラは、子どもたちを対象にした実験を行いました。
手順は次の通りです。
- 子どもたちに、大人がボボ人形(パンチしても倒れない人形)を殴る映像を見せる。
- その後、子どもたちを同じ部屋に入れ、自由に遊ばせる。
結果──
大人が暴力的に人形を扱う映像を見た子どもは、同じように人形を叩いたり蹴ったりする行動を取ったのです。
一方、暴力的な映像を見なかったグループでは、そうした行動はほとんど見られませんでした。
つまり、「実際にやってみなくても、他人の行動を見るだけで模倣が起こる」ことが証明されたのです。
「暴力の模倣」ではなく、“行動様式の模倣”
ここで誤解してはいけないのは、
この実験が「暴力を誘発した」わけではないという点です。
子どもたちは人間を攻撃したわけではなく、
あくまで人形を叩くという“遊び的・象徴的行動”を模倣したに過ぎません。
このことから、バンデューラが示したのは、
「他人の行動パターンを観察し、それを自分の行動の一部として再現する」
という学習のメカニズムであり、暴力の直接的な再現ではありません。
現実の暴力行動とは異なる
実際の暴力行動が起きるかどうかは、
その後の社会的環境・道徳意識・感情コントロールによって大きく左右されます。
つまり、「叩く」という行為を見たとしても、
- 社会的に禁止されている
- 相手の痛みを理解している
- 周囲がそれを評価しない
といった要因があれば、現実の暴力にはつながりません。
この実験が明らかにしたのは、模倣が生じる条件であり、
「暴力を増やすメディアが悪い」という単純な結論ではないのです。
この実験が示したこと
この実験は、それまでの行動主義(S-R理論)では説明できなかった学習の仕組みを明らかにしました。
行動主義では、「人は報酬や罰によって行動を学ぶ」とされていましたが、
バンデューラの実験はそれを覆します。
🔸 観察によっても行動は学習される。
🔸 直接的な報酬がなくても、人は他人を通じて学ぶ。
この「観察から学ぶ力」こそが、社会的学習理論の根幹です。
さらに、バンデューラはこの現象を「代理強化(vicarious reinforcement)」と呼びました。
他人が褒められる・成功する姿を見ただけでも、私たちは「自分もやってみよう」と思う心理が働きます。
現代への応用|メディア・SNSが与える影響
ボボ人形実験の意義は、半世紀を超えた現代にも当てはまります。
テレビ、映画、YouTube、SNS──
これらは、私たちが他人の行動を観察する機会を爆発的に増やしました。
- 子どもがアニメのキャラの言葉づかいを真似する
- 若者がTikTokのトレンドダンスを模倣する
- 社会人がインフルエンサーの働き方を真似して起業する
これらはすべて、「観察→模倣→行動」の流れで起こる社会的学習の実例です。
一方で、暴力的・攻撃的な表現が模倣されるリスクもあります。
ただし、それは表現そのもののせいというより、見る側の心理状態や性格の影響が大きいのです。
そのため、教育やメディアリテラシーの分野では、
単に表現を制限するよりも、「それをどう受け取り、どう考えるか」を教えることが重視されています。
✅ まとめ:ボボ人形実験が伝えること
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 実験者 | アルバート・バンデューラ(1961年) |
| 対象 | 幼児 |
| 方法 | 大人が人形を殴る映像を見せる |
| 結果 | 子どもも同じように人形を殴った |
| 意味 | 人は観察によって行動を学ぶ/報酬がなくても模倣が起こる |
| 現代への応用 | SNS・メディアの模倣行動、教育・子育て・広告の設計に応用可能 |
ボボ人形実験は、
「人は見たものから学び、社会の中で行動を形づくる」という根本原理を示しました。
社会的学習理論を実生活で活かす方法

社会的学習理論は、ただの心理学の知識ではなく、
「人を育てる」「影響を与える」「行動を変える」ための実践的なツールです。
ここでは、教育・職場・SNSという3つの場面に分けて、
日常での活かし方を具体的に見ていきましょう。
教育・子育てでの活かし方
子どもは、言葉よりも大人の行動から多くを学びます。
「こうしなさい」と口で言っても、親自身がそれをやっていなければ、子どもは真似しません。
つまり、教育の原則は「教えるより、見せる」です。
実践ポイント
- 良い行動を実際に見せる(例:挨拶・片づけ・感謝を伝える)
- 行動を褒めるときは具体的に(「ありがとうと言えたね」など)
- 悪い行動を叱るときは人格ではなく行動を指摘(「この行動は危ないね」)
また、子どもは親だけでなく、先生・友達・テレビの登場人物など、
多くの「社会的モデル」から影響を受けます。
したがって、どんなモデルに触れるかが成長に大きく関わるのです。
職場・OJTでの活用法
職場でも社会的学習理論は非常に有効です。
新入社員は上司や先輩の行動を観察しながら、
「こうすればうまくいく」「これは避けた方がいい」という判断を学んでいます。
つまり、職場では誰もが誰かのモデルになっているということ。
応用のヒント
- 上司は「背中を見せる」意識を持つ(挨拶・言葉遣い・問題対応の仕方)
- 成功事例を共有して「良いモデル」を増やす(報告会・ナレッジ共有)
- 褒められる文化をつくる(代理強化により、他者も良い行動をまねしやすくなる)
一方で、ネガティブな行動(愚痴・無責任・非協力)も観察されているため、
リーダーが率先して良い行動を見せることが、職場文化の形成につながります。
SNS時代の社会的学習|人がインフルエンサーを真似する心理
現代の社会的学習は、SNSの中で毎日起きています。
私たちはインフルエンサーや有名人を観察し、
「その行動をすれば認められる・人気が出る」と学んでいます。
これはまさに、代理強化(vicarious reinforcement)の典型です。
他人が「いいね」や称賛を得ているのを見ることで、
私たちも同じ行動をとりたくなるのです。
SNSでの学習の仕組み
- 承認欲求が観察学習の動機づけになる
- バズった投稿や行動が「成功モデル」として模倣される
- フォロワー数や反応が報酬のように働く
ただし、ここには注意も必要です。
他人の価値観をそのまま取り入れると、自分の軸を失い、
「他人に合わせてしまう学習」が起こるリスクもあります。
SNSを使うときこそ、
「自分は何を見て、誰をモデルにしているのか」を意識することが大切です。
✅ まとめ:日常のあらゆる場面が“観察学習”のチャンス
| 場面 | モデルとなる存在 | 学びのポイント |
|---|---|---|
| 教育・子育て | 親・教師・友達 | 行動で示す・褒め方の工夫 |
| 職場・OJT | 上司・同僚 | 良い行動を共有・代理強化を活かす |
| SNS・メディア | インフルエンサー・フォロワー | モデル選びの意識・承認欲求とのバランス |
社会的学習理論と関連する心理学理論
社会的学習理論は、単独の理論として存在しているわけではありません。
その後の心理学に大きな影響を与え、いくつかの重要な理論へと発展していきました。
ここでは特に、
- 自己効力感理論(Self-Efficacy)
- 社会的認知理論(Social Cognitive Theory)
- モデリング理論(Modeling Theory)
の3つを取り上げ、関連性をわかりやすく解説します。
①自己効力感理論(Self-Efficacy)との関係
バンデューラが社会的学習理論を発展させる中で、
特に注目されたのが「自己効力感(self-efficacy)」という概念です。
自己効力感とは、
「自分にはそれを達成できる能力がある」という信念
のことです。
たとえば、同じ状況でも──
- 「自分ならできる」と思う人は挑戦し、
- 「どうせ無理」と思う人は行動しません。
社会的学習理論では、他人の成功を観察することで、
「自分にもできそうだ」と感じる=代理経験(vicarious experience)
が生まれると考えます。
この「他人の成功が自分の自信になる」プロセスが、
自己効力感を高め、行動の継続を支えるのです。

②社会的認知理論への発展
バンデューラは後に、社会的学習理論をさらに発展させ、
社会的認知理論(Social Cognitive Theory)を提唱しました。
この理論では、
人間の行動は、「環境・行動・認知」の3要素が相互に影響し合う
と説明されます。
これを相互決定論(reciprocal determinism)と呼びます。
| 要素 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 環境 | 周囲の人・文化・状況 | 職場の雰囲気、SNSの空気感 |
| 行動 | 自分の具体的な行動 | 投稿する、挑戦する、話しかける |
| 認知 | 思考・価値観・期待 | 「どう思われるだろう」「これならできそう」 |
たとえば、SNSでポジティブなコメントをもらう(環境)ことで、
「自分の発信に価値がある」と思い(認知)、さらに投稿を続ける(行動)ようになる──
こうした相互作用のループが、人の行動変化を生み出すのです。


③モデリング理論との違いと関係性
モデリング理論は、社会的学習理論の中核をなす「観察学習」のメカニズム部分を指します。
簡単に言えば、
社会的学習理論=全体の枠組み
モデリング理論=その中の具体的プロセス
です。
モデリングには3つのタイプがあります:
- 直接モデリング:実際に目の前で行動を見る(例:上司の対応を見て覚える)
- 象徴的モデリング:映像・本・SNSなどを通じて学ぶ(例:YouTubeで学ぶ)
- 自己モデリング:過去の自分の成功体験を再現する(例:以前うまくいった方法を思い出す)
つまり、モデリングとは「誰の行動を、どのように観察して学ぶか」という具体的な部分であり、
社会的学習理論を“動かすエンジン”のような役割を持っています。

✅ まとめ:関連理論をつなぐキーワード
| 理論名 | 提唱者 | キー概念 | 社会的学習理論との関係 |
|---|---|---|---|
| 自己効力感理論 | バンデューラ | 「できる」という信念 | 観察学習が自信を育てる |
| 社会的認知理論 | バンデューラ | 相互決定論 | 社会的学習理論の発展形 |
| モデリング理論 | バンデューラ | 模倣・代理強化 | 観察学習の具体的プロセス |
まとめ|社会的学習理論を理解すれば、人の変化は見えてくる
「人はなぜ変わるのか」「なぜ真似してしまうのか」——
その答えを教えてくれるのが、社会的学習理論です。
この理論を理解すれば、
子どもや部下、そして自分自身の行動変化の“仕組み”が見えてきます。
4段階モデルの要点の振り返り
社会的学習理論の中核となるのが、観察学習の4段階モデルでした。
おさらいとして、もう一度流れを整理しておきましょう。
| 段階 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 注意(Attention) | 誰の行動に注目するか | 魅力・信頼性・類似性が高い人を見て学ぶ |
| ② 保持(Retention) | 見た行動を記憶に残す | 言語化・イメージ化で記憶を強化 |
| ③ 再生(Reproduction) | 実際にやってみる | 真似して行動を再現する |
| ④ 動機づけ(Motivation) | 続ける理由を持つ | 報酬・称賛・代理強化によるモチベーション維持 |
この4つのステップが揃うと、人は観察を通して自然に行動を変えられます。
逆に、どれかが欠けると「見ても真似しない」「続かない」という結果になります。
学習・成長・教育に共通する「見せる力」の重要性
社会的学習理論が伝える最大のメッセージは、
「人は教えられるより、見せられて変わる」
ということです。
教育者やリーダーが「何を言うか」よりも、
「どう行動しているか」のほうが強い影響を与えます。
たとえば:
- 子どもに「感謝しなさい」と言うより、親自身が「ありがとう」と言うほうが効果的。
- 上司が「失敗してもいい」と言うより、実際に自分のミスを共有したほうが部下は安心する。
このように、「行動で伝える」「モデルになる」ことが、最も自然な教育法であり、
信頼されるリーダーシップや子どもの成長にもつながります。
今後の応用:AI・SNS・組織学習にも広がる可能性
社会的学習理論は、いまや心理学の枠を超えて、
AI・SNS・企業研修・組織学習など、幅広い分野で応用されています。
- AI教育:ChatGPTのようなAIが「成功例・失敗例」を示すことで、人が効率的に学習できる。
- SNSマーケティング:他人の成功体験(レビュー・事例)が代理強化を起こし、購買行動を促す。
- 組織学習:社内で「成功事例を共有」することで、全員の行動変化を促す。
このように、人が「見て学ぶ」力を活かすことは、
教育・ビジネス・テクノロジーのすべてに通じる、普遍的な原理なのです。
まとめのまとめ|社会的学習理論で人の成長をデザインする
- 人は「見る・覚える・真似する・続ける」の4段階で学ぶ
- 他人の成功・失敗も、自分の学びに変えられる
- 見せ方・見られ方を意識すれば、行動変化は加速する
社会的学習理論を理解することは、
「自分と他人の成長をデザインする」ことでもあります。
🌱 見せることが、教えること。
観察が、人を変える行動につながります。



