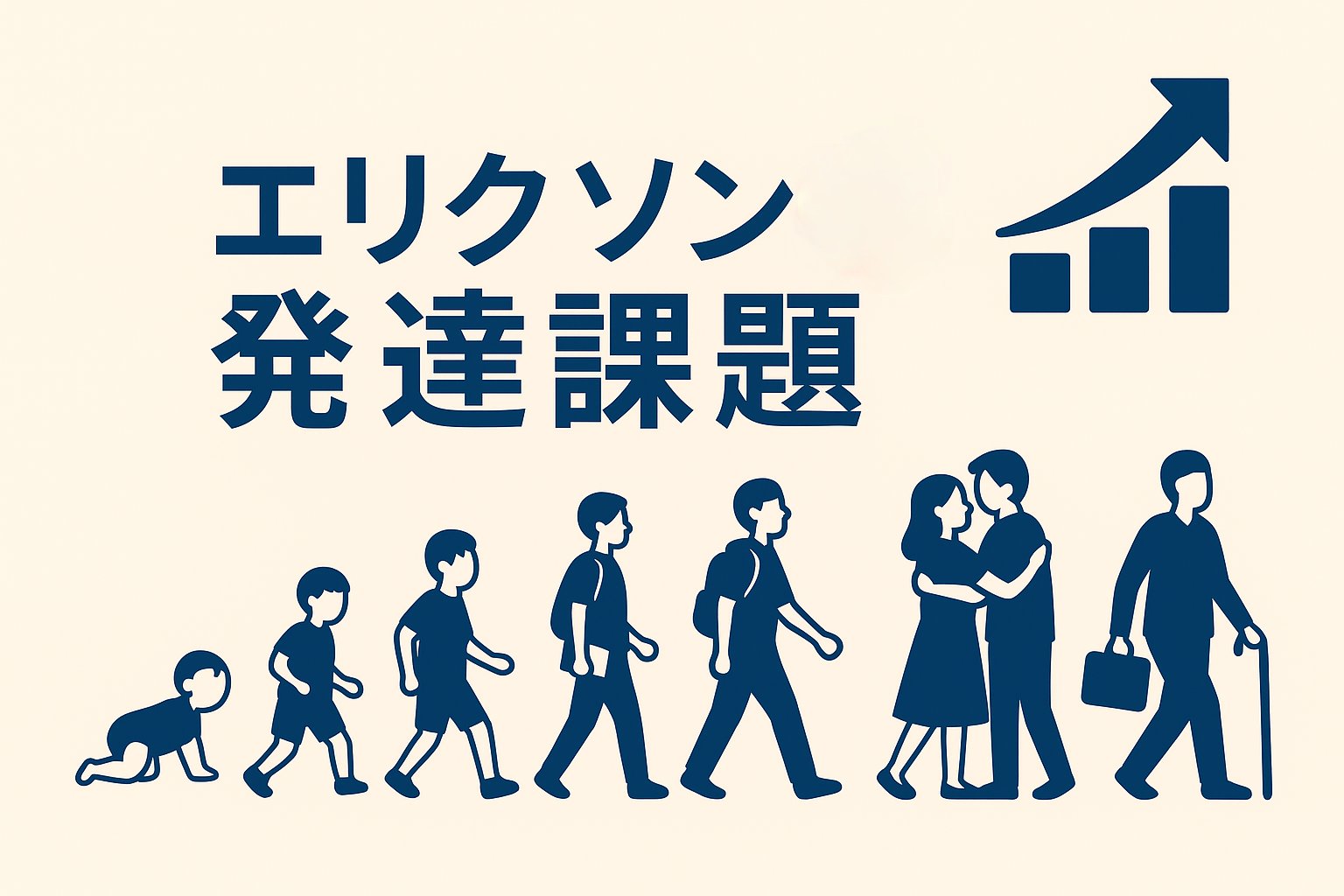「自分は今、人生のどんな課題に向き合っているんだろう?」そんな疑問を持ったことはありませんか?
- 将来が見えずに不安…
- 周りと比べて劣等感を抱く
- 過去の失敗を引きずって前に進めない
この記事では、
- エリクソンの発達課題の基本と背景
- 年齢ごとの8つの段階と具体例
- 課題は「やり直せる」という前向きな視点
- 日常やキャリアでの活用法
をわかりやすく解説します。人生を整理する地図のように役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
エリクソンの発達課題とは?心理学での基本的な考え方
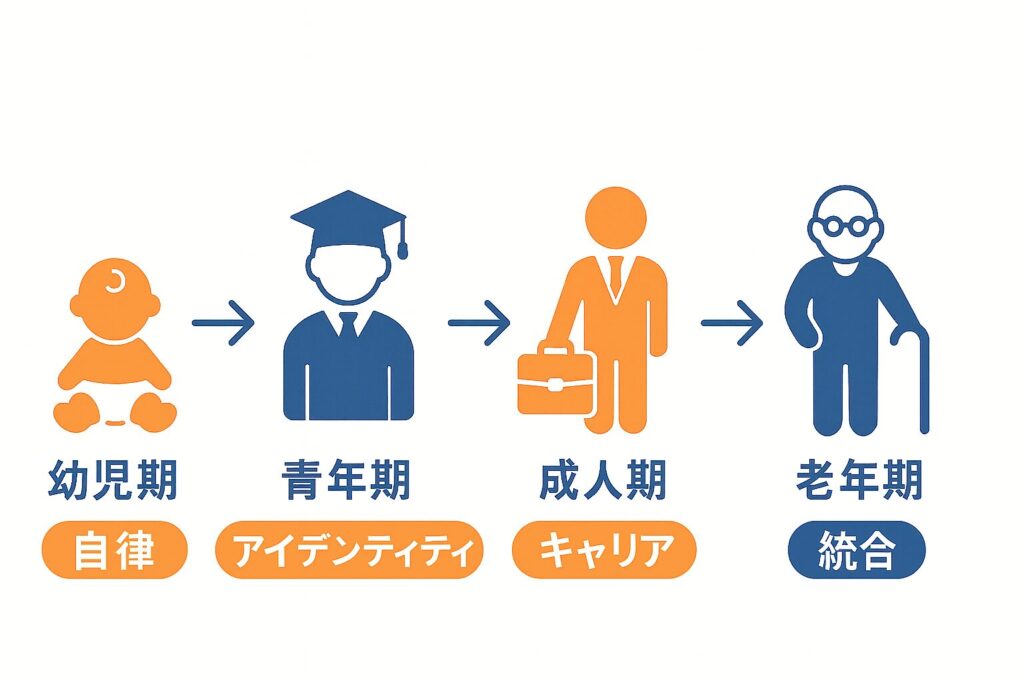
「発達課題」の定義と意味をやさしく解説
発達課題とは、人が成長していく過程でその時期ごとに直面する「心理的・社会的なテーマ」のことを指します。
たとえば、子どものころには「自分でトイレに行けるようになる」「友だちと仲良く遊ぶ」といった課題があります。大人になれば「自分のキャリアを築く」「家族や社会に貢献する」といった課題に変わります。
つまり、発達課題は「年齢や人生の段階ごとに現れる、心の宿題」のようなものだと考えると分かりやすいでしょう。
エリクソンが注目した「心理社会的発達」とは?
アメリカの心理学者エリク・エリクソンは、フロイトの精神分析を土台にしつつ、「人間は一生を通じて発達する」という新しい視点を打ち出しました。
彼が重視したのは心理社会的発達。これは「心の成長(心理)」と「人との関わり(社会)」が互いに影響し合いながら、人の人格が形づくられていくという考え方です。
たとえば、青年期に「自分は何者か?」という問い(アイデンティティ探し)に向き合うのは、社会との関係性の中で自分を確立する必要があるからです。心理的な課題と社会的な役割が重なって現れるのが、エリクソン理論の特徴です。
ハヴィガーストの発達課題との違い
エリクソンより少し前に、教育学者のハヴィガーストが「発達課題」という言葉を使いました。彼は「年齢に応じて達成すべき課題」を整理し、例として「学童期には読み書きを覚える」「成人期には職業に就く」といったリストを提示しました。
一方で、エリクソンは課題を“心理社会的な危機”として捉えたのが大きな違いです。
単なるスキル習得や社会的役割ではなく、心の中で「信頼できるか/できないか」「自分は何者か」という葛藤を乗り越えることが重要だとしたのです。

エリクソンの発達課題:8つの段階を年齢別に整理
エリクソンは、人の一生を8つの発達段階に分け、それぞれに心理社会的な「課題」があると説明しました。
課題は「対立する二つのテーマ」として示されており、そのどちらに傾くかによって、その後の人格形成に影響を与えます。
ここでは、各段階をわかりやすく整理します。
| 段階 | 年齢 | 課題(対立するテーマ) |
|---|---|---|
| 乳児期 | 0〜1歳 | 基本的信頼 vs 不信 |
| 幼児期 | 1〜3歳 | 自律性 vs 恥・疑惑 |
| 遊戯期 | 3〜6歳 | 主導性 vs 罪悪感 |
| 学童期 | 6〜12歳 | 勤勉性 vs 劣等感 |
| 青年期 | 12〜18歳 | 同一性 vs 同一性拡散 |
| 成人期初期 | 18〜40歳 | 親密性 vs 孤立 |
| 成人期中期 | 40〜65歳 | 生産性 vs 停滞 |
| 老年期 | 65歳〜 | 自我統合 vs 絶望 |
乳児期(0〜1歳):基本的信頼 vs 不信
- 内容:養育者が安心・安定して世話をしてくれると、「人は信じられる」という感覚=基本的信頼が育つ。逆に不安定だと「世界は危険だ」という不信感を持ちやすい。
- 例え:お腹がすいたら必ずミルクをもらえる赤ちゃんは「安心感」を覚えますが、放置されると「世の中は怖い」と感じるようになる。

幼児期(1〜3歳):自律性 vs 恥・疑惑
- 内容:歩く・排泄するなど、自分でできることが増えていく時期。成功体験が積み重なると自律性が育つ。失敗を過度に叱られると恥や疑惑を持ち、自信を失う。
- 例え:トイレトレーニングで「できたね!」と褒められると自信になるが、「まだできないの?」と責められると萎縮してしまう。
遊戯期(3〜6歳):主導性 vs 罪悪感
- 内容:好奇心旺盛で「やってみたい!」と積極的になる時期。挑戦を応援されれば主導性が育ち、自発的に動ける。逆に禁止ばかりされると「ダメなんだ」と感じて罪悪感を抱く。
- 例え:砂場でお城を作ろうとする子を応援するか、邪魔扱いするかで将来の積極性に差が出る。
学童期(6〜12歳):勤勉性 vs 劣等感
- 内容:学校で勉強や作業を通じて「やればできる」という勤勉性を学ぶ。努力しても認められなかったり失敗続きだと劣等感を感じやすい。
- 例え:テストで頑張ったことを認めてもらえれば自信になるが、常に比較されると「自分はダメだ」と思い込みやすい。
青年期(12〜18歳):同一性 vs 同一性拡散
- 内容:自分は何者か、どんな人生を送りたいのかを模索する時期。自分の価値観や生き方を見出せれば同一性(アイデンティティ)が確立される。迷い続けると同一性拡散に陥る。
- 例え:将来の夢を探す高校生が部活や進路を通じて自分を確立する一方、方向性が定まらないと「自分は何者でもない」と感じてしまう。

成人期初期(18〜40歳):親密性 vs 孤立
- 内容:恋愛・友情・結婚など、他者と深い関係を築く力が問われる。信頼関係を築ければ親密性が育ち、失敗すると孤立を感じやすい。
- 例え:パートナーや友人と本音を語れる関係を築くか、それとも距離を置いて孤独感を抱えるかが分かれ目。
成人期中期(40〜65歳):生産性 vs 停滞
- 内容:家庭や仕事を通じて「次世代や社会に貢献すること」が課題。うまく役割を果たせれば生産性を実感でき、役割を見失うと停滞感を抱く。
- 例え:子育てや後輩指導を楽しめる人は充実感を得られるが、「自分だけのこと」に閉じこもると虚しさが残る。
老年期(65歳〜):自我統合 vs 絶望
- 内容:自分の人生を振り返り、「これでよかった」と思えれば自我の統合が得られる。後悔ばかりが残ると絶望を感じやすい。
- 例え:過去の出来事を「学びだった」と受け入れられる人は安らかに老後を過ごせるが、「あのとき失敗した」と悔やむ人は心が苦しくなる。
まとめ:エリクソンの「心理社会的発達の8段階」
| 段階 | 時期(目安) | 発達課題(対立テーマ) | 得られる徳(成功時) | 否定的側面(失敗時) | 主な焦点・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 乳児期(0〜1歳半) | 基本的信頼 vs 不信 | 希望(Hope) | 不安・猜疑 | 愛情深く世話されることで「人を信じても大丈夫」と学ぶ。育児放棄などで不信感が形成されることも。 |
| 第2段階 | 幼児期(1歳半〜3歳) | 自律性 vs 恥・疑惑 | 意志(Will) | 恥・依存 | 自分でやってみる経験が自立心を育てる。過干渉や失敗への罰が強いと、自信を失いやすい。 |
| 第3段階 | 遊戯期(3〜6歳) | 自主性(積極性) vs 罪悪感 | 目的(Purpose) | 罪悪感 | 行動を自ら起こす力。失敗を責められすぎると「やってはいけない」と感じて意欲を失う。 |
| 第4段階 | 学童期(6〜12歳) | 勤勉性 vs 劣等感 | 有能感(Competence) | 劣等感 | 学校や社会の中で努力と成果を学ぶ。成功体験が自信を育てる。比較や失敗で劣等感を抱くことも。 |
| 第5段階 | 青年期(12〜18歳) | 同一性 vs 同一性拡散 | 忠誠(Fidelity)※自分を裏切らず、同時に他人も尊重するバランス感覚 | 同一性の拡散・迷い | 「自分は何者か」を模索する時期。職業・価値観・人間関係を通して自己を確立。 |
| 第6段階 | 成人初期(18〜40歳) | 親密性 vs 孤立 | 愛(Love) | 孤立・拒絶感 | 他者と深くつながる力。自己が確立していないと親密関係に踏み込めず孤独を感じやすい。 |
| 第7段階 | 成人中期(40〜65歳) | 生産性(次世代育成) vs 停滞 | 世話(Care) | 停滞・無気力 | 子育て・仕事・社会貢献を通じて次世代へ関わる。成長が止まると虚しさを感じる。 |
| 第8段階 | 老年期(65歳以降) | 自我統合 vs 絶望 | 英知(Wisdom)※他人や過去を裁くよりも、理解し、赦し、受け入れる姿勢 | 絶望・後悔 | 自分の人生を振り返り、納得できれば「生きてよかった」と感じる。後悔が残ると死の恐怖に苦しむ。 |
エリクソンの発達課題は「やり直せる」のか?

課題は「絶対的な壁」ではなく心理的テーマ
エリクソンが示した発達課題は、「その年齢で必ず乗り越えなければならない壁」というものではありません。
ただ、その時期に直面しやすい心理的テーマを示しているにすぎません。
たとえば、青年期に「アイデンティティの確立」にうまく取り組めなかったとしても、後の人生で再び自分を見つめ直すチャンスは訪れます。課題は「一度限りの試験」ではなく、何度でも取り組めるテーマなのです。
つまり、日々の中で「これは自分にとって大切な課題だ」と感じたときに、改めて意識して取り組むことができるのです。
大人になってからでも再チャレンジできる理由
人は環境や経験によって、何度でも成長できます。
- 信頼関係を築く経験
- キャリアのやり直し
- 新しい人間関係や学び
こうした場面は、過去に取りこぼした課題に再び向き合うチャンスです。
失敗した課題を克服する例(信頼・アイデンティティなど)
- 信頼のやり直し:幼少期に親との関係で不信感を抱いた人が、大人になってパートナーや友人との安定した関係を通じて「人は信じられる」と感じ直す。
- アイデンティティの再確立:青年期に進路を見失った人が、30代や40代で自分の強みを発見し、仕事や趣味を通じて「これが自分だ」と納得できるようになる。
- 生産性の再発見:中年期に停滞感を抱いていた人が、地域活動や副業を通じて社会とのつながりを感じ直し、生きがいを得る。
このように、発達課題は「やり直し可能なテーマ」。過去にうまくいかなくても、人生のどこかで再挑戦できるのがエリクソン理論の大きな魅力です。

エリクソンの発達課題から学べること|日常や人生への活用例

自己理解やキャリア形成に役立てる方法
エリクソンの発達課題は、自分の今の位置を見直すための地図として使えます。
たとえば「今の自分はどの課題に向き合っているのか?」を考えることで、やるべきことや課題が整理されます。
- 青年期なら「自分は何者か?」という問いに取り組む
- 中年期なら「次世代や社会への貢献」を考える
- 老年期なら「これまでの人生をどう意味づけるか」を振り返る
キャリアの迷いや人生の岐路で立ち止まったときに、エリクソンの理論は自己分析の指針になります。
教育やカウンセリングでの活用シーン
学校教育やカウンセリングでも、発達課題の視点は広く活用されています。
- 教育現場:学童期の子どもには「できた!」という体験を積ませて勤勉性を育てる
- カウンセリング:青年期のクライエントにアイデンティティ探しのサポートを行う
- 福祉・介護:老年期にある人が過去を受け入れ、自我統合を感じられるように寄り添う
このように、発達課題を理解すると「その人の今の段階に合った支援」ができるようになります。
家庭や人間関係で意識したいポイント
発達課題は、家庭や人間関係を築くうえでも役立ちます。
- 子どもに対して:その年齢に応じた課題を知ることで、成長を促す関わりができる
- パートナーに対して:中年期の停滞感や老年期の振り返りを理解すると、相手を責めずに支えられる
- 自分自身に対して:過去の課題をやり直す意識を持ち、前向きに行動できる
人はそれぞれ異なるペースで発達課題に取り組んでいるため、相手を理解するヒントとしても有効です。
まとめ|エリクソンの発達課題を理解して人生に活かそう
8つの段階を理解することで得られるメリット
エリクソンの発達課題を学ぶと、人生を長期的な流れで捉えられるようになります。
- 「今の自分はどの段階の課題に直面しているのか?」が分かる
- 子どもや親、パートナーなど周囲の人の心理状態も理解しやすくなる
- 教育や仕事、家庭での関わり方に応用できる
つまり、理論を知るだけで「人生を見通す地図」を持てるのが大きなメリットです。
「やり直せる」視点を持つことで前向きになれる
エリクソンの理論で特に希望が持てるのは、課題はやり直せるという点です。
- 過去に失敗したからといって一生ダメになるわけではない
- 大人になってからでも信頼やアイデンティティを取り戻せる
- 人生のどの段階でも、新しい挑戦を通して発達を続けられる
「やり直し可能」という視点があることで、後悔よりも再チャレンジに目を向けられるようになります。