「どうしてあの人は楽しそうに努力できるんだろう?」そんな疑問を持ったことはありませんか?
やる気が続かない、報酬や評価がないと動けない、勉強や仕事がただの義務に感じる──そんなモヤモヤに悩む人は多いはずです。
実は心理学では、人が「やりたいからやる」と思える仕組みを内発的動機と呼び、これを高めるための理論がたくさん研究されています。この記事では、自己決定理論・フロー理論・認知評価理論・自己効力感理論など、代表的な心理学モデルをわかりやすく解説。さらに、日常やビジネスで内発的動機を高める具体的な方法も紹介します。
「やらされる」から「やりたい」に変わるヒントが見つかるはず。ぜひ最後まで読んでくださいね。
内発的動機とは?外発的動機との違いをわかりやすく解説
まず、内発的動機とは「自分がやりたいからやる」という自然なやる気のことを指します。
たとえば、子どもがブロック遊びに夢中になるのは「楽しいから」であって、誰かに褒められるためではありません。これが内発的動機です。
一方で、外発的動機は「ご褒美や罰」によって行動するものです。
「テストでいい点を取ればゲームしていい」「締め切りに遅れると怒られるから仕事をやる」など、外側からの圧力や報酬が理由になります。
内発的動機の基本的な定義
- 内発的動機=行動そのものが楽しい・意味があるから取り組むこと
- 外部の報酬や強制に頼らず、自分の興味や好奇心に従って行動が続く状態。
外発的動機との違い|ご褒美や罰に左右されない特徴
- 内発的動機:行動が目的そのものになる(例:楽器を弾くのが楽しいから練習する)
- 外発的動機:結果が目的になる(例:発表会で褒められるために練習する)
この違いを表にすると分かりやすいです。
| 動機の種類 | 行動の理由 | 例 |
|---|---|---|
| 内発的動機 | 興味・楽しさ・成長 | 好きなゲームをやる、絵を描く |
| 外発的動機 | 報酬・罰・評価 | お金のために残業、テストで褒められるために勉強 |

日常に見られる具体例(学習・仕事・趣味)
- 学習:歴史が好きで本を読み漁る → 内発的動機
- 仕事:プロジェクトが楽しくて新しい工夫を試す → 内発的動機
- 趣味:写真撮影が面白くて毎週出かける → 内発的動機
- 対比例:給料のために働く/怒られないために提出物を出す → 外発的動機
このように、内発的動機は「楽しさや意味があるからやる」という点で、外発的動機と大きく異なります。
そして、心理学では「この内発的動機をどう高めるか」が長年研究されてきました。
内発的動機を説明する代表的な心理学モデル
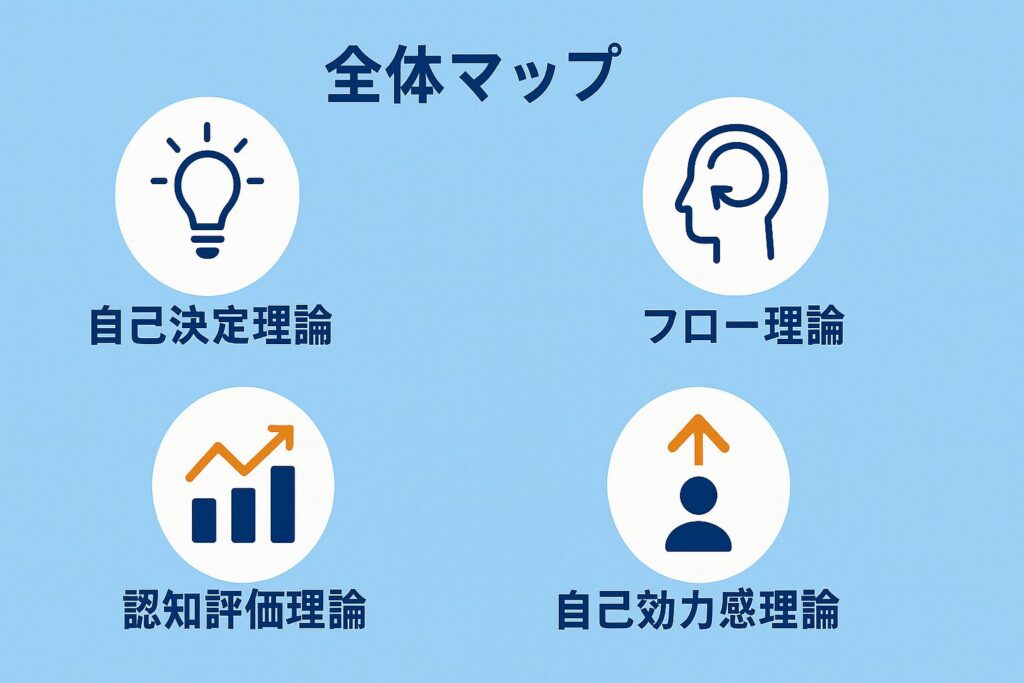
内発的動機がどうして生まれるのかを理解するには、心理学の有名な理論を押さえることが重要です。ここでは初心者でも分かりやすい形で、代表的な4つのモデルを紹介します。
①自己決定理論(デシ&ライアン)|自律性・有能感・関係性の3要素
自己決定理論(Self-Determination Theory)は、内発的動機を最もよく説明する理論として有名です。
デシとライアンという心理学者が提唱し、人間には以下の3つの基本的欲求があると説明しました。
- 自律性:「自分で選んで行動している」という感覚
- 有能感:「自分にはできる」という自信
- 関係性:「人とつながっている」「役に立っている」という安心感
この3つが満たされると、人は「やりたいからやる」という内発的動機が自然に高まります。
たとえば、子どもに「どの本を読む?」と選ばせると、自律性が満たされて勉強に前向きになりやすいのです。

②フロー理論(チクセントミハイ)|没頭と楽しさの心理学
フロー理論(Flow Theory)は、「時間を忘れて没頭する状態」を説明する理論です。
心理学者チクセントミハイが提唱しました。
- 課題の難しさと自分のスキルがちょうど釣り合うと、集中が極限まで高まる
- その状態では「楽しいからやる」という気持ちだけで行動が続く
例:スポーツ選手が「ゾーン」に入る、ゲームに夢中で気づいたら数時間経っていた、など。
フロー体験は、まさに内発的動機の最たる例です。

③認知評価理論|報酬がやる気を奪うアンダーマイニング効果
認知評価理論(Cognitive Evaluation Theory)は、心理学者デシが提唱した理論です。
この理論は、外からの報酬や評価が「自分で決めてやっている」という感覚(=自律性)を奪い、内発的動機を下げてしまう可能性があることを示しました。
たとえば…
- お金やご褒美があると「やらされている」と感じやすくなる
- その結果、行動そのものの楽しさや意味が薄れてしまう
このときに実際に起こる現象を、アンダーマイニング効果(Undermining Effect)と呼びます。
実験では「子どもにパズルをさせ、最初はお金を与えるとやる気が上がるが、報酬がなくなると以前より取り組まなくなる」という結果が確認されました。
つまり、
- 認知評価理論=外的報酬がやる気を奪う仕組みを説明する理論
- アンダーマイニング効果=その理論を裏付ける代表的な現象
という関係になります。
例:子どもに「お手伝いしたら100円あげる」と言うと、最初はやりますが、やがて「お金がないならやらない」となりやすいのです。

④自己効力感理論(バンデューラ)|「できる感覚」が意欲を高める
心理学者バンデューラが提唱した自己効力感理論(Self-Efficacy Theory)では、
「自分にはできそうだ」という感覚が行動意欲を大きく左右すると説明されています。
- 小さな成功体験を積み重ねると「自分にもできる」と感じる
- それが次の挑戦につながり、やる気が自然に続く
例:英単語を10個覚えられた → 自信がつく → さらに勉強を続けたくなる。

内発的動機に関連するその他の有名な理論
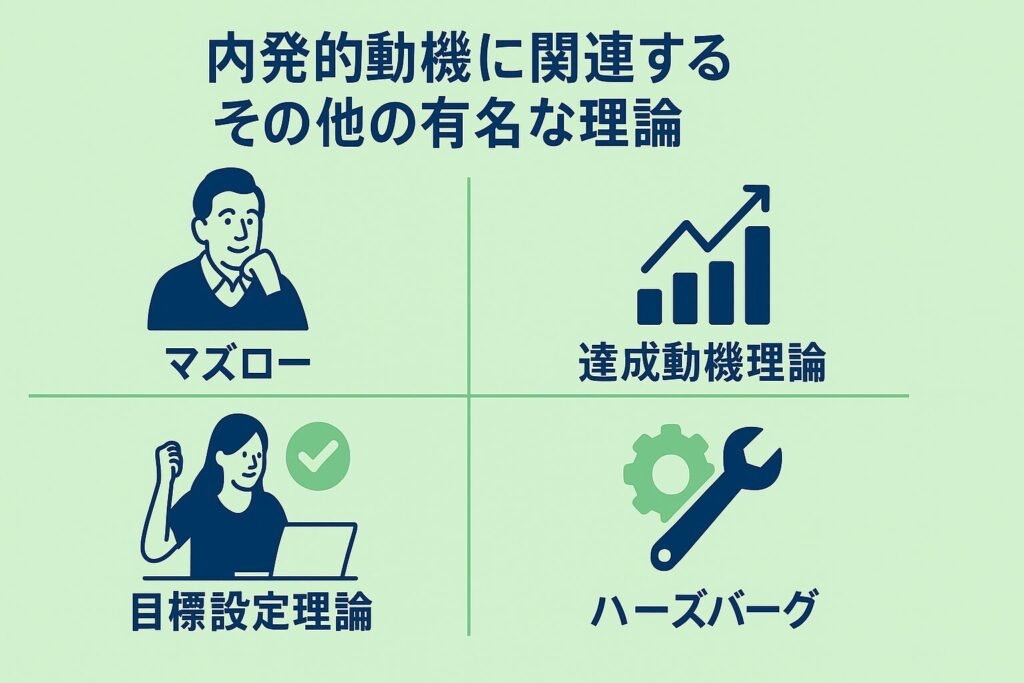
内発的動機を理解するためには、先ほど紹介した代表的なモデルに加えて、教育やビジネスの現場でもよく言及される理論を押さえておくと役立ちます。ここでは4つの有名な心理学理論を紹介します。
①マズローの欲求段階説と自己実現欲求
アメリカの心理学者マズローが提唱した欲求段階説は、人間の欲求を5段階のピラミッドで表したものです。
- 下から「生理的欲求 → 安全欲求 → 所属欲求 → 承認欲求 → 自己実現欲求」
- 最上位の自己実現欲求は「自分の可能性を発揮したい」という気持ちで、これは内発的動機と直結しています。
例:お金を稼ぐ(承認欲求)だけでなく、「本当にやりたい仕事に挑戦する」ことが内発的動機につながる。


②達成動機理論|挑戦への意欲と成功回避の心理
アトキンソンが提唱した達成動機理論は、人が行動する背景には次の2つの力があると説明しました。
- 成功したい欲求:挑戦して成果を得たい
- 失敗を避けたい欲求:恥をかいたり損をしたくない
このバランスによって人の動機は変わります。
内発的動機は「挑戦して成長したい」という欲求と特に深く関係しています。

③目標設定理論と「自分で決めた目標」の効果
ロックとレイサムが提唱した目標設定理論は、モチベーションにおいて「目標の質」が重要だと説きました。
- 具体的で、やや難しい目標のほうがやる気が高まる
- 特に「自分で決めた目標」は、外発的動機ではなく内発的動機を刺激する
例:上司に言われたからではなく「自分で立てた学習計画」だから頑張れる。

④ハーズバーグの動機づけ・衛生理論とやりがい
ハーズバーグは、仕事のやる気に影響する要因を「衛生要因」と「動機づけ要因」の2つに分けました。
- 衛生要因(給与・労働条件・人間関係など)
→ 整っていないと強い不満につながるが、整えたからといって大きなモチベーションの高まりには直結しにくい。
→ 例:給料が低すぎると不満だが、高くなっても「ずっとやる気が続く」とは限らない。
→ デスク環境を整えることは集中力や快適さを高める効果はあるが、それだけで長期的な意欲を生むわけではない。 - 動機づけ要因(やりがい・成長・達成感など)
→ 満たされると「もっとやりたい」という内発的動機が高まり、長期的なやる気につながる。
→ 例:自分のアイデアが認められた、スキルアップできた、目標を達成できた。
👉 つまり、衛生要因は「不満を減らす土台」になり、動機づけ要因が「やる気を持続させる原動力」になる、というのがこの理論のポイントです。

内発的動機を高める方法|日常やビジネスでの活用

ここまでで理論を学んできましたが、「実際にどう活かすのか?」が一番気になるところですよね。
内発的動機は誰にでも備わっているものですが、ちょっとした工夫でさらに高めることができます。ここでは教育・ビジネス・個人生活の3つの場面での実践方法を紹介します。
①教育の場での工夫(自主性を与える授業・選択肢の提示)
- 生徒に「どの課題からやる?」と選択肢を与えることで、自律性が満たされる
- 単なる暗記ではなく、探究型の学び(調べ学習・実験)を取り入れると好奇心が刺激される
- 成績やご褒美だけに頼らず、「学ぶこと自体が楽しい」という感覚を大切にする
例:自由研究で「自分の興味あるテーマを選ぶ」と、自然に夢中になりやすい。
②ビジネス現場での応用(裁量・やりがい・エンゲージメント)
- 裁量権を持たせる:やり方を自分で決められるとモチベーションが高まる
- フィードバックで有能感を高める:小さな成果でも「よくやったね」と認める
- チームとの関係性を強める:一体感が内発的動機を刺激する
例:Googleの「20%ルール」(勤務時間の一部を自由なプロジェクトに使える制度)から、Gmailなど新しいサービスが生まれた。
③個人ができる実践方法(小さな成功体験・好奇心を活かす)
- 小さな目標をクリアする → 自信がつき、「もっとやりたい」という気持ちが生まれる
- 好奇心に従って学ぶ → 「興味があるからやる」ことを優先する
- 習慣化する → やりたいことを日常のルーティンに組み込むと自然に続く
例:英単語を1000個覚えようとするより、毎日10個ずつ覚える方が「できた!」という達成感を感じやすく、内発的動機が持続する。
まとめ|内発的動機を理解すれば、やる気は自然に生まれる
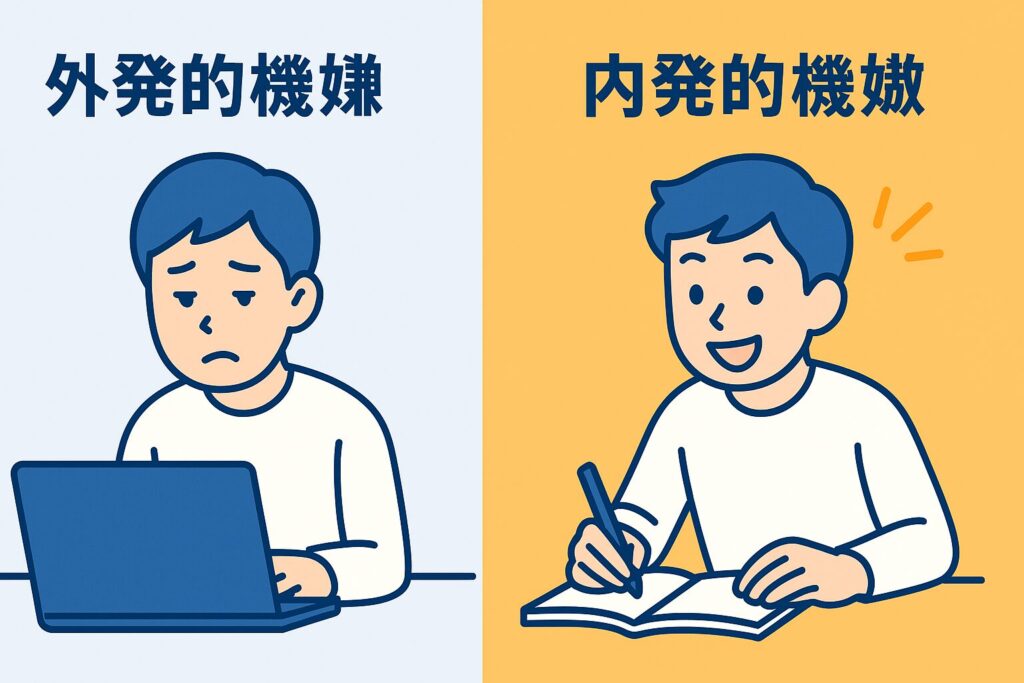
ここまで、内発的動機の基本から有名な心理学モデル、日常やビジネスでの活用法まで解説してきました。最後に大切なポイントを整理しておきましょう。
心理学モデルでやる気の仕組みを知る意義
- 自己決定理論・フロー理論・認知評価理論・自己効力感理論などを知ることで、「なぜやる気が出るのか」を理解できる。
- 理解することで、やる気を「外から与えられるもの」ではなく「自分の中から育てるもの」として捉えられる。
- 教育・仕事・趣味など、どんな場面でも活かせる知識になる。
「やりたいからやる」習慣づくりが人生を豊かにする
- 内発的動機は「楽しさ・好奇心・やりがい」から生まれる。
- ご褒美や罰に頼らず「やりたいからやる」習慣を作ると、自然に行動が続きやすい。
- それは結果的に、学び・仕事・人生の満足度を高めることにつながる。


