「どうして自分はこんな性格なんだろう?」
「人によって、同じ出来事でも感じ方や反応が違うのはなぜ?
こうした疑問を持ったことはありませんか?
実は私たちの性格は、ただ一言で「性格」と片付けられるものではなく、
気質・性格特性・価値観という三つの層が積み重なってできています。
この記事では、パーソナリティ心理学の階層モデルを解説し、
それぞれの層がどんな意味を持ち、どのように関係し合っているのかを詳しくお伝えします。
「性格は変えられるのか?」という疑問や、
年齢を重ねると性格が丸くなる理由も、きっとクリアになるはずです。
読み終わる頃には、自分や周りの人の性格を、より深く理解できるようになるでしょう。
パーソナリティ心理学とは?意味と基本の考え方

パーソナリティ心理学が扱うテーマとは
パーソナリティ心理学とは、簡単に言うと「人それぞれの性格や行動の違いを研究する学問」です。
たとえば同じ出来事が起きても──
- 「落ち込む人」
- 「すぐ立ち直る人」
- 「怒り出す人」
がいるのはなぜでしょう?
その違いを科学的に解き明かそうとするのが、パーソナリティ心理学です。
この分野が扱うテーマはとても広く、たとえば以下のようなものがあります:
- 性格の特徴(どんな傾向があるか)
- 性格の原因(遺伝か環境か)
- 性格と行動・健康の関係(性格がストレスにどう影響するか)
- 性格の変化(変えられるのか、年齢でどう変わるか)
つまり「人ってなぜそんなふうに考えるの?行動するの?」という日常の疑問に答えてくれる学問です。
性格研究の代表的な理論(ビッグファイブ・アイゼンクなど)
パーソナリティ心理学にはいくつもの有名な理論があります。中でもよく名前が出るのが以下の二つです:
ビッグファイブ理論
これは人間の性格を5つの因子で説明しようという考え方です。5つとは:
- 外向性(社交的か、人と関わるのが好きか)
- 協調性(人に優しいか、協力的か)
- 誠実性(きちんとしているか、責任感があるか)
- 情緒安定性(感情の浮き沈みが少ないか)
- 開放性(新しいことが好きか、好奇心旺盛か)
「人の性格を大まかに知りたい」というときに、とても役立つ理論です。

アイゼンクの性格次元論
もうひとつ有名なのがハンス・アイゼンクの理論です。
彼は性格を以下の三つの軸で説明しました:
- 外向性/内向性
- 神経症傾向(不安になりやすいか)
- 精神病傾向(攻撃性や衝動性の強さ)
例えば、外向的で神経症傾向が高い人は「社交的だけど落ち込みやすい」という傾向が出やすい、という具合に使われます。
なぜパーソナリティ心理学が注目されるのか
パーソナリティ心理学が注目される理由は、とても実用的だからです。
- 自己理解
「自分はどういう性格なのか」「なぜストレスに弱いのか」がわかると、気持ちが楽になる人が多いです。 - 他者理解
「あの人はなんであんな反応をするんだろう?」という疑問にもヒントをくれます。 - 人間関係や仕事に活かせる
たとえばビジネスの場で、人の性格に合わせた接し方を工夫できればトラブルが減ります。 - 心理的問題の解決
不安、抑うつ、ストレスなどメンタルヘルスの問題にも、パーソナリティ心理学の知識が役立ちます。
パーソナリティの階層モデルとは?三層構造をわかりやすく解説
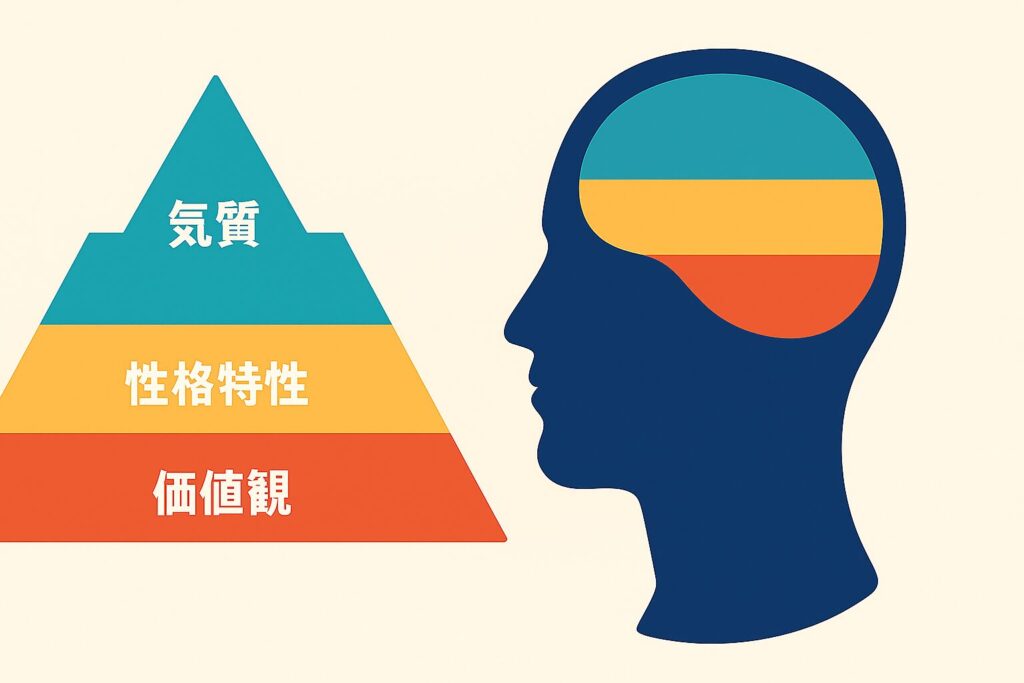
気質・性格特性・価値観とはそれぞれ何か
パーソナリティの階層モデルとは、性格を「層(レイヤー)」で捉える考え方です。
これは、人の性格を一枚岩のものではなく、いくつかの層が積み重なってできているとする理論です。
主に次の三層で説明されます:
① 気質(Temperament)
- 生まれつきの「反応の仕方」や「神経の敏感さ」など
- 赤ちゃんの頃から現れ、遺伝や脳の働きが関わる
- 例:
- 刺激に敏感ですぐ泣く赤ちゃん
- 活発で落ち着きがない子ども
気質は、人間でいえば性格の土台のようなものです。
② 性格特性(Traits)
- 気質に環境や経験が加わって作られる「行動の傾向」
- 「この人はいつもこうだな」と感じる特徴
- 例:
- 社交的
- 几帳面
- 内向的
ビッグファイブ理論などが、この層を説明しています。
③ 価値観・信念(Values / Beliefs)
- 「人は信じるべきか」「努力は報われるか」などの考え方や人生観
- 社会経験や教育、家庭環境で形成される
- 例:
- 「人間関係は大事にすべき」
- 「成功こそ人生の価値だ」
これは、行動や判断の「理由づけ」になる層で、最上位のレイヤーといえます。
どんな理論が階層モデルを支えているか(例:トレイト理論(特性論)、精神分析など)
階層モデルの考え方は、いくつかの心理学理論を土台にしています。
代表的なものを紹介します:
✅ トレイト理論(特性論)
- 人の性格は「特性(Trait)」の組み合わせでできているとする考え
- ビッグファイブ理論やキャッテルの16PFなどが有名
- 性格診断や心理テストでよく使われる
✅ 精神分析の構造論(フロイト)
- 人間の心を
- 本能(イド)
- 現実的判断(自我)
- 道徳や良心(超自我)
の三層構造で説明
この考え方も「人の心は多層構造でできている」という発想につながっています。

✅ アイゼンクの性格次元論
- 遺伝や脳の働きを重視
- 外向性、神経症傾向など「気質」と性格特性の関係を論じた
階層モデルで自分を理解するメリット
階層モデルを知ると、次のようなメリットがあります:
- 自分を客観的に見られる
「これは気質だから仕方ない」「これは価値観の問題だ」と切り分けて考えられる - 変えられる部分・変えにくい部分がわかる
- 気質は変えにくい
- 価値観や信念は変えやすい
- 性格特性は価値観を変えれば少しずつ変わる可能性あり
- 人間関係が楽になる
相手もまた気質・性格特性・価値観を持つ存在だと理解できると、衝突を避けやすい
例えば:
自分は人見知り → 気質が敏感で緊張しやすいから
↓
でも「人付き合いは悪いものじゃない」という価値観に変えれば、性格特性の行動も変わってくる
このように、自分の性格を分析しやすくなるのが階層モデルの魅力です。
気質とは?生まれつきの性格の土台を知る
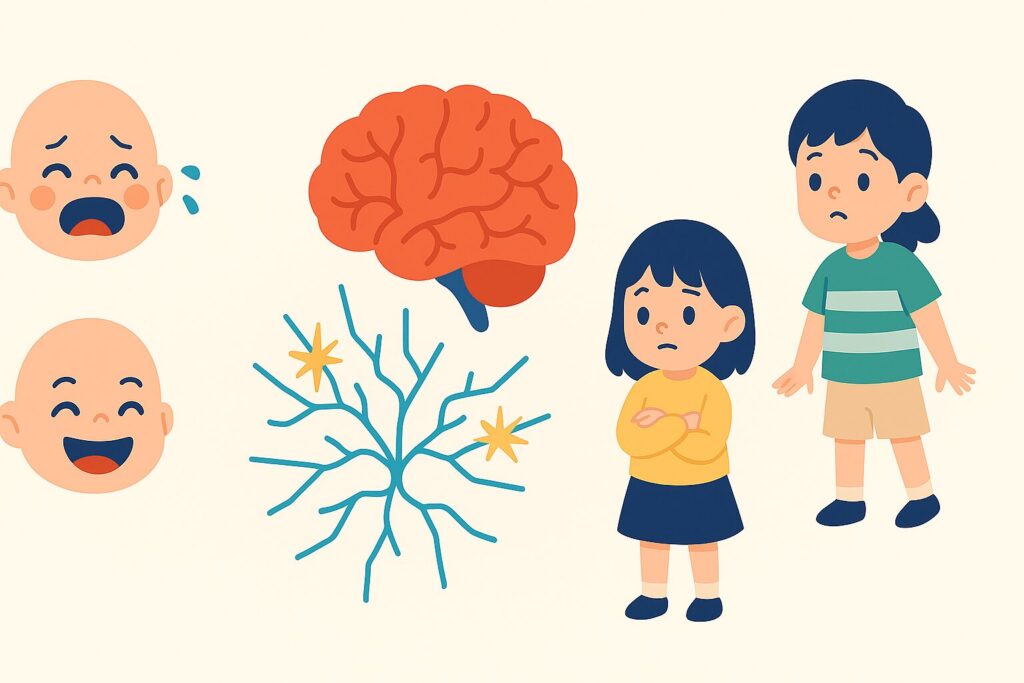
気質の特徴と代表的な例
気質(Temperament)とは、簡単に言うと「生まれつきの反応の仕方」のことです。
たとえば赤ちゃんを見ていると:
- すぐ泣く子
- 落ち着いて周りを見ている子
- 声や音にびっくりしやすい子
…など、同じ年齢でも反応がまるで違うことがありますよね。
このように、生まれたときから備わっている性質を気質と呼びます。
ポイントは以下のとおりです:
- 遺伝や脳の働きに強く影響される
- 人によって「刺激への敏感さ」「感情の強さ」が異なる
- 赤ちゃんの頃から観察できる
代表的な気質の例としては、次のようなものがあります:
- 刺激に敏感で音や光に驚きやすい
- 活動的でじっとしていられない
- 慎重で新しいことを怖がる
- 穏やかで感情の起伏が少ない
✅ トーマス&チェスの「気質の9つの特性」
心理学者トーマス&チェスは、子どもの気質を9つの特性で分類しています。
- 活動レベル(Activity Level)
→ 子どもの動きが活発か、おとなしいか
例:じっとしていられない vs. 落ち着いて座っていられる
- 規則性(Rhythmicity / Regularity)
→ 睡眠・食事・排泄など生活リズムが整っているかどうか
例:決まった時間に眠くなる vs. 不規則でバラバラ
- 接近・回避傾向(Approach / Withdrawal)
→ 新しい人・物・状況に積極的に近づくか、避けるか
例:初めての場でもすぐ遊ぶ vs. 慣れるまで時間がかかる
- 適応性(Adaptability)
→ 環境の変化にどれくらい早く慣れるか
例:引っ越し後すぐ友達を作る vs. 長く慣れない
- 反応の閾値(Threshold of Responsiveness)
→ 刺激にどれくらい敏感に反応するか
例:小さな音でも起きる vs. 大きな音でも平気
- 反応の強さ(Intensity of Reaction)
→ 喜怒哀楽など感情表現の強さ
例:大声で泣く・笑う vs. 表情が穏やかで静か
- 気分の質(Quality of Mood)
→ 機嫌が良いことが多いか、不機嫌がちか
例:いつもニコニコ vs. すぐ不機嫌になる
- 注意持続性(Attention Span)
→ 一つのことに集中していられる時間の長さ
例:絵本を長く読む vs. すぐ飽きる
- 気が散りやすさ(Distractibility)
→ 他の刺激で注意がそれやすいかどうか
例:周りの音で気が散る vs. 気にせず作業を続けられる
「これら9つの特性の組み合わせが、その子の『気質の個性』を形作ると説明されています。」
トーマス&チェスは、この特性をもとに子どもを「易しい子」「気難しい子」「ゆっくり型の子」などのタイプに分類する研究も行っています。
気質は変えられないのか?変わる可能性は?
ここで多くの人が気になるのが「気質は変えられるのか?」という点です。
✅ 結論から言うと:
- 気質そのものを劇的に変えるのは難しい
- しかし年齢や経験で、表に出る強さが和らぐことはある
例えば:
- 子どもの頃はとても恥ずかしがり屋(刺激に敏感)
- 大人になったら、経験を積んで「人前でも話せるようになった」
この場合、気質そのものが変わったわけではないけど、行動や見た目の反応が変わっただけなんです。
✅ なぜ気質は変わらないのか?
- 気質というのは、脳や神経系の「反応しやすさ」「敏感さ」など、生まれつきの体質的な部分です。
- 神経が敏感な人は、大人になっても基本的に刺激に強くはなりにくいんです。
つまり:
- 子どもの頃 → 人前で緊張しやすい、ドキドキする
- 大人になっても → 実は心臓はドキドキしている
✅ では、何が変わったのか?
変わったのは以下のような 「解釈」や「対処のスキル」 です。
例えば:
- 「緊張するのは悪いことじゃない」と考えられるようになった
- 人前で話す経験を重ねて「なんとかなる」と思えるようになった
- 緊張しても笑顔を作ったり、深呼吸できるようになった
だから、大人になると 同じ刺激(人前で話す)でも、心の中の解釈や行動の工夫によって、外から見た行動が変わる のです。
子どもの頃:
刺激に敏感 → 人前で赤面して何も話せない
大人:
刺激に敏感 → 内心はドキドキしてるけど、
- 「緊張しててもいいや」と思う
- 堂々と話すふりができる
- 終わってからすぐ立ち直れる
つまり:
- 気質は変わっていない(脳は刺激に敏感なまま)
- でも行動は変わる(対処法や考え方を身につけたから)
✅ 結論
- 大人になって行動が変わるのは、気質が変わったからではない
- 経験や考え方の変化で、行動を変えられるようになっただけ
- だから見た目は変わったように見えるけど、脳や神経の敏感さは残っている
この違いがわかると、自分を責めすぎずに「自分らしく対処する方法を探そう」という気持ちになれるのが、パーソナリティ心理学の素晴らしいところなんです!
「丸くなる」とは気質の変化なのか解釈の変化なのか
よく「歳をとると性格が丸くなる」と言われますよね。
これは、多くの場合、気質そのものが変わったわけではなく、解釈や対応の仕方が変わった結果です。
例えば:
- 若い頃は「失敗したら終わりだ」と思っていた人が
- 年齢を重ねて「失敗しても大丈夫」と思えるようになる
この変化は以下の要素が大きいです:
- 経験が増えて、同じ出来事にも慌てなくなる
- 人間関係で「他人も完璧じゃない」と思えるようになる
- 心の余裕が出てくる
つまり:
丸くなる = 気質が変わったのではなく、解釈や物事の受け止め方が変わったということ
まとめると:
- 気質は生まれつきで変わりにくい
- でも「どう捉えるか」「どう行動するか」は変えられる
- 丸くなるのは、解釈の変化の賜物!
性格特性とは?気質とどう違うのか
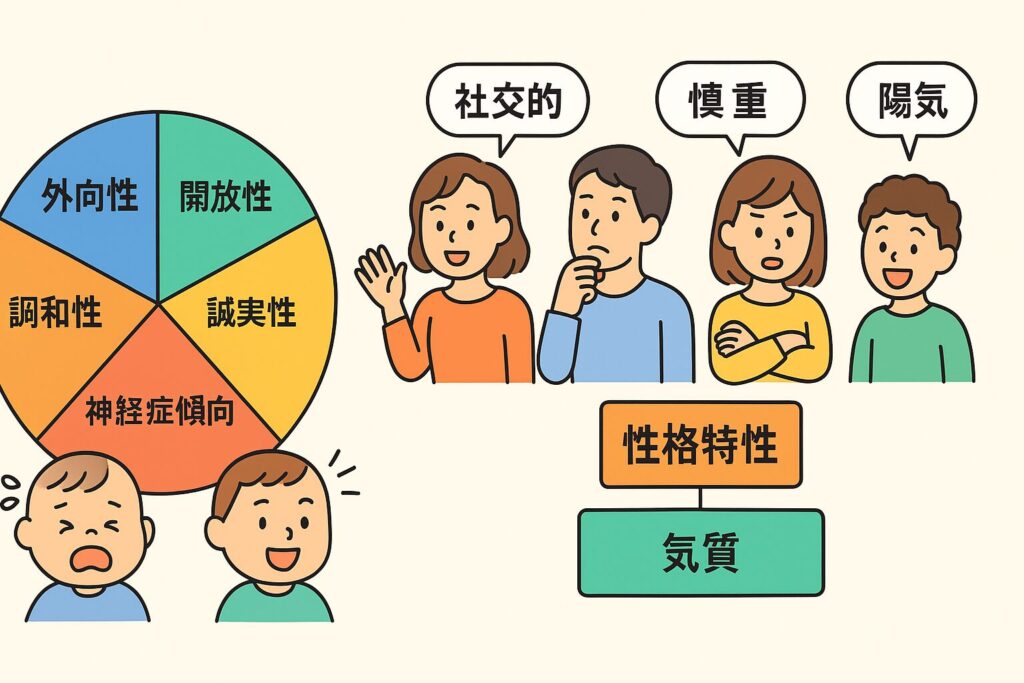
性格特性の定義と具体例(ビッグファイブなど)
性格特性(Traits)とは、簡単にいうと「その人らしい行動パターンや傾向」のことです。
例えば、こんなふうに言われることはありませんか?
- 「あの人は社交的だよね」
- 「几帳面で細かいところまで気がつく」
- 「落ち込みやすい性格かも」
これらはすべて、性格特性を表す言葉です。
つまり、「いつもこういう反応をする」という比較的安定した傾向を指します。
代表的な理論が、ビッグファイブ理論(Five Factor Model)です。
これは人の性格を5つの軸で説明します:
- 外向性(Extraversion)
社交的・活発・人といるのが好き - 協調性(Agreeableness)
思いやりがある・優しい・人と協力できる - 誠実性(Conscientiousness)
きちんとしている・責任感がある・計画的 - 情緒安定性(Neuroticism の低さ)
不安が少ない・感情が安定している - 開放性(Openness)
新しいことが好き・好奇心が強い・芸術的
例えば:
「私は外向性が高いけど、情緒安定性が低いかも」
という人は、社交的だけど感情の波が激しい傾向があるかもしれません。
ビッグファイブは性格診断や心理テストでもよく使われる、とても有名な理論です。
気質と性格特性の関係
ここでよく出てくる疑問が、「気質と性格特性ってどう違うの?」という点です。
簡単にまとめると:
- 気質 → 生まれつきの「反応の仕方」や神経系の特徴
- 例:刺激に敏感、慎重、活発
- 性格特性 → 気質に環境や経験が加わって作られる「行動の傾向」
- 例:社交的、几帳面、楽観的
つまり、性格特性は気質を土台にして育つもの。
例えば:
気質:刺激に敏感
↓
性格特性:人見知りしやすい
↓
価値観:人との距離は取った方が安心
こんなふうに、気質 → 性格特性 → 価値観 という順に積み重なっていくことが多いですが、実際には価値観が先に変わることで性格特性が変わるなど、影響し合うこともあります。
性格特性は変えられるのか?価値観との関連
ここで多くの人が知りたいのが、
「性格って変えられるの?」
という疑問ですよね。
✅ 結論としては:
- 気質は変わりにくい
- でも、性格特性は「価値観や信念」を変えることで変化する可能性がある
たとえば:
- 人見知りしやすい性格特性を持っている人が
- 「人と話すのも悪くない」と考えられるようになると
- 少しずつ人と接する行動が増える
もちろん、劇的に別人のようになるわけではありませんが、
- 「社交的になりたい」
- 「不安に振り回されない自分になりたい」
という目標に向かって行動を工夫することで、性格特性の出方を変えることは十分に可能です。
まとめると:
- 性格特性は気質より柔軟
- 価値観・信念を変えることで、行動の傾向が変わる可能性がある
- 自己理解を深めることで、より生きやすくなる
価値観・信念とは?性格特性とのつながり

価値観・信念の役割とは何か
価値観や信念とは、簡単に言うと「自分が大事だと思うこと」や「物事をどう見るか」という考え方です。
これは性格の中でも、特に人生観や行動の理由づけに深く関わる部分です。
例えば、以下のようなものが価値観・信念の例です:
- 「努力は必ず報われる」
- 「人を信じるべきだ」
- 「人付き合いはほどほどが一番」
- 「正直が何より大事」
- 「成功することが人生の価値だ」
こうした価値観や信念が、私たちの行動や選択に大きな影響を与えます。
例えば:
「人を信じるべき」という価値観が強い人は、人間関係で裏切られてもすぐには相手を疑わないかもしれません。
ポイント
- 気質や性格特性の上に築かれるもの
- 経験や環境によって大きく変わる可能性がある
- 自分の行動や生き方の「理由」になる
経験で価値観や信念はどう変わるか
価値観や信念は、生まれつきではなく、経験や環境の影響で形作られる部分です。
変わるきっかけは色々あります。例えば:
- 人間関係のトラブル
- 成功体験や失敗体験
- 読んだ本や映画
- カウンセリングや心理療法
- 人生の節目(進学、就職、結婚、離婚、病気など)
たとえば:
- 若い頃は「人に頼るのは弱いことだ」と思っていた人が
- 大きな病気を経験し、「人に助けを求めるのも大事だ」と価値観が変わる
また、心理療法の現場でも、信念の書き換えはとても重要なテーマです。
特に、認知行動療法(CBT)では
- 「本当にそうだろうか?」
- 「別の見方はないか?」
と、自分の信念を見直す練習を行います。

価値観を変えると性格特性は変わるのか?
ここがとても面白いポイントです。
✅ 結論
- 価値観を変えることで、性格特性の「出方」は変わる可能性がある
例えば:
- 気質:刺激に敏感で人見知りしやすい
- 性格特性:内向的で人付き合いを避ける
- 価値観:「人と関わるのは疲れるだけだ」
↓
もし価値観が
「人との交流も悪いことばかりじゃない」と変われば、
- 人付き合いを少しずつ試せるようになる
- 内向的でも「社交的な場面で頑張れる人」という印象に変わる
つまり、気質そのものは変わらなくても、
- 価値観や解釈が変わる → 行動が変わる → 周囲からの性格の印象が変わる
という流れが起こるのです。
まとめると:
- 価値観・信念は後天的で変わりやすい
- 経験や学びで価値観は変化する
- 価値観の変化は、性格特性の行動パターンに影響を与える
パーソナリティ心理学とABC理論のつながり
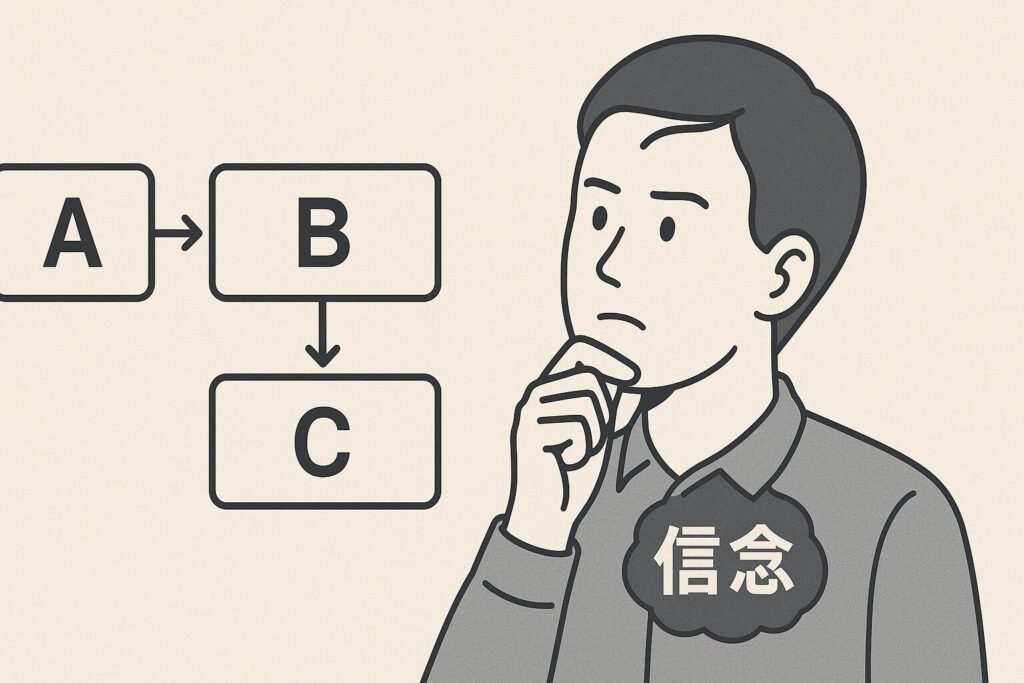
ABC理論とは何か?簡単に解説
パーソナリティ心理学を語るうえで欠かせないのが、ABC理論です。
これは、アメリカの心理学者アルバート・エリスが提唱した理論で、認知行動療法(CBT)の基本にもなっています。
ABC理論では、人がストレスを感じたり落ち込んだりするのは、出来事そのものが原因ではなく、その解釈(信念)が原因だと考えます。
具体的には次のような流れです:
- A(Activating Event)= 出来事
- 例:上司に注意された
- B(Belief)= 信念・考え方
- 例:「自分はダメな人間だ」「上司に嫌われたに違いない」
- C(Consequence)= 結果(感情や行動)
- 例:落ち込む、やる気が出ない、人を避ける
多くの人は
A(出来事)→ C(感情・行動)
だと思いがちですが、
実際は
A → B → C
という順番なんですね。
信念(B)が性格特性や感情に与える影響
ここでポイントになるのが、B(信念)の部分です。
人はそれぞれ、以下のような「思い込み」や「信念」を持っています:
- 「失敗したら人生終わりだ」
- 「人に嫌われたら生きていけない」
- 「努力しない人は価値がない」
こうした信念が強いと、出来事が起きたときに感情や行動が激しく反応しやすくなります。
例えば:
A:友達にLINEを無視された
B:「私は嫌われたに違いない」
C:落ち込む、引きこもる
もしBが変われば:
B:「忙しくて返事できないだけかも」
C:落ち込まずに過ごせる
ここで大事なのは、
- 気質が敏感な人 → ネガティブな信念を持ちやすい
- 信念がネガティブだと → 性格特性(不安が強い、避けがち)が強化される
という点です。
解釈を変えることで感情は変わるのか?
結論から言うと、解釈を変えれば感情は変わる可能性が高いです。
これがABC理論の大きな強みです。
たとえば:
- 「失敗は人生の終わりだ」という信念を
- 「失敗は学びのチャンスだ」と変える
こうした解釈の転換ができると、以下のように結果も変わります:
- 同じ失敗をしても、落ち込まずに次の行動ができる
- 人間関係のトラブルも「自分が全部悪いわけじゃない」と思える
- 不安が減り、自分に優しくなれる
ただし重要なのは、
- 気質が敏感だと、どうしてもネガティブな考えが浮かびやすい
- それでも「考え方を変える練習」を繰り返すことで、感情の波を穏やかにすることはできる
という点です。
まとめると:
- 出来事そのものより「解釈」が感情を決める
- 信念(B)を書き換えれば、性格特性の出方や感情も変わりうる
- 気質は変わりにくくても、解釈を変える工夫はできる

パーソナリティ心理学の「階層モデル」でいうと、
気質 → 性格特性 → 価値観・信念
この最上位にある「価値観・信念(B)」を変えることが、性格や感情をより生きやすくする大きなポイントなのです。
まとめ|パーソナリティ心理学を自己理解や生き方に活かす方法
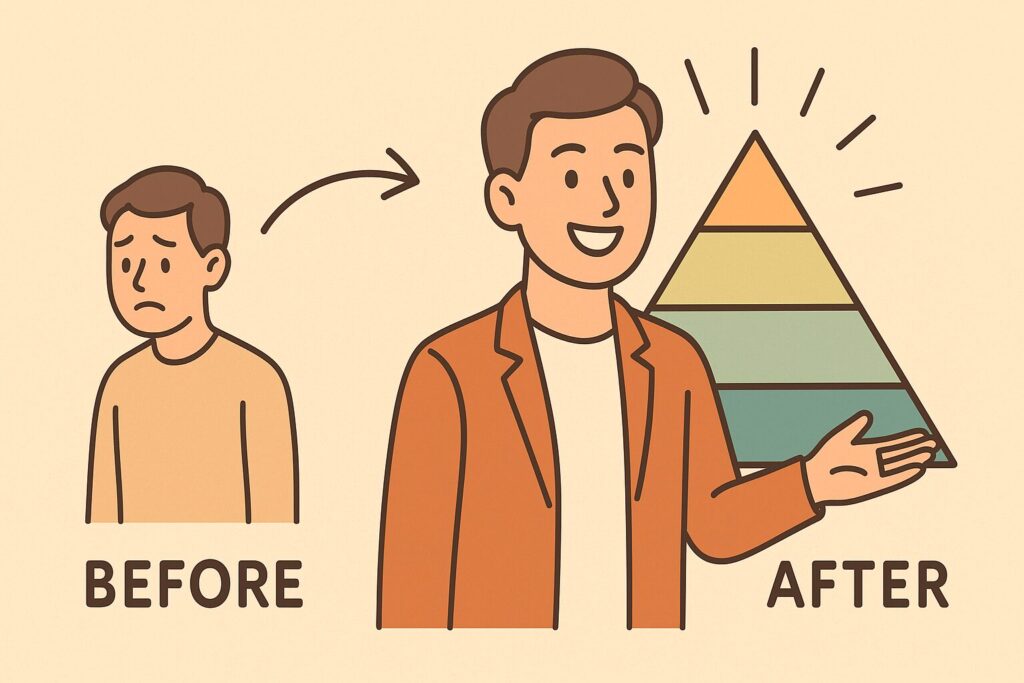
自分の気質を知るメリット
まず大事なのは、自分の気質を知ることです。
なぜかというと、気質は変えにくい「自分の土台」だからです。
自分の気質を理解していないと、こんなことが起きがちです:
- 「どうして自分ばかり疲れやすいんだろう」
- 「なぜ些細なことで落ち込むんだろう」
- 「みんな平気なのに、自分は不安ばかり感じる」
でも、自分の気質を知ると:
✅ 「これは生まれつきの反応だから仕方ない」と思える
✅ 必要以上に自分を責めなくなる
✅ 対処の工夫ができるようになる
例えば:
刺激に敏感な気質を持つ人なら
→ 静かな環境を作る
→ 予定を詰め込みすぎない
といった工夫ができます。
気質は「弱点」ではなく、個性や強みでもあるんです。
敏感な人は、人の気持ちに気づける繊細さも持っています。
まずは、自分がどんな傾向を持っているかを知ることが、自己理解の第一歩です。
性格特性を変えたいときにできること
次に気になるのが、
「性格を変えたいけど、どうしたらいいの?」
という疑問ですよね。
結論から言うと、性格特性は少しずつ変えられます。
その鍵になるのが、価値観や信念を見直すことです。
具体的なステップとしては:
① 自分の思い込みを言葉にする
- 例:「人に嫌われたら終わりだ」
② 本当にそうか問いかける
- 「嫌われたら人生終わりなのか?」
- 「過去に嫌われたけど、乗り越えたことはなかった?」
③ 別の考え方を探す
- 「嫌われることもあるけど、全員には好かれなくていい」
- 「大事にしてくれる人もいる」
④ 小さな行動を試す
- 苦手な場面で、いつもと少し違う行動をしてみる
- 例:無理に話しかけなくても、笑顔でうなずくだけ試してみる
自己理解を深めるための心理学的アプローチ
パーソナリティ心理学には、自己理解に役立つさまざまなツールや考え方があります。
おすすめのアプローチをいくつかご紹介します:
✅ 性格診断を活用する
- ビッグファイブ診断
- MBTI
- エニアグラム
診断結果を鵜呑みにするのではなく、自分の傾向を客観的に知るためのヒントにすると良いでしょう。
✅ ABC理論で自分の考え方を見直す
- 「私はなぜこんなに落ち込みやすいのか?」
- 「何を信じて、こう感じているのか?」
こう問いかけるだけでも、心の整理が進みます。
✅ 日記やメモに感情を書き出す
- 今日どんなことがあったか
- それをどう感じたか
- どんな考えが浮かんだか
書き出すことで、気質・性格特性・価値観のつながりが見えてきます。
✅ カウンセリングやコーチングを活用する
- 専門家と一緒に考えることで、自分一人では気づきにくい価値観に気づけることも。
自分の性格は一生変わらないものではありません。
気質という土台は残っていても、解釈や行動の幅を広げることで、より自分らしく生きやすくなるのがパーソナリティ心理学の素晴らしさです。
まとめると:
- 気質を知ると自己理解が進む
- 性格特性は小さな行動の変化で変わる可能性がある
- 心理学の知識を活かせば、より生きやすい自分になれる
今日から少しずつ、自分らしい生き方を見つけてみてくださいね。

