「つい感情的になって後悔する」
「なんだか同じ失敗を繰り返してしまう」
「人間関係でモヤモヤするけど原因が分からない」
そんな経験はありませんか?
それらの原因のひとつが、メタ認知の力が十分に働いていないことかもしれません。
この記事では、そもそもメタ認知とは何か、
そしてメタ認知が高い人と低い人の違い、鍛える方法まで、わかりやすく解説します。
メタ認知を知り、鍛えることで——
- 自分の感情に振り回されず冷静に行動できる
- 人間関係のトラブルを減らせる
- 自分らしく前向きに生きられる
そんな変化がきっと訪れます。
メタ認知とは?意味をわかりやすく解説
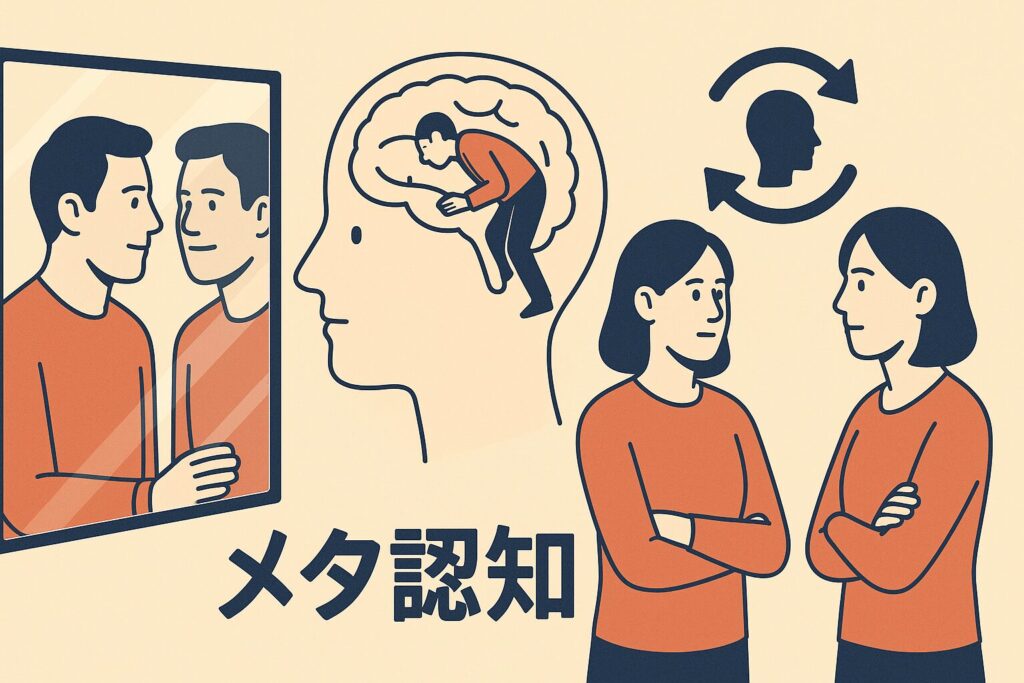
メタ認知の基本的な意味とは
メタ認知とは、簡単に言うと
「自分の考え方や感じ方を、一段高い場所から眺めているように意識する力」
のことを指します。
たとえば、あなたが勉強をしているとき、
- 「今のところちゃんと理解できてるかな?」
- 「なんだか集中できないな、どうしたんだろう」
と 自分の状態を自分で確認すること。これがまさにメタ認知です。
言い換えるなら、メタ認知は
- 「考えている自分を、さらに別の自分が見ている感覚」
- 「心の中に“もう一人の自分”を持つような感覚」
とも表現できます。
この力が高い人は、自分の間違いや思考の偏りに気づきやすく、修正もしやすいのが特徴です。
メタ認知は自分を客観視する力
メタ認知はよく 「自分を客観視する力」 と言われます。
たとえば——
- イライラしているときに「自分はいまイライラしている」と気づく
- ミスをしたときに「なんで失敗したのか考えてみよう」と振り返る
- 人間関係でトラブルが起きたときに「相手の立場ではどう感じるかな」と想像する
こうした行動はすべてメタ認知の働きです。
もしメタ認知が低いと、感情に飲まれたり、同じ失敗を繰り返しやすくなります。
逆にメタ認知が高いと、物事を冷静に見られ、自分の行動を柔軟に変えられます。
脳科学では「自我は幻想」という説とメタ認知の関係
ここで面白いのが、脳科学の世界では「自我は幻想」だという説があることです。
脳の研究によると、私たちが「自分」と呼ぶ存在は、実は脳の中でたくさんの情報をまとめあげた結果として作られた感覚にすぎないのでは?と言われています。
つまり、脳には「自我」という実体はなく——
- 見たこと
- 感じたこと
- 考えたこと
を統合する「お話の主人公」のようなものが 自分だと錯覚しているだけ という考え方です。
しかし興味深いのは、たとえ自我が幻想だったとしても、脳はしっかりとメタ認知の機能を持っています。
- 自分の思考や感情を観察する
- 自分の行動を振り返る
- 「今の自分、大丈夫かな?」と確認する
これらは脳内の情報処理としてきちんと行われているのです。
ですから、「自我がない」という話と、メタ認知が機能することは矛盾しないと言えます。
メタ認知が高い人・低い人の特徴とは?

メタ認知が高い人の特徴と行動パターン
メタ認知が高い人には、いくつか共通する特徴があります。例えば——
- 感情をうまく整理できる
- イライラしても「なぜ自分が怒っているのか」を考えられる
- 感情に流されにくい
- 自分の考えを振り返るクセがある
- 「今の自分のやり方でいいのか?」と常に問いかける
- 失敗しても次に活かせる
- 他人の立場に立って考えられる
- 「相手ならどう思うだろう」と想像できる
- コミュニケーションが円滑になりやすい
- 柔軟に考えを修正できる
- 固定観念にとらわれにくい
- 状況に合わせて行動を変えられる
たとえば、会議で意見を述べた後に
「今の説明、相手に伝わったかな?言い方を変えた方がよかったかも」
と考えられる人は、メタ認知が高い人の典型です。
メタ認知が低い人の特徴と困りごと
一方で、メタ認知が低い人は、自分の内面を客観的に見ることが苦手です。具体的には——
- 感情に飲み込まれやすい
- 怒りや不安で頭がいっぱいになる
- 気持ちを切り替えにくい
- 自分の行動を振り返らない
- 失敗の原因を考えず、同じことを繰り返す
- 「自分は正しい」と思い込みやすい
- 他人の立場に立つのが難しい
- 「自分がこう思うんだから相手もそう思うはず」と決めつけがち
- 思考の偏りに気づきにくい
- 物事を一方的にしか見られない
たとえば、仕事でうまくいかないときに
「全部周りが悪い」と決めつけ、自分の振る舞いを省みない人は、メタ認知が低い傾向があります。
メタ認知が低いと起きやすい問題(例:ダニング=クルーガー効果など)
メタ認知が低いと、いくつかの問題が起きやすくなります。その代表例が——
ダニング=クルーガー効果
これは心理学の有名な現象で、
「能力が低い人ほど、自分を過大評価しやすい」
というものです。
たとえば:
- テストの成績が悪いのに「自分は理解してる!」と思い込む
- 経験が少ないのに「自分なら簡単にできる」と過信する
これは、自分の理解度を客観視する力(メタ認知)が低いことが原因です。
このほかにも——
- ネガティブ思考が止まらない
- 人間関係でトラブルを起こしやすい
- 同じ失敗を繰り返す
など、さまざまな問題に繋がることがあります。
自分のメタ認知力をチェックするポイント
「自分のメタ認知って高いの?低いの?」と気になりますよね。
以下のポイントをチェックしてみましょう。
✅ 感情編
- 怒りや不安を感じたとき、「なぜこう感じているのか」と考えられるか?
- 落ち着いて気持ちを整理できるか?
✅ 思考編
- 自分の考えが偏っていないか疑うクセがあるか?
- 「本当にこのやり方でいいのかな?」と自問自答できるか?
✅ 行動編
- 失敗したとき、原因を分析し次に活かしているか?
- 他人の立場に立って物事を考えられるか?
一つでも「できていないかも」と思ったら、それはメタ認知を伸ばすチャンスです!
メタ認知は、生まれつきの能力だけではなく、後から鍛えられる力です。
メタ認知を鍛えるトレーニング方法

メタ認知トレーニングとは?意味と目的
メタ認知トレーニングとは、簡単に言うと——
「自分の思考や感情の動きを意識し、それを調整できるようになるための練習」
のことです。
たとえば、以下のような力を養うのが目的です:
- 自分の考えが偏っていないか気づく力
- 感情に飲み込まれず、冷静に行動する力
- 問題解決のために自分の考え方を修正する力
心理学や教育の分野では、メタ認知トレーニングは非常に注目されていて、うつ病や強迫性障害の治療プログラムにも応用されています。
日常でできる簡単なメタ認知トレーニング例
「トレーニング」と聞くと難しそうですが、実は日常生活で簡単にできる方法がたくさんあります。
以下はおすすめの方法です:
① 自分に問いかける習慣をつける
- 「今、どんな気持ちかな?」
- 「どうしてこう思ったんだろう?」
- 「別の見方はないかな?」
たとえばイライラしたときに
→「なんでイライラしてるんだろう?」と自分に聞くだけでも効果大です。
「ちなみに、こうしたメタ認知トレーニングをもっと手軽に続けたい方には、【Awarefy】
![]() もおすすめです。
もおすすめです。
Awarefyでは、感情を書き出す機能や、自分に問いかけるワークがアプリ上で簡単にできるので、反省ノートを書く習慣をつけたい人や、客観視の練習をしたい人にぴったりですよ。」
② 反省ノートを書く
- 今日の出来事を書き出す
- そのときの自分の気持ちや考えを書き添える
- 「別の対応ができたかな?」と振り返る
書くことで頭の中が整理され、客観視しやすくなります。
③ 人の立場を想像する練習
- 相手の目線で考えてみる
- 「もし自分が相手ならどう感じるか?」を想像する
人間関係でトラブルを減らすために非常に有効です。
書く習慣がメタ認知力を高める理由
書くことはメタ認知トレーニングの王道ともいえます。
理由は以下の通りです:
- 頭の中のモヤモヤを外に出すことで、自分の考えを客観的に見られる
- 書いたものを読み返すことで、思考のクセや感情の偏りに気づける
- 言葉にする過程で、自分の考えが整理される
たとえば——
- 日記を書く
- 感情を書き出す「感情ノート」
- 問題と解決策を書き出す
こうした習慣はメタ認知力アップにとても効果的です。
ビジネスや学習への活かし方
メタ認知はビジネスや学習の場面でも非常に役立ちます。
ビジネスでは——
- 会議で自分の発言を振り返る
- プレゼンで「相手に伝わっているか」を意識する
- ミスが起きたとき、冷静に原因を分析する
学習では——
- 「どこが理解できていないか」を自覚する
- 勉強法が合っているかを振り返る
- 試験中に焦りをコントロールする
特にビジネスパーソンや受験生にとって、自分を客観視して修正する力は武器になります。
メタ認知トレーニングの注意点や続けるコツ
最後に、メタ認知トレーニングを続ける上での注意点とコツをお伝えします。
✅ 完璧を目指さない
- 常に自分を分析しすぎると疲れてしまいます。
- 「気づけたらラッキー」くらいの気持ちでOKです。
✅ 小さな振り返りから始める
- 一日の終わりに「今日よかったこと」「改善したいこと」を書くだけでも立派なメタ認知です。
✅ 人に話してみる
- 書くことが苦手な人は、信頼できる人に話すだけでも効果的です。
- 話すことで自分の考えを整理できます。
✅ ポジティブな視点を忘れない
- メタ認知は「自分の悪いところ探し」ではありません。
- 良いところにも目を向け、自己肯定感を育てることが大切です。
メタ認知が注目される理由と活かし方

なぜ今、メタ認知が注目されているのか
ここ数年、メタ認知という言葉をよく耳にするようになりましたよね。
その理由は、とてもシンプルです。
「変化の多い現代社会を、自分らしく生き抜くために必要な力」
だからです。
例えば——
- SNSやネット情報があふれ、情報を取捨選択する力が求められている
- ストレス社会の中で、自分の感情をうまく整理する必要が高まっている
- AIや技術革新が進み、自分で考え判断する力が以前より重要になっている
こうした背景から、ビジネス界や教育界、心理学の分野でも
「メタ認知が大事だ!」という声が高まっているのです。
教育・ビジネス・メンタルヘルス分野での活用例
メタ認知はさまざまな分野で活用されています。以下の例を見てみましょう。
教育の現場での活用
- 勉強中に「どこが分かっていないか」を把握する力
- 自分に合った学習方法を選べるようになる
- テスト後に「どこでミスしたか」を振り返る習慣がつく
特に最近の学校教育では、「主体的・対話的で深い学び」が重視されており、
メタ認知は欠かせないスキルになっています。
「主体的・対話的で深い学び」というのは、文部科学省が最近の学習指導要領で掲げている教育方針です。簡単にいうと——
✅ 主体的 → 子どもが「自分で考え、自分から学ぼうとする」こと
✅ 対話的 → 友達や先生と「話し合い、考えを広げる」こと
✅ 深い学び → 知識をただ覚えるだけでなく、「なぜ?どうして?」を考え、自分の考えを深めること
ここで大事なのが、自分の理解度や考え方を振り返る力です。
例えば:
- 「今の説明、ちゃんと理解できたかな?」
- 「友達の意見と自分の意見、どこが違うんだろう?」
- 「別のやり方はないかな?」
こうした問いかけができるのは、まさにメタ認知の力なんです。
つまり、学校で「自分で考え、対話して、深く学ぶ」ためには——
自分の考えを客観的に見たり、整理したりするメタ認知が欠かせない
というわけです。
まとめると、この一文の意味は:
最近の学校では「自分で学びを深める力」が大事にされていて、
そのためには自分を振り返るメタ認知の力が必要不可欠だよ
ということです。
ビジネスでの活用
- 会議や商談で「相手の立場」で考える力
- 自分の意見が独りよがりになっていないか確認する
- プロジェクトの進行を冷静に分析し、修正する
例えば、リーダー職やマネジメントをする人ほど
「自分を俯瞰する力」 が仕事の質を左右します。
メンタルヘルスでの活用
- ネガティブ思考に気づき、切り替えられる
- 不安やストレスに飲み込まれにくくなる
- 自分の感情のパターンを把握して対策できる
最近では、うつ病や不安障害の治療法にもメタ認知を活かしたプログラムが開発されています。
自己理解や人生の質を高めるメタ認知の力
最終的に、メタ認知が一番役立つのは「自分を知ること」です。
- 「自分はどんな考え方のクセがあるのか」
- 「どんな場面でストレスを感じやすいか」
- 「何をしているときが一番自分らしいか」
こうしたことを知ることで、人生の質が大きく変わります。
たとえば——
- 感情に振り回されず、冷静に選択できるようになる
- 人間関係でのトラブルを減らせる
- 自分の強みや弱みを知り、より良い行動がとれる
さらに、メタ認知が高まると、人生において次のような力が身につきます:
- 問題解決力
- 柔軟な思考
- ストレス耐性
- 自己肯定感
つまり、メタ認知は「自分らしく生きるための土台」とも言えるのです。
これまでメタ認知というと「ちょっと難しい心理学の話かな?」と思われがちでしたが、
実は私たちの日常に深く関わっていて、誰にとっても必要な力なんですね。
まとめ:メタ認知を知り、人生に活かそう

今日から実践できるメタ認知のヒント
ここまで読んで、「メタ認知って大事そうだけど、難しそう…」と思った方もいるかもしれません。
でも、メタ認知は特別な才能ではなく、意識すれば誰でも少しずつ鍛えられる力です。
今日からできる簡単なヒントをまとめてみました!
✅ 感情に名前をつける
- イライラしているとき → 「私は今イライラしてるんだ」と心の中で言う
- 不安なとき → 「今、不安を感じてるな」とつぶやく
たったこれだけで、感情に飲まれにくくなります。
✅ 一歩引いて自分を眺めるイメージを持つ
- 「もし自分を第三者が見たら、どう思うだろう?」
- 「5年後の自分が今の自分を見たら、なんて声をかけるだろう?」
こうした問いかけは、自分を客観視する練習になります。
✅ 振り返りノートをつける
- 今日あった良かったこと
- うまくいかなかったこと
- 次はどうしたいか
書くことで、自分の思考や行動のパターンが見えてきます。
✅ 人の立場を想像する
- 相手の立場になって「どう感じるか」を考えてみる
- 会話やトラブルの場面で、特に効果的
人間関係のストレスを減らす大きなヒントになります。
記事全体の振り返り
最後に、この記事のポイントをまとめますね!
- メタ認知とは?
→ 自分の考えや感情を、一段上から客観的に見る力 - メタ認知が高い人の特徴
→ 感情を整理できる、振り返りが得意、柔軟に考えを修正できる - メタ認知が低い人の特徴
→ 感情に飲まれやすい、自分の偏りに気づきにくい - メタ認知を鍛える方法
→ 書く習慣、問いかけ、立場を変えて考えるなど - メタ認知の大切さ
→ 自己理解が深まり、人生の質が上がる
メタ認知は、人生をより良い方向に変えるための能力です。
特別な人だけの能力ではなく、誰でも少しずつ伸ばしていけます。
「自分を見つめる目」を育てることで、きっと——
- ストレスが減る
- 人間関係が楽になる
- 自分らしく行動できるようになる
そんな未来が待っています。
