「仕事の不満が減ったのに、なぜかやる気は戻らない…」
そんなことを考えたことはありませんか?
- 給料は悪くないのに、仕事が楽しくない
- 人間関係も問題ないのに、モチベが上がらない
- “不満”はないのに、“やる気ゼロ”のまま
こんなモヤモヤを感じている人は、実はとても多いんです。
その原因は、不満とやる気がまったく別の仕組みで動いているから。
この記事では、ハーズバーグの二要因理論(不満の原因とやる気の原因を分ける心理学)を使って、
「なぜ不満が消えてもやる気は出ないのか?」をわかりやすく解説します。
さらに、
- 不満とやる気を見分けるチェックリスト
- 仕事がつまらない理由の特定方法
- どうすればやる気が戻るのか
もまとめて紹介。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
仕事の不満とやる気はなぜ別物なのか
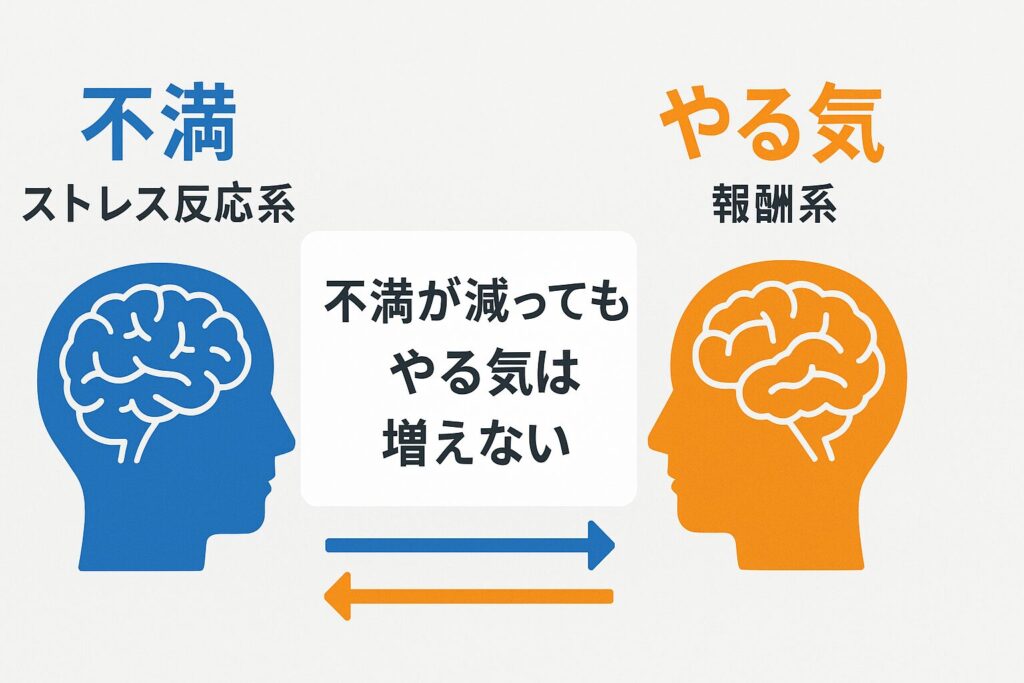
多くの人がまず抱く疑問は、
「不満が減れば、やる気も自然に上がるんじゃないの?」
というものです。
しかし、心理学的には “不満” と “やる気” はまったく別のメカニズム で動きます。
ここを理解しないと、職場の改善もキャリアの判断もズレ続けてしまいます。
この章では、次の4つのポイントから「不満とやる気が別物である理由」を、ゼロから分かるように解説します。
①ストレスが減ってもやる気が上がらない理由
まず押さえたいのは、
ストレスが減ること=やる気が増えること
ではないという点です。
脳はストレスと意欲を、別々の場所で処理しています。
- ストレス反応(不満)
→ 扁桃体やストレス系の回路が反応 - やる気(モチベーション)
→ 報酬系(ドーパミン)によって強化される
この2つは、電気のスイッチで言えば「別の回路」。
だから、
ストレスが減る=ストレス回路が静まるだけ
やる気が出る=報酬系が活性化する必要がある
つまり、
ストレスが消えても“やる気スイッチ”は押されないのです。
②「不満の解消=マイナスをゼロに戻す」仕組み
不満がある状態は、いわばマイナス(−)の状態。
- 上司が怖い
- 給料が低い
- 労働環境が悪い
- 人間関係が疲れる
これらが改善されると、確かに気持ちは楽になります。
しかし、それは 「マイナスがゼロに戻っただけ」 であり、
プラス(やる気)になるわけではありません。
例:エアコンの壊れた部屋で作業できない問題
- エアコン無し → 暑すぎて集中できない
- エアコンを修理 → 集中できるようになる
でも、冷房がついただけで
- 新しい仕事をしたくなる
- 夢中で働きたくなる
とはなりません。
エアコンは「不満消し」
やる気は「仕事そのものの意味」から出ます。
③やる気は「報酬系・内発的動機づけ」が動かないと増えない
やる気(モチベーション)が高まるときには、
次のような内発的動機づけが働いています。
- 成長できている実感
- 達成感
- 自分の意思で進められる裁量(自律性)
- 意味を感じる仕事
これらは “報酬系” を刺激するため、意欲が自然に湧いてきます。
不満の解消とは関係なく、
意欲は「プラスの刺激」で生まれるものなのです。
④不満が減ると“動きやすくなるだけ”という心理学的理由
ここまで読むと、
「でも不満が減れば、軽く動けるようになる気がする…」
と思った人もいるはずです。
これは正しいです。
しかし、それは やる気が増えたわけではありません。
不満がなくなると、
- 心が軽くなる
- 落ち着く
- 集中しやすくなる
- 行動のハードルが下がる
といった“ゼロ地点への回復”が起きるため、
あたかも「やる気が上がったように見える」だけ なのです。
つまり、
不満が減る=動ける環境が整った
やる気が出る=自分の内側から意欲が湧く
まとめ
- 不満とやる気は「別の脳システム」で処理される
- 不満の解消は“マイナスをゼロに戻す”だけ
- 本当のやる気は「達成感・成長・自律性」などの内発的動機づけから生まれる
- 不満が減ると動きやすくなるが、それはやる気が増えたわけではない
この理解こそ、ハーズバーグの二要因理論を学ぶ上で一番大事なポイントです。
ハーズバーグの二要因理論とは?|初心者向けに要点をシンプル解説
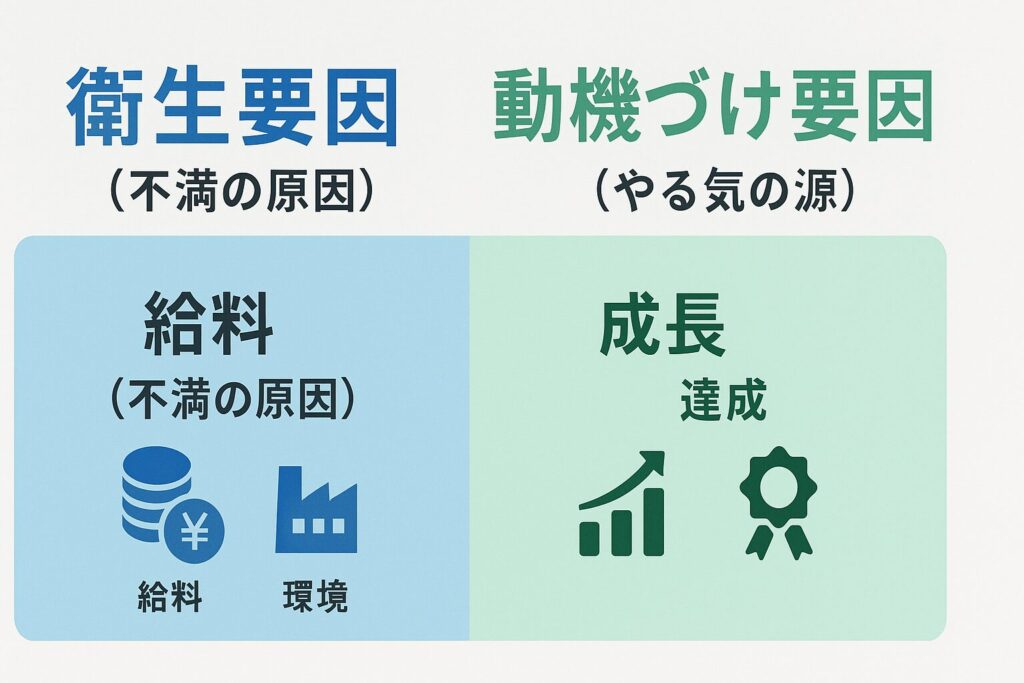
ここからは、この記事の中心テーマである
「ハーズバーグの二要因理論」を、初心者でも理解できる形で解説します。
二要因理論の核心はとてもシンプルで、
「仕事の満足(やる気)」と「仕事の不満」は、別々の要因で決まる
という考え方です。
人は「不満が減ったからやる気が増える」と思いがちですが、
ハーズバーグの研究では この2つが独立している と分かりました。
①衛生要因(不満を減らすもの)とは?
まず1つ目は 衛生要因(Hygiene Factors)。
これは “不満の原因になりやすい外的要因” を指します。
代表例はこちらです。
- 給料
- 労働時間・勤務環境
- 上司や同僚との関係
- 会社の方針やルール
- 安定性(雇用の安心感)
これらは、
欠けると強い不満になる
一方で、
整っても「やる気アップ」にはほとんど繋がらない
という特徴があります。

②動機づけ要因(やる気を生むもの)とは?
2つ目は 動機づけ要因(Motivators)。
こちらは “満足・やる気を生む内的要因” です。
代表例は、以下のような「内側の充足」です。
- 成長の実感
- 達成感
- 裁量・自律性
- 意味のある仕事
- 責任の拡大
- 認められる経験(承認)
これらがあると、仕事が一気に「プラス側」に振れます。

つまり、
- 衛生要因=不満を減らす
- 動機づけ要因=やる気が出る
この構造が二要因理論のポイントです。
なぜ2つの要因が“別の仕組み”なのか
ハーズバーグは200名以上の労働者に
「仕事で満足した経験」
「仕事で不満だった経験」
をインタビューしました。
すると、
- 満足→達成・成長・裁量など“内的な経験”が中心
- 不満→給料・上司・環境など“外的な条件”が中心
というように、
全く違うカテゴリの要因が出てきたことに驚いたのです。
そのため、
やる気と不満は同じ軸では語れない。
別々の要因で動く。
という結論に至りました。
この章のまとめ
- 二要因理論は「満足」と「不満」が別物という発見
- 衛生要因は、不満を防ぐための要因
- 動機づけ要因は、プラスのやる気を生む要因
- この2つは完全に独立した仕組みで働く
不満が減っても“やる気が出ない理由”を心理学で説明する
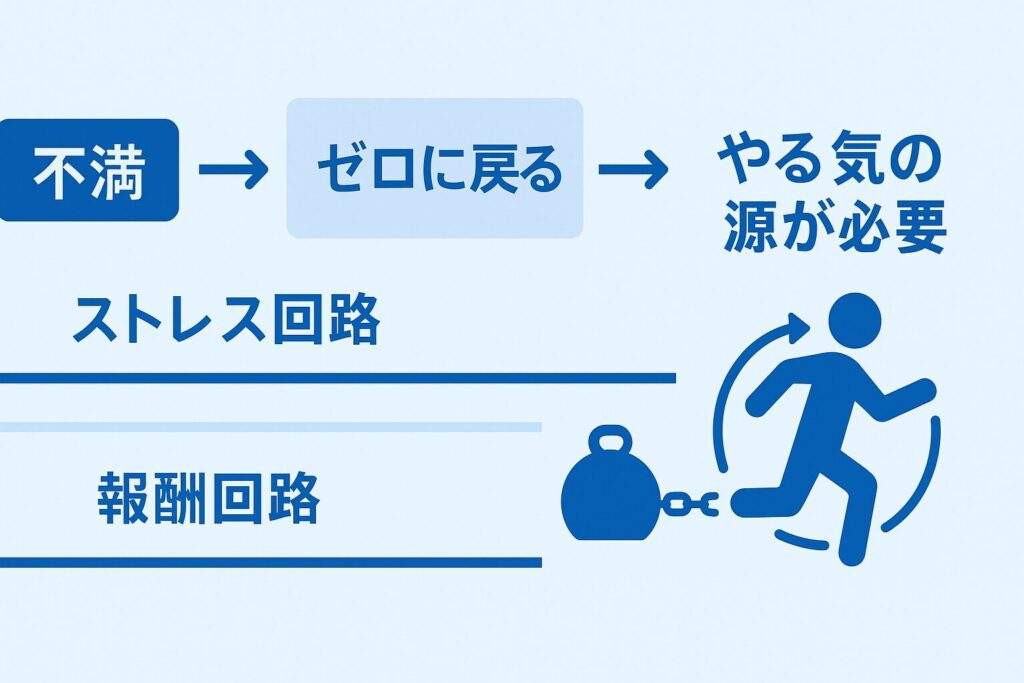
ここからは、
「不満が減ったのに、なぜやる気は出ないのか?」
という根本的な疑問を、心理学の仕組みに沿って解説します。
「二要因理論」の理解が一気に深まる重要なパートです。
不満と意欲は違う脳システム(ストレス反応系と報酬系)
まず最初に押さえておきたいのは、
不満(ストレス)とやる気(意欲)は、脳の別システムが司っている
という事実です。
- 不満・ストレス → 扁桃体・ストレス反応系
危険や脅威に反応して体を守るシステム - やる気・意欲 → 報酬系(ドーパミン)
達成・興味・成長に反応して意欲を高めるシステム
つまり、
ストレスが減る=ストレス回路が静まるだけ
やる気が出る=報酬回路が活性化する必要がある
2本のまったく別の線路で動いているので、
ストレスが弱まっても報酬系は自動では動きません。
衛生要因は「苦痛除去」カテゴリーに過ぎない
衛生要因(給料・環境・人間関係など)は、
心理学では “苦痛除去要因(negative reinforcement)” と呼ばれることがあります。
つまり、
- 苦痛(不満)が減る → 楽にはなる
- しかし意欲(プラス)は上がらない
という構造。
給料アップ・労働環境改善・残業減少などは、
「痛み止め」に近い働き方しかできません。
これはハーズバーグの主張だけでなく、
現代の「組織心理学」でも一致しています。
動機づけ要因は「意味・達成・成長」で決まる
やる気は プラス方向の刺激 がないと生まれません。
具体的には次の3つが強い影響を与えます。
① 成長(成長実感)
- できることが増えている
- 学びがある
- スキルが上がっている
人は“前に進めている感覚”に強く反応します。
② 達成(進捗・成果)
- タスクを終えた
- 目標に近づいた
- 自分の影響力を感じられる
これはドーパミンを強く刺激します。
③ 意味(Meaning)
- 自分がやっていることに価値を感じる
- 誰かに役に立つ
- 自分の選択で動いている感覚(自律性)
意味は、動機づけ要因の中心です。
つまり、
やる気=成長 × 達成 × 意味(+裁量)
これらが揃わない限り、不満がゼロになっても、
プラスの意欲は生まれません。
“やる気が増えたように見える錯覚”が生まれる理由
不満が消えると、
- 心が軽くなる
- 集中しやすくなる
- 行動しやすくなる
- 感情が安定する
こういった変化が起きます。
すると、人は
「前より動きやすい → やる気が出てきたかも?」
と錯覚しやすい。
しかし、実際には
- やる気が増えたのではなく
- “不満の重り”が外れて元の状態に戻っただけ
というケースがほとんどです。
まとめ
- 不満(ストレス)と意欲(やる気)は脳の別システム
- 衛生要因は「苦痛除去」であり、やる気の増加には直結しない
- 動機づけ要因(成長・達成・意味)がないと意欲は湧かない
- 不満が減ると動けるようになるが、それは“錯覚”であり本物のやる気ではない
衛生要因と動機づけ要因の違いを具体例で理解する
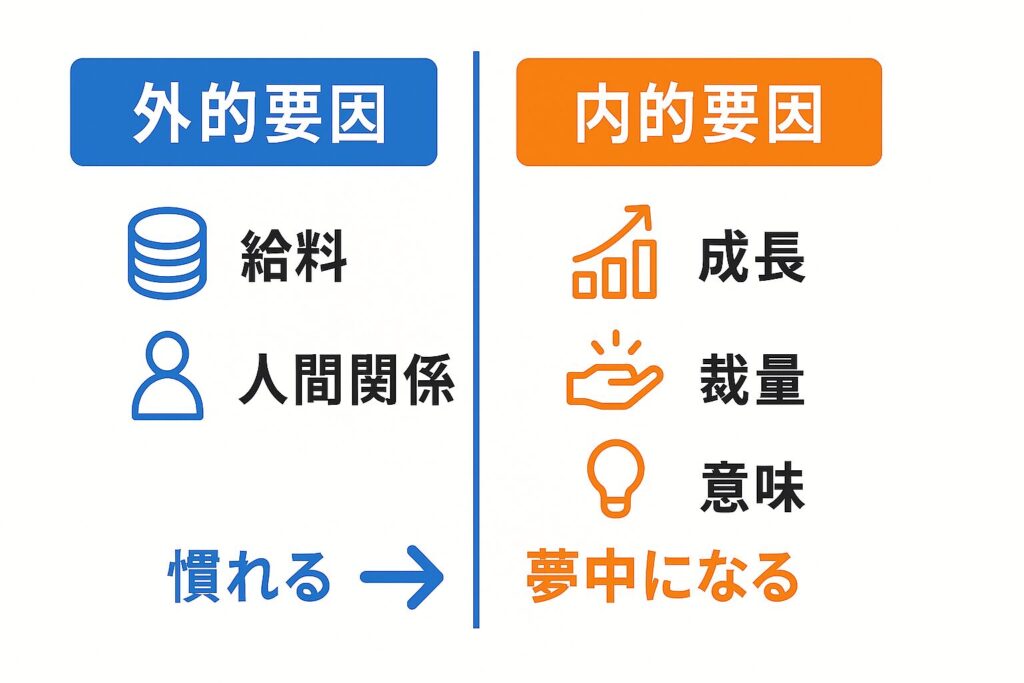
ここでは、
「衛生要因」と「動機づけ要因」の違いを“現実の仕事”でどう感じるのか?
を、具体的な例を使いながらわかりやすく解説します。
給料・環境・人間関係が整っても満足し続けない理由
「給料が上がればやる気が出る」
「人間関係がよければ働きやすい」
これは多くの人が信じていますが、実は すぐに慣れます。
心理学ではこれを “快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)” と呼びます。
給料が上がったり、良い環境が整うと、最初は嬉しいですが…
- 数週間で「当たり前」になる
- 不満は消えるが、やる気は持続しない
- 刺激として弱く、慣れが早い
だから衛生要因は、
不満予防の役割はあるけれど、満足を生み続ける力は弱いのです。
例えるなら、
「新しいスマホを買っても、1ヶ月で普通になる」のと同じ現象です。

達成感・裁量・成長機会があると人が夢中になる理由
一方で、動機づけ要因は “内側から湧き上がる満足” を生みます。
- 達成感 → 小さな成功体験でも意欲が上がる
- 裁量(自律性) → 自分で決められると集中力が上がる
- 成長機会 → スキルが伸びる実感があると、継続できる
これらは「報酬系」を刺激するため、
やる気が長期的に持続するという特徴があります。
ポイントは、
- 外から与えられたものではなく
- 自分の内側で感じる価値であり
- 人によって強烈に異なる
という点です。
やる気に最も影響する「自律性・成長・意味」の3要素
動機づけ要因の中でも、特に重要なのがこの3つ。
① 自律性(Autonomy)
- 自分の裁量で進められる
- “やらされている感”が弱まる
- 自分の選択だと意欲が上がる
② 成長(Competence)
- できることが増える
- 進歩が見える
- 小さな成功体験が積み重なる
③ 意味(Meaning)
- 仕事に意義を感じる
- 誰かの役に立っている実感
- 自分の価値観とつながる
現代の働き方(エンゲージメント)との関連
最近よく耳にする 「エンゲージメント(仕事への活力・熱意)」 も、
ほぼ動機づけ要因で決まります。
エンゲージメントが高い人の特徴は…
- 自律的に動いている
- 自分の仕事に意味を感じている
- スキルが活かせる・伸びている
- 認められている・感謝されている
これらは衛生要因とは違い、
本人の内側の状態が整っているからこそ生まれるものです。
だから、企業がエンゲージメントを高めようとすると
「給料アップ」「設備投資」だけでは限界があるのです。
まとめ
- 衛生要因は慣れが早く、満足はすぐ“ゼロ”にもどる
- 動機づけ要因は内側の価値から生まれるので、長期的に満足が続く
- やる気に必要なのは「自律性・成長・意味」の3つ
- エンゲージメントは動機づけ要因の高さで決まる
仕事が楽しくない理由を特定する方法|二要因理論を使った自己分析

ここでは、
「自分はなぜ仕事が楽しくないのか?」
その原因を、ハーズバーグの二要因理論を使って“正確に切り分ける”方法を解説します。
実は多くの人が、
「不満の原因」と「やる気の原因」を混同してしまうため、
改善の方向性がズレてしまいます。
ここで一度、自分の状況を客観的に整理してみましょう。
「不満の原因」と「やる気の原因」を切り分ける
まず、大前提として──
- 不満の原因=衛生要因(外的要因)
- やる気の原因=動機づけ要因(内的要因)
この2つは 別のカテゴリ です。
混乱してしまう理由は、
「不満が大きいと何もできないため、やる気があるように見えない」
からです。
しかし実際には、
- 不満が減る → ゼロに戻る
- やる気が出る → プラスへ進む
というように、方向がまったく違います。
そのため、
まず「どちらが原因か?」を特定することが最優先 です。
自分がどの要因でつまずいているか判断するチェックリスト
以下のリストで、
あなたの不満/やる気のどちらが問題なのか
を確認できます。
衛生要因(不満)のチェック
- 給料が低いと感じる
- 上司・同僚との関係がストレス
- 評価が不透明で納得できない
- 残業が多くワークライフバランスが悪い
- 会社や事業の将来性に不安がある
- 職場の空気が悪い、心理的安全性が低い
1つでも強く当てはまる →「不満」が主原因
動機づけ要因(やる気)のチェック
- 最近、成長している実感がない
- 達成感が得られない
- 裁量がなく“やらされている感”が強い
- 仕事に意味を感じられない
- 自分の強みが活かされていない
- 貢献実感や承認が少ない
複数当てはまる →「やる気不足」が主原因
両方当てはまる場合
どちらも該当する場合は、次の順番で改善が必要です。
- 衛生要因(不満)の改善
- 動機づけ要因(やる気)の向上
なぜなら、
不満が強い環境では、動機づけ要因が働かないからです。
(痛みが強い状態で、やる気どころではないのと同じ)
衛生要因が悪いのか、動機づけ要因が足りないのか?
判断の目安は、次のとおりです。
【衛生要因が原因の人】
- 職場に行くのが重い
- 毎朝の通勤で気分が沈む
- 会社の仕組み・人間関係のストレスが大きい
- 仕事そのものへの興味はあるが、環境がつらい
→ 環境改善・部署異動・転職検討が効果的。
【動機づけ要因が原因の人】
- “頑張っているのに満たされない”
- 仕事はできるのに楽しくない
- 価値を感じられない
- 自己成長が止まっている
- ルーティンばかりで刺激がない
→ 役割拡大・学習・裁量を増やす工夫が有効。
転職すべきか/続けるべきかの判断基準として使う方法
二要因理論は、転職判断にも非常に役立ちます。
転職を検討したほうがいいケース(衛生要因が深刻)
- 人間関係が壊滅的
- パワハラ・過剰なストレス環境
- 経営が不安定
- 勤務条件が改善されない
- 健康が損なわれるレベルの負荷
これらは個人の努力で改善がほぼ不可能です。
環境を変えるほうが合理的。
今の職場で改善できるケース(動機づけ要因が不足)
- 成長できていない
- やりがいが感じられない
- 裁量がない
- 単調な仕事で飽きている
これらは 仕事の進め方の工夫 や
上司とのコミュニケーションで改善できる可能性があります。
例えば…
- 新しいプロジェクトに手を挙げる
- “役割を増やす”提案をする
- 業務の意味づけを変える(ジョブ・クラフティング)
- 自分の強みを活かせる領域にシフトする
など。
二要因理論で判断すると迷いが減る理由
- 「不満」と「やる気」が別物だと理解すると、
どこを変えるべきか明確になる - 単純に「転職すべき/すべきでない」ではなく、
“何を変えれば、状況が改善するのか” が見えてくる - 迷いの正体が言語化され、決断がしやすくなる
まとめ
- 不満(衛生要因)とやる気(動機づけ要因)は混同しやすい
- チェックリストで原因を切り分けると改善の方向が明確になる
- 衛生要因は“環境の問題”なので、改善が難しければ転職も選択肢
- 動機づけ要因は“仕事の中身”なので、工夫によって改善できる
- 二要因理論を使うと「迷いの正体」が可視化される
マネジメントで使える二要因理論|部下のやる気を上げたい人向け
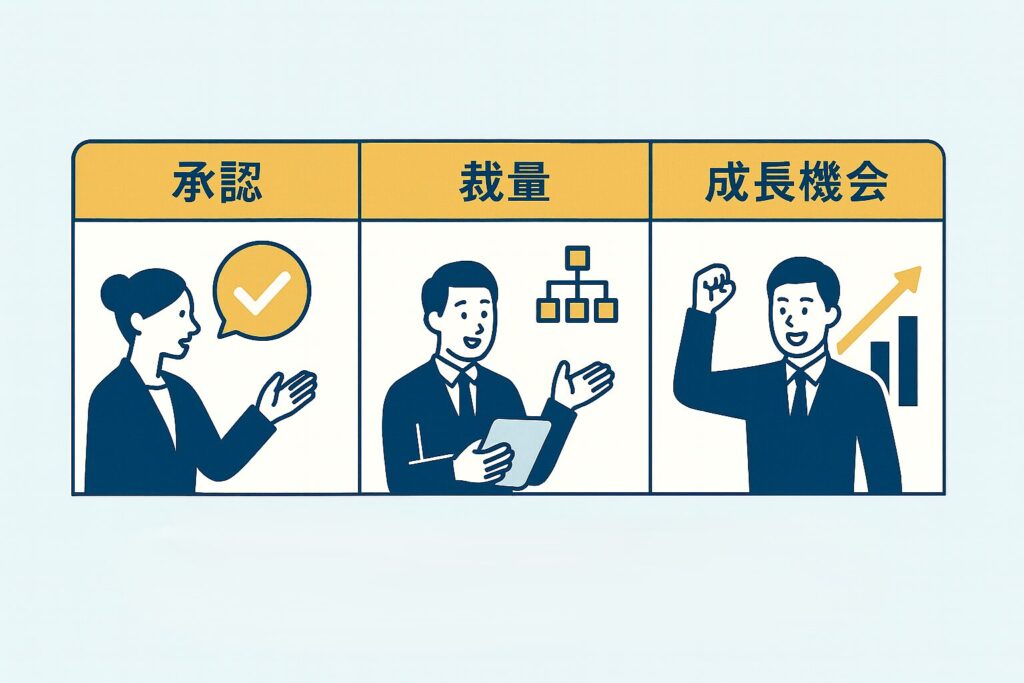
ここからは、
管理職・リーダー・人事担当者が「部下のやる気」を正しく引き出すための実践パート です。
二要因理論は「個人の自己分析」だけでなく、
組織・チームのマネジメントにも非常に強力に使えます。
衛生要因ばかり改善しても部下は動かない理由
多くのマネジメントが陥るのが、
- 給料を上げる
- 福利厚生を整える
- 労働時間を改善する
- オフィス環境を良くする
といった 衛生要因ばかり手を打つこと です。
もちろん、これらは重要です。
しかし、決定的に欠点があります。
衛生要因は“不満は減るが、やる気は増えない”
部下はこう感じてしまいます。
- 「よかった、やっと普通になった」
- 「ストレスは減ったけど、別に仕事が楽しいわけではない」
- 「改善されたのはありがたいけど、それ以上ではない」
つまり、
環境改善 → 不満がなくなるだけ
やる気が出るわけではない
です。
衛生要因は、
“マイナスをゼロに戻す施策” であり、
ゼロからプラスに押し上げる力はありません。
やる気を高めるために必要な“動機づけの設計”
部下の意欲を本気で引き出したいなら、
次の3つを意識した 動機づけ設計 が必要です。
① 自律性を高める(裁量)
- 自分で考えて動ける範囲を広げる
- やり方を任せる
- 「どうしたい?」と問いかける
- 過干渉を避ける
自律性はやる気の“エンジン”です。
② 成長を感じさせる(有能感)
- 小さな成功体験を積ませる
- 難度のちょうどよい仕事を任せる
- フィードバックを丁寧に伝える
- 強みを活かせる役割を与える
「できるようになった」という感覚は、
意欲を爆発的に高めます。
③ 仕事の意味を伝える(意義づけ)
- 仕事が誰の役に立つか説明する
- 目的や背景を共有する
- チームや会社への貢献を可視化する
- 自分の価値観と仕事を結びつける
「意味」を感じた瞬間、
人は自発的に動くようになります。
承認・裁量・成長機会をどう設定するか
動機づけ要因は、
企業側が“環境として設計できる要素” でもあります。
その実践例は以下の通り。
承認(認める)
- 毎週1回、進捗や成果のフィードバック
- 小さな努力を言語化して褒める
- 感謝を言葉で伝える
- 「見ているよ」という存在感を示す
承認はもっともコストが低く、
もっとも効果が高い動機づけ要因とも言われます。
裁量(任せる)
- 役割分担に“自由度”を持たせる
- 判断基準だけ共有し、方法は任せる
- 自己管理型のタスクに切り替える
- 権限移譲の範囲を少しずつ広げる
裁量は 「やらされ感」を激減 させます。
成長機会(伸ばす)
- 新プロジェクトへの参加
- チャレンジできる仕事を割り当てる
- 外部研修・学習機会の提供
- スキルアップ計画を一緒に作る
成長実感は、長期的なモチベーションの核です。
よくある失敗パターン:給料“だけ”上げても長期的なやる気は生まれにくい
多くの会社が、
「やる気がない → 給料を上げよう」
という短絡的なアプローチに陥ります。
しかし、二要因理論では「給料は衛生要因」と考えられています。
給料アップで起こること
- 数ヶ月で慣れる(快楽適応)
- 不満は減る
- しかし仕事の楽しさは変わらない
- 本質的なやる気は出ない
だから、
“給料=やる気” という方程式は成立しない
とされています。
給料アップは“直接”のやる気にはなりにくいが、 “背景にある評価”が成長や達成感を生むことはある
給料そのものは外的な報酬なので、長期的なモチベーションにはつながりにくいとされています。
ただし、給料が上がるプロセスの中で
- 成果が認められた
- 努力が評価された
- 役割や裁量が増えた
と感じられる場合、その“意味”や“成長実感”がやる気につながることがあります。
つまり、
お金そのものより「昇給の理由」がモチベーションを生む
というのが二要因理論の本質です。
まとめ
- 環境改善(衛生要因)は必要だが、やる気は上がらない
- 部下を動かすのは「動機づけ要因(自律性・成長・意味)」
- 承認・裁量・成長機会の設計がカギ
- 給料アップだけではモチベーションは持続しない
- 二要因理論は「やる気の設計図」
二要因理論の限界と最新モデルとの比較(JD-Rモデル・自己決定理論)
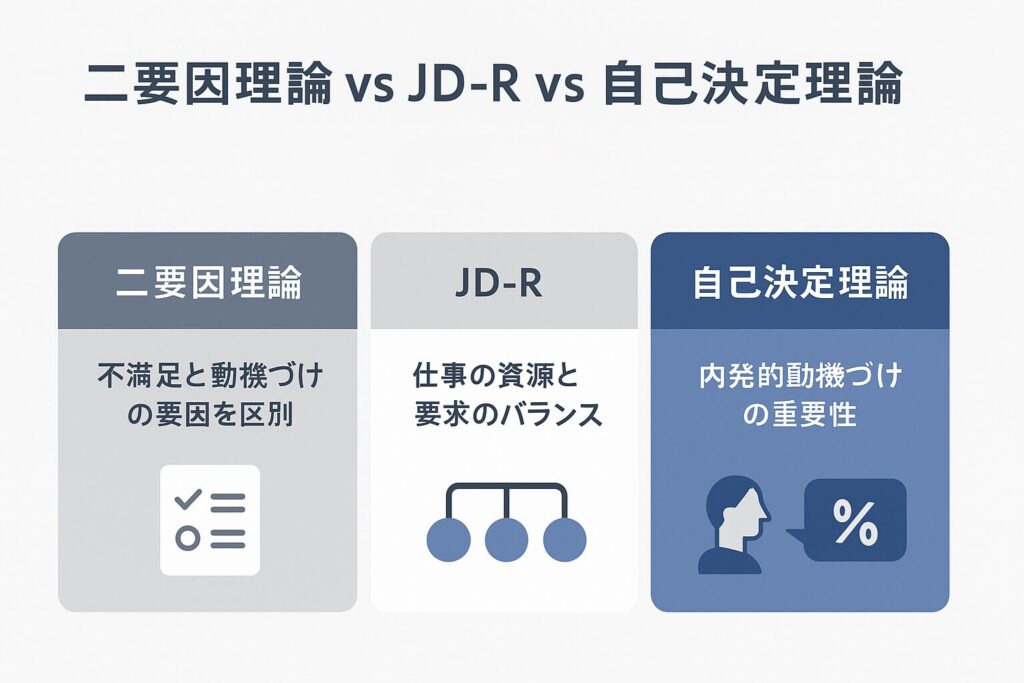
この章では、
「二要因理論は便利だけど万能ではない」
という視点を押さえつつ、
- どんな限界があるのか
- その弱点をどう補えばよいのか
- 最新の心理学モデルとどう組み合わせるべきか
をわかりやすく解説します。
専門性が高い内容ですが、
初心者にも理解できるようにかみ砕いて説明します。
二要因理論の「職務内容に偏っている」問題
ハーズバーグの二要因理論が批判される代表的な理由は、
「仕事の中身だけに焦点が当たりすぎている」 点です。
具体的には、
- 仕事の設計(タスク内容)
- 達成・承認・責任などの内部要素
- 職場環境や政策などの外部要素
といった“職務特性中心”の世界観で作られています。
しかし現代の働き方では、
- 働き方(リモート、柔軟性)
- 会社の価値観・文化
- チームの心理的安全性
- 個人のキャリア志向
- ワークライフバランス
といった “組織文化・働き方・心理面” がより重要です。
JD-Rモデルで見る“資源”と“ストレス”の関係
二要因理論の弱点を補うのが、
近年の組織心理学で最も重要なモデル JD-Rモデル(Job Demands–Resources)です。
JD-Rモデルの考え方(超シンプル版)
仕事は次の2つで決まる。
- 要求(Demands)…負荷・ストレスの源
- 資源(Resources)…支え・活力の源
そして、
資源が多いほど、ストレスに強くなり、仕事への活力(ワークエンゲージメント)が高まる
という理論です。
ここで重要なのは、
「資源」は環境だけでなく、個人の特性も含む
という点。
- スキル
- 自己効力感(できる感)
- 上司の支援
- チームの心理的安全性
- 意味や価値の理解
これらはすべて“資源”。
つまり、二要因理論よりもずっと広い視点で職場を捉えられます。
自己決定理論(自律性・有能感・関係性)との違い
やる気の本質を知りたい場合、
最も精度の高い理論が 自己決定理論(SDT) です。
自己決定理論は、
人間が本来持つ“自発的に動く力”を解明した理論で、
世界の学術界で最も引用されています。
やる気の3大要素はこれ。
① 自律性(Autonomy)
自分で選べている感覚。
② 有能感(Competence)
できる感・成長している感。
③ 関係性(Relatedness)
つながり・信頼感。

二要因理論との違い
- 二要因=「職務内容 × 環境」
- SDT=「人間の内側の欲求」
視点がまったく違います。
しかし、
“動機づけ要因=自律性・成長(有能感)・意味(関係性の一部)”
と見ると、両者は驚くほど一致しています。
それでも二要因理論が今も使われ続ける理由
1950年代の古い理論なのに、
なぜ今も企業や人事が使い続けるのか?
理由はシンプルです。
1. “不満”と“やる気”を分けて考える枠組みが圧倒的にわかりやすい
- 不満=衛生要因
- やる気=動機づけ要因
この分け方は直感的で、仕事の整理に強い。
2. 実務ですぐ使える
- 部下が動かない原因
- 仕事がつまらない理由
- 離職のメカニズム
- 給料の効果の限界
こうした“現場の悩み”を簡単に説明できる。
3. 他のモデルと組み合わせると効果的
- 不満が強い → 衛生要因(環境改善)
- やる気が低い → SDT(自律性・成長・関係性)
- 疲れている → JD-R(資源不足)
このように、
複数モデルを統合すると“仕事の心理学”が一気にクリアになります。
まとめ
- 二要因理論は「職務内容中心」で現代の働き方には一部限界がある
- JD-Rモデルは“資源の多さ”が活力を決めるという最新視点
- 自己決定理論はやる気の3要素(自律性・成長・関係性)を示す最強理論
- 二要因理論は「不満とやる気を切り分ける道具」として今も超有用
まとめ|不満を減らすだけではやる気は上がらない理由
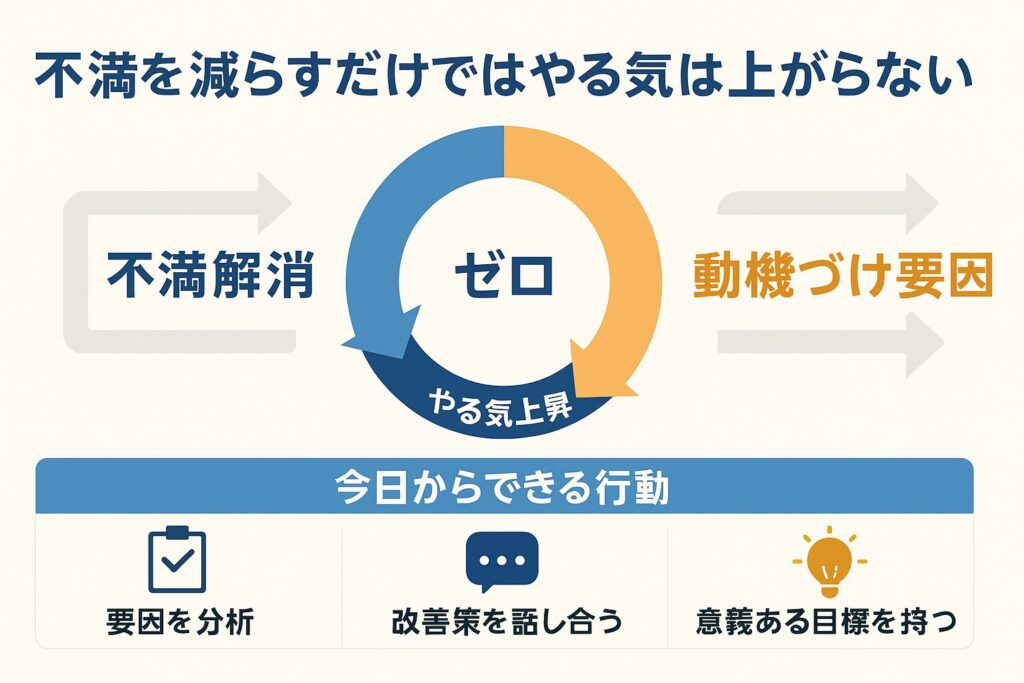
この記事の最後に、
「仕事の不満」と「やる気」がなぜ別物なのか?
そして、どうすれば仕事が楽しくなるのかを、
もう一度シンプルに整理して締めくくります。
不満解消はスタートラインにすぎない
まず押さえておくべき本質はこれ。
不満がゼロになっても、やる気は自動的には増えない。
これは心理学的に見ると明確で、
- 不満 → ストレス反応系が関係
- やる気 → 報酬系(ドーパミン系)が関係
というように、
まったく別の“脳の回路”が働いているからです。
衛生要因(給料・環境など)を整えるのは大切ですが、
それはあくまでも マイナスをゼロに戻す作業。
ゼロ地点に立っただけで、
まだプラスのやる気は生まれていません。
やる気を上げるのは「動機づけ要因」だけ
仕事を楽しいと感じたり、夢中になったりするのは、
衛生要因では生まれません。
鍵を握るのは 動機づけ要因 です。
動機づけ要因の中心はこの3つ
- 自律性(自分で選べる感)
- 成長(できるようになっている実感)
- 意味(価値や目的を感じること)
これらは「報酬系」を刺激し、
本物のやる気(内発的動機づけ)を生みます。
逆に言えば、
この3つが欠けていれば、どれだけ環境を良くしても
“やる気が湧かない状態”から抜け出すことはできません。
仕事を楽しむには“意味・成長・裁量”が欠かせない
仕事が楽しくなる瞬間は、
決まって以下の3つが揃ったときです。
① 意味
自分の仕事が誰かの役に立っているという感覚。
② 成長
昨日より今日の自分のほうが“できている”という感覚。
③ 裁量(自律性)
やらされているのではなく、自分で選んでいるという感覚。
この3つが揃うと、
やる気は自然に高まっていきます。
逆に、
ストレスがなくても“やる気が出ない”人は、
たいていこの3つのどれかが不足しています。
今日からできる小さな改善行動(自己版・管理職版)
最後に、すぐ実践できる具体的なアクションを紹介します。
【個人向け】今日からできる改善行動
- 業務の意味付けを言語化する
「私は誰の役に立っているのか?」を紙に書く - 小さな成功体験をつくる
5分で終わるタスクからスタート - 裁量を広げる工夫をする
自分で決められる部分を意識して増やす - 学びの時間を意図的に入れる
“成長実感”をつくるのは自分の行動次第 - 自分の強みを使える仕事を選ぶ
強みと仕事が重なると疲れにくくなる
【管理職向け】すぐにできる改善行動
- 努力と成果をこまめに承認する
- 目標ではなく“役割”を明確にする
- メンバーに裁量を渡す仕組みを作る
- 成長機会を計画的に提供する
- プロジェクトの“意味”を一緒に言語化する
最後に:不満を消すだけでは、人生は変わらない
この記事全体を一言でまとめると、
不満を減らすのは重要だが、
仕事を楽しむには「やる気の源泉」を育てる必要がある。
これがハーズバーグの二要因理論が伝えたかった本質です。
環境を整えることは、人生のスタートラインに立つこと。
そこから先、充実した働き方を作るのは、
自分の“意味・成長・裁量”をどれだけ育てられるか にかかっています。




